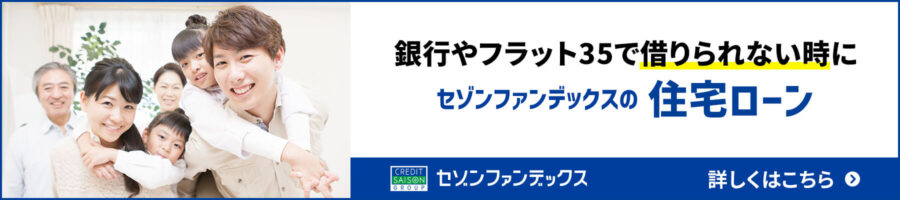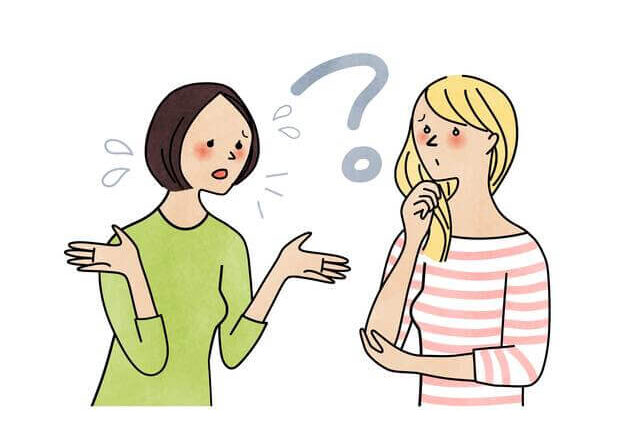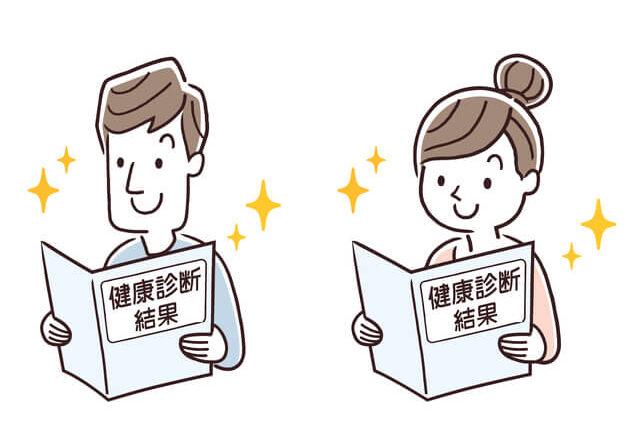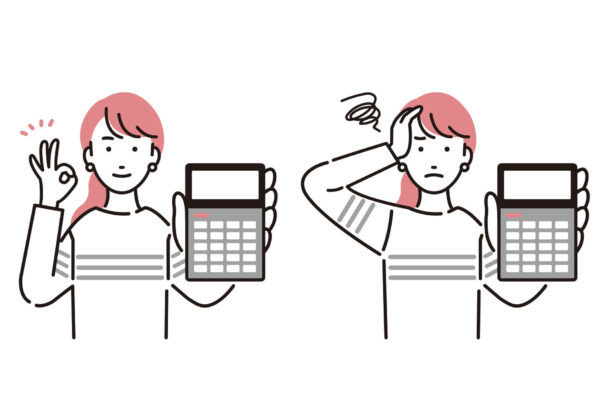住宅ローンの借入金が目標額に達しない場合、収入合算やペアローンを利用することで、借入金額を増やせます。
しかし、購入した物件を所有する割合や、転職などで収入が減ったときのことも考慮せずに住宅ローンを組むと、将来家族間トラブルが発生する可能性があることを知っておきましょう。
この記事では、収入合算で住宅ローンを組んだ際のメリットやデメリット、万が一離婚することになった際の対処方法などについて解説します。
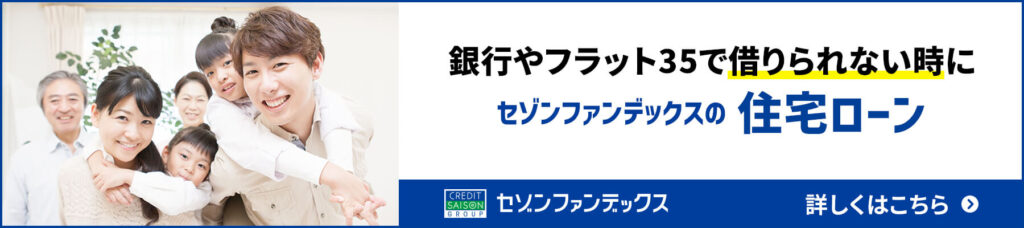
住宅ローンの収入合算とは?

住宅ローンの収入合算とは、契約者となる方の収入と、配偶者や家族の収入を合算し、その金額をもとに住宅ローンを組む方法です。ひとりの収入で住宅ローンを組むよりも大きな金額を借りられるため、単独ローンでは購入できないマイホームを入手する手段として利用されています。
住宅ローンの収入合算は2種類ある
収入合算には「連帯保証型」と「連帯債務型」の2種類があります。それぞれローンの契約者や債務責任の所在が異なるため、契約前に特徴を理解しておくことが重要です。
また、住宅ローンを組む金融機関によっては、どちらか一方しか扱っていないこともあるため、利用できる方法を事前に確認しておきましょう。
各種類の違いについては、以下の表をご覧ください。収入合算の種類と特徴
| 項目 | 連帯保証型 | 連帯債務型 | ||
| 対象者 | 契約者 | 配偶者や親族 | 契約者 | 配偶者や親族 |
| 契約関係 | 主債務者 | 連帯保証人 | 主債務者 | 連帯債務者 |
| 債務を負う責任 | あり | あり (主債務者が返済不可の場合) | あり | あり |
| 物件の所有権 | あり | なし | 一部あり (持分割合) | 一部あり (持分割合) |
| 住宅ローン控除 | あり | なし | あり | あり |
連帯保証型
連帯保証型は、契約者が主債務者としてローンを契約し、もうひとりが連帯保証人となる収入合算の方法です。この方法では、基本的に連帯保証人に返済を求めることはありません。ただし、主債務者が返済できなくなると、連帯保証人に債務を負う責任が生じます。
例えば、夫が主債務者で妻が連帯保証人となった場合、夫が住宅ローンを返済できなくなると、妻が返済していかなければいけません。また、連帯保証人である妻には物件の所有権がなく、住宅ローン控除も受けられないため、返済の負担が大きくなるでしょう。
よって、連帯保証型は基本的に主債務者が返済する必要のある仕組みですが、返済できない状態になった場合、連帯保証人の負担が大きくなるという特徴があります。
連帯債務型
連帯債務型は、契約者が主債務者として住宅ローンを借り、もうひとりが連帯債務者となる収入合算の方法です。連帯債務型では、それぞれが住宅ローン全額について返済義務を負うため、どちらかが返済できなくなると、もうひとりが全額を返済しなければいけません。
例えば、連帯債務型の収入合算を利用して、主債務者の夫が2,000万円、連帯債務者の妻が1,000万円を出資して3,000万円の住宅ローンを組んだとします。この場合、夫と妻は3,000万円全額について返済義務を負います。
ただし、所有権の割合は出資額に応じて決まるため、妻の所有権割合は3分の1です。この出資額に応じた所有権の割合を「持分割合」といいます。
連帯債務型は、2人で債務責任を持つ一方で、不動産の所有権は出資額に応じた持分割合によって決まるのが特徴です。
収入合算とペアローンの違い
夫婦や親子で住宅ローンを組む方法のひとつに「ペアローン」があります。ペアローンとは、夫婦や親子などが、それぞれ独立したローン契約を結ぶ方法です。ローン契約が2本になる点や、債務責任が完全に分かれている点が、収入合算とは異なります。
ペアローンと収入合算の違いについては、以下の表をご確認ください。
ペアローンと収入合算の比較
| 項目 | ペアローン | 収入合算 | |
| 連帯保証型 | 連帯債務型 | ||
| 借入額 | それぞれの収入に応じた金額 | 合算した収入に応じた金額 | |
| 債務者 | それぞれが債務者 (お互いに連帯保証人) | どちらかが主債務者 (もうひとりが連帯保証人) | どちらかが主債務者 (もうひとりが連帯債務者) |
| 名義 | 共有名義 | 主債務者の名義 | 共有名義 (出資額に応じた持分割合) |
| 住宅ローン控除 | それぞれ利用可 | 主債務者のみ利用可 | それぞれ利用可 |
| 団体信用生命保険 | それぞれ加入可 | 主債務者のみ可 | 主債務者のみ可 (金融機関によっては連帯債務者も可) |
収入合算とペアローンの大きな違いは、債務責任が独立していることです。収入合算は主債務者を決定し、ペアローンはそれぞれが債務者となって返済を行います。
収入合算では、主債務者が返済不能になると、もうひとりが全額の返済義務を負います。互いが連帯保証人となるペアローンも同様で、パートナーが返済不能になった場合は、返済負担が大きくなってしまうでしょう。
ただし、団体信用生命保険の加入者が主債務者のみの収入合算を選択した場合、パートナーが死亡や病気となってしまったときの保障がありません。一方ペアローンの場合は、それぞれが団体信用生命保険に加入するため、万が一のことがあったときでもパートナーの返済を負わずに済みます。
なお、ペアローンは2本のローン契約を結ぶため、事務手数料や保証料などの諸費用が2倍になる点は理解しておきましょう。
収入合算のデメリット

収入合算は、主債務者の収入が減少した際に、連帯債務者や連帯保証人の負担が大きくなるリスクがあります。また、住宅ローン控除を受けられないなどのデメリットにも注意が必要です。具体的な収入合算のデメリットは、以下の3つです。
- 収入が減少すると家計への負担が大きくなる
- 連帯保証人は住宅ローン控除などの優遇が適用されない連帯債務者や連帯保証人は団体信用生命保険へ加入できないことが多い
ここでは、収入合算のデメリットについて詳しく解説します。
収入が減少すると家計への負担が大きくなる
収入合算では、どちらかの収入が減少すると、家計への負担が大きくなります。なぜなら、家計全体の収入が下がっているにもかかわらず、毎月の返済額は変わらないからです。
例えば、連帯債務者が育児や介護で働けなくなった場合、主債務者の収入だけで返済しなければいけません。しかし、2人分の収入を見込んで返済計画を立てているため、その後の返済が難しくなるケースもあります。
収入合算で住宅ローンを組む際には、どちらかの収入が減る可能性も考慮して、無理のない返済額を設定することが大切です。
連帯保証人は住宅ローン控除の優遇が適用されない
収入合算の連帯保証人となった方は、住宅ローン控除の優遇を受けられないため、よく検討してから契約しましょう。
住宅ローン控除は、控除できる金額が大きいため、積極的に利用したい制度です。
しかし、連帯保証型の収入合算でローンを組んだ場合、主債務者しか住宅ローン控除やすまい給付金などの制度を利用できません。一方、連帯債務型の収入合算やペアローンは、2人とも優遇を受けられます。
2人で住宅ローン控除の優遇を受けたい方は、連帯債務型の収入合算やペアローンを利用しましょう。
連帯債務者は団体信用生命保険へ加入できない可能性がある
収入合算で住宅ローンを組む場合、連帯債務者や連帯保証人は、原則として団体信用生命保険へ加入できません。一部の金融機関では、連帯債務者が加入できる場合もありますが、基本的には加入できないことが多いでしょう。
一方、ペアローンは、どちらも団体信用生命保険に加入することが可能です。よって、どちらかが死亡や病気などになると、返済が免除され、住宅ローンの返済負担が軽くなります。
収入合算では、2人分の収入を見込んで返済額が設定されています。そのため、万が一の際に、主債務者がひとりで返済していくのは困難です。
収入合算を検討する際には、ケガや病気、死亡といったリスクにどこまで備えるか考えて契約しましょう。また、団体信用生命保険へ加入できない方は、保険会社の生命保険を活用して病気や死亡などのリスクに備えるのもひとつの方法です。
収入合算のメリット

収入合算を利用するメリットには、以下の2つがあります。
- 契約時の諸費用を抑えられる
- 借入金額の増額が検討できる
ここでは、収入合算のメリットについて、それぞれ詳しく解説していきます。
契約時の諸費用を抑えられる
収入合算は、2人の収入を合算して1本の住宅ローンを契約する方法です。そのため、契約時に必要な諸費用を抑えられるメリットがあります。
ペアローンを契約する場合、それぞれローン契約を結ぶため、契約時に必要な費用も2倍用意しなければいけません。一方、収入合算であれば、契約時の諸費用を最小限に抑えられます。
住宅ローン契約時に発生する諸費用は、以下のとおりです。
- 事務手数料:金融機関の手続きに対する費用
- 保証料:保証会社を利用する場合に発生
- 印紙税:契約書に必要
- 登記関連費用:登記費用や司法書士への報酬など
- 団体信用生命保険料:加入者ごとに負担する
特に、金額が大きくなりがちな費用は印紙税です。ローンの契約金額によっては、1契約につき6万円以上必要なケースもあります。
契約時の諸費用を抑えたい方は、ペアローンよりも収入合算を選ぶとよいでしょう。住宅ローン契約時の諸費用について気になる方は、こちらの記事もご参照ください。


借入金額の増額が検討できる
収入合算では、2人分の収入を合算してローンを組めるため、借入金額を増やせる可能性があります。
例えば、夫婦で利用する以外でも、二世帯住宅を購入するときに収入合算は検討できるでしょう。不動産価格が高く、子どもの単独ローンでは購入できないときに、親の収入を合算することで、必要な資金を借りられる可能性があります。
ただし、収入合算する親の年齢が高齢である場合、申し込みができないケースもあるので、手続きの前に制限がないか確認が必要です。
収入合算で借入金額を増額できれば、購入できる住宅の選択肢も広がります。単独ローンの借入金が足りなかった場合の対策として、収入合算を検討するとよいでしょう。
収入合算を検討するケース

単独ローンの借入金が足りない場合や、夫婦どちらかの収入が安定しない場合には、収入合算を検討するとよいでしょう。
収入合算を検討すべきケースは以下の2つです。
- 単独ローンでは借入金が足りない
- 契約の諸費用を抑えつつ2人でローンを組みたい
ここでは、収入合算を検討すべきケースについて詳しく解説します。
単独ローンでは借入金が足りない
単独ローンの借入金が少ない場合に、収入合算を活用できます。収入合算で住宅ローンを組めば、単独ローンの借入限度額以上の資金を用意できる可能性があります。
例えば、3,000万円の住宅を購入したいと思っていても、単独ローンで2,500万円しか借りられずに諦めてしまう方もいるでしょう。しかし、2人の収入を合算することで、3,000万円を借りられる可能性もあります。
特に、配偶者や家族の収入が高いご家庭では、収入合算によって借入金を大幅に増やせる可能性があります。単独ローンで資金を用意できずに困っている方は、収入合算を検討しましょう。
契約の諸費用を抑えつつ2人でローンを組みたい
2人で住宅ローンを組む方法として、ペアローンを検討している方も多いでしょう。しかし、ペアローンの場合は、ローン契約時に2人分の諸費用を用意しなければいけません。一方、収入合算であれば、契約時の諸費用を抑えられます。
例えば、ペアローンで1,500万円ずつ出資した場合、夫婦で合計4万円の収入印紙代が必要です。一方、収入合算で3,000万円の住宅ローンを組んだ場合、2万円の収入印紙代で契約できます。さらに、契約手続きも1本分で済むため、契約に必要な時間と手間を大幅に削減できるメリットもあります。
契約の諸費用を抑えつつ、2人で住宅ローンを組みたいと考えている方は、収入合算を利用するとよいでしょう。
収入合算の注意点

共有名義と持分割合の関係性に注意する
持分割合とは、対象不動産の所有割合のことです。お金を出し合って共同購入した不動産は、共有名義の住宅となります。基本的には、各所有者の出資額に応じた所有権が設定され、この所有権比率を示したものが持分割合です。
例えば、夫と妻の出資割合が「8:2」でマイホームを購入した場合、夫と妻の持分割合も「8:2」となるのが一般的です。このように、連帯債務型の収入合算で住宅ローンを組んだ際に、出資割合に応じた持分割合が設定され、共有名義の不動産として登記されます。
一方、連帯保証型の場合は、主債務者となるのは夫婦どちらか一方であるため、連帯保証人となる方には持分がありません。そのため、登記簿上では、主債務者名義の不動産として登記されます。
出資額と持分割合が異なると贈与税が発生する
出資額の割合が低い方の持分割合を高く設定した場合、贈与税が発生するケースもあるため注意しましょう。
例えば、夫が3,000万円、妻が2,000万円を出資して5,000万円の不動産を購入した際、出資割合に応じて夫と妻の持分割合は「6:4」となるのが通常です。しかし、持分割合を夫4割、妻6割と設定すると、夫から妻へ2割分の贈与があったとみなされ、妻に贈与税が課せられる可能性があります。
贈与税は、贈与を受けた金額に応じて10%〜55%の税率で計算され、基礎控除額は110万円です。上記の事例の場合、夫から妻へ発生した2割(1,000万円)の贈与に対して、231万円が贈与税として徴収されます。詳細な計算式は、以下のとおりです。
| 事例 | 贈与税の計算 |
|---|---|
| 夫から妻へ1,000万円の贈与があった場合 | (1)贈与額から基礎控除110万円を差し引く 1,000万円 - 110万円 = 890万円 (2)税率を適用する(890万円は「700万円超~1,000万円以下」の範囲で税率40%、控除額125万円) 890万円 × 40% - 125万円 = 231万円 |
ただし、贈与された金額が基礎控除額「110万円」以下だった場合は、贈与税は発生しません。
収入合算で住宅ローンを組む際は、贈与税が発生することも考慮しつつ、持分割合を設定することが大切です。
離婚したときの対処方法も決めておく
離婚と住宅ローンの契約内容は別問題です。そのため、離婚をしても住宅ローンの契約が継続される点に注意しておかなければいけません。
例えば、夫と収入合算で住宅ローンを組んだ妻が、離婚を機に別居したとします。主債務者である夫が住宅ローンの返済を滞らせてしまうと、連帯保証人や連帯債務者となっている妻に返済義務が生じます。
離婚後に住宅の債務を負わないようにするためには、住宅ローンを完済するか、住宅ローンの借り換え、家の売却が必要です。
しかし、収入合算で住宅ローンを組んでいると、単独ローンへの借り換えは審査にとおりにくく、単独名義に変更できない可能性が高いでしょう。
また、離婚後は不動産の取り扱い方法についてトラブルが生じる可能性もあります。
連帯債務型の収入合算では、離婚後も夫婦双方が共有持分を保有している状態です。そのため、離婚後の住宅を「売却するか」「どちらかが住み続けるか」について意見が分かれ、処分方法を巡って争いが起きることがあります。
一方、連帯保証型で主債務者の単独所有となっている場合でも、「どちらが住み続けるのか」という問題で対立する可能性があります。
離婚後のトラブルを防ぐには、事前に共有持分や住宅の取り扱いについて話し合い、合意しておくことが重要です。
離婚時の共有持分を解消する方法とは?

収入合算で住宅ローンを組んだ方が、離婚後に共有状態を解消したい場合、以下の選択肢があります。
- 住宅を第三者に売却する
- どちらかの持分を他方に売却もしくは財産分与する
- 他の住宅ローンに借り換える
不動産の共有持分がある状態で売却や財産分与をする際には、親族間で主張が食い違い、争いになる可能性があるので注意しましょう。共有持分を解消するための最も現実的な方法として、親族間・夫婦間の不動産売買を目的とした融資の利用があります。
セゾンファンデックスの住宅ローンは、銀行などの金融機関が取り扱わない共有持分を解消するための親族間・夫婦間売買における融資にも対応しています。
担保を重視した独自の基準を用いて審査をするため、銀行やフラット35の住宅ローンで借り入れが難しい方でも審査に通過できる場合があります。
実際に、離婚時の持分買取だけでなく、創業して間もない自営業者や永住権を持たない外国人、過去の滞納歴から住宅ローンを断られた方が、セゾンファンデックスの住宅ローンの審査に通過した例もあります。
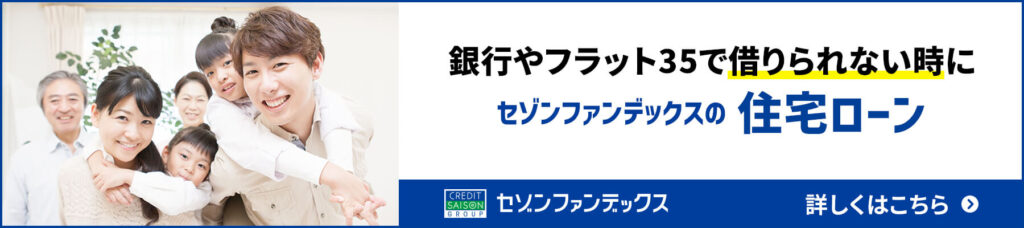
おわりに
収入合算とは、夫婦や親子などの収入を合算して住宅ローンを組む方法です。収入合算で住宅ローンを組むことで、単独でローンを組むよりも大きな金額を借り入れすることが可能になります。
しかし、収入合算で住宅ローンを組むと、一方の収入が減ったときや、病気で働けなくなったときに家計への負担が大きくなるなどのデメリットがあります。
また、離婚時に不動産の取り扱いで争う可能性がある点にも注意しておかなければなりません。
特に、トラブルとなりやすい「共有持分の問題」を解消する方法として、相手側の持分を購入し不動産の所有権をどちらかひとりにする方法がおすすめです。
収入合算のメリットとデメリットを理解したうえで住宅ローンを組みたい方は、セゾンファンデックスの住宅ローンを検討してみてはいかがでしょうか。
セゾンファンデックスは、担保を重視した独自の基準を用いて審査をしています。よって、他の金融機関で審査に通らなかった方も、住宅ローンを組める可能性があります。収入合算などの方法を利用して、理想のマイホームを購入しましょう。
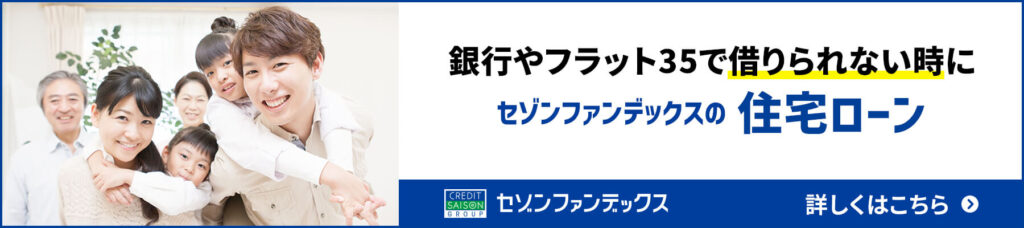
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。