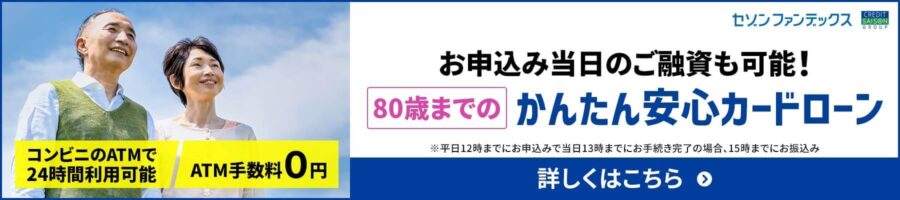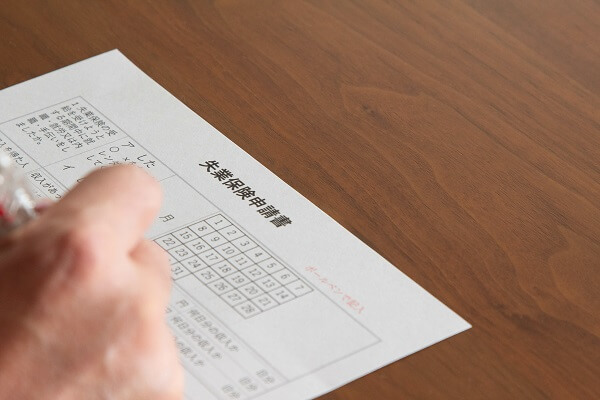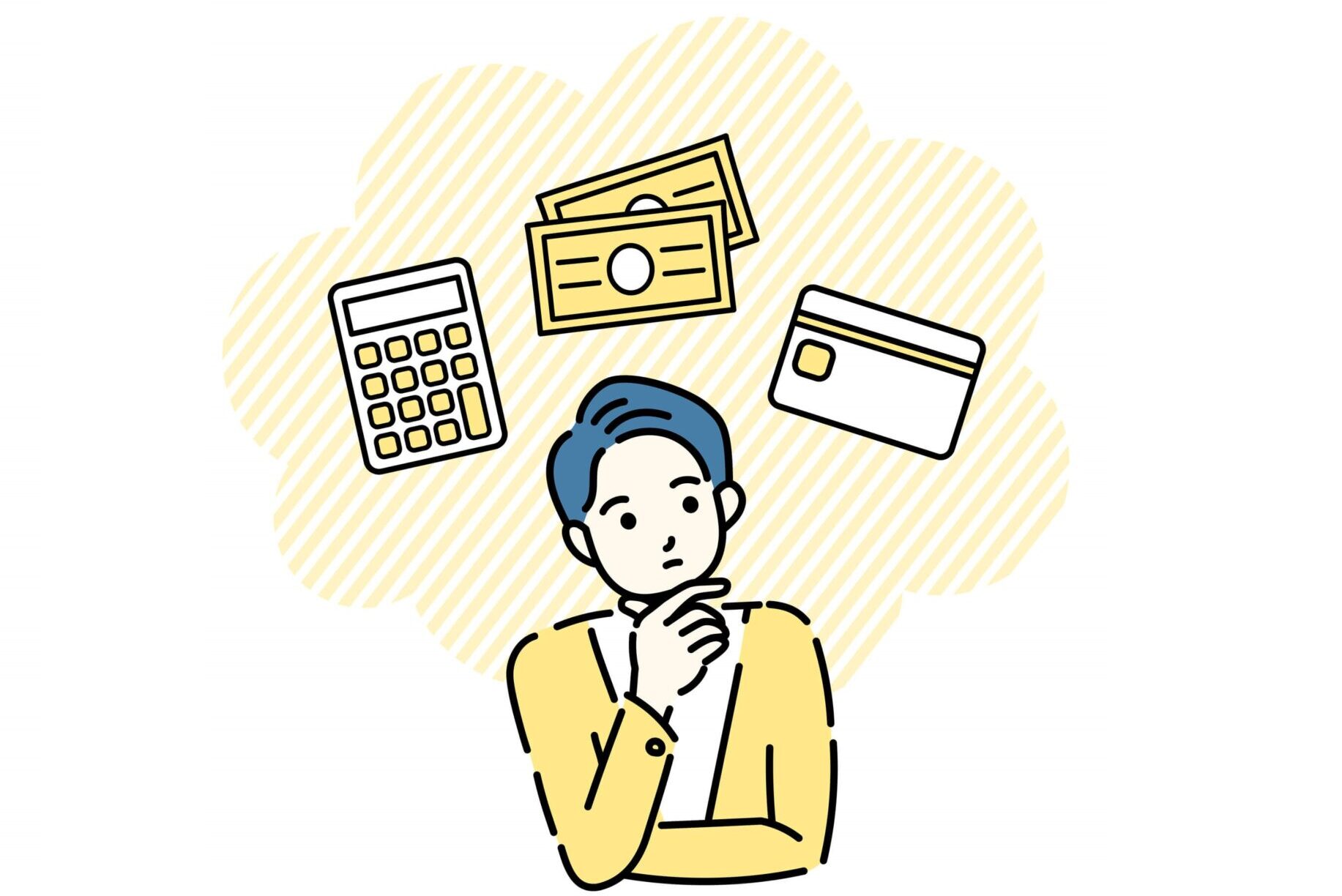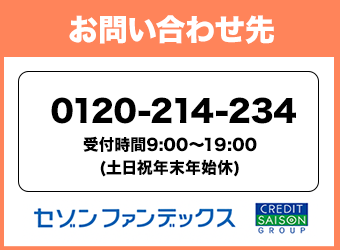定年退職後でも考慮すべきなのが税金です。見落とすと予期せぬ負担となるケースもあるため、納付時期を正確に把握し、事前に資金計画を立てておくことが大切です。
この記事では、老後にかかる税金や社会保険料を解説します。
また納税資金が用意できないときの対処法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
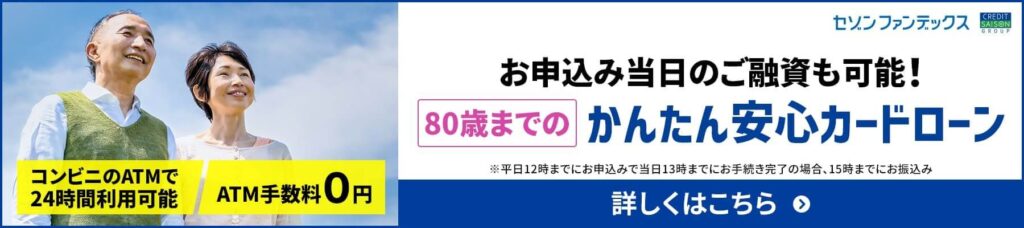
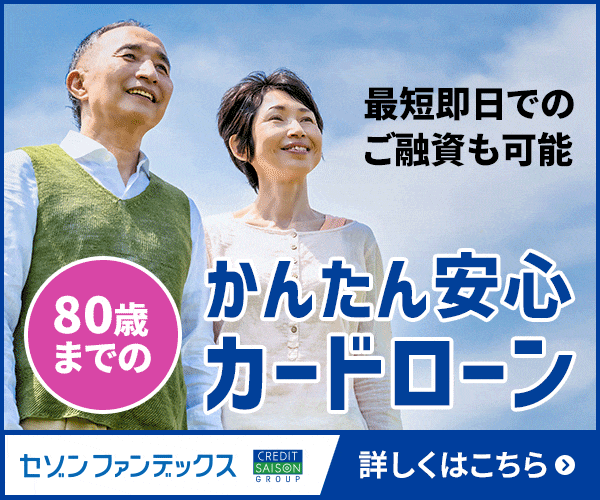
老後にかかる主な税金

老後生活にかかる主な税金は、以下のとおりです。
- 所得税
- 住民税
- 固定資産税
- 自動車税
なお所得税と住民税は国民年金と厚生年金の受給者が対象で、障害年金や遺族年金にはかかりません。
所得税
所得税は、年金の受給額に応じてかかる税金です。1年間の受給額が以下の場合に課税対象となります。
- 65歳未満:108万円以上
- 65歳以上:158万円以上
年金は「公的年金等控除」が適用されるため、課税所得が減額されます。1年間の所得が年金のみ、または年金以外の所得が1,000万円以下の場合に適用される控除額は、以下のとおりです。
| 1年間の年金額 | 公的年金等控除額 | |
|---|---|---|
| 65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 |
| 130万円超~410万円以下 | 年金額×25%+27万5,000円 | |
| 410万円超~770万円以下 | 年金額×15%+68万5,000円 | |
| 770万円超~1,000万円以下 | 年金額×5%+145万5,000円 | |
| 1,000万円超 | 195万5,000円 | |
| 65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 |
| 330万円超~410万円以下 | 年金額×25%+27万5,000円 | |
| 410万円超~770万円以下 | 年金額×15%+68万5,000円 | |
| 770万円超~1,000万円以下 | 年金額×5%+145万5,000円 | |
| 1,000万円超 | 195万5,000円 |
参照元:日本年金機構「所得金額の計算方法」
なお年金にかかる所得税は、以下の式で計算します。
- (年金額−公的年金等控除額−各種所得控除額)×(所得税率+復興特別所得税率)
例:65歳・独身・年金額180万円の場合
- 180万円-110万円(公的年金等控除額)=70万円(雑所得金額)
- 70万円-48万円(基礎控除額)=22万円(課税所得金額)
- 22万円×+5.105%(所得税率5%+復興特別所得税率0.105%)=11,231円(年額)
課税対象者は、毎月の年金額から公的年金等控除額を引いた金額に5.105%を乗じた金額が源泉徴収されます。通常は確定申告が必要になりますが、以下の条件をすべて満たす場合は不要です。
- 年金額の合計が年間400万円以下
- 年金以外の所得が年間20万円以下
ただし、医療費控除や生命保険料控除などの控除を申請する場合は、確定申告が必要になります。
参照元:国税庁「No.1199 基礎控除」「No.1600 公的年金等の課税関係」
住民税
住民税も年金の受給額に応じてかかる税金です。
住民税は「均等割」と「所得割」の2種類で構成されています。均等割は所得に関係なく均等に課され、金額は自治体により異なります。一方、所得割は前年の所得に応じた負担が必要です。
4月1日時点で65歳以上の年金受給者は、年金額が年間18万円以上の場合、住民税を特別徴収されます。特別徴収とは、年金から住民税を差し引いて徴収する方法です。なお、年金から特別徴収される住民税は年金にかかる分のみで、給与所得がある場合は別に支払いが必要になります。
ただし、年金収入のみで受給額が以下の金額の方は、住民税がかからな場合があります。例えば、横浜市では以下に該当する場合、住民税が非課税となります。
- 65歳未満・配偶者なし:105万円以下
- 65歳未満・配偶者あり:172万円以下
- 65歳以上・配偶者なし:155万円以下
- 65歳以上・配偶者あり:211万円以下
参照元:横浜市「年金収入に対する市民税・県民税が非課税となる目安はいくらですか?」
上記の金額は目安で、詳細な金額は自治体により異なるため、詳しくは居住先の市区町村へお問い合わせください。
固定資産税
住宅や土地を保有する場合は、固定資産税の納付が必要です。
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課される税金で、税額は固定資産税評価額を基準に算出します。この評価額は3年に1度見直され、おおむね公示価格の70%程度になるように調整されます。なお税額の計算式は以下のとおりです。
- 課税標準額×税率(原則1.4%)
課税標準額とは、固定資産税評価額から特例措置などを適用して算出した金額です。なお納付は年4回(4月・7月・12月・翌年2月)に分けて行われるケースが一般的です。
税率や納付回数は自治体により異なるため、詳しくは居住する市区町村へお問い合わせください。
参照元:総務省「固定資産税」
自動車税
毎年4月1日時点で自動車を保有する場合は、自動車税が課せられます。税額は以下の表になり、排気量や新車登録した年月日により異なります。
自動車税は都道府県(軽自動車は市区町村)によって異なる場合があります。例えば、東京都港区の税額は以下のとおりです。
| 排気量 | 令和元年10月1日以降に新車登録 | 令和元年9月30日以前に新車登録 |
|---|---|---|
| 軽自動車(乗用・自家用) | 10,800円 | |
| 1,000cc以下 | 25,000円 | 29,500円 |
| 1000cc超から1500cc以下 | 30,500円 | 34,500円 |
| 1500cc超から2000cc以下 | 36,000円 | 39,500円 |
| 2000cc超から2500cc以下 | 43,500円 | 45,000円 |
| 2500cc超から3000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 |
| 3000cc超から3500cc以下 | 57,000円 | 58,000円 |
| 3500cc超から4000cc以下 | 65,500円 | 66,500円 |
| 4000cc超から4500cc以下 | 75,500円 | 76,500円 |
| 4500cc超から6000cc以下 | 87,000円 | 88,000円 |
| 6000cc超 | 110,000円 | 111,000円 |
参照元:東京都主税局「自動車税種別割」、東京都港区「軽自動車税(種別割)について」
新車登録から13年経過したガソリン車と軽自動車は、以下の割合で増税されます。ただし、電気自動車やハイブリット車などのエコカーは対象外です。
- ガソリン車:約15%増
- 軽自動車:約20%増
また、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに対象のエコカーを新車登録した場合は、翌年度に限り自動車税が減免される「グリーン化特例」が適用されます。
- 電気自動車
- 燃料電池自動車
- 天然ガス自動車
- プラグインハイブリッド自動車
上記の乗用車は、概ね75%自動車税が減額されます。
老後に税金以外でかかる費用
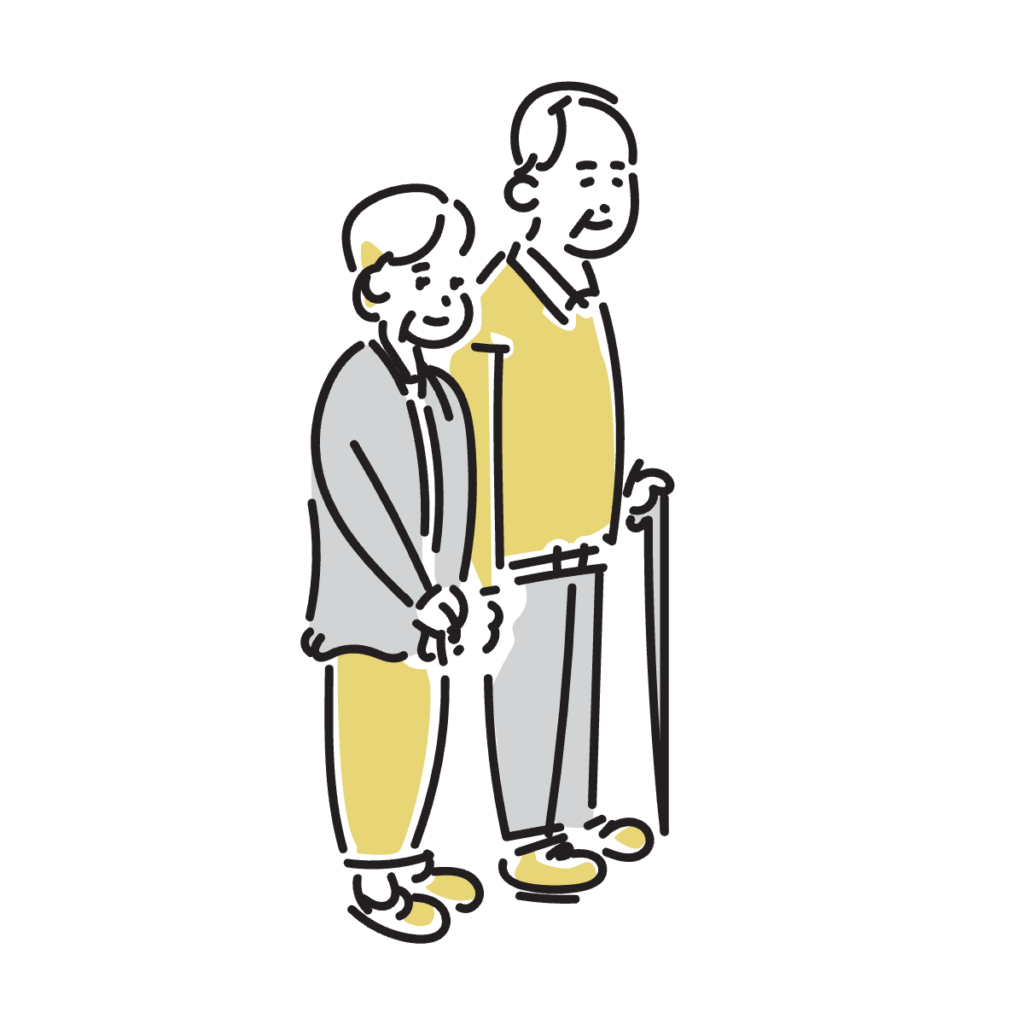
老後には税金以外にも定期的に発生する費用があります。老後の生活設計を立てる際は、これらの費用の計上を忘れないようにしましょう。
- 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
- 介護保険料
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
会社に勤めていない場合は、国民健康保険料の負担が必要です。
日本は国民皆保険制度を採用しているため、会社員でない場合は国民健康保険への加入が義務付けられています。
保険料は自治体により異なりますが、65歳以上で年金受給額が180万円の場合、国民健康保険料は年額約96,000円となります。75歳を超えると、後期高齢者医療保険へ切り替わります。正確な保険料は各自治体へお問い合わせください。
介護保険料
65歳以上の方は、国民健康保険料とは別に介護保険料の納付が必要です。介護保険料は、40歳以上65歳未満の方は加入する健康保険と併せて徴収されますが、65歳以上の方は別途納付となります。
第1号被保険者となる65歳以上の方は、介護が必要な状態になった場合、原因を問わず原則1割負担でサービスを受けられます。
保険料は自治体により異なりますが、厚生労働省の調査では令和3年度から令和5年度の全国加重平均は、月額6,014円でした。
年金額が18万円以上の方は、年金から天引きされる「特別徴収」により支払います。一方、年金額が18万円未満の方は普通徴収となるため、納付書や口座振替での支払いが可能です。
保険料の詳細は各自治体へお問い合わせください。
参照元:「令和5年度 介護納付金の算定について(報告)(PDFファイル)」
老後の税金を納めなかったらどうなる?
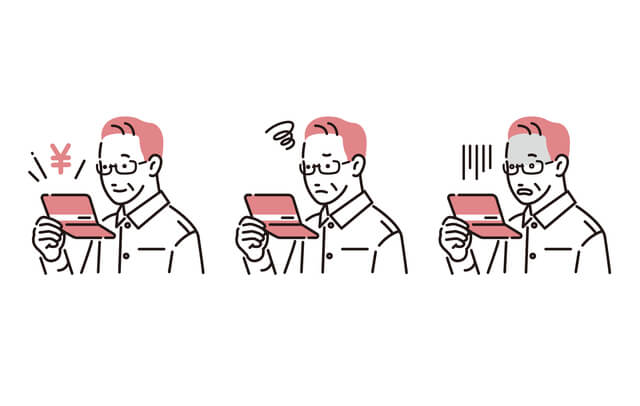
税金は定められた期限までに納付する必要があります。納税できない場合は、以下のリスクがあります。
- 延滞税が加算される
- 行政処分を受ける
余計な税負担を避けるためにも、期限内の納付を心がけましょう。
延滞税が加算される
税金を期限内に納めない場合、納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞税が加算されます。なお期限後に提出した確定申告書や修正申告書も対象です。
税率は以下の割合が適用されます。
- 期限の翌日から2ヵ月まで:年2.4%
- 期限の翌日から2ヵ月経過分:年8.7%
滞納が長くなるほど税率が高くなるため、延滞に気づいたら早めに納付しましょう。
行政処分を受ける
税金を滞納すると、国税徴収法や地方税法に基づいて行政処分が実施されます。
最初に督促状が送られますが、納付が確認されない場合は財産調査が実施されます。
調査で差し押さえ可能な財産が特定されたあとは、自由に売買や贈与ができません。差し押さえられた財産はその後現金化され、納税に充てられます。
税金を納めるお金がない場合は?
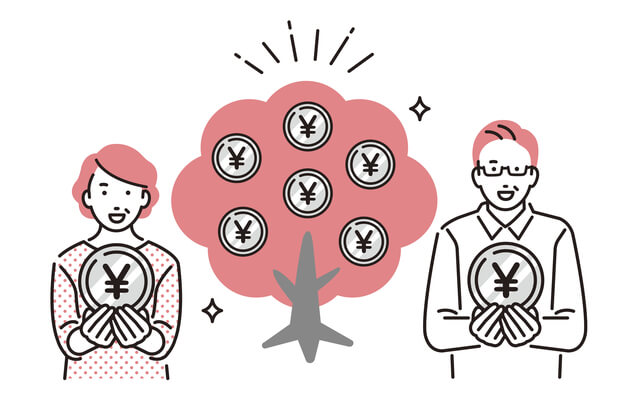
所得税や社会保険料など、老後もさまざまな税金を納める必要があります。納税時期が重なると、資金の用意が難しくなるケースもあるでしょう。納税が難しいときはローンの利用を検討してみてください。
ローンにはカードローンやフリーローンがありますが、80歳まで申し込みできる「セゾンファンデックスのかんたん安心ローン」なら、資金使途を問わず自由に利用できます。
まとまった金額を一括で借り入れる場合はフリーローン、必要なだけ借り入れたいなら、カードローンがおすすめです。
期限までに税金を納めると延滞税や行政処分を免れるため、ローンの賢い利用が求められます。いざというときのために「セゾンファンデックスのかんたん安心ローン」を検討してみてください。
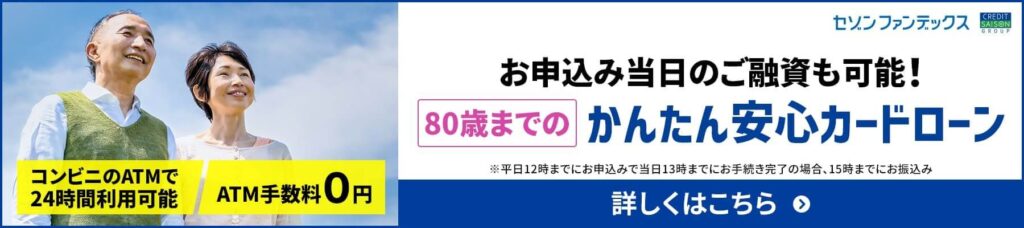
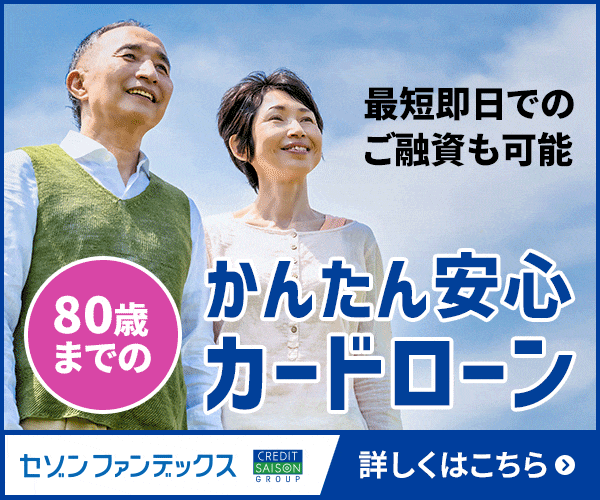
おわりに
収入が年金のみになると、税金や社会保険料が重くのしかかる場合があります。また老後資金を用意していても、切り崩していくうちに余裕がなくなるケースも考えられます。
事前に準備しておくことが理想ですが、一時的な資金不足の際はカードローンやフリーローンを上手に活用して未納を防ぎましょう。
ローン商品は年齢制限が設けられているものが多いですが、高齢でも利用できるものもあるので、自分に適した商品を探して活用してみてください。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。