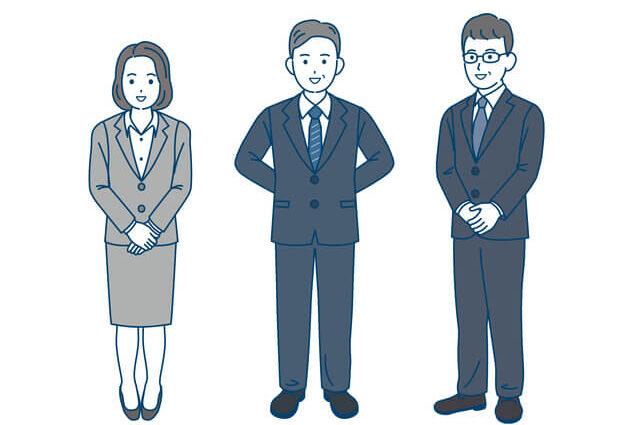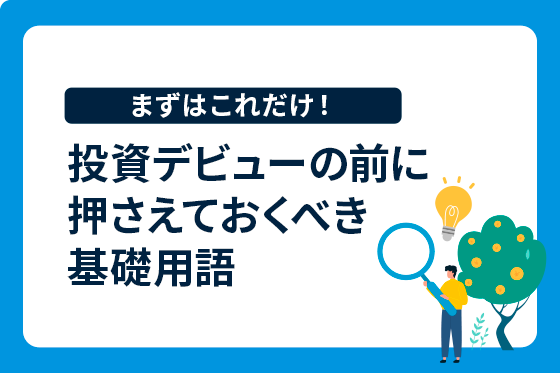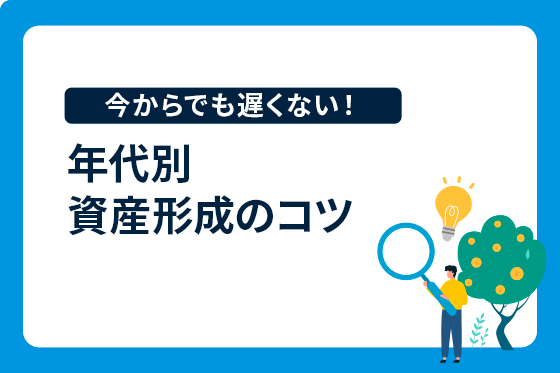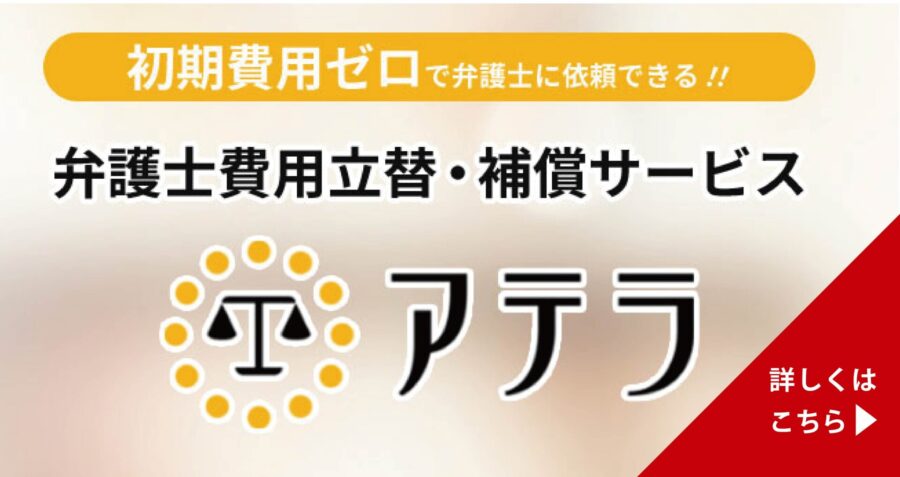弁護士を必要とするトラブルに備えて、弁護士費用保険に加入している方もいるのではないでしょうか。しかし「どのような保険なのか」「どこまで補償してくれるのか」など、わからない部分も多いでしょう。
この記事では、弁護士費用保険の概要やメリット・デメリットなどを解説します。
なお、弁護士費用保険は、すでにトラブルが発生している場合は適用外となります。それを知らない方も多く、利用する際には注意しなければなりません。
「弁護士費用保険について理解を深めて、万一に備えたい」と考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

弁護士費用保険制度とは
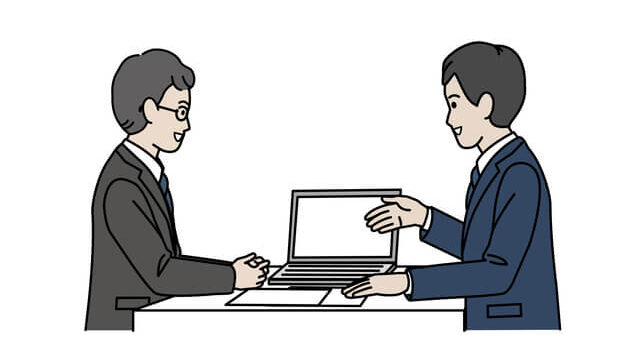
弁護士費用保険制度とは、一体どのような制度なのでしょうか。以下に詳しく解説します。
弁護士費用保険制度とは
弁護士費用保険とは、弁護士を必要とするトラブルが発生した際に、弁護士費用分の保険金が支払われる損害保険のサービスです。法的なトラブルや紛争が発生する前に加入し、保険料を支払います。
ただし、保険金は損害保険の契約で定めるトラブルにのみ支払われます。また、保険契約の日から一定の待機期間が設けられており、その間に発生したトラブルに関しては保険金が支払われない点に注意が必要です。
日弁連と協定を締結している保険会社
日弁連と協定を締結している保険会社や共済協同組合の保険・共済に加入している場合、トラブルが発生し弁護士に依頼しようと思った際には、日弁連や各地の弁護士会を通して弁護士の紹介を受けることが可能です。
2024年11月時点で、日弁連と協定を締結している保険会社および共済協同組合は以下のとおりです。
(保険会社)
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
AIG損害保険株式会社
au損害保険株式会社
キャピタル損害保険株式会社
共栄火災海上保険株式会社
ジェイコム少額短期保険株式会社
セゾン自動車火災保険株式会社
ソニー損害保険株式会社
損害保険ジャパン株式会社
SOMPOダイレクト損害保険株式会社
大同火災海上保険株式会社
chubb損害保険株式会社(チャブ保険)
チューリッヒ保険会社
ミカタ少額短期保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
三井ダイレクト損害保険株式会社
明治安田損害保険株式会社
楽天損害保険株式会社
(共済連合会)
全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)
全国自動車共済協同組合連合会
全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済 coop〈全労済〉)
中小企業福祉共済協同組合連合会
全国トラック交通共済協同組合連合会
弁護士費用保険への加入を検討している方は、協定を締結している保険会社および共済協同組合を頭に入れておきましょう。
参照元:日本弁護士連合会「弁護士費用保険(権利保護保険)について」
弁護士費用保険の保険料
弁護士費用保険には、損害保険商品(自動車保険など)の特約として位置づけられているものや単独の商品があります。
特約以外の商品であれば、保険料の相場は月額3,000円程度です。もちろん、もっと保険料の低い商品もあれば、高い商品もあります。選ぶ際には、保険料と補償内容を比較して決めるようにしましょう。
弁護士費用保険ADR
弁護士費用保険に関する裁判外の紛争解決機関として、弁護士費用保険ADRが用意されています。
取り扱う内容は、弁護士費用保険からの保険金の支払いの適否や支払われる保険金の額の妥当性、その他免責事由などの有無に関するトラブルです。被保険者、保険契約者、そして協定保険会社などが当事者となれることはもちろん、依頼を受けた弁護士も被保険者などの代理人ではなく、独立した当事者の立場で申し立てなどができる点が特徴です。
具体的な手続きには、主にトラブル解決手続きとして、和解あっせんの手続きと裁定手続きがあります。さらに相手方が手続きに応じない場合や、和解あっせんを行ったけれど成立に至らなかった場合に対して、見解書の交付を求める手続きも用意されています。利用の際には、弁護士費用保険に関する専門知識を持った担当者がサポートしてくれるため安心です。
弁護士費用保険に加入する3つのメリット

弁護士費用保険に加入するメリットは以下のとおりです。
- 費用面の心配がなくなる
- 保険料は少額である
- さまざまなトラブルに対応している
順番に見ていきましょう。
費用面の心配がなくなる
弁護士にトラブルの解決を依頼する場合、着手金を始め成功報酬を含めるとかなりの費用がかかります。項目ごとの相場は、以下のとおりです。
- 相談料:0円~5,000円(30分~1時間)
- 着手金:10万円~500万円
- 報酬金:10万円~500万円(依頼者が得た成果に応じて変動)
- 日当:5万円~11万円
なお、あくまでも目安であり、法律事務所や相談内容によって弁護士に支払う費用は異なります。
弁護士費用保険に加入しておくことで、着手金や報酬金などの費用を保険金でまかなえます。
参照元:相続会議「弁護士費用の相場はいくら? 分野別の一覧表や安く抑える方法、払えない場合の対処法を解説」
保険料は少額である
損害保険のため、掛け捨てになりますが保険料は比較的少額に設定されています。生活しているうえでトラブルに巻き込まれる可能性が全くないとはいいきれません。そのような際に、高額な弁護士費用を負担しなくてもよいと考えれば、安心できるのではないでしょうか。
さまざまなトラブルに対応している
弁護士費用保険は、さまざまなトラブルに対応しています。トラブルの例として「偶発事故」によるものであれば、以下のようなものがあります。
- 交通事故:自動車で信号待ちをしていたところ、後続車に追突され、けがをした
- 交通事故(刑事):自動車で交通事故を起こし、歩行者にけがをさせてしまったため、刑事事件となった
- 暴行などによる被害:学校で子どもが一方的に暴力を振るわれ、ケガをした
また、「一般案件」のトラブル例として以下のものがあります。
- 遺産相続:父が亡くなったが、遺言書には同居していた妹に全財産を譲ると記載されていた
- 労働トラブル:会社が残業代を支払ってくれない、もしくは労働者から労働裁判を起こされた
- 業務妨害:職員の対応に立腹した利用者の家族が、施設内で暴れ、業務に支障が出た
このように、偶発事故によるものだけでなく、遺産相続など一般案件のトラブルにも対応している点もメリットです。
弁護士費用保険は役に立たない?3つのデメリット
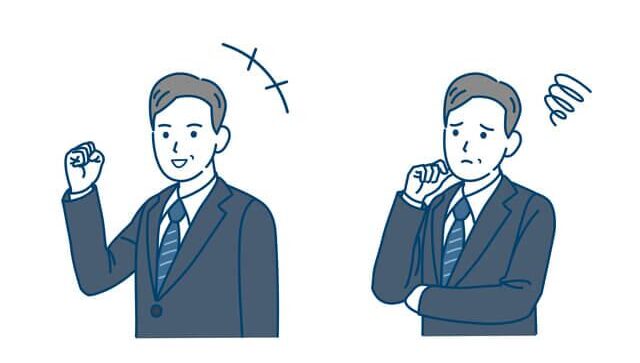
メリットばかりに思える弁護士費用保険には、実はデメリットがあります。
保険適用外となる期間がある
弁護士費用保険は、加入したあとすぐに補償を受けられるわけではなく、補償を受けられない期間が設定されています。
該当するトラブルは、離婚や相続、労働問題などの「一般事件」です。一般事件は、弁護士費用保険に待機期間は契約日から3ヵ月に設定されていることが多く、保険適用外となる期間がある点を頭に入れておきましょう。
保険適用外のトラブルがある
保険契約前に発生済みのトラブルや、待機期間中のトラブルなど待機期間や不担保期間があるほか、破産、民事再生などの法律事件や被非保険者側の問題による暴力行為や詐欺など保険適用外の案件がある点がデメリットです。契約の際には、どのようなケースで保険が適用されるのか、またどのような場合に保険の適用外となるのか確認しておくことが大切です。
免責金額・縮小てん補の設定がある
弁護士費用保険商品によっては、契約時点で自己負担額を設定しているものがあります。その自己負担額部分を免責金額といい、その費用は自分で払わなければなりません。
また、補償額を算出する際に、補償対象額に契約時点で定めた「基本てん補割合」を乗じて計算することがあります。これを縮小てん補といい、この設定があると、着手金や成功報酬の一部は保険金が下りないため、自己負担となります。保険金額には上限が定められているため、着手金や成功報酬が上限額を超える場合の差額も自己負担です。
すでに発生しているトラブルであれば「アテラ」がおすすめ
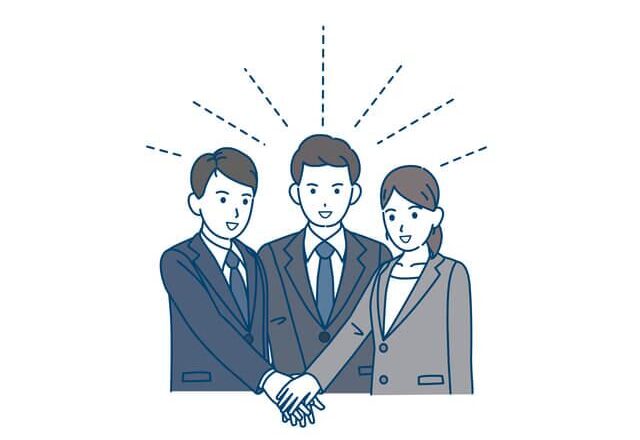
「アテラ」は、弁護士が代表を務めるATE株式会社が提供する法的なトラブルに関して相手に金銭等を請求する方向けに、弁護士費用などの「立替払い」と、敗訴した場合や金銭の回収に失敗した場合の損失リスクを引き受ける「補償」サービスです。
「アテラ」は以下のようなトラブル・手続きで利用できます。
・75万円以上の金銭等の請求を行う事案
・示談交渉、調停、裁判などすべての法的手続
なお、刑事事件や法的な請求を受けている側(債務者)の方は「アテラ」の対象外です。

「アテラ」のメリット
「アテラ/ATEリスク補償」のメリットは、契約より前に発生したトラブルでも立替・補償の対象となる点です。通常の弁護士費用保険のように毎月の保険料の支払いは発生せず、費用を支払うのは、勝訴などにより金銭の回収に成功した時のみで、しかも相手からの金銭回収後となっています。
つまり、自己負担なく弁護士保険に加入できます。さらに、敗訴や回収失敗時は実質「負担なし」で利用できます。なんといっても、すでに発生しているトラブルの敗訴などの非常にリスクをカバーしてくれるため、安心して利用できるでしょう。
※審査の結果、立替金額が初期費用用の一部のみとなる場合もあります。
「アテラ」はリスクなし
契約前に発生したトラブルにも対応してくれ、敗訴や回収失敗時の自己負担は必要ないため、「アテラ」の利用にリスクはありません。
ただし、勝訴して相手から現金を回収できた場合には、「アテラ」に立て替えてもらったお金を返すとともに、相手が支払った費用の一部をリスク補償料として「アテラ」に支払う必要があります。
なお、「アテラ」の利用にあたっては審査が必須です。審査により、利用可否と立替可能額、リスク補償料をお知らせいたします。審査の結果、初期費用全額を立替できない場合もあります。
おわりに
「アテラ」が提供する損失「補償」は、「敗訴などによって支払いを受けられなくなるリスク」や「勝訴はしたけれど、現金を回収できないリスク」をカバーしています。
また、通常の弁護士費用保険は「発生するかどうかわからないトラブルに関するリスク」をカバーするのに対し、「アテラ」では、すでに発生しているトラブルのリスクをカバーしてくれます。
また、「法テラス」が用意している民事法律扶助は、契約前に発生したトラブルにも対応可能です。一方、利用できるのは一定の収入以下などといった基準が設けられており、誰もが利用できるわけではありません。また、敗訴した場合や現金を回収できなかった場合でも、立て替えてもらった費用は原則として返済しなければならない点がデメリットです。
法的トラブルの解決の目的で弁護士に依頼する際にはまとまった費用がかかります。分割払いを認めている弁護士もいますが、それでも敗訴や回収不能となった際にはその分赤字になってしまいます。「アテラ」では、弁護士に依頼する際の初期費用を立て替えてくれるほか、敗訴や回収不能となった際には、立て替えた初期費用を補填してもらうことが可能です。
弁護士に依頼する際の不安は、なんといっても敗訴や回収不能となった場合の弁護士費用の支払いに当たっての赤字発生でしょう。その部分が解消される「アテラ」のサービスは非常に画期的といえます。電話やメール、LINEで受付を行っているため、気になった際は気軽に問い合わせしてみましょう。そして気になっている内容を全て確認したうえで、利用することをおすすめします。また、よくある質問の内容も確認し、最終的に自分の希望と合っているかを判断するのが良いでしょう。
裁判費用のことを考えて泣き寝入りするのではなく、「アテラ」に問い合わせるなど、解決策を見いだすために行動を起こすことが大切です。興味を持たれた方はぜひ問い合わせてみてはいかがでしょうか。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。