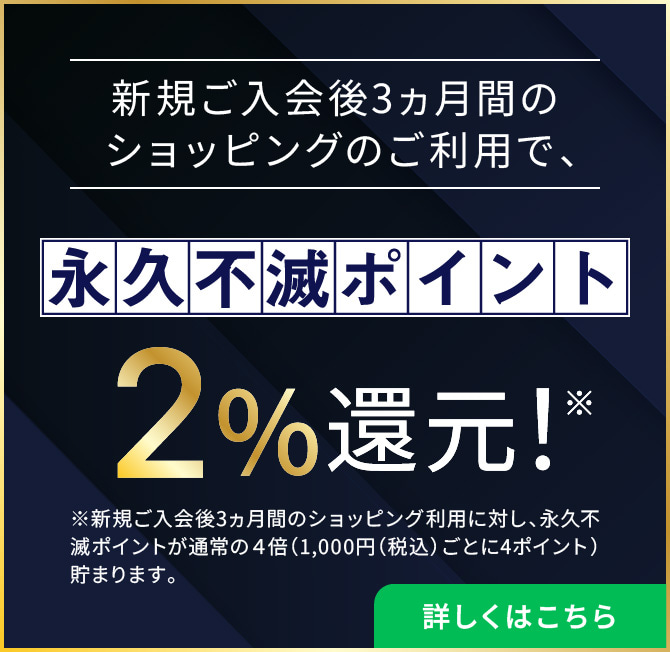個人事業を始めるにあたり「どのような事務手続きがあるのかな?」と、気になる方は多いのではないでしょうか。手続きを疎かにすると、後々トラブルに発展するケースもあるため、正しい理解が求められます。
特に重要な申請が「開業届」と「青色申告」の2つです。これらを申請しないと税制上の優遇を受けられず、結果的に年間で数万円以上も損する可能性もあるため、開業前に制度を知ることが大切です。
この記事では、開業届と青色申告の関係について詳しく解説します。税制面のメリットを活かしたい方や、これから開業するにあたって知識を深めたい方は、ぜひ参考にしてください。
青色申告をするには開業届の提出が必要
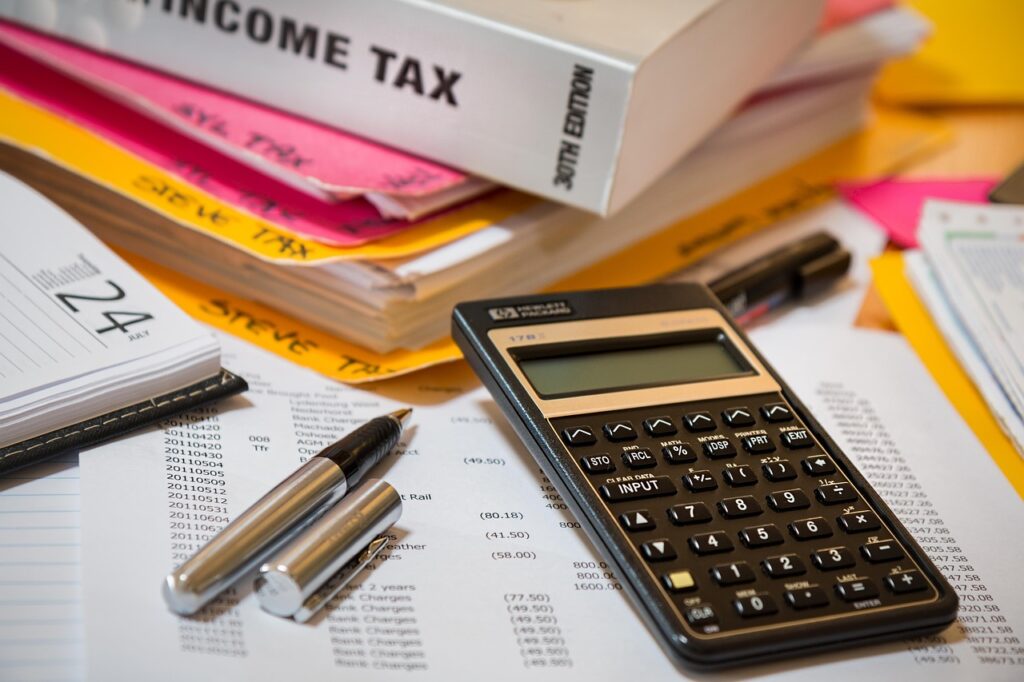
個人事業主として事業を営む際は「開業届」の提出が必要です。さらに、確定申告で青色申告を希望する場合は「青色申告承認申請書」も提出しなければなりません。
青色申告は開業届が未提出だと申請できません。また、どちらの書類にも提出期限があるため、忘れないよう早めの準備が必要です。
以降の章で、青色申告と開業届について、詳しく解説します。
青色申告のメリット3選

確定申告を青色申告にすると、以下のメリットを受けられます。
- 最大65万円の所得控除を受けられる
- 家族に支給した給与を経費にできる
- 赤字を3年繰り越せる・前年に繰り戻せる
確定申告で青色申告を選ぶ利点を、正しく理解しておきましょう。
1.最大65万円の所得控除を受けられる
青色申告では確定申告時に以下の条件を満たすことで、最大65万円の所得控除を受けられます。
- 複式簿記での記帳
- 貸借対照表と損益計算書の添付
- 期限内にe-Taxで申告または電子帳簿での保存
複式簿記とは、ひとつの取引を「借方」と「貸方」に分けて記入する方法です。記帳には多少の手間がかかる一方、資金の流れが明確になるメリットがあります。
現在は会計ソフトを利用して記帳するケースも多く、複式簿記であっても比較的簡単に帳簿を作成できるようになりました。さらに、会計ソフトはe-Taxでの申告にも対応しているため、青色申告のメリットを受けやすい環境が整っています。
なお、上記の条件を満たさない場合でも、55万円または10万円の控除を受けられる可能性があります。
参考:国税庁「65万円の青色申告特別控除」
2.家族に支給した給与を経費にできる
青色申告では、家族に支給した給与を経費計上できる「青色事業専従者給与」制度を利用できます。
この制度で該当する事業専従者と認められる要件は、以下のとおりです。
- 青色申告者と生計を一にする配偶者や親族
- 申告する年の12月31日現在で15歳以上
- 1年間で6ヵ月以上事業に従事
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署長に提出
「生計を一にする」とは、共通の資金で生活する状態を指し、一般的な家族であればこれに該当します。なお「青色事業専従者給与に関する届出書」は確定申告前に提出が必要なため、忘れずに準備しましょう。
参考:国税庁「青色事業専従者給与と事業専従者控除」
3.赤字を3年繰り越せる・前年に繰り戻せる
青色申告を選ぶと、事業で赤字が出た場合に損失を翌年以後3年間繰り越すことが可能です。これにより、赤字と利益を相殺して税金を減らせます。以下のケースを見てみましょう。
| 損益 | 課税所得 | |
|---|---|---|
| 1年目 | 損失100万円 | 0円赤字のため |
| 2年目 | 利益50万円 | -50万円(=50万円(利益)-100万円(1年目の赤字)) |
| 3年目 | 利益100万円 | +50万円(=100万円(利益)− 50万円(前年から繰り越した赤字)) |
また、青色申告では赤字を繰り越すだけでなく、繰り戻すことも可能です。たとえば、
- 1年目:利益100万円
- 2年目:損失50万円
この場合は、2年目の損失50万円を1年目に繰り戻し、1年目の課税所得を50万円に減らせます。その結果、払い過ぎた所得税が還付されるしくみです。
参照元:国税庁|青色申告制度
参照元:[手続名]純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続|国税庁
青色申告を利用する3つの注意点

青色申告を利用する際は、以下の3点に注意しましょう。
- 控除を受けられる所得が限られる
- 開業日から2ヵ月過ぎた場合の青色申告は翌年からになる
- 開業届と青色申告承認申請書は同時に提出できる
青色申告は開業届と密接な関係があるため、続く内容をしっかり確認しておきましょう。
1.控除を受けられる所得が限られる
青色申告で控除を受けられる所得は、以下の3種類です。
- 事業所得
- 不動産所得
- 山林所得
なお、不動産所得で65万円もしくは55万円の控除を受ける場合は「事業的規模」に該当している必要があります。事業的規模の基準は、以下のとおりです。
- アパート:部屋数10室以上
- 戸建て:5棟以上
- 駐車場:50台以上
また、山林所得で適用可能な控除額は10万円のみです。
2.申請書の提出が開業日から2ヵ月過ぎた場合の青色申告は翌年からになる
青色申告承認申請書には、提出期限が設けられています。
- 1月1日〜1月15日までに開業した場合:その年の3月15日まで
- 1月16日以降に開業した場合:開業日から2ヵ月以内
上記の期限を過ぎて申請書を提出した場合、青色申告の適用は翌年からとなります。
なお、青色申告承認申請書の提出期限日は「新たに事業を開始した日から」であり、開業届を提出した日ではありません。
開業届を提出して個人事業主になると、事業用のクレジットカードが作れます。たとえばビジネスカードである「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード」なら、さまざまなビジネスシーンに役立つ機能やサービスを受けられるため便利です。ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
参照元:国税庁|[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
参照元:国税庁|[手続名]所得税の青色申告承認申請手続
3.開業届と青色申告承認申請書は同時に提出できる
青色申告承認申請書は、開業届と同時に提出可能です。
開業届は開業日から1ヵ月以内、青色申告承認申請書は2ヵ月以内(1月1日〜1月15日までに開業した場合はその年の3月15日まで)と提出期限が定められています。別々に提出すると手間が増えるため、確定申告を青色申告で行う予定なら、同時提出を視野に入れて準備しておくとよいでしょう。
開業届とは

開業届は、正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、個人事業を始める際に税務署へ提出する書類です。ここでは、以下の3点について解説します。
- 出さない場合のデメリット
- 1年出し忘れても罰則はない
- 出していなくても経費は計上可能
個人事業を始めるうえで必須の書類ですので、これから提出する予定の方は押さえておきましょう。
1.出さない場合のデメリット
開業届を提出しない場合、主に以下のデメリットがあります。
- 青色申告を利用できない
- 事業用の銀行口座を作成できない
- 融資や助成金の申請が難しくなる
長期的に見れば、事業における信用や拡大を図る面で不利になる可能性があります。特に、青色申告を利用できなと納税額が増えるデメリットは大きいため、開業したら早めの提出がおすすめです。
2.1年出し忘れても罰則はない
開業届は、「開業日から1ヵ月以内の提出」が義務付けられていますが、未提出でも罰則はありません。1年後や2年後に提出しても通常どおり受理されます。
一方で、開業した後だと事業で忙しくなって提出が後回しになりがちなため、やはり開業したタイミングで提出しておく方がスムーズです。
3.出していなくても経費は計上可能
開業届を出していなくても、事業のために支出した経費の計上は可能です。
ただし、この場合は青色申告を利用できないため、白色申告になります。白色申告でも領収書の保管が義務付けられているため、捨てることがないように気をつけましょう。
開業届と青色申告承認申請書の提出方法
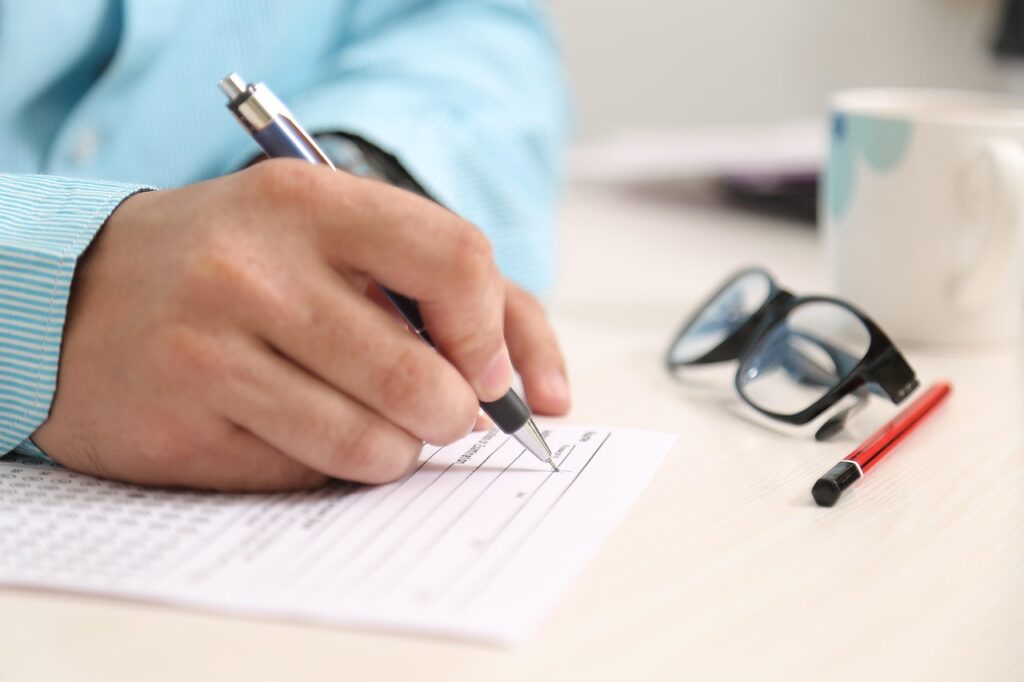
開業届と青色申告承認申請書は、税務署の窓口で受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードできます。
- 開業届の必要書類や書き方
- 青色申告承認申請書の必要書類や書き方
- 提出方法
ここでは、それぞれの書き方と提出方法を紹介します。
1.開業届の必要書類や書き方
開業する場合は「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。書類には以下の項目を記入してください。
- 開業日
- 氏名
- 生年月日
- 職業
- 屋号
- マイナンバー
氏名の横に押印する箇所も忘れずに記載しましょう。
屋号とは法人の会社名にあたる事業の名称ですが、必須ではありません。未定の場合は空欄で提出でき、翌年以降の確定申告で記載しても問題ありません。
2.青色申告承認申請書の必要書類や書き方
青色申告を利用するには、「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。申請書に記入するのは、以下の項目です。
- 管轄の税務署と提出日
- 事業と事業主の基本情報(氏名・生年月日・職業・屋号)
- 青色申告を開始する年度
- 事業の所在地(自宅を事業所にする場合は「住所地」、別に事務所がある場合は「事業所」にチェック)
- 所得の種類
- 過去の青色申告の履歴
- 開業日
- 簿記の形式と帳簿名
「8.簿記の形式」は、特別控除の金額に影響します。特別控除は65万円・55万円・10万円の3種類があり、65万円や55万円の控除を受けたい場合は複式簿記を、10万円の控除で良い場合は簡易簿記を選びましょう。なお、65万円控除を受けるには、複式簿記による帳簿付けに加えてe-Tax(電子申告)または電子帳簿による保存が必要です。
3.提出方法
個人事業の開始から原則1ヵ月以内の提出が義務付けられています。提出方法は、以下の3つです。
- 税務署へ持参
- 郵送
- e-Tax
開業届を提出すると、青色申告が可能になったり、屋号を設定して事業用の銀行口座を作成しやすくなったりするメリットがあります。
青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告の違いをまとめると、以下の表のとおりです。
| 青色申告 | 白色申告 | |
|---|---|---|
| 申請方法 | 青色申告承認申請書の提出 | 手続き不要 |
| 記帳方法 | 複式簿記 | 単式簿記 |
| 確定申告時の提出書類 | ・確定申告書 ・青色申告決算書 ・貸借対照表 ・損益計算書 など | ・確定申告書 ・収支内訳書 |
| 優遇措置 | ・最大65万円の青色申告特別控除 ・赤字の繰越控除(3年間) ・家族従業員の給与を経費計上可能 | ・特別控除なし ・赤字の繰越控除不可 ・家族従業員の給与の経費計上に制限あり |
白色申告は青色申告に比べて、手続きを簡潔に済ませられます。一方、青色申告で利用できる最大65万円の特別控除が受けられないため、税負担が増えることは理解しておきましょう。
おわりに
個人事業主が青色申告を利用するには、開業届の提出が必要です。青色申告には以下のメリットがあるため、申請を検討してみてください。
- 最大65万円の所得控除
- 家族に支給した給与の経費計上
- 赤字の繰越しと繰戻し
青色申告には提出期限があるため、開業届と同時に申請しておくとスムーズです。また、開業届は開業日から1ヵ月以内の提出が求められます。未提出による罰則はありませんが、次のようなデメリットを考えると早めに出すほうが望ましいでしょう。
- 青色申告での最大65万の控除は不可
- 事業用の銀行口座は作成不可
- 融資や助成金の申請が困難
個人事業を始める際は、事務手続きを早めに済ませておくと後々慌てずに済みます。事業に集中するためにも、開業届と青色申告をできるだけ早く申請しておきましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。