不動産を取得すると、不動産取得税を納める必要があります。しかし、一定の条件を満たすと軽減措置があることをご存知でしょうか。
この記事では、不動産取得税の基本的な仕組みや軽減措置の適用条件、非課税になるケースを解説します。申請に必要な書類や期限についても触れるので、不動産を取得する予定のある方は参考にしてください。
- 不動産取得税は、住宅や土地に課せられる地方税。固定資産税評価額が高いほど税額も大きくなるが、一定の要件を満たすと軽減措置が受けられる
- 新築・中古・土地・マンションなど、物件の種類によって軽減措置を受ける条件が異なる
- 不動産取得後60日以内(東京都は30日以内)に申告が必要だが、取得から5年以内なら還付を受けられる可能性もある
- 不動産の取得方法や状況によっては、不動産取得税が非課税になるケースもある
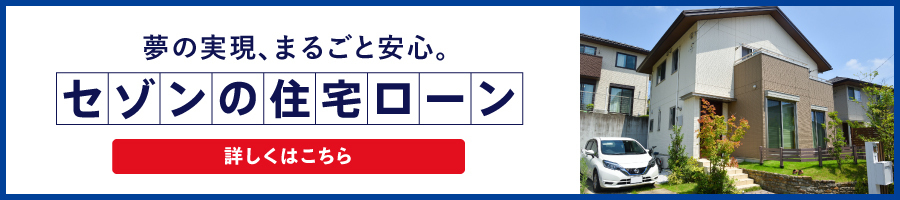
不動産取得税は不動産取得時に課せられる地方税

まずは、不動産取得税とはどのような税金なのか確認しましょう。
不動産取得税とは
不動産取得税とは、住宅や土地を取得した際に課せられる地方税です。土地・戸建て・マンションを問わず、新築・中古、有償・無償、登記の有無にも関係なくすべての不動産が課税対象となります。
不動産取得税は、取得したときに一度だけ支払えばよい税金であり、固定資産税などのように毎年課税されるものではありません。
課税される不動産の取得方法は、以下のとおりです。
- 購入
- 贈与(無償でも課税対象)
- 交換(等価交換でも課税対象)
- 建築(新築・増改築)
また、事業用に取得した不動産でも個人・法人を問わず課税対象です。これから不動産を取得予定の方は、費用計画に不動産取得税も組み込んでおきましょう。
不動産取得税の計算法
不動産取得税は「固定資産税評価額 × 税率」で算出します。税率は原則4%です。ただし、令和9年(2027年)3月31日までは特例措置により、土地または住宅を取得した場合に限り3%に軽減されます。
例えば、5,000万円で購入した住宅の固定資産税評価額が3,500万円(5,000万円 × 70%)前後になることが多いです。この場合の不動産取得税は105万円(3,500万円 × 3%)です。
なお、固定資産税評価額の詳細は後述します。
固定資産税評価額とは?
固定資産税評価額とは、不動産取得税や固定資産税の算出基準となる価格です。各自治体が総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づいて算定し、3年ごとに評価額の見直しが行われます。固定資産税評価額は、以下3つの方法で調べられます。
- 固定資産税課税明細書の確認
- 固定資産評価証明書の確認
- 固定資産税課税台帳の閲覧
固定資産税課税明細書は、毎年4月初旬頃に自治体から送付される書類です。
固定資産評価証明書とは、土地や建物の評価額を証明する書類です。この書類は、不動産のある市町村役場の窓口または郵送で取得できます。手数料は市町村によって異なりますが、数百円程度です。
固定資産課税台帳は、固定資産税の課税対象となる土地や建物などの情報が記載された帳簿です。不動産の所在地が東京23区内であれば各都税事務所で、それ以外は所在地の市区町村の役所で閲覧・取得できます。最新の情報や手続きの詳細は、不動産が所在する自治体のWEBサイトをご確認いただくか、直接お問い合わせください。
一般的に手数料はかかりませんが、一部有料の場合もあるので事前に確認しましょう。
固定資産評価証明書と固定資産課税台帳は、どちらも原則として不動産の所有者や関係者でないと取得・閲覧はできません。そのため、不動産の所有者以外の方が固定資産税を調べる際は、どのような方が関係者として認められるか各自治体で確認してください。
固定資産税評価額は、納税者間の公平性を保ちつつ、不動産の価格変動に対応するという2つの目的を達成するために不動産価格の70%程度されています。
そもそも不動産価格は、以下のような期待から相場よりも取引価格が高くなることがあります。
- インフレが進行しているので不動産価格も上昇するだろう
- 将来再開発によって土地の値段が上昇するだろう
税金の計算でまだ実現していない将来の見込みまで含めてしまうと、評価額が相場と比べて高くなりすぎてしまうのです。そこで、将来の期待や予測により高くなっている部分を少し差し引いて、より現実的な価格に近づけるために不動産価格の70%程度を目安に設定するとされています。
また土地の価格は常に変動するので、評価額を決めるときと実際に計算するときにズレが生じることは珍しくありません。例えば、評価額を決めたときよりも実際の不動産価格が下がるケースもあります。
一方、上記のように不動産価格にズレが生じても、評価額を不動産価格の70%程度にしておけば価格変動リスクが軽減されるため、納税者が不利益を被りにくいです。
このように、70%という数字は税負担の公平性を保ちつつ、不動産の価格変動に対応するための目安となっています。
物件購入前におおよその課税額を知りたい場合は、「物件価格 × 70%(0.7)」でおおよその固定資産税評価額がわかります。
不動産取得税の軽減措置
不動産取得税は、一定の条件を満たすと軽減措置が適用され、なかには不動産取得税が0円になる場合もあります。軽減措置の適用条件を把握して、活用できそうか確認してみましょう。ここでは主に以下の3つのパターンを取り上げます。
- 新築住宅に対する控除
- 中古住宅に対する控除
- 土地に対する控除
軽減措置の適用条件を順番に確認していきましょう。
新築住宅に対する控除
床面積50㎡以上240㎡以下の新築住宅を購入した場合、固定資産税評価額から最大で1,200万円が控除されます。ただし、賃貸用のマンションやアパートの場合の床面積の要件は、40㎡以上240㎡以下です。
建物の固定資産税評価額が1,200万円以下であれば、不動産取得税はかかりません。
また、固定資産税評価額が1,200万円を超えていても、軽減措置の適用の有無で税額に大きな差が生まれます。
例えば、固定資産税評価額が1,400万円、かつ特例措置により税率3%が適用されるケースを考えてみましょう。
【軽減措置を受けなかった場合】
1,400万円 × 3%=42万円
【軽減措置を受けた場合】
(1,400万円 – 1,200万円) × 3%=6万円
今回のケースでは、軽減措置によって不動産取得税は42万円から6万円となり、36万円もの税負担の軽減につながりました。
認定長期優良住宅の場合は1,300万円が控除される

令和8年(2026年)3月31日までに新築された認定長期優良住宅を取得した場合、固定資産税評価額の控除額が1,300万円に増額されます。認定長期優良住宅とは、耐震性や住宅環境などのさまざまな条件を満たしている機能が優れた住宅のことです。
固定資産税評価額1,400万円の新築住宅(認定長期優良住宅)を例に、不動産取得税額をシミュレーションしてみましょう。
【軽減措置を受けなかった場合】
1,400万円 × 3%=42万円
【認定長期優良住宅の軽減措置を受けた場合】
(1,400万円 – 1,300万円) × 3%=3万円
このケースのように、認定長期優良住宅の軽減措置を適用することで、不動産取得税は42万円から3万円となり、実に39万円もの税負担の軽減につながりました。
さらに、認定長期優良住宅を取得すると、登録免許税や固定資産税の税率や税額が軽減されるといった、税制面で以下のような優遇措置を受けられます。
| 登録免許税 | 固定資産税 | |
|---|---|---|
| 優遇措置 | 所有権保存登記の税率:0.1% ※一般住宅特例は0.15% | 固定資産税額が1/2 ※戸建て(2階以下)は5年間適用(一般住宅特例は3年間) ※マンションなど(3階以上の中高層耐火住宅)は7年間適用(一般住宅特例は5年間) |
| 所有権移転登記の税率 戸建て:0.2% マンション:0.1% ※一般住宅特例は0.3% | ||
| 適用を受けるための要件 | ① 主として居住の用に供する家屋であること ② 住宅の新築又は取得から1年以内に登記をすること ③ 床面積が50㎡以上あること | 床面積が50㎡以上(貸家は40㎡以上) 280㎡以下であること |
| 適用を受けるために必要なこと | 登記を行う際に市区町村が発行する 「住宅用家屋証明書」が必要。 | 長期優良住宅認定通知書または その写しを添付して市区町村への申告が必要。 |
| 備考 | 令和9年(2027年)3月31日までに取得した者が対象。 | 令和8年(2026年)3月31日までに新築された住宅が対象 |
中古住宅に対する控除
中古住宅にかかる不動産取得税の軽減措置は、「耐震基準に適合する中古住宅の取得」と「中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合」で、適用条件や控除額が異なります。
耐震基準に適合する中古住宅の取得
耐震基準に適合する中古住宅を取得する場合、以下3つの要件を満たすと不動産取得税の軽減措置が適用されます。
| 居住要件 | 個人が居住用のために取得した住宅であること ※住宅以外の家屋を取得する場合、取得前にリフォーム済みであること | |
| 床面積 | 50㎡以上240㎡以下 | |
| 耐震基準要件 (①と②いずれかを満たすこと) | ① 昭和57年(1982年)1月1日以降に新築された家屋 | ② 昭和56年(1981年)12月31日以前に新築された住宅で、耐震診断によって新耐震基準に適合していると証明されたもの ※上記の調査が取得日前2年以内に終了しているものに限る |
参照元:主税局「不動産取得税 Q13」
また、固定資産税評価額からの控除額は新築日に応じて変わるので注意が必要です。
| 新築日 | 控除額 |
|---|---|
| 平成9年(1997年)4月1日以降 | 1,200万円 |
| 平成元年(1989年)4月1日〜 平成9年(1997年)3月31日 | 1,000万円 |
| 昭和60年(1985年)7月1日〜 平成元年(1989年)3月31日 | 450万円 |
| 昭和56年(1981年)7月1日〜 昭和60年(1985年)6月30日 | 420万円 |
| 昭和51年(1976年)1月1日〜 昭和56年(1981年)6月30日 | 350万円 |
| 昭和48年(1973年)1月1日〜 昭和50年(1975年)12月31日 | 230万円 |
| 昭和39年(1964年)1月1日〜 昭和47年(1972年)12月31日 | 150万円 |
| 昭和29年(1954年)7月1日〜 昭和38年(1963年)12月31日 | 100万円 |
参照元:主税局「不動産取得税 Q13」
中古住宅の建物の不動産取得税は、「(固定資産税評価額 – 建物の控除額) × 税率3%」で算出します。固定資産税評価額が1,000万円、新築日が平成9年(1997年)3月31日の住宅を取得したケースで、軽減措置が適用されるとどのくらい不動産取得税が減額されるのか計算してみましょう。
【軽減措置を受けなかった場合】
1,000万円 × 3% = 30万円
【軽減措置を受けた場合】
(1,000万円 – 控除額1,000万円) × 3% = 0円
この条件でシミュレーションすると、軽減措置が適用された場合、不動産取得税を支払う必要がなくなります。
中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合
中古住宅取得後に耐震工事を行う場合は、以下4つの条件を満たすと、軽減措置が適用されます。なお、平成26年(2014年)4月1日以降に取得した中古住宅に限ります。
| 耐震基準不適合要件 | 前述した耐震基準要件①と②どちらも充足しないこと | |
| 床面積 | 50㎡以上240㎡以下 | |
| 耐震改修要件 (①と②を満たすこと) (取得日から6ヵ月以内) | ① 取得した方が、当該中古住宅の耐震改修工事を行うこと | ② 耐震改修工事後の住宅が、耐震診断などにより耐震基準に適合していることの証明がなされていること |
| 居住要件 (取得日から6ヵ月以内) | 耐震基準要件の①の工事後に住宅に居住すること | |
参照元:主税局「不動産取得税 Q13」
中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合は、当該住宅の新築日に応じて税額が減額されます。
| 新築日 | 減額額 |
|---|---|
| 昭和56年(1981年)7月1日〜 昭和56年12月31日 | 12.6万円 |
| 昭和51年(1976年)1月1日〜 昭和56年(1981年)6月30日 | 10.5万円 |
| 昭和48年(1973年)1月1日〜 昭和50年(1975年)12月31日 | 6.9万円 |
| 昭和39年(1964年)1月1日〜 昭和47年(1972年)12月31日 | 4.5万円 |
| 昭和29年(1954年)7月1日〜 昭和38年(1963年)12月31日 | 3万円 |
参照元:主税局「不動産取得税 Q13」
なお、昭和29年(1954年)6月30日以前に新築された住宅は、要件を満たしていても減額の対象とはならないので注意が必要です。
中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合の税額は、以下の流れで算出できます。
- 固定資産税評価額 × 税率3% = 本来の不動産取得税
- 本来の不動産取得税 – 減額額 = 軽減措置適用後の不動産取得税
例として、固定資産税評価額が1,000万円、新築日が昭和38年(1963年)12月31日の住宅を取得したケースで不動産取得税を計算してみます。
- 1,000万円 × 3% = 30万円
- 30万円 – 3万円 = 27万円
よって、このケースでは不動産取得税額が3万円減額されるとわかります。
土地に対する控除
土地に対する控除が適用されるためには、以下の条件を満たさなければなりません。
| 土地を先に取得した場合 | 土地を取得し3年以内に、当該土地に住宅が新築されていること ※次の①②のいずれかに該当する場合に限る |
| ① 土地の取得者が、住宅の新築までその土地を引き続き所有していること | |
| ② 土地の取得者からその土地を取得した方(前の所有者)が住宅を新築したこと | |
| 新築住宅を先に取得した場合 (同時取得を含む) | ① 住宅を新築した方が、新築後1年以内にその土地を取得していること |
| ② 新築未使用の住宅とその敷地を、新築後1年以内(同時取得を含む)に同じ方が取得していること |
参照元:主税局「不動産取得税 Q.14」
なお、物件が先述した新築住宅に対する軽減措置の条件を満たしていないと、土地に対する控除も適用されないため注意が必要です。
土地の不動産取得税額は、「(土地の固定資産税評価額 × 1/2)×3% – 減額額(AとBのいずれか高い方が適用)」で算出します。
※固定資産税評価額が1/2になるのは、宅地等を取得した場合に限ります。
A:4.5万円
B:(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2 ) × 住宅の床面積の2倍(一戸当たり限度200㎡) × 住宅の取得持分 × 3%
例えば土地面積が200㎡で住宅床面積が150㎡、土地の固定資産税評価額が1,500万円、住宅の取得持分が100%だったとしましょう。
まずは土地1㎡当たりの評価額を求めます。
固定資産税評価額(1,500万円 × 1/2) ÷ 土地面積200平方メートル = 3.7万円(1,000円未満切り捨て)
次に、減額額を算出します。
3.7万円(土地1㎡当たりの評価額) × 200㎡(住宅の床面積150㎡×2=300㎡になるので200㎡とする)× 100% × 3%=22.2万円(1,000円未満切り捨て)
この場合はAよりもBの方が高いので、減額額は22.2万円が採用されます。
【軽減措置を受けなかった場合】
1,500万円 ×1/2 × 3%=22.5万円
【軽減措置を受けた場合】
1,500万円 × 1/2 × 3%-22.2万円=3,000円
このケースでは軽減措置の適用によって、不動産取得税が22.5万円から3,000円に軽減され、実に22.2万円もの減税効果があることがわかります。
軽減措置を受けるときには申請が必要
不動産取得税の軽減措置の適用を受けるためには、申請が必要です。本項では、以下の3つを解説します。
- 必要書類
- 不動産取得の申告は原則60日以内
- 不動産取得税は納税通知書が届いたら支払う
特に不動産取得の申告を忘れると、過料が科されるケースもあるので申告漏れには注意が必要です。
必要書類

必要書類は各自治体・不動産の種類によって異なりますが、主に以下の書類を求められることが多いです。
| 書類名 | 概要 |
|---|---|
| 不動産取得申告書 | 正式名称は「不動産取得税課税基準の特例適用申告書」という。建物と土地、それぞれの用意が必要。 |
| 不動産取得税の納税通知書 | 不動産の取得から半年〜1年経過すると、都道府県より送付される。 |
| 土地と住宅の売買契約書 (住宅引渡証書) | 工事完了後に、不動産取得者へ住宅を譲渡する内容が記載された契約書。 登記申告の際にも必要な書類。 |
| 住宅の登記事項証明書 (もしくは登記薄謄本) | 登記簿に記録された登記記録をデータ化した証明書。 登記簿謄本でも代用可能。 |
不動産取得の申告は原則60日以内
不動産取得の申告は、取得日から60日以内に行う必要があります。ただし、東京都は30日以内と定められています。正当な理由なく申告が遅れた場合は過料を科す自治体もあるので、申告期限は厳守しましょう。
申告は取得した不動産が所在する都道府県税事務所で行います。必要書類を持って直接税事務所に出向く方法と、郵送の2つの申請方法があります。
不動産取得税は納税通知書が届いたら支払う
不動産取得税は納税通知書が届いてから支払います。納税通知書は、申告後おおむね4ヵ月〜1年後に届きます。
納税通知書には、納めるべき税額や納付期限が記載されているので必ずチェックしましょう。なお、納付期限は自治体によって異なるので注意が必要です。一般的には、納税通知書が届いてからおよそ1ヵ月後に設定されています。
支払い方法は自治体によって異なりますが、一般的には以下の方法があります。
- スマートフォン決済アプリ(PayPay、楽天Payなど)
- クレジットカード
- ペイジー(インターネットバンキング・ATM)
- 金融機関・郵便局の窓口
- コンビニエンスストア
※納付書1枚あたりの金額が30万円までの納付書に限る
参照元:主税局「不動産取得税Q.10」
具体的な支払い方法や、各支払い方法の利用条件は、納税通知書に同封されている案内を確認するか、各自治体のWEBサイトで確認してください。
不動産取得税がかからない5つのケース
そもそも、不動産取得税がかからないケースもあります。本項では、不動産取得税が課税されない5つのケースを解説します。
- 相続で不動産を取得したとき
- 学校法人や社会福祉法人が事業用に不動産を取得したとき
- 法人の合併もしくは分割で不動産を取得したとき
- 公共の用に供する道路や土地、土地区画整理の換地の場合
- 取得した不動産の固定資産税評価額が免税点未満のとき
ご自身がこれらのケースに該当していないか、確認しましょう。
相続で不動産を取得したとき
不動産を相続で取得した場合、原則として不動産取得税は課税されません。相続は売買・贈与と異なり、形式的な所有権の移動としてみなされるためです。
ただし、生前贈与は「贈与」とみなされるため不動産取得税が課税されます。また、法定相続人以外への遺贈は、特定遺贈、包括遺贈のどちらであっても不動産取得税の課税対象となるため注意が必要です。
特定遺贈とは、財産を指定して遺贈することです。例えば、「友人には自宅を譲りたい」という場合には、特定遺贈を活用して相続を行います。
特定遺贈で財産を指定する際は、遺言書に財産を具体的に特定して記載する必要があります。記載例は以下のとおりです。
- 土地:〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇所在の土地
- 預金:〇〇銀行〇〇支店の普通預金口座(口座番号〇〇)
上記のように財産の種類、所在地、数量などを明確に記述することで、遺贈対象となる財産を他の財産と区別できるようにします。
一方、包括遺贈とは「全財産の1/2を遺贈する」など、財産の全部または一定の割合を指定して遺贈することです。包括遺贈の場合、法定相続人であれば不動産取得税は課税されませんが、法定相続人以外への包括遺贈は課税対象となります。
法定相続人以外への遺贈は、特定遺贈と包括遺贈いずれも不動産取得税が課税されると覚えておきましょう。
学校法人や社会福祉法人が事業用に不動産を取得したとき
学校法人・社会福祉法人などが本来の事業を目的に不動産を取得した場合も、不動産取得税は課税されません。
例えば、学校法人が校舎や体育館、グラウンドなどの教育施設として使用する不動産を取得する場合や、社会福祉法人が特別養護老人ホームや児童養護施設などの福祉サービス提供のために使用する不動産を取得する場合が該当します。
ただし、本来の事業とは異なる用途のために取得した不動産は不動産取得税が課されるので注意が必要です。
具体的には、学校法人が収益事業用の賃貸マンションとして使用するために不動産を取得した場合や、社会福祉法人が職員の福利厚生施設として保養所を建設するために不動産を取得した場合は、課税対象になると考えられます。
法人の合併もしくは分割で不動産を取得したとき
法人が合併した場合や分割によって不動産を取得した場合も、不動産取得税はかかりません。実質的な不動産の名義変更や、包括的な事業の移転とみなされるためです。
ただし分割の場合は、分割の形態や状況によって不動産取得税の課税・非課税の取り扱いが異なるため注意が必要です。
東京都主税局「会社分割に係る不動産取得税の非課税措置について」によると、法人の分割による不動産取得税の非課税措置を受けるためには、原則として以下の要件を満たす必要があります。分割の要件は、大きく分けて「1.分割型分割と分社型分割それぞれの要件」と「2.共通要件」の2つに分類され、両方を満たす必要があります。
1.分割型分割と分社型分割それぞれの要件
| 分割型分割 | ① 分割対価資産として、分割承継法人の株式以外の資産が交付されないこと ② 当該株式が分割法人の株主等の有する当該分割法人の株式の数の割合に応じて交付されるもの |
| 分社型分割 | ① 分割対価資産として、分割承継法人の株式以外の資産が交付されないこと |
参照元:主税局「会社分割に係る不動産取得税の非課税措置について」
分割型分割とは、会社を分割する際に事業を引き継ぐ会社(承継会社)が、分割する会社(分割会社)の株主に対して、事業の対価として主に自社(承継会社)の株式を渡す方法です。分割後、分割会社の株主は承継会社の株主にもなります。
一方、分社型分割とは承継会社が、分割会社に対して分割代価を支払う方式です。分割後、分割会社は承継会社の株主を保有するため、多くのケースでは親会社(分割会社)と子会社(承継会社)の関係になります。
つまり、承継会社の株式を分割会社の株主に渡すのか、分割会社そのものに渡すのかの違いといえるでしょう。
2.共通要件
分割型分割と分社型分割どちらの場合でも、以下3つの共通要件を満たす必要があります。
- 当該分割により分割事業にかかる主要な資産及び負債が分割承継法人に移転していること
- 当該分割に係る分割事業が分割承継法人において当該分割後に引き続き営まれることが見込まれていること
- 当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね 100 分の 80 以上に相当する数の者が当該分割後に分割承継法人に従事することが見込まれていること
参照元:主税局「会社分割に係る不動産取得税の非課税措置について」
1の要件は、分割する事業の中心となる財産や借金が、分割会社から承継会社に移転する必要があるということです。つまり、一部の資産や負債を移すだけでは1の要件は満たされません。
2の要件は、承継会社が分割会社から引き継いだ事業をその後も継続していく見通しがあることを意味します。一時的に事業を引き継ぐだけでは、2の要件は満たされません。
3の要件は、分割会社の事業で働いていた従業員の大部分が、分割後も引き続き承継会社で働く予定であることを意味します。例えば、100人の従業員がいた場合、少なくとも80人は承継会社で雇用しなければいけません。
詳細な要件は、分割の形態によって異なりますので、事前に税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
公共の用に供する道路や土地、土地区画整理の換地の場合

公衆用道路(不特定多数の方が利用する私道)の取得時も不動産取得税はかかりません。
また、換地によって取得した土地も不動産取得税の課税対象外です。換地とは、土地区画整理事業などで、新しく割り当てられる土地を指します。
取得した不動産の固定資産税評価額が免税点未満のとき
取得した不動産の固定資産税評価額が免税点未満の場合は、不動産取得税はかかりません。不動産の種類ごとの免税点は下記のとおりです。
| 不動産の種類 | 免税点 |
|---|---|
| 土地 | 10万円 |
| 家屋 (新築・増築・改築) | 23万円 |
| 家屋 (その他売買など) | 12万円 |
参照元:主税局「不動産取得税 Q.7」
おわりに
不動産取得税は、個人・法人を問わず、不動産を取得した際に一度だけ支払う地方税です。
しかし、一定の条件を満たすことで軽減措置が適用され、固定資産税評価額が控除されたり、税額が減額されたりします。
軽減措置の適用を受けるためには、必要書類の提出や申告期限を守ることが重要です。
不動産はそもそも取得費用が高額になりやすいため、銀行などの住宅ローンを活用して費用負担を抑える方が多いでしょう。
クレディセゾンが提供している「セゾンのフラット35(保証型)」は、自己資金が多いほど低金利が適用されるのが特徴です。例えば、自己資金が10%の場合の適用金利は年1.49%ですが、40%以上になると年1.39%まで金利が下がります。
不動産購入の予定がある方は、ぜひ「セゾンのフラット35(保証型)」も検討されてはいかがでしょうか。
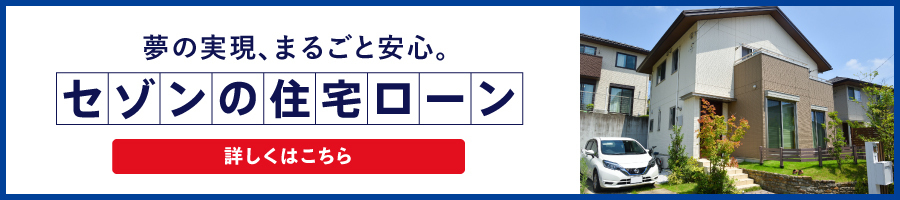
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。






























