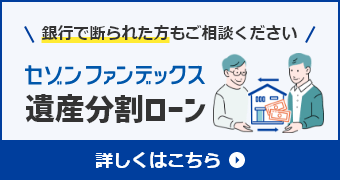相続が発生した際、それぞれの財産を相続人で分割しますが、不動産はその性質上、物理的に分けることは難しいです。そのため「共有持分」として相続されることも多いですが、税金や維持費などの支払いでトラブルに発展するケースは珍しくありません。
結論として、共有持分として相続した不動産の固定資産税は、共有者全員が負担するのが原則です。しかし、実際の納税は代表者が行うため、他の共有者に負担を求めても支払いに応じてもらえない場合があります。
この記事では「共有持分の固定資産税」について、基本的な仕組みや起こりやすいトラブル例を解説します。今後不動産の相続が見込まれる方は、事前に情報を把握しておきましょう。
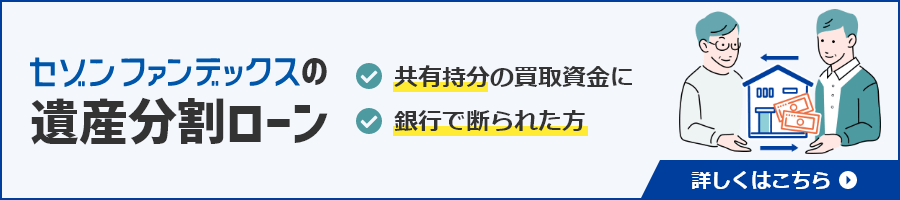
共有不動産の固定資産税は全員が負担する義務がある

不動産を共同所有する場合、すべての共有者が固定資産税を負担しなければなりません。ここでは以下の2点を解説します。
- 納税通知書は代表者に届く
- 共有持分に応じて固定資産税を負担する
今後、相続で不動産を共有する予定がある方は、参考にしてください。
固定資産税の納税通知書は代表者に届く
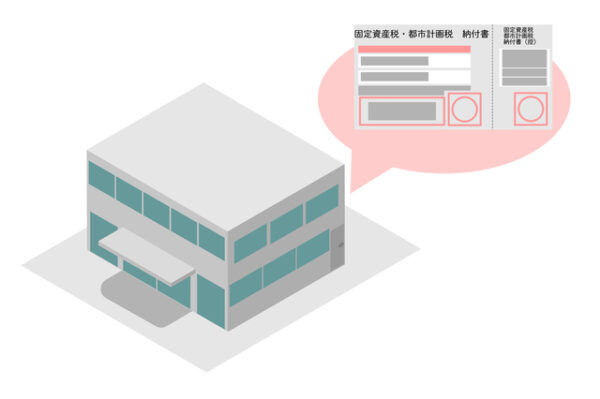
2名以上で不動産を共有する場合、所有者の中から代表者を設定します。代表者には固定資産税の納税通知書が送付され、共有者の分も含めて全額を納める必要があります。
相続で不動産を共有するケースでは、自治体から届く「相続人代表者指定届」を返送すると代表者が決定します。なお、代表者を指定しない場合は、自治体が以下の項目を基に決定します。
- 持分割合が多い方
- 対象の物件に居住する方
- 対象物件の所在地に居住する方
- 登記簿の登録順位が早い方
ただし、代表者の決定基準は自治体ごとに異なります。「相続人代表者指定届」を返送しなかった場合は、決定基準を各自治体に問い合わせるのがおすすめです。
共有不動産の固定資産税でよくあるトラブル例
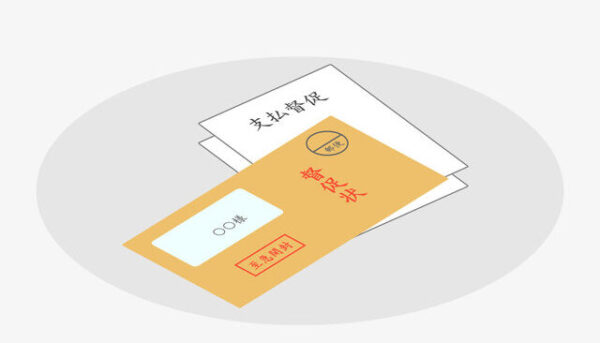
不動産を複数人で共有すると、金銭面でのトラブルが起こりがちです。ここでは代表的な事例を具体的に紹介します。
- 共有者が固定資産税の支払いに応じてくれない
- 共有者が死亡した
- 共有者が持分を売却した
今後の相続で共有を検討する際は、以下のような可能性があることを把握しておきましょう。
共有者が固定資産税の支払いに応じてくれない
固定資産税はすべての共有者に負担義務がありますが、現実には支払いを拒否されるケースも少なくありません。
例えば、すでに共有状態にある不動産で、特定の共有者がこれまで単独で納税していた場合、新たに負担を求めても応じてもらえないことがあります。また、一方の共有者が物件に住み、もう一方が使用していない場合、「住んでいないのに支払う理由がない」と拒否されることも考えられます。
こうしたトラブルを防ぐため、不動産を共有する前に他の共有者の有無を調査し、税金や維持費の負担方法について話し合っておくことが重要です。
なお、納税義務があるにも関わらず支払いに応じてもらえない場合、代表者が肩代わりした分を「求償権」によって請求できます。求償権とは、他人の債務を支払った人が後からその相手に費用を請求できる権利のことです。例えば、代表者が固定資産税を納めると、他の共有者の債務を肩代わりした形になるため、この権利を行使できます。求償権は以下の方法により行使するケースが一般的です。
- 相手に直接交渉する
- 内容証明郵便を送付する
ただし、求償権には時効が成立するケースもあるため、必ずしも全額を請求できるわけではありません。
話し合いで解決できない場合は、調停や訴訟なども検討してみてください。
共有者が死亡した

不動産の共有者が死亡すると、その持分は相続人が引き継ぎます。これにより、面識のない方が新たな共有者となるケースもあり、固定資産税の負担に関してトラブルが発生する可能性があります。
例えば、親族と不動産を共有していた場合、その親族が亡くなると持分は配偶者や子どもに引き継がれます。相続人が遠方に住んでいたり、面識がなかったりすると、突然の税金負担に抵抗されることもあります。また、これまで固定資産税をすべて支払っていた共有者が亡くなると、新たな共有者から支払いを求められ、思わぬトラブルに発展することも考えられます。
特に、共有者が高齢であったり、持分が多かったりする場合は、相続後の混乱を防ぐために、遺言書の作成や生前贈与などを前向きに検討することが重要です。
共有者が持分を売却した
不動産の共有持分は売却できますが、その際は以下の点に注意が必要です。
- 新たな共有者と固定資産税の負担割合を決めなければならない
- 修繕や維持の費用についての話し合いが必要になる
- 不動産全体の売却や賃貸時の意思決定が難しい
特に、不動産買取会社や血縁関係のない第三者に持分を売却すると、関係構築が難しく、合意形成に時間がかかることがあります。
なお、共有持分を売却する際、他の共有者には優先購入権があります。第三者に売却される前に、自分で買い取ることでトラブルを回避する選択肢も考慮しましょう。
固定資産税のトラブル以外にも不動産を共有する際に注意すべき点
不動産を共有する場合は、以下の点にも注意が必要です。
- 売却には共有者全員の同意が必要となる
- 持分割合に関係なく物件を利用できる
不動産の共有にトラブルは付き物なので、相続前に注意点を確認しておきましょう。
売却には共有者全員の同意が必要となる
共有不動産を売却する際は、共有者全員の同意が必要です。たとえ自分の持分が他者より多くても、全員の合意がなければ売却はできません。また、物件の価値を高める修繕や設備追加といった「管理行為」は、共有者の持分の過半数の合意が必要となります。
一方で、自分の持分のみに関しては単独で売却することが可能です。さらに、共有不動産の現状を維持する「保存行為」は共有者単独でも行えます。建物の屋根や外壁等の修繕など、現状維持のための行為であれば実施可能なケースが多いでしょう。
持分割合に関係なく物件を利用できる
不動産を共有している場合、共有持分の割合に関わらず、共有者はその物件のすべてを使用できます。共有持分の少ない共有者が不動産を専有しても、賃料の請求はできますが明け渡してもらうことは基本的にできません。
また、占拠している共有者と「使用貸借契約」を結んでいる場合は、賃料請求もできません。たとえ契約を結んでいなくても、長期間黙認すると無償使用を認めたと見なされ、使用賃借契約が成立したと判断されるおそれがあります。ご自身では利用できない状態の共有不動産に対し、費用だけが生じることになってしまいます。
他の共有者に一方的に使用されないためには、共有名義にする前にしっかりと取り決めを結ぶことが重要です。
不動産の共有トラブルを回避・解消する方法
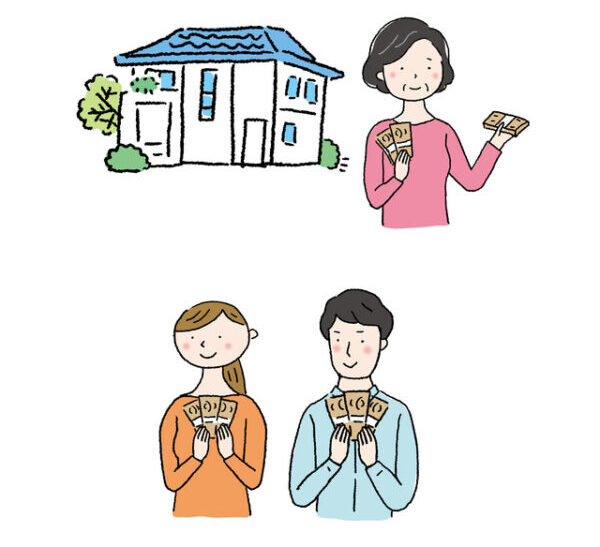
相続で不動産を共有すると、後々大きなトラブルに発展するケースは少なくありません。無用なトラブルを避けたい場合は、そもそも不動産を共有を回避・解消する方法を検討するのも一案です。
不動産共有を回避・解消するための方法は、以下のとおりです。
- 相続前|相続放棄する
- 相続後|共有持分を買取・売却する
- 相続後|リースバックを利用する
順番に解説します。
相続前|相続放棄する
相続により意図せず不動産の共有者となる場合は、「相続放棄」により自分の持分を手放しトラブルを回避することが可能です。
相続放棄とは、すべての財産や負債の相続を放棄することを指します。これにより不動産を他者と共有する事態を避けられますが、他の財産もすべて放棄することになる点には注意が必要です。そのため、相続放棄は相続財産に負債が多い場合に利用されるケースが一般的です。
相続放棄するためには、被相続人(死亡した方)が住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に申請します。その際に必要になる書類は主に以下のとおりです。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 相続放棄申述書 | ・裁判所のホームページで書類の取得が可能 ・記入例(成人・未成年) |
| 被相続人の住民票除票または戸籍附票 | ・被相続人の死亡時の市区町村役場で取得可能 |
| 相続放棄する方の戸籍謄本 | ・市区町村役場で取得可能 |
| 被相続人の戸籍謄本 | ・被相続人の配偶者や子またはその代襲者が申請する場合:被相続人の死亡が記載されている戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 ・被相続人の直系尊属(父母や祖父母)や兄弟姉妹またはその代襲者が申請する場合:被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 ・被相続人の死亡時市区町村役場で取得可能 |
必要書類は被相続人と相続放棄する方の関係により異なるため、詳しくは裁判所のホームページを確認してください。
なお、相続放棄は相続があることを知った日から3ヵ月以内の届出が必要です。
参照元:裁判所「相続の放棄の申述」
相続後|共有持分を売却する
相続時に共有持分を買取や売却することにより、不動産の共有によるトラブルを避けられます。
不動産は性質上分割することができないため、相続人が共同で所有することになります。実際に住んでいるのはひとりでも、納税義務はすべての共有者にあるため、使用していないにも関わらず費用負担を求められる可能性もあります。
不動産を使用する方が決まっている場合は、共有持分を使用する方に売却することでトラブル回避が可能です。また、共有者から持分を買い取る場合は資金が必要になりますが、親族間の売買は不正を疑われるため、銀行での融資は難しい傾向にあります。そのため、後述する「遺産分割ローン」の活用がおすすめです。
また、共有持分を買取会社などに売却する場合は、以下の点に注意してください。
- 買取価格が安くなるケースが多い
- 他の共有者とトラブルに発展する場合がある
- 契約条件が不利になる可能性がある
なお、売却時は譲渡所得税や登録免許税がかかる可能性があります。
相続後|リースバックを利用する
リースバックとは不動産を一旦売却し、その後は賃貸として住み続ける手法です。これにより、転居することなく不動産を現金化し、共有者間で売却金額を分割できます。
被相続人が相続人と同居していた場合は、引き続き住み続けるケースが多々あります。一方、居住しない相続人でも共同所有すると固定資産税の納税義務が発生するため、居住者に負担を求められる可能性もあるでしょう。
リースバックを利用して住宅を売却すると、共有持分が消滅する他、相続した不動産を公平に現金で分けられるためトラブル回避につながります。
セゾンファンデックスでは、リースバックに関する無料相談を受け付けています。気になる方はお気軽にご相談ください。


おわりに

不動産を共有する場合、固定資産税は共有者全員で負担します。固定資産税の負担割合は共有持分に基づき決められますが、共有者間の話し合いでも決定が可能です。
なお、通常は代表者に納税通知書が送付され、納税も一括で行います。
納付期限を過ぎた場合は延滞税を求められるケースもあるため、忘れずに納付しましょう。
不動産を複数人で共有すると、共有者の死亡や売却などによって所有者が途中で変わることがあります。結果、固定資産税の納税を拒否されたり、必要以上に負担を求められたりするトラブルが起こることも考えられるでしょう。
無用なトラブルを回避するためには、相続時に不動産を共有しない選択も必要になります。その際は、相続放棄や共有持分の売却などを専門家へ相談するのもよいでしょう。まずは自分の状況を整理することが重要です。
共有状態を解消するための資金調達にはセゾンファンデックスの遺産分割ローンがおすすめです。
遺産分割ローンは、銀行の融資が難しい親族間売買にも利用可能です。不動産の担保価値を重視する審査方法のため、信用力の問題で銀行の審査に通らなかった方にも融資を行っています。相続でのトラブルを回避したい方は、共有持分の買取や売却に利用できる「遺産分割ローン」を検討してみてください。
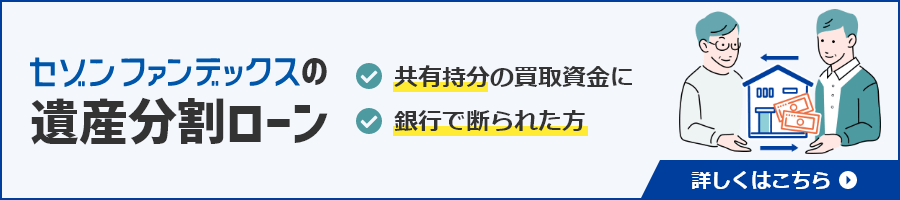
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。