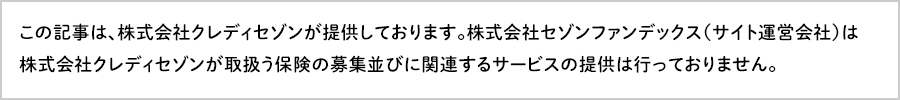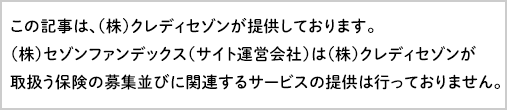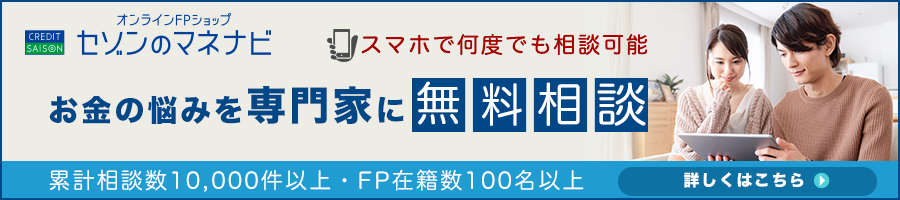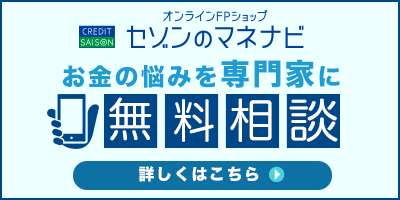相談者の悩みに真摯に向き合い、老後まで見据えたマネープランを作成し助言を行うなど、お金の面で人生の伴走者となってくれる「ファイナンシャルプランナー(FP)」。“貯蓄から投資へ”と叫ばれるなか、そんなFP自身はどのような資産形成に取り組んでいるのでしょうか。
社会保険労務士法人エニシアFP代表の三藤桂子さんが自身の経験を交えて、おすすめの資産形成方法について解説します。
就職→結婚→出産と、「順風満帆」な人生のはずが…

現在はFPと社会保険労務士の二刀流でさまざまな相談を受けている筆者ですが、社会人として初めて就いた職業は公務員でした。ちょうどバブルが崩壊したタイミングだったこともあり、「定年退職まで安泰の職業につけた」と内心ホッとしたものです。
5年後に結婚し、仕事・プライベートともに順風満帆な人生!と思いきや…詳しくは語れませんが、お金の苦労はいつもついて回っていました。
2人の子どもに恵まれましたが、事情により退職。仕事が上手くいかないと家庭内の風向きも怪しくなり、やがて離婚することになりました。
シングルマザーとして、ゼロからの再出発
厚生労働省の2021(令和3)年度「全国ひとり親世帯等調査結果の概要」※1によると、ひとり親家庭の「母」の平均年収は272万円、世帯全員の平均年収は373万円となっています。私自身も児童手当と児童扶養手当をあわせて、ようやく平均と同じくらいの収入でした。
また、子どもが大きくなるにつれて、教育費の負担はよりいっそう重くのしかかっていきます。いま思えば、経済的にはかなり苦しい状況にありました。生活費はできるだけ切り詰め、節約は当たり前。自宅近くにある野菜の無人販売所にもよくお世話になりました。地元の農家さんがつくった新鮮な野菜を安く購入でき、とてもありがたかったです。
資産形成を始めたきっかけ
立ち直るまでの約10年はなにもやる気になれず、子育てをしながらただ仕事をこなすだけの毎日を送っていましたが、奮起のきっかけとなったのは資格の勉強です。
「お世話になった人に恩返ししたい」「頑張る姿を子どもたちに見せたい」と猛勉強し、いくつかの資格をゲットしました。その集大成が、お金の専門家であるファイナンシャルプランナー(FP)と社会保険労務士(社労士)の資格でした。
しかし、お金に詳しいだけでは仕事になりません。まずは自分自身で実証する必要があると考え、FPの資格を取った49歳のタイミングで資産形成をスタートさせました。
初めての資産形成は、「NISA」と「iDeCo」から

資産形成を始めた当時は、子どもたちが大学生となり、もっとも教育費のかかった時期です。
幸いなことに、同じタイミングで給付型の奨学金制度がはじまり、とても助かりました。とはいえ、学費を全額賄えたわけではありません。つまり、積立に回せる金額はほんのわずかです。
そこで、初めての資産形成は、「つみたてNISA」と「iDeCo」を選びました。それぞれ月1万円ずつ、計2万円の積立でも当時の私にとっては苦しいものでしたが、振り返ってみるとたしかにメリットが大きかったと感じます。
「NISA」なら少額でも積み立てられる
「NISA」は、私のように少額しか投資できない人にもおすすめの資産形成方法です。
少額で始められ、非課税であることから、つみたて投資枠(旧つみたてNISA)は貯蓄ができないと諦めている人でも手が届きます。金融機関によりますが、月100円からの積立が可能です。
もうひとつの「iDeCo(個人型確定拠出年金)」も非課税で、かつ掛金の全額が所得控除の対象となり、所得税や住民税の負担が軽減されることから、初めての資産形成におすすめです。ただし、iDeCoは60歳まで解約することができないため、注意しましょう。
自宅のリフォームを迫られ「大ピンチ」も…“コツコツ”が救いに

FPと社労士の二刀流として事務所を開業したのは、50歳になってからです。資格を取得したからといって、すぐに売上につながるというものではありません。収入が安定するまでは、副業として業務にあたっていました。
自己投資をするために、本業と副業のほかにさらに仕事をして、トリプルワークをしていた時期もあります。その後、FPと社労士の仕事を通じてさまざまな人とのご縁が生まれ、少しずつ売上につながるようになりました。
相談者のバックグラウンドはさまざまです。なかには、私のように日常生活が厳しく、なかなか貯蓄ができない母子家庭の人からの相談もあります。
厚生労働省が2019年に行った調査によると、貯蓄があると答えた世帯のうち、児童がいる1世帯あたりの平均貯蓄額は約723万円です。全世帯の平均貯蓄額は約1,077万円、高齢者世帯は約1,213万円、母子世帯は約389万円となっています※2。
また、「貯蓄がない」と答えた母子世帯は母子世帯全体の31.8%にものぼります。母子世帯の貧困と、それにともなう子どもの貧困は、深刻な社会問題となっていることがわかるでしょう。
FPと社労士としての仕事が軌道に乗ってきたところ、新たな問題が出てきました。
それは「リフォーム」です。離婚したときから、負担付贈与で住宅ローンを払い続けていた自宅は、すでに築20年が経過していました。同時期に建ったご近所さんの外壁はきれいに塗り替えられていますが、我が家の外壁は色あせています。
そのころには2人の子どもも大学を卒業し、教育費の負担からは解放されていたものの、「もう少し余裕が出るまでは」と先送りにしていました。しかしある日、「屋根が2枚剥がれている。このままでは雨漏りする危険性がある」と指摘を受けたのです。
リフォーム業者に相談したところ、さらに「外壁の目地も数ヵ所剥がれています。屋根を直すなら、外壁も一緒に直したほうが1回で済みますよ」と言われてしまいました。
屋根と外壁の修理と防水で、見積額は270万円。教育費負担が終わったばかりの我が家には、非常に厳しい金額でした。
とはいえ、そのままにしておくわけにはいきません。どうやって予算を捻出するか、私は悩みました。iDeCoは老齢給付金として受け取ることが目的になっていることから、原則、途中で解約することができません。
他方、NISAを使って少しずつ積み立ててきた資産を確認したところ、5年6ヵ月で評価損益率※は平均70%になっていました。もったいないと思いましたが、これを一部解約することで、家のリフォームにあてることができました。
※一般に信用取引残高の買残高に対する評価損益の割合のことを指します。
NISAとiDeCoの「二刀流」で、金銭的な不安はぐっと減らせる
ただ銀行に預けているだけなら、リフォームはできていなかったと思います。仕事をきっかけに始めた資産形成ですが、少額でも長期の積立を続ければ将来大きな資産になることを自分自身で実証できた形です。FP・社労士になって本当によかったと嬉しく感じています。
NISAやiDeCoは運用益が非課税で再投資でき、iDeCoはさらに掛け金が全額控除、受け取るときも大きな控除があります。NISAとiDeCo両方に取り組むことで、もしものときの備え(NISA)と老後の備え(iDeCo)がどちらも叶います。
NISAは子どもが独立してから積立金額を増やし、iDeCoは金額を増やすことなく、いまも細々と続けています。iDeCoは5年7ヵ月続け、損益率は53%(2024年12月現在)です。
私が資産形成を始めたきっかけは「仕事」でしたが、きっかけは人それぞれ。ぜひ、少額でも自身の備えのために実践してみることをおすすめします。
<参考・出典>
※1 厚生労働省「2021(令和3)年度 全国ひとり親世帯等調査結果の概要」
※2 厚生労働省「2019年 国民生活基礎調査の概況」
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。