2024年に「新NISA」がはじまって以降、投資を始める人が急増しました。一方、そのような状況でも「聞いたことはあるけれど、いまいちよくわからない」と、まだ始められていない人も少なくありません。ただ、それではあまりにも「もったいない」といえる状況になってきました。。
そこで今回は、「新NISA」の仕組みと利用時の注意点を見ていきましょう。15年間の証券会社勤務を経て、現在はJ-FLEC(金融経済教育推進機構)の講師としても活動するCFPの倉橋孝博さんが解説します。
運用して得た利益は「全額もらえる」わけではない

いきなりですが、問題です。あなたが、ある投資信託を毎月2万円(年間24万円)、30年間購入し続けたとしましょう。すると、24万円×30年で合計720万円の買い付け金額になります。
仮に、その投資信託が平均年3%の運用利回りを確保できたとします。さて、720万円の買い付け金額は30年後、いくらになっているでしょうか?
答えは、1,141万円。30年で421万円増えました。400万円超というと、ちょっといい車が買えてしまう値段です。
では、この421万円増えた投資信託を、すべて売却するとしましょう。その際、1,141万円全額が手元に入ってくるかというと、そうではありません。増えた421万円には約20%の税金がかかるので、そのうち84万円強が差し引かれてしまいます。
84万円といえば、国家公務員のボーナス1回分程度。無条件で差し引かれるにしては大きな額でしょう。
そこで、この「20%の税金」がかからない仕組みがあったとしたら、どうでしょう。もしあるのなら、利用しなきゃ損! ですよね。この税金がかからない仕組みが、実際に存在します。それが「NISA」です。
改正後、使い勝手がよくなった「新NISA」
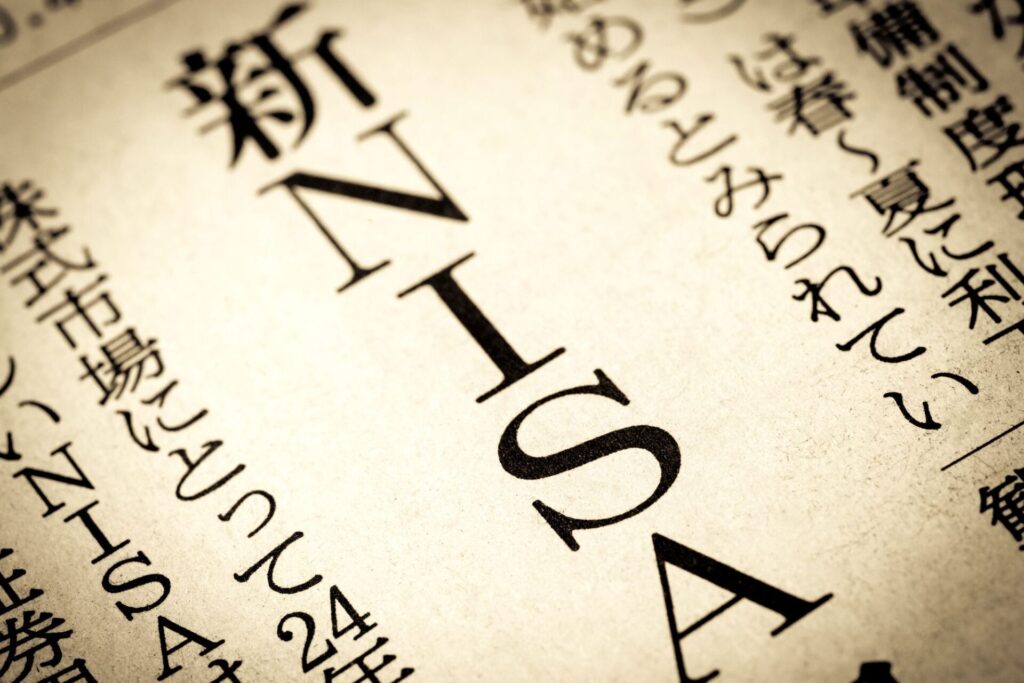
NISAは2024年にリニューアルされ、とても使い勝手がよくなりました。「新NISA」とも呼ばれます。
旧NISAで設けられていた非課税保有期間が新NISAでは無期限になり、NISA口座で投資信託や株を購入すれば、10年・20年・30年…と保有しているあいだずっと、税制面で優遇を受けられるのです。
前述の例を考えると、NISA口座で投資信託を行えば、利益の421万円を売却しても、84万円強の税金はまったくかかりません。
また、分配金も非課税です。たとえば、1万円の分配金が出た場合、通常であれば約20%(2,000円強)の税金が差し引かれ、手元に残るのは8,000円弱になります。しかし、NISA口座であれば1万円をまるまる受け取ることができるのです。
だんだんと「NISA、使わなきゃ」という気持ちになってきたのではないでしょうか。
「つみたて投資枠」は少額から始められていつでも換金可能

新NISAには、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2種類があります。
「つみたて投資枠」は、皆さんが「これはお金が増えそうだな」と思った投資信託を選び、定期的に(たとえば月に1度)買い続けるというスタイルです。1年間に購入できる上限は120万円なので、仮に月に1度であれば、毎月10万円ずつ買い付けることができます。
もちろん、この金額は皆さんのマネープランにあわせて設定してください。金融機関によっては、100円以上1円単位で始めることができます。
お子さんの教育費がかさむ時期は投資額を減らし、大学を卒業して手が離れたら増額するなど、ライフステージに合わせた運用ができます。また、場合によっては買い付けを休止することも、急に現金が必要になった場合には売却も可能です。
投資信託の選び方
「投資信託は買ったことがないから、どれを選んだらいいのかわからない」という人も多いでしょう。安心してください。「つみたて投資枠」では、金融庁がオーソドックスでわかりやすい銘柄をピックアップしています。
簡単にいうと、「これからは日本が巻き返す」と思えばTOPIXや日経平均株価などに連動する銘柄を、「やっぱり世界をリードするのはアメリカでしょう!」と思えばS&P500と同じような動きをする銘柄を、「20年以上運用するのが前提なのでバランスが大切だ」と考える人は世界の株で運用する銘柄を選ぶといいでしょう。
現在アメリカや世界の株が人気ですが、新興国株などリスクがある分、より良いパフォーマンスを目指して運用する銘柄もあります。銘柄は多数あり、つみたて投資枠の対象銘柄は約300本となっています。
つみたて投資枠なら、運用にかかるランニングコストも抑えられる
投資信託には、保有している間かかり続ける「信託報酬」というコストがあります。
たとえば、信託報酬が1.5%の投資信託を100万円購入した場合、仮に運用が鳴かず飛ばずの横ばいでも、年間1万5,000円ほど差し引かれてしまいます。長期投資が前提の資産運用なのに、このコストは大きな負担といえるでしょう。
しかし「つみたて投資枠」ならこの点も心配無用。「つみたて投資枠」対象商品の多くはこの信託報酬が0.5%以下に設定されており、最近では0.1%未満のものも増えています。さらに、「つみたて投資枠」では購入手数料がかかりません。
利益に対して税金がかからない、信託報酬が低い、しかも購入手数料はゼロ。新NISAのつみたて投資枠はメリットが多いといえるでしょう。
株価は常に上下する…つみたて投資で重要な「心構え」
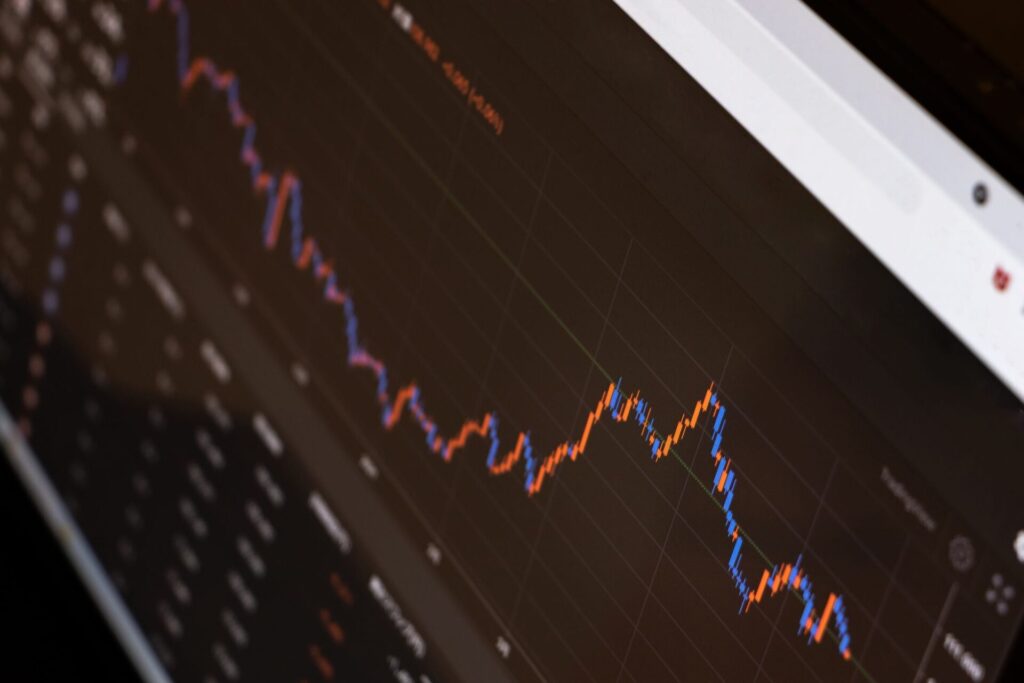
しかし、「つみたて」というワードに惑わされないでください。「つみたて投資枠」は「つみたて預金」ではなく、あくまでも投資信託を買い続ける仕組みです。
投資信託は株や債券で運用するため、常に価格が上がったり下がったりしています。
したがって、仮に毎月投資信託を買い続け、100万円購入した時点でリーマンショックのような株価大暴落に見舞われた場合、100万円だったお金は半分ほどに目減りしてしまうかもしれません。背筋が凍ってしまいますね。しかし、ここで大切なのは「長期投資」の心構えです。
わかりやすいシミュレーションがあります。2003年1月から2022年12月までの240ヵ月、毎月末に世界株式で運用する投資信託を1万円ずつ買い続けました。2008年秋にリーマンショックが訪れた際、それまでの購入金額70万円は大きな評価損を抱え、その後4年間、買い付け金額を上回ることができませんでした。
参照:金融庁「つみたてNISA早わかりガイドブック」(P.5)
しかし、経済は構造を改革し、新陳代謝を繰り返しながら成長します。リーマンショックが起きた際にも、財政出動や金融政策のバックアップがあり、株価はなんとか回復しました。そして2022年12月、トータル240万円購入した投資信託は、690万円に増えていたのです。
株は常に動くものですから、損失を被ることも多々あります。アメリカの大手企業の株価ですら、3年に1年は下落する時期があることが多いといわれています
しかし、20年以上運用していれば、過去の実績ではあるものの、おおよそ満足のいく結果になっています。「つみたて投資枠」も、運用のセオリーでは、20年以上継続していればある程度安定し、それ以降は購入金額を上回るところで上下するといったイメージです。時間を味方につけましょう。
新NISAは「株式投資の恩恵」を受けられる

また、新NISAにはもう1つ、「成長投資枠」があります。「成長投資枠」では、約2,000本の投資信託のほかに個別株も購入でき、1年間に最大240万円の買い付けが可能です。
購入方法はつみたて投資枠と異なり、1度の取引で240万円を使い切ってもいいですし、数回複数の銘柄に分けて使っても構いません。なお、金融機関によっては「成長投資枠」のなかでも「つみたて投資枠」のように、毎月コンスタントに投資信託を買い続けることもできます。
ただし、株や投資信託を購入する際の手数料が必要となる金融機関も多いため、この点は注意してください。
さて、皆さんは、株式投資にどのような魅力を感じるでしょうか。多くの人があげる魅力は「配当収益」「購入した株の値上がり益」「株主優待」の3つです。
まず「配当収益」。薬品会社Tは、100株購入するのに40万円強が必要ですが、1年間におおよそ2万円の配当金を受け取ることができます。利回りにすると5%弱になりますが、0.1~0.2%程度の預貯金金利に比べると魅力的でしょう。
もちろん、新NISAの成長投資枠で購入すれば、配当金2万円に対する4,000円あまりの税金もかかりません(注1)。
(注1)配当金の受け取り方法は株式数比例配分方式を選択。株価や配当金の額は変動するため確定したものではありません。
次に「購入した株の値上がり益」です。大手電気機器の会社Hは、2024年1月時点では100株購入するのに200万円必要でしたが、現在は400万円まで上昇しています。仮に「NISAの成長投資枠」で購入していれば、いま売却しても40万円強の税金はかかりません。
3点目の「株主優待」については、NISAによる特別な優遇は特にありません。ただ、通常の投資・NISA口座を使った投資いずれにせよ、さまざまな特典を楽しむことができます。
NISAは資産形成の心強い味方
新NISAの「つみたて投資枠」と「成長投資枠」は同時に利用することができ、合計で1,800万円まで購入が可能です(注2)。
(注2)つみたて投資枠だけで1,800万円の投資も可能。ただし成長投資枠の上限は1,200万円。
資産運用のキホンは「長期・積立・分散」。大切なのは、無理をせず気長にお金を育てることです。
「千里の道も一歩から」
20年以上かけてセカンドライフのゆとり資金を作るイメージを持つといいでしょう。NISAは皆さんの資産形成の心強い味方になってくれるはずです。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。



















