一般社団法人投資信託協会「60歳代以上の投資信託等に関するアンケート調査報告書2021年(令和3年)」によると、退職金を受け取った人のおよそ5人に1人(20.3%)は資産運用のための金融商品の購入に使うとしています。しかし、周りに流されて“なんとなく”で投資を始めると、あとで後悔するケースも…。
65歳元公務員の事例をもとに、投資を始める際の注意点と、失敗しないためのポイントを見ていきましょう。株式会社よこはまライフプランニング代表取締役の五十嵐義典さんが解説します。
老後を思い切り楽しみたい…退職金を使って「投資」を始めることに
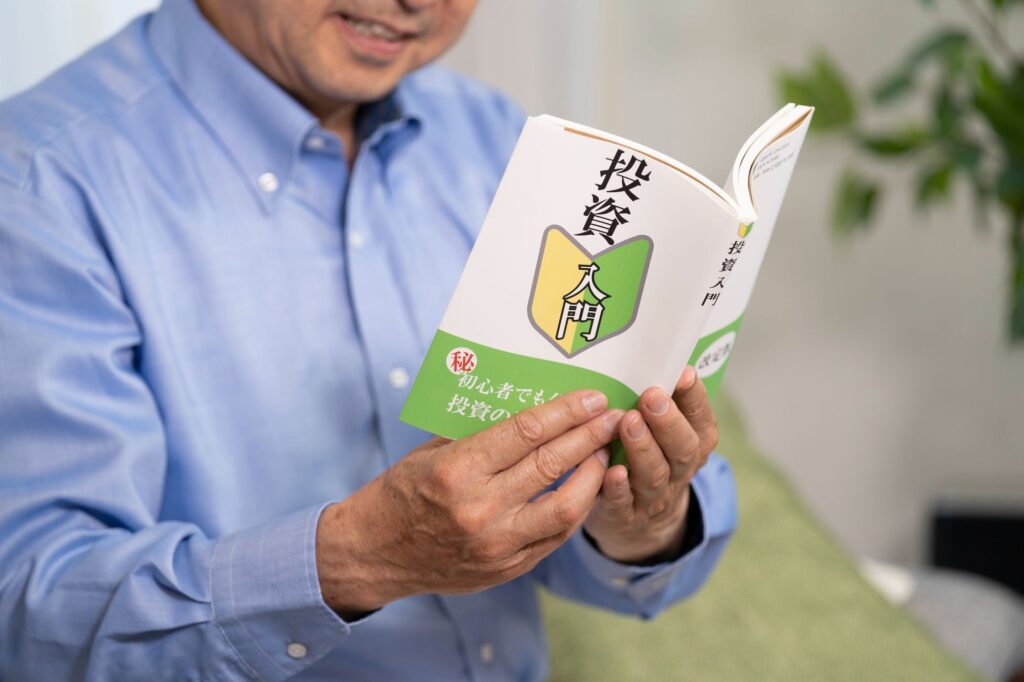
Aさんは長年公務員として職務をまっとうし、その後の再任用期間も終え、65歳から本格的な「年金生活」が始まりました。民間企業と異なり、職域加算部分(※2015年9月以前の共済組合加入期間が対象)も受けられることから、Aさんは「民間企業に勤務するより年金も多いだろう」と考えており、年金額にも不満はありません。
しかし、「退職後は趣味も旅行もめいっぱい楽しみたい」と、老後にやりたいことがたくさんあったAさんは、老後に使えるお金を増やすべく、退職金を投資に回そうと考えました。
というのも、新聞やテレビ、同時期に退職した友人の話などから投資に興味を持ち、「自分もやってみたい」と考えるようになったのです。
そこでAさんは、証券会社主催の「資産運用セミナー」に参加。講師の話に触発され、退職金の2,500万円で投資信託を購入することに。「なるべく多くリターンが欲しい」と考えたAさんは、証券会社の担当者に勧められるまま、とあるハイリスク・ハイリターンのファンドを選択。そのファンドは、運用の成果に応じて毎月分配金があるもので、「年金の足しになる」という点にも魅力を感じたのです。
ただ、毎月分配型の投資信託は新NISA対象外のため、新NISAの枠は日経平均に連動するインデックス型の投信を購入。残りの全額を毎月分配型のファンドに投資しました。
順調な滑り出しに思えたが…「突然の大暴落」に狼狽

Aさんが購入したファンドは、良好な市場環境を背景に基準価額も上昇傾向にありました。あまりにも調子がいいので「公務員として長年真面目に働き、コツコツ貯蓄を続けていたのが馬鹿馬鹿しく思えるな」と思ったほどです。
しかし、世界経済情勢の影響を受け、ある日突然基準価額が急落。それまでも多少の上下はありましたが、ここまでの暴落は予想外です。
証券会社からの連絡を受け、Aさんは青ざめるしかありません。大金を費やした投資信託は、気がついたときにはなんと300万円もマイナスになっていました。
「理想の老後を叶えるはずだったのに…。このままじゃ、さらに下がり続けるかもしれない」
Aさんは恐怖を感じるようになりました。
暴落前は基準価額の推移を見るのが日課でしたが、暴落後は恐怖でPCを開くこともできません。その後、基準価額が回復する局面もありましたが、好調だった頃はもちろん、当該ファンド購入時点の水準にすらなかなか戻りそうにありませんでした。
Aさんは頭を抱えます。
「この歳から投資なんてすべきではなかったのかもしれない。だけど…せっかく始めたのに、いま本当にやめていいのだろうか。ここで売却してしまったら損が確定してしまう。どうしよう…」
証券会社に相談するも「基準価額が下がったいまこそ買い増しのチャンスです」と言われてしまい、いまいち信用できません。
そこで、Aさんは知り合いのファイナンシャル・プランナー(FP)に話を聞きに行くことにしました。そのFPは特定の金融機関に所属しておらず、公平に話を聞いてくれると思ったのです。
投資のポイントは「時間を味方につけること」

「Aさん、投資のポイントは時間を味方につけることです」
Aさんがこれまでの一連について説明すると、FPはAさんに対し、投資の基本と投資を行う際の心構えについて説明してくれました。
「投資対象が一時的にマイナスになってしまっても、再びプラスになることも十分あります。短期的に結果が出ず、焦る気持ちもよくわかりますが、突然暴落したからといって、二度と元の基準価額に戻らないわけではありません。慌てて売却せず、冷静にどっしりと構えて、長い目で投資を続けることが重要です」
「また、Aさんが購入されたのは、日経平均に連動するインデックスファンドと、分配金が毎月分配されるタイプの投資信託です。運用会社や商品の特性によって分配金の有無や頻度が異なりますが、毎月分配型は投資額に応じて毎月分配金が支払われることになっています」
「Aさんは『毎月のお小遣いになれば』とこの分配金に魅力を感じたそうですが、ファンドの特性上、分配金を払うとその分ファンドの純資産総額が減り、基準価額の下落につながります。毎月分配型の場合、分配金が支払われる回数が多いため、価額が下がるタイミングもその分多くなるのです」
「そうなると、ひいてはファンドの複利による運用効果も弱まってしまいます。毎月分配金は収入として計算できる一方、基準価額は暴落前になかなか戻りにくいところがあります。そのため、分配金があるタイプのファンドを選んだ場合には、分配金のないファンドを持つより長期的に辛抱強く見守る必要があるでしょう」
なお、分配金には「普通分配金」と「特別分配金」の2種類がありますが、このうち「特別分配金」は「元本払戻金」とも呼ばれ、NISAでの投資でも、そうでなくても非課税となります。
ただし、この場合は元本の払い戻しを受けたに過ぎず、その分元本を減らします。
“一極集中”はキケン…Aさんの投資手法の致命的なミス

投資にあたっては、1つのファンドや商品、銘柄に集中するのではなく、分散して投資することもポイントです。投資先を分散することで、リスクを抑えながら安定したリターンを目指すことができます。
しかしこの点、Aさんは毎月分配型のファンドに退職金のほとんどをあてていました。
Aさんの投資方法では、順調なときはいいものの、そのファンドがハイリスク・ハイリターンだったこともあり、ある日を境に青ざめるほどの大暴落を直視することとなってしまいました。
リスクの高いファンドを選ぶ際には、同時にリスクの低いファンドも購入し、リスクの分散を図ることが大切です。そうすれば、たとえ1つの基準価額がマイナスになっても、そのマイナスの程度を軽減することができます。
事実、Aさんが新NISA枠で購入していたインデックスファンドの運用成績はプラスとなっていました。
また、Aさんは一度の投資に2,500万円もの大金を費やしてしまいましたが、そもそも投資は余剰資金を使うことが鉄則。毎月少額ずつ、無理なく積み立て投資を行うことが重要です。
退職金以外に貯蓄もあるAさん。これからの長い老後生活のなかで、自分や家族の病気、冠婚葬祭などで、まとまった現金が必要になることもあるでしょう。
急な支出が必要な際に、年金収入や貯蓄だけでは賄えなくなる可能性もあります。そんなときは、基準価額がたとえ暴落していたとしても、保有している投資信託を売却せざるを得ません。含み損を抱えているなかで売却すると、損が確定してしまいます。
一度に大量の資金を投資に回すことには、こうしたリスクがあることも想定しておかなければなりません。投資をする場合であってもできる限り貯蓄をし、万が一の際に備えて現金や預金を用意しておくことが重要です。
投資は「余剰資金」で長期・分散を意識…押さえておきたい投資の基本
Aさん「長期投資、分散投資、余剰資金での投資…老後の贅沢に目がくらんで、まったく考えていませんでした。改めて自分に合った投資方法で続けていきたいと思います」
すでに購入してしまった投資信託は、引き続き保有することに。焦って売却せず、基準価額の推移は長期で見守ることになりました。
また、今後の方針については、いざというときに備え、年金収入から少額でも貯蓄に回すことにし、今後もし新たに投資信託を購入することになった場合、リスクの低い複数のファンドについても無理のない範囲で少しずつ購入することにしました。
昨年大きく改正され、新NISAの認知度も高まる昨今、投資を始める際はその基本的な心構えを理解することから始めることをおすすめします。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。



















