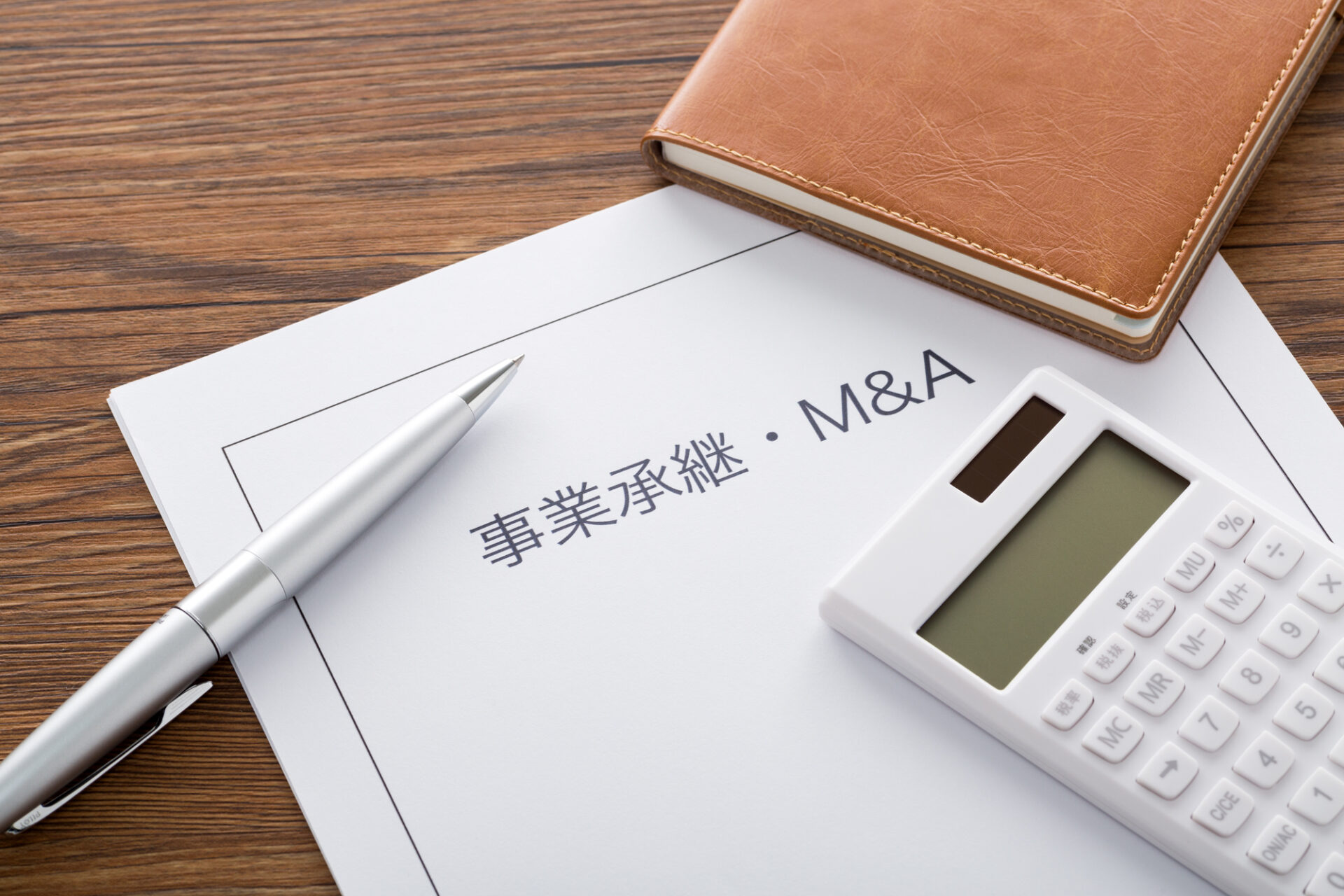企業経営において「M&A(Mergers and Acquisitions:合併・買収)」は、成長戦略や事業承継、経営課題解決の有効な手段として広く活用されています。近年は規模や業種を問わずM&A市場が活発化しています。
しかし、M&Aには数百万円から数億円、ときには数十億円規模の大きな資金が必要となるケースも少なくありません。自己資金だけでは到底まかないきれないため、適切な資金調達手段をどう選ぶかが、M&Aの成功を左右する重要なカギとなります。
本記事では、公認会計士・税理士の立場から、M&Aにおける資金調達の具体的な手法や選択基準、実行ステップ、注意点について解説します。
M&Aにおける主な資金調達方法と特徴

M&Aで必要となる資金調達方法は、大きく次の4つに分類されます。それぞれの特徴を理解し、状況に応じて最適な手法を選択することが求められます。
(1)銀行融資(M&Aローン)
金融機関からの「M&A専用融資(M&Aローン)」は、最も一般的な資金調達手段の一つです。
・既存の資金繰りへの影響を抑えられる
・審査には買収先の事業内容や将来性も評価される
特に、事業承継型M&Aでは、買収資金だけでなく、運転資金もセットで融資されるケースが多く、スムーズな承継・経営安定化を支援する金融商品も登場しています。
(2)ベンチャーキャピタル・ファンドからの出資
スタートアップや成長企業によるM&Aでは、VCやPEファンドからの資本出資を活用するケースもあります。
・ファンドの経営支援やネットワーク活用が可能
・出資比率によっては経営権に影響を受けるリスクも
特に、スピード重視・成長投資型M&Aでは、資本調達が有効な選択肢となります。
(3)セルフファンディング(自己資金・内部留保活用)
自己資金や、これまで積み上げた内部留保を活用する方法もあります。
・自社の財務力・信用力をアピールできる
・資金規模に制約があるため、大型M&Aには不向き
中小規模M&Aや、買収金額が比較的少額な場合には、自己資金活用も現実的な選択肢です。
(4)第三者割当増資・社債発行など
上場企業や中堅企業では、株式や社債による市場調達を行うケースもあります。
・株主や債権者との関係性・ガバナンスに配慮が必要
・調達までに時間やコストがかかる場合も
未上場企業にはハードルが高い手法ですが、中長期的な成長戦略を見据える企業にとっては有効な選択肢の一つです。なお、実際のM&A資金調達では、これらの手段を組み合わせて活用するケースも一般的です。単独にこだわらず、複数手法の併用も視野に入れましょう。
M&Aの資金調達における選択基準

M&A資金調達を検討する際には、次のポイントを踏まえて選択肢を絞り込むことが重要です。
(1)買収規模・資金ニーズの大きさ
・中規模(数千万円~数億円):銀行融資・ファンド出資
・大規模(数億円以上):ファンド出資・社債・株式調達
(2)返済負担・資金繰りへの影響
・返済しながら安定経営を続けたい→融資型
(3)経営権やガバナンスへの影響
・資本提携や成長支援を重視→ファンド出資・第三者割当増資
(4)調達スピードと実現可能性
・中長期計画型→出資・市場調達
これらを踏まえ、事業戦略・財務状況・将来計画に合わせた調達設計が求められます。
M&A資金調達のステップ

実際にM&Aを成功させるためには、「資金調達」と「M&A実行」を並行して進める計画力と実行力が求められます。ここでは、一般的な資金調達プロセスを4つのステップに整理して解説します。
(1)M&A計画・資金ニーズの明確化
最初にやるべきは、「なんのために、どこを、いくらで買うのか」を明確にすることです。
・ターゲット企業の選定・絞り込み
・買収スキーム(株式取得・事業譲渡など)や条件設計
・買収資金+諸経費+PMI(Post Merger Integration=買収後の経営統合プロセス)費用の算定
ここを曖昧にしたまま資金調達を始めると、「調達できた額に合わせたM&A」になってしまい、本来狙っていた成果を取り逃すリスクが高まります。
また、この段階で必ず「デュー・ディリジェンス(DD:財務・法務・ビジネスなどの精査)」の準備も進めましょう。
DDは資金調達審査にも直結し、会計士・弁護士など専門家の早期関与が必須です。自己流で進めると思わぬリスクがあるため、専門家相談は初期から行うのが安全です。
「目的ありき」「戦略ありき」で計画を固めることが、最初の重要ステップです。
(2)調達手段の検討・パートナー選定
必要資金額が見えたら、次は「どこから、どう調達するか」を設計します。
・銀行・信用金庫・ファンド・投資家など調達先候補のリストアップ
・各調達手段の条件や実現可能性を比較・検証
この段階では、「資金だけでなく、どんな事業支援が期待できるか」も見極めるべきポイントです。信頼できる金融機関や、経営支援・ネットワークを提供してくれるパートナー選びが、調達後の事業成長を左右します。
(3)資金調達交渉・契約締結
調達先が絞り込めたら、具体的な交渉・契約フェーズに進みます。
・出資条件(出資額・議決権・ガバナンスへの影響など)の調整
・投資契約・融資契約・各種契約書の締結
この交渉フェーズは、法務・税務・財務の専門知識が求められるため、弁護士や公認会計士・税理士など専門家のサポートを活用しながら慎重に進めることがポイントです。
(4)M&A実行・資金実行・PMI(統合プロセス)開始
資金調達が整ったら、いよいよM&A実行フェーズに進みます。
・クロージング(資金決済・株式・事業引き渡し完了)
・統合準備・PMI(Post Merger Integration)の開始
資金調達だけで満足してしまう経営者もいますが、本当の勝負は「買収後、事業をどう成長させるか」にあります。資金実行後すぐにPMI(統合計画)に着手し、買収シナジーを着実に実現していくことが、M&A成功の決め手です。
(5)調達とM&A実行は「並行管理」がカギ
調達スピードや審査状況によっては、M&A交渉のタイミングを逃すリスクもあるため、「資金調達」と「M&A実行」を別々に捉えるのではなく、「一体として並行管理する」スケジュール設計・タスク管理が成功のポイントです。
資金調達に時間がかかる前提で、「早め・早め」の準備と行動を意識しましょう。
M&Aにおける資金調達の注意点

最後に、M&A資金調達を進めるうえで注意すべきリスクや落とし穴を押さえておきましょう。
(1)無理な資金調達・過剰投資のリスク
・実態に見合わない高額買収
・実行後の資金繰り悪化
「資金が調達できたから」ではなく、「調達後の返済・運営も含めた事業計画の実現可能性」を冷静に判断する必要があります。
(2)ガバナンス・経営権の変化リスク
・ファンドや投資家による過度な介入
調達条件をしっかり見極め、「経営の自由度」と「資金調達メリット」のバランスを取ることが求められます。
(3)調達スケジュール遅延・実現困難リスク
・想定通りに資金確保できないリスク
「資金調達は時間がかかるもの」という前提で、早めに動き出すことが成功への鉄則です。
もし調達が想定より遅れたり、審査でNGとなった場合には、条件の再検討や他の調達手段への切り替え、M&Aプランの見直しなど「リカバリー策」もあらかじめ用意しておきましょう。専門家とともに柔軟な対応策を考えることが、リスク管理の要です。
まとめ

M&Aは、単なる買収や合併ではなく、「事業の未来をつくる戦略投資」です。その成否は、買収対象選定や条件交渉だけでなく、「どのように資金を確保するか」にかかっているといっても過言ではありません。
・ファンド出資による成長加速
・自己資金活用による独立経営
・事業規模や戦略に応じた柔軟な調達設計
M&Aや資金調達のプロセスは非常に専門的です。少しでも不安があれば、会計士・税理士・弁護士・金融機関など専門家に早めに相談することが、トラブル防止と成功への近道です。初動の設計段階からプロの意見を仰ぎましょう。
公認会計士・税理士として、これまで数多くのM&Aや資金調達支援に携わってきた経験からも、「M&A=資金調達戦略」ともいえるほど、調達設計の重要性を強く実感しています。
資金調達から逆算し、実行可能性の高いM&Aプランを描く。これが、M&A成功の第一歩です。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、最新情報はホームページ等でご確認ください。