「利益が出ていたのに倒産してしまって……」そんな話を聞いたことはありませんか?
中小企業の倒産理由で意外に多いのが“黒字倒産”です。損益計算書上は利益が出ていても、手元資金が足りないがゆえに支払いができず倒産してしまうといったケースが実は増えてきているのです。
本記事では、そんな黒字倒産を防ぐために、成功事例と失敗事例をもとに「運転資金のための借入(ローン等)」の検討ポイントを解説します。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、融資の勧誘や成果を保証するものではありません。制度や金利・条件は変更される場合があるため、利用にあたっては必ず最新の公的情報と専門家の助言をご確認ください。
黒字倒産は他人事じゃない

「利益が出ているのに倒産した」──そんな話を聞いたことはありませんか? 中小企業の倒産理由の中で意外に多いのが“黒字倒産”です。これは、損益計算書上は利益が出ていても、手元資金が足りずに支払いができないために倒産する現象です。
原因は、資金のタイムラグ。売掛金の回収が遅れる一方で、仕入れ・人件費・家賃などの支払いが先行すると、資金は一気に枯渇します。
資金繰りが危ういとき、融資が通るかどうかが会社の命運を左右します。資金不足は単なる数字の問題ではなく、経営者の判断スピードや備えの有無によって結果が大きく変わります。
成功事例と失敗事例に学ぶ「運転資金ローン」

成功事例
• A社(飲食業)
コロナ禍で売上が前年同月比40%減。固定費の支払いが重くのしかかるなか、日本政策金融公庫の当時の特例的な低利・据置制度を活用し、6ヵ月分の運転資金を確保。テイクアウト・デリバリー事業に転換しました。
オーナーは毎週の売上・原価をモニタリングし、不要な経費を即カット。その効果により、売上もコロナ前の水準まで回復しました。
• B社(製造業)
大口受注が入り仕入れ額が月商の1.5倍に急増。既存の銀行枠では不足していましたが、地元信用金庫が月次試算表や受注契約書をもとにスピード融資を決定。資金を確保し、納期遅延を回避。
結果として、新規取引先からの追加発注も獲得し、翌期は売上20%増を達成。
• C社(ITスタートアップ)
サービス好調ながら創業3年未満で銀行審査に通らず。開発中の新サービスが資金難で遅れそうになったところ、ノンバンクの短期ローン(金利5%台)で3ヵ月分の運転資金を確保。
予定通り新サービスをリリースでき、その成功が評価されてシリーズAで約2億円の資金調達につながった。
失敗事例
• D社(小売業)
新規店舗展開を急ぎ、曖昧な事業計画のまま複数の金融機関から借入。返済計画が甘く、売上予測も現実と乖離。半年後には返済滞納が発生し、信用情報に事故情報が登録され、追加融資を受けるのが困難になりました。結果として店舗閉鎖を余儀なくされました。
• E社(建設業)
過去に税金や社会保険料の滞納歴があり、複数の金融機関で審査否決。資材仕入先への支払いも遅延し、主要取引先との契約を失う。工事の継続が困難になり、事業を清算せざるを得なくなりました。
※本記事に記載の事例は一例であり、すべての企業に当てはまるものではありません。成果を保証するものではありません。
運転資金と設備資金の違い

運転資金
日常の事業運営に必要な短期資金(仕入れ、人件費、家賃、光熱費など)。不足すると事業継続に直結する重大なリスク。
例:小売業で仕入れ資金が途切れると、商品が入荷せず売上がゼロに近づき、固定費だけが重くのしかかります。
設備資金
店舗開設や機械導入など、長期投資に充てる資金。回収まで時間がかかるため、返済計画と事業計画の精度が求められます。
設備投資の失敗は徐々に経営を圧迫しますが、運転資金不足は短期間で資金繰り危機に直結しやすいため注意が必要です。
資金不足が起こる主な原因

掛売りと現金払いのタイミング差
売上が立っても入金は1〜3ヵ月先。一方で仕入れや給与は即時支払い。特に下請企業などでは、このギャップが大きくなりやすい傾向があります。
売上増時の資金不足
受注増はポジティブですが、仕入れ・外注費・人件費が先行し、手元資金を圧迫。資金繰りが一時的に厳しくなる「成長の罠」です。
突発的支出
機械の故障、災害対応、急な仕入れ価格上昇など、予期せぬ支出で計画が崩れるケースも多いです。
運転資金ローンの種類と特徴
運転資金ローンと特徴については以下の表のようになります。

審査で見られるポイント
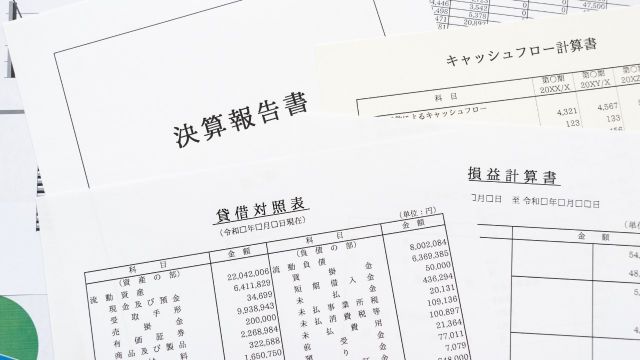
審査でみられるポイントは以下のような点が挙げられます。審査担当者は、「貸したお金を期日通り返せるか」を最も重視します。
・資金繰り表(6〜12か月先まで)
・事業計画書(売上・利益・資金見込み)
・税金・社会保険の納付状況
・代表者の信用情報(過去の返済履歴や金融事故の有無など)
借りすぎを防ぐ資金計画の立て方
資金計画の立て方の手順は以下になります。
2.キャッシュフロー予測表を作る(売上減少やコスト増のシナリオも織り込む)
3.予備費を確保(1〜2か月分の運転資金を現金で持つ)
成功する会社の「借り方の知恵」
成功する会社は以下のような点に注意を払っています。
・複数の資金調達ルートを確保(銀行・信金・公庫・ノンバンクなど)
・制度融資や助成金など、低コスト資金の情報を常に把握
・財務が苦手な経営者は、資金調達に詳しい顧問税理士など頼れる相手を持つ
「足りなくなる前」の備えが決め手

運転資金不足に気づいたときには、すでに資金繰りは深刻化しています。普段から資金繰り表や売掛・買掛の動きを定期的にチェックし、予兆を早期に察知できる体制を整えることが重要です。
予兆をつかんだら、すぐに借入申込や条件交渉などの対策に着手できるよう、必要資料や情報は平時から準備しておきましょう。
多くの経営者は、困っているとき、貸してほしいときに貸してくれないと金融機関に不満を抱きます。しかし逆に考えてみてください──もしあなたが金融機関の立場なら、資金不足に気づくのが遅く、計画や根拠もなく、数字に弱い経営者に、お金を貸したいでしょうか。
いちど運転資金不足に陥ると、税金・社会保険の滞納、取引先からの信用低下、追加融資の困難など、雪だるま式に問題が増えていきます。
運転資金不足になる前に資金調達ができるかどうかで、会社の未来は決まります。資金不足になってからでは対応が難しくなるため、事前の備えが重要です。
まとめ

運転資金不足は黒字倒産の主要因の一つです。成功する会社は必要額の根拠・返済計画・信用維持を徹底し、資金不足の予兆にも即応します。失敗する会社は計画性の欠如や信用失墜で資金を得られません。
借入は悪ではなく、経営戦略の一部。日頃の備えと関係構築で、“救われる側”になれるよう準備しましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。


























