DXや環境対応など、経営環境が大きく変化するなかで、事業の成長には戦略的な設備投資が欠かせません。本記事では、公認会計士の村木謙介氏が、初めて設備投資ローンを検討する経営者に向けて、融資を成功させるためのポイントを解説します。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の節税や投資の勧誘ではありません。税制・社会保険料率は改定される可能性があります。最終判断は必ず税理士等の専門家にご確認ください。
なぜ今、設備投資ローンが注目されているのか?

中小企業の経営環境は、この数年で大きく変化しています。人材不足や競争激化といった従来の課題に加えて、デジタル化や環境規制の強化、消費者ニーズの変化など新しい要素が経営に影響を与えるようになりました。
こうした背景から、今や設備投資は単なる支出ではなく、「事業の存続と成長を左右する戦略的な投資」と位置付けられています。
具体的には以下のような分野が注目されています。
デジタル化・DX対応
製造業ではIoT機器や生産管理システムの導入、小売業ではECやPOSシステムの高度化、サービス業では顧客データ分析やAI活用など、デジタル技術を取り入れることで業務効率や顧客満足度を高める動きが広がっています。
老朽化設備の更新
長年使用してきた機械や建物は、故障や事故のリスクが高まるだけでなく、生産効率の低下や品質不安にも直結します。更新を行うことで、作業効率や安全性を改善できると同時に、従業員の働きやすさ向上にもつながります。
脱炭素・環境対応
省エネ設備や再生可能エネルギーの導入は、光熱費削減や環境規制対応のためだけでなく、取引先や顧客からの信頼向上にもつながります。近年は「環境に配慮した企業活動」を取引条件とする大企業も増えているため、中小企業にとっても避けて通れない投資です。
低金利環境が続く今、これらの投資をローンで行うことで資金負担を分散させ、補助金制度と組み合わせることで、実質的なコスト負担を大幅に抑えられる場合もあります。
設備投資ローンとは?

設備投資ローンは、中小企業が長期的に使用する設備や資産を購入・導入する際に利用できる金融商品です。
設備投資ローンの対象
- 生産設備や工場ラインなどの機械類
- 営業用・配送用の車両
- サーバーやソフトウェアといったIT関連設備
- 店舗や工場の改装、建設
一方で、仕入代金や人件費、光熱費など日常的な支出は「運転資金ローン」として扱われます。設備投資ローンは、耐用年数のある資産の取得や長期的な収益に結び付く投資が対象となる点が特徴です。
実際の使い分け
たとえば新しい工場を建設する場合、建設費や機械導入費は設備投資ローンで調達し、工場稼働までの人件費や原材料費は運転資金ローンで賄うといったように、複数の資金調達手段を組み合わせるのが一般的です。
ここで注意すべきなのは「予定より投資額が下がって資金が余った場合の扱い」です。原則として余剰資金を運転資金に流用することは認められず、一部返済に充てるのが基本とされています。
これは資金使途を厳格に守るという金融機関の基本姿勢であり、違反した場合には資金使途違反として一括返済を求められるリスクもあります。
融資申込時に必要な書類は?

設備投資ローンを申し込む際、金融機関に提出する典型的な書類は次のとおりです。
見積書・契約書
機械やシステム導入の場合はメーカーからの見積書、建築や改装では設計書や請負契約書を提出します。資金の使い道が正しいことを裏付ける根拠資料です。
資金計画書
設備投資の総額を明記し、自己資金、借入金、補助金の内訳を整理した計画書です。補助金を利用する場合には、入金スケジュールを反映しておくことが重要です。
事業計画書(資金繰り計画を含む)
設備投資によって売上がどう伸びるか、コスト削減がどう実現するかを具体的に数値で示します。これが返済可能性の根拠となります。
金融機関が最も重視するのは、「返済原資をどのように確保するのか」という点です。そのため、売上計画や利益計画を現実的かつ説得力ある形で提示することが欠かせません。
設備投資ローンの種類

設備投資ローンは提供主体によって性質が大きく異なります。
銀行や信用金庫などの金融機関系ローン
取引実績がある企業ほど有利に進みやすく、金利や条件の交渉余地もあります。
日本政策金融公庫などの政府系金融機関
中小企業や創業者向けの制度が整備されており、低金利で長期返済が可能な場合があります。無担保や無保証で利用できるケースもあります。
地方自治体の制度融資
自治体が金融機関と連携し、金利や保証料の一部を補助する制度です。省エネ投資や創業支援など、特定分野に限定した支援もあります。
リースとの違い
ローンは自社の資産として計上できる一方、リースは所有権がリース会社にあり、費用処理がしやすいメリットがあります。導入目的や会計処理の考え方に応じて選択します。
メリットとデメリット
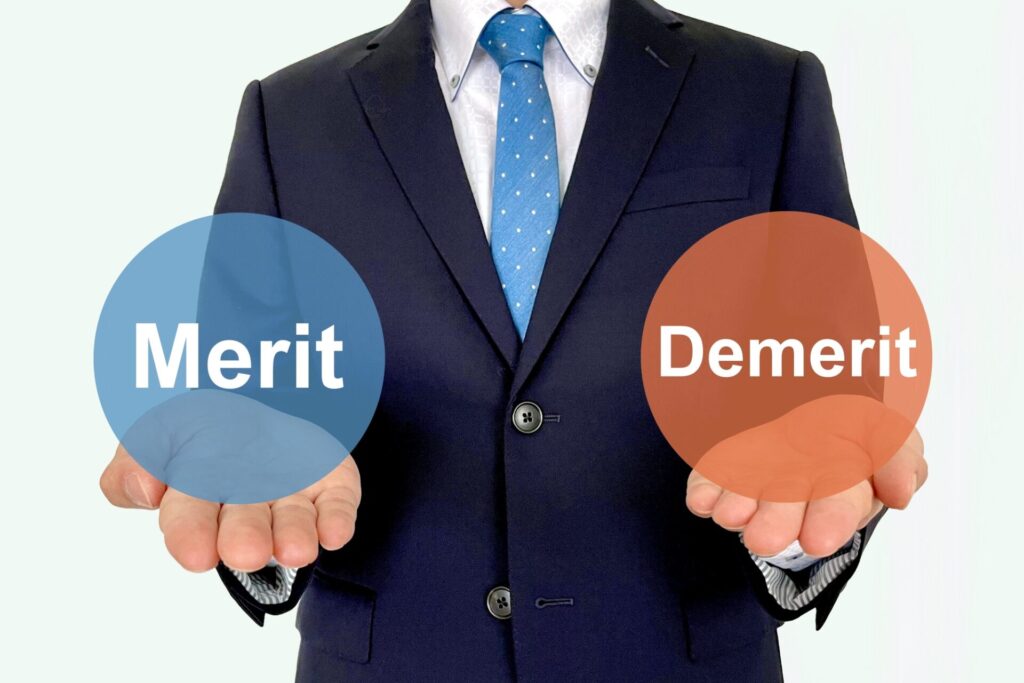
〈メリット〉
- 長期固定金利により返済計画を立てやすい
- 自己資金を温存でき、資金繰りが安定する
- 設備更新により競争力や生産性の向上が期待できる
〈デメリット〉
- 審査が厳しく、時間を要することがある
- 担保や保証を求められる場合がある
- 資金使途違反は一括返済のリスクがある
金融機関がチェックする審査ポイント

金融機関が審査で特に確認するのは以下の点です。
- 財務内容:過去3期分の決算書、自己資本比率、キャッシュフローの安定性
- 返済能力:設備導入後の売上予測、返済負担率(年間返済額÷営業利益)
- 投資計画の妥当性:見積金額の妥当性、導入効果の合理性、市場環境の分析
- 経営者の姿勢・信頼性:金融機関との取引姿勢や説明力、誠実さ
数字の裏付けに加え、経営者の熱意や信頼性も融資判断に影響する重要な要素となります。
設備投資ローンを成功させるポイント

設備投資ローンをより効果的に使うために、補助金や助成金を組み合わせる方法があります。
設備投資に活用できる代表的な補助金
- ものづくり補助金:製造業やサービス業の生産性向上を目的とした投資を支援(上限1,250万円)
- IT導入補助金:会計ソフトや基幹システム、クラウドサービス導入を補助
- 中小企業省力化投資補助金(一般型):人手不足解消に効果があるデジタル技術等を活用した設備の導入を後押し
- 小規模事業者持続化補助金:販路開拓や店舗改装など比較的小規模な投資に利用可能
補助金活用の注意点
- 契約タイミングに注意
補助金は「交付決定通知前に契約・発注したものは対象外」とされるケースが多く、申請前の契約は原則として認められません。焦って契約すると補助金が使えなくなるため注意が必要です。 - 相見積もりが必要な場合がある
多くの補助金は公正性を確保するため、2〜3社から相見積もりを取得し提出することを求めています。これを怠ると不採択や対象外となります。 - 入金までのタイムラグ
補助金は後払いが原則で、入金まで数ヵ月を要する場合がります。ローン返済とのスケジュール調整を資金繰り表に反映しておくことが大切です。
実務上の注意点まとめ
- 設備投資ローンと運転資金ローンは資金使途を厳密に区分する
- 見積書・契約書・資金計画書・事業計画をセットで準備する
- 補助金を活用する場合は交付決定前に契約しない、相見積もりを確保する
- 設備投資に使った後に資金が余った場合は、原則として融資の一部返済に充てる。余剰資金を運転資金に流用することはできない
- 複数の返済シミュレーションを用意し、売上想定が外れた場合にも備える
- 金融機関には早めに相談し、丁寧かつ誠実に説明する
資金調達は「準備の質」で結果が変わる

設備投資ローンは、中小企業の成長を支える重要な資金調達手段です。投資の目的を明確にし、書類で資金使途を裏付け、金融機関の審査ポイントを押さえた計画を提示することが成功の鍵となります。
さらに補助金や助成金を併用すれば、投資効果を最大化することが可能です。
資金調達は「準備の質」で結果が大きく変わります。計画性を持ち、資金使途を適切に管理しながら、成長への一歩を着実に踏み出すことが重要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の融資・補助金等の勧誘や推奨を目的とするものではありません。制度・税率・料率・金利・支給要件等は変更される場合があり、補助金・助成金の適用可否は各制度の要件に左右されます。成果や節税効果を保証するものではありません。ご利用にあたっては、最新の制度概要・重要事項説明書等で内容をご確認のうえ、必要に応じて専門家へご相談ください。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。


























