最近では、夫婦2人で必要な老後資金は5,000万円と言われています。その根拠は何なのでしょうか。そもそも老後についてのイメージができないという声も多く聞かれます。要因となる社会情勢や取り巻く環境を知ることで、自分でできる資産形成の手段を考えましょう。この記事では、実際に必要となる金額の考え方やシミュレーションの方法、資産形成の選択肢などについて解説します。この記事を読むことで、まずは一歩を踏み出すことで不安を安心に変えていきましょう。
- 老後資金に5,000万円必要と言われるのには、年金財源や物価上昇リスク、介護費用の必要性、平均寿命の伸びといった理由がある。
- 夫婦2人が老後に必要な月あたりの最低額は230,000円、ゆとりある生活には379,000円。
- 現在の65歳以上世帯のうち4,000万円以上の貯蓄がある世帯は17.7%にのぼる
- 効率よく老後資金を貯めるためには、ライフプラン→必要な額→どうやって貯めるかの順で考えよう


夫婦2人の老後に5,000万円が必要とされる理由

2019年に話題となった「老後2,000万円問題」について記憶されている方は多いでしょう。金融庁の金融審議会市場ワーキング・グループが報告書のなかで老後の資金として2,000万円が必要としたことは、多くのメディアでも取りあげられ、数字が明確に示されたことで、それまで漠然としていた不安は危機感や焦燥感に繋がりました。
「老後2,000万円問題」の根拠となった家計調査報告(2017年)では、高齢夫婦無職世帯の実収入が209,198円であり、実支出は263,717円であるため、月あたりの赤字が54,519円と示されています。
この数字から年間で654,228円、65歳から95歳までの30年間で計算すると1,962万6840円という計算になります。
ただし、ある意味で、老後について「お金」について考えるきっかけとなったとも言えます。あれから5年経ち、最近では、夫婦の老後資金に5,000万円が必要といわれることがあります。5,000万円という大きな数字に、あらためて不安を感じる方も多いでしょう。その理由としては、年金財源、物価高騰、介護費用負担、平均寿命の延びなどがあげられます。以下で詳しく解説しましょう。
年金受給額が今後減る可能性があるため
まず、将来の年金受給額は、現在と比較すると減る可能性について考える必要があります。
現在の公的年金制度では、原則65歳から老齢年金を受け取ることができます。受給額については、厚生労働省が発表する「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」が参考になります。年金受給者の平均年金額は、会社員など厚生年金加入者であった方で144,982円、専業主婦など国民年金のみであった方で56,428円です。会社員であった夫と専業主婦であった妻とすると、夫婦2人で月あたりの平均年金額は201,410円となります。
ただし、日本は今、少子高齢化の課題に直面しています。予想を上回るペースで出生数は年々減少しており、将来の労働人口が減ることで年金財源を確保することが難しくなることが予測されます。国として、パートなど短時間労働者の社会保険加入や子育て支援といった取組みが進められていますが、一方で年金受給開始年齢の繰下げや給付水準が引き下げられることも可能性として考えられます。
物価上昇のリスクがあるため
つぎに、年金生活者となる将来にむけて、物価上昇リスクがあることを想定する必要があります。どのくらい上昇するのか予測することは難しいとしても、少なくとも現状よりも上昇していることは想定されます。
食料品を含むさまざまなモノの値段が相次いで上昇しており、家計を直撃している現状です。総務省が毎月発表する消費者物価指数(2024年4月)は、前年同月比2.5%(生鮮食品を除く総合では2.2%)上昇し、2020年を100とすると、107.7(同 107.1)とデータでも物価上昇を確認することができます。
こうした物価高騰には、ウクライナ情勢による原油高や海外との金利差による円安の進行などさまざまな要因が考えられます。最近の急激な上昇率は落ち着くとしても、緩やかに物価(モノの値段)が上昇することは想定しておく必要があります。モノの値段が上がると生活は苦しくなるため、物価上昇リスクに備えた資金計画や資産形成を考えたいものです。
介護費用が必要になるケースがあるため
また、将来の老後資金を考えるにあたって、日々の生活だけでなく、病気や介護などのリスク、費用について考える必要があります。
元気で毎日が過ごせれば何よりですが、とくに介護状態になった場合には、生活環境の整備といった初期費用に加え、継続費用が発生します。
生命保険文化センターの「生命保険に関する全国実態調査2021(令和3)年度」によると、手すりの設置や段差解消等の住宅改造、また介護用ベッドの購入費など初期費用として平均740,000円、公的介護保険サービスの自己負担費用を含む月々の費用は平均83,000円となっています。
同調査より介護期間の平均5年1ヵ月として計算すると継続費用は506万3,000円となり、初期費用を合わせると580万3,000円かかる計算です。
平均寿命が延びているため
そして、平均寿命が延びていることにも注目すべきです。長生きできることは喜ばしいことですが、同時に生活していくためにお金が必要であることも確かです。
厚生労働省の「簡易生命表の概況(令和4年)」によると、平均寿命は男性81.05歳、女性は87.09歳といずれも80歳を超えています。最近では100歳を超える元気な高齢者も珍しくありません。老後資金を考える場合には、100歳までを想定して考えておくと安心です。
老後資金は実際いくらあれば安心?シミュレーションしてみよう

では、老後資金として必要な額は、いったいいくらあれば安心なのでしょうか。ここでは、前述の「老後2,000万円問題」の前提条件と同様に、高齢夫婦無職世帯のうち夫は、現役時代は会社員として厚生年金加入者、妻は専業主婦で国民年金加入者(第3号被保険者)であったと仮定してシミュレーションしてみます。
なお、公的年金制度については現在の制度が維持することを前提に65歳から受給とし、夫婦年齢は同じ、95歳までの30年間とします。
「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況 」をもとに、
夫(老齢厚生年金+老齢基礎年金)144,982円
妻(老齢基礎年金) 56,428円
あわせて、月あたりの年金額201,410円を受け取るものとします。
夫婦2人の老後に必要な最低限の資金
生命保険文化センター「生活保障に関する調査2022(令和4)年度」によると、老後を夫婦2人で暮らしていくうえで、日常生活費として月々最低いくらぐらい必要だと考えるかという問いに対し、回答の平均額は、月額232,000円でした。
回答をもとに、老後に必要な最低額を計算すると、
老後の最低日常生活費月額232,000円 - 夫婦2人の公的年金額201,410円 = 30,590円(赤字)
30,590円 × 12月 × 30年 = 11,012,400円 となります。
現在の価値で、約1,100万円が必要というシミュレーションができます。
夫婦2人の老後に必要なゆとりある資金
同調査より、夫婦2人のゆとりある老後生活費の月額については、平均379,000円という回答でした。
回答をもとに、老後のゆとりある生活費を計算すると、
老後のゆとりある生活費月額379,000円 - 夫婦2人の公的年金額201,410円 = 177,590円(赤字)
177,590円 × 12月 × 30年 = 63,932,400円
現在の価値で、約6,400万円が必要という計算になります。
上記のシミュレーションでは、いずれも物価上昇率を加味していません。仮に毎年1%の物価上昇率が継続した場合、232,000円の生活費は10年後253,000円、20年後には280,000円、30年後には309,000万円となります。ただし、公的年金についても、物価の変動を加味した改定が行われるため、年金受給額は一定でなく変動します。
あくまでも必要となる金額を知り、目標額の目安とするシミュレーションであることに注意が必要です。
65歳以上で貯金額が5,000万円ある世帯の割合は?
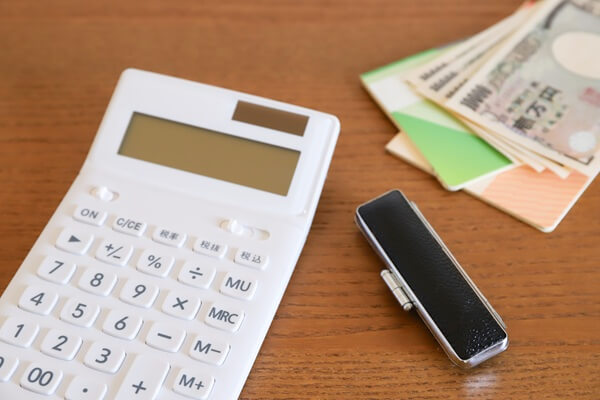
本来であれば、自分自身の老後資金については、自分なりの価値観や考え方を持つことが大切です。しかしながら、これまで経験したことのない「人生100年時代」においては、将来の生活をイメージすることは難しく、適切な数字を把握することにも限界があります。
そういった意味もふくめて、同年代の人たちがどのような状態にあるのかデータとして参考とすることには意味があります。内閣府の「令和5年版 高齢社会白書」や総務省の「家計調査」のデータが参考になりますので、以下で詳しく解説しましょう。
4000万円以上の貯蓄がある世帯は17.7%
内閣府の「令和5年版 高齢社会白書」によると、二人以上の世帯の貯蓄残高について、世帯主の年齢が65歳以上の世帯(中央値1,588万円)とすべての世帯(中央値1,104万円)と高齢世帯に貯蓄残高が集中していることがわかります。
また、世帯主の年齢が65歳以上の世帯のうち4,000万円以上の貯蓄がある世帯は、全体の17.7%を占め、多くの世帯で4,000万円以上の貯蓄があるようです。
現在の65歳以上世帯では、世帯主が定年まで勤めあげ、退職金を受け取っているケースが多いことも考えられます。
世帯主65歳以上の貯蓄額の平均値・中央値
総務省の「家計調査報告(貯蓄・負債編)2023年」によると、世帯主が65歳以上の世帯では、貯蓄高が2500万円以上の世帯が約3分の1を占めることが記載されています。1世帯あたりの平均値は2,504万円、中央値1,604万円となっています。
貯蓄の種類別に見ると、定期性預貯金が846万円と最も多く、通貨性預貯金754万円、有価証券480万円、生命保険などが413万円、金融機関外が110,000円とドル建てなどの通貨性預貯金や有価証券が増加していることには選択肢の広がりが感じられます。
老後資金を効率よく貯めるためのステップ

ここでは、老後資金を効率よく貯めるためのステップについて紹介しましょう。時代とともに、働き方や住まい方、資産形成の手段は変わってきています。多様性の時代ともいわれる昨今、自分らしい生き方、そして、自分にとって最適な資金計画が求められます。ステップごとに説明していきます。
その1|ライフプランを考える
まずは、自分の年齢とともに、家族の年齢を左から右に1つずつ足しながら書き込んでいきましょう。10年後の自分の年齢は想像つきやすいものですが、意外と配偶者や子どもの年齢はイメージがつきにくいものです。
それぞれ卒業や入学、退職といった決まったライフイベントを書き込むとともに、希望に応じて、車の買換えや住宅のリフォームなども追加していきます。将来をイメージすることから始めると、楽しみとともに安心に繋がりますので、ぜひ実行してみてください。
その2|現在の資産状況をもとに老後に用意すべき資金額を決定
その1のライフプランを考える時点では、今後の予定ややりたいことをピックアップするのが目的でしたが、その2では、具体的に実行するためには「いつまでに、どのくらいのお金が必要なのか」「用意すれば良いのか」を考えます。
可能な範囲で予算や必要となる金額も追加します。家族のイベントを可視化することで、例えば、子どもの大学入学と車の買換え、さらに住宅のリフォームが重複することなどもあり得ます。目に見えるようにすることで、他のプランや忘れかけていたイベントを思い出すかもしれません。
多額の出費が難しそうであれば、タイミングを移動させたり、スキップさせたりコントロールが可能となります。
その3|資金調達方法を検討する
具体的に、いつまでに、何のために、いくら必要なのかが明確になると、その次のステップとして、そのためには、どのように資金を準備するのかといった検討を行います。最近では、さまざま選択肢が増えており、悩む事も多いでしょう。
とくに、価格変動のある商品については、向き不向きがありますし、複雑なしくみとなっているものも少なくありません。いずれにしても、きちんと理解し、納得したうえで取り組むことが大切です。
夫婦2人で老後資金5,000万円を準備する方法
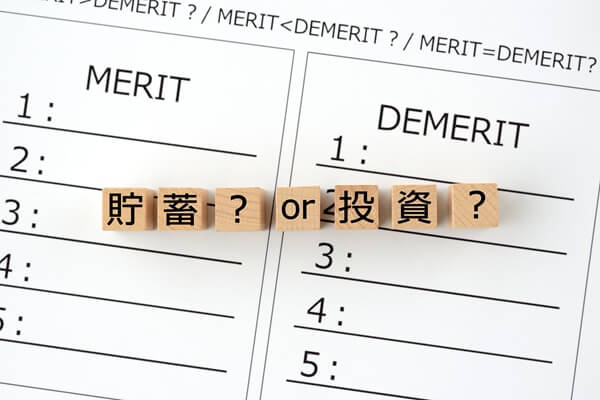
超低金利時代と言われ、銀行に預けておくだけでは資産は増えない時代です。国の後押しもあり、投資に目を向ける方も多いのですが、価格変動リスクに一喜一憂するようでは、ストレスとなり得るため、自分に合った方法を選びたいものです。
ここでは、夫婦2人で老後資金を5,000万円準備するための資産形成として、預金、NISAやiDeCoなどの「投資」、「貯蓄型保険」「持ち家の活用」など参考となる方法を紹介します。
預金
各種銀行やゆうちょ銀行などに預ける預貯金は、元本が保証された貯蓄商品です。ただし、決まった金利が利息として受け取ることができますが、超低金利が続く昨今、資産は増えないのが現状です。近い将来に発生するライフイベントについては、流動性あり元本を確保する預貯金で準備することをおすすめします。
基本的に、預けた資金が減ることはありません。そのため、元本を減らしたくない、確実に積み上げていきたいといった方にはおすすめです。毎月積み立てる金額を決めたうえで、継続することが目標額に近づくポイントとなります。
投資
値上がりすることを期待しつつ、資金を投じることを「投資」といいます。当然ながら、価額は上昇することもある一方で、想定外に値下がりすることもあります。ただし、老後資金の資産形成が目的であれば、ある程度の期間を設定することができるため、投資は有効な選択肢です。目標額と期間を逆算したうえで、毎月の積立額を決定することをおすすめします。
例えば、40歳の夫婦が2人で目標額3,000万円とした場合、年金受給開始年齢の65歳までの25年間投資をするとしたら、年間120万円を積み立てる計算となります。毎月100,000円とか、月50,000円プラス賞与200,000円×2回といった方法も考えられます。投資利回りを全期間3%で想定したとすると、4,375万円にふえる計算です。
利回りを含めた資産形成を考える方法、もしくは、増えた分については余裕ある暮らしのために享受するという方法どちらもおすすめです。
新NISA
投資を始めるにあたって、新しいNISAは、ぜひ活用したい制度です。通常約20%の源泉所得税が差し引かれる投資が、NISA口座での取引であれば非課税となるのは、大きなメリットです。これまでのNISAと比較すると、投資枠も広がり、期限も恒久化されたことで格段に使い勝手がよくなっています。月々一定額の積立て投資枠を使いつつ、まとまったお金で株式を成長投資枠を使って買い付けることができるのも新しいNISAの特長です。
新NISAでは、毎年120万円の非課税枠が設けられ、長期・分散・積立を実現できる投資信託専用の口座です。夫婦それぞれの口座で毎月50,000円ずつ(2人で100,000円)を積立投資枠で積み立てれば、分散投資効果も得られます。
NISA口座での取引は、急に資金が必要になった場合でも、売却により引き出すことも可能です。そういった状況に応じて臨機応変に対応できるのも魅力といえるでしょう。口座を開設する金融機関と選ぶ投資先については、それぞれのメリットやデメリット、手数料などを比較したうえで行いましょう。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCo(イデコ)は、個人型確定拠出年金の愛称です。日本版401kとも言われ、もともとは、企業に勤める会社員の退職金として企業が導入する制度でしたが、個人事業主や専業主婦などでも活用できる個人版として始まったのがiDeCoです。
投資商品としては、運用益が非課税となるメリットはNISAと共通しますが、目的が「老後資金」に限定されるため、60歳までは引き出すことができません。
一方で、拠出金(積立てたお金)は、全額所得税の対象となるため、節税に繋がります。また受取り時にも退職所得控除や年金形式で受取る場合に雑所得控除が適用されるなど税制面で有利です。
勤め先の企業型確定拠出年金と別枠で加入可能ですが、限度額が決まっているため、確認が必要です。
貯蓄型の保険
資産形成の手段として、終身保険や変額保険、個人年金保険といった保険の活用も選択肢です。終身保険や変額保険の場合には、もしもの場合の死亡保障として、資産形成とともにリスク対策として活用できるため、子育て世代などには、1本の契約で備えることも可能です。
ただし、保険商品であるため、保管会社の運営管理費用などが含まれるため、投資の運用益をすべて享受できないことがデメリットであり、割高感があります。
預貯金や自分で行う投資においては、家計状況によっては投資に回せないといった状況に陥ることも懸念されますが、契約である保険商品は、毎月きまった日に確実に引き落とされます。割高でも確実に積み上げたい、運用を任せたいといった方におすすめです。
個人年金保険については、保険会社で扱っているものの、保障機能については期待できませんが、要件をみたせば、生命保険料控除の対象となるため所得税負担の軽減につながることがメリットです。NISAで資産形成をしつつ、個人年金保険でも資産形成を行うことも有効です。
なお、保険会社により、保険商品により仕組みや受取方法が異なります。とくにドル建てなど為替が関係する商品については、きちんと理解したうえで加入することをおすすめします。
持ち家の活用
持ち家がある場合、不動産としてすでに資産を保有していることになります。築年数やエリアなど諸条件にもよりますが、評価額を知ったうえで、有効活用することも選択肢です。
子どもが独立して夫婦2人では広過ぎるといった声も多く、住み替えなども可能です。また高齢期になると、段差による転倒なども心配です。売却したうえで、快適な高齢者住宅へ移るといった方も増えています。
ほかにも、持ち家を担保に融資を受ける「リバースモーゲージ」や最近では「リースバック」といった老後資金を確保するための活用方法として珍しくなくなりました。リースバックについては、次の章で詳しく解説します。
老後資金の確保に「セゾンのリースバック」もおすすめ!
「リースバック」は、持ち家を売却して現金化した後に、賃貸契約により賃借人として継続して住み続けることのできるものです。
通常の売却のように買い手が決まるまで悶々と過ごすこともなく、だれにも知られずにそれまでどおりの生活ができることに注目されています。契約にあたっては、注意点も多く、メリットとデメリットを理解し進めることが大切です。
リースバックとは?
リースバックによる売却契約をすることで、所有権はなくなります。その代わり、賃貸契約を締結することで、賃借人として、引き続き、生活を変えることなく、毎日を過ごすことができます。
これまで支払ってきた固定資産税や火災保険の負担はなくなりますが、賃料を支払うことになります。売却代金を一時金で受け取ると生活に余裕ができる反面、自分でお金のコントロールする必要があり、想定外の資金枯渇は回避したいものです。
とは言え、有効活用できる資産があること、そして有効活用できる手段があることは老後資金の不安を安心とする効果が得られるでしょう。
セゾンのリースバックがおすすめの理由
最近では、多くの金融機関や不動産会社が取り扱うサービスとなりつつあります。ただし、売買契約と賃貸借契約という契約を取り交わすため、いずれの契約書も不利な条件が記載されていないか確認する必要があり、きちんと対応してくれる相手を選ぶことが成否のカギとなります。
「セゾンのリースバック」は、クレディセゾングループのセゾンファンデックス社が提供し安心です。「セコムのホームセキュリティ」、「HOME ALSOKみまもりサポート」サービスのどちらかをお選び頂き、さらにセゾンの「永久不滅ポイント20,000ポイント」、ハルメク社の「50代からの女性が人気の月刊誌が3年間定期購読無料」、くらしのセゾン社の「ハウスクリーニング」など選べるサービスなどもあります。また、わからないことや不明点についても担当者が丁寧に説明し、納得したうえで契約いたします。選択肢のひとつとして、まずは相談(無料)してみてはいかがでしょうか。


おわりに
最近では、夫婦2人で必要な老後資金は5,000万円といわれることもあります。数年前の2,000万円でも「困った」といった不安や危機感がありましたが、さらに必要となる金額は増えているようです。これには、少子高齢化による年金財源の確保や物価高騰、平均寿命の延びに伴う介護費用の備えの必要性などさまざまな要因があります。実際のところ、それぞれの働き方や家族構成にもよりますが、こうした不確定要素に対応できるだけの自助努力は行う必要があることは確かです。今後のライフプランを考えたうえで、少しずつ資産形成を実現していきましょう。面倒くさいと後回しにせず、少しでも早めに始めること、そして継続することが大切です。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。




































