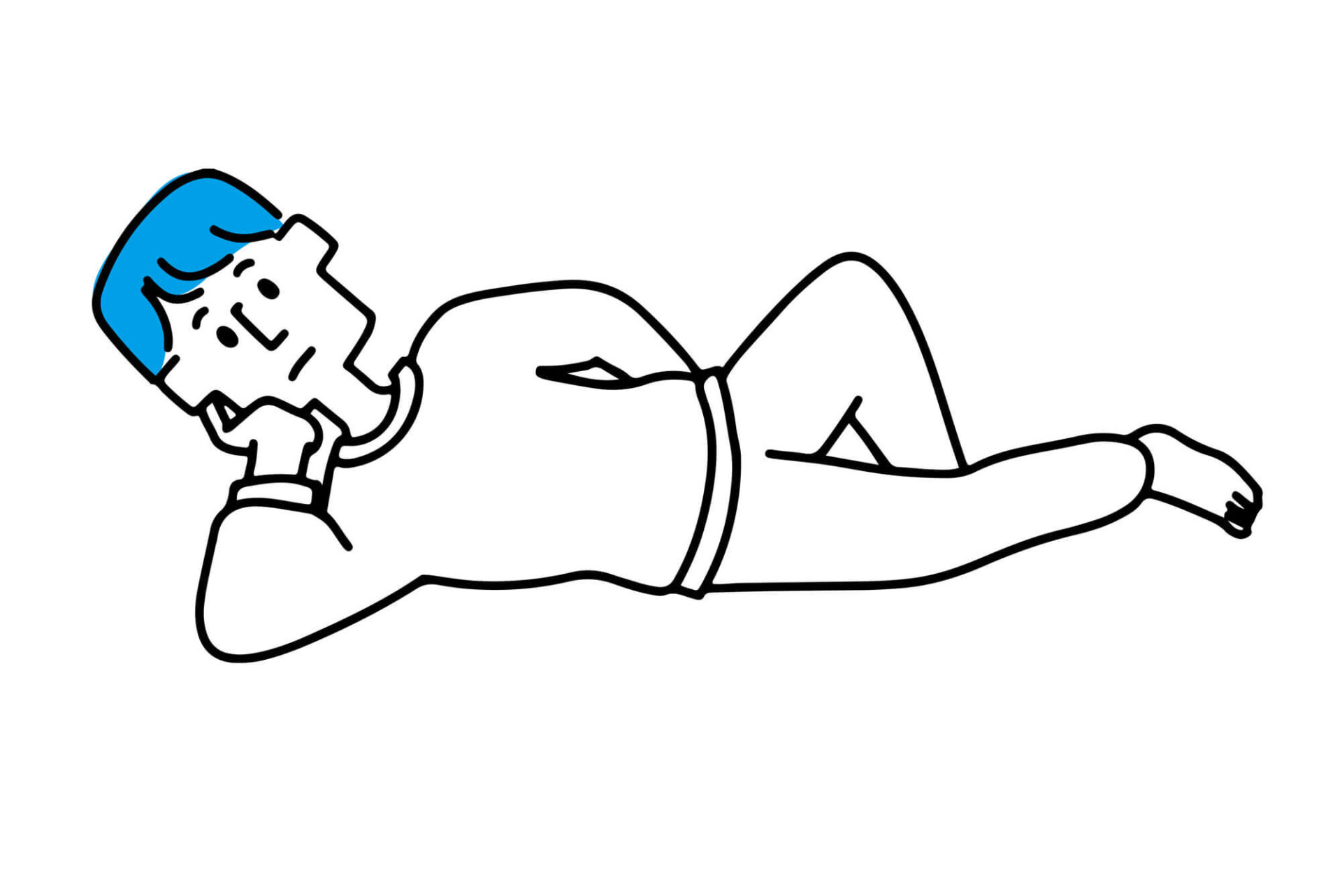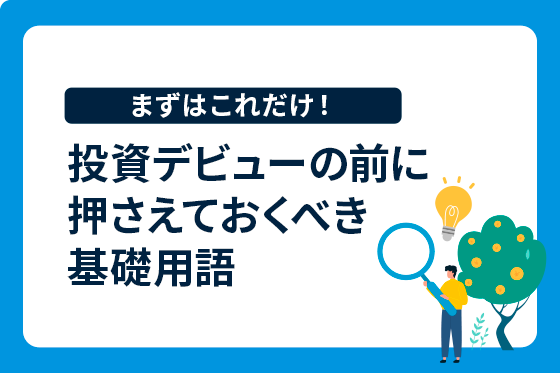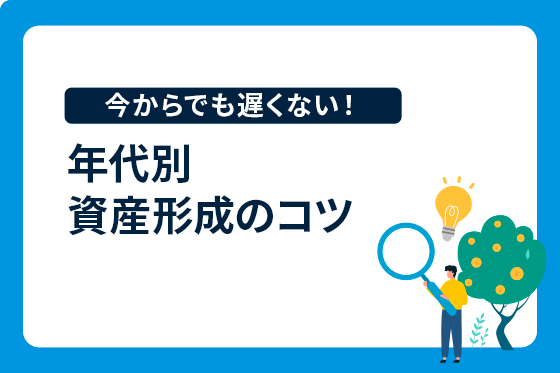日本では20歳になると、国民年金保険料の納付義務が生じます。しかし収入が少ない方や働いていない方、学生などは、納付が難しいケースも少なくありません。
国民年金は一定の条件を満たすと納付免除が可能です。しかし免除にはデメリットもあるため、正しく理解することが重要です。
この記事では、国民年金の免除について詳しく解説しています。年金を未納せずに免除申請することで、将来受け取れる金額が増える可能性もあります。年金の納付が難しい収入の少ない方や働いていない方、学生は、参考にしてください。
日本の年金制度
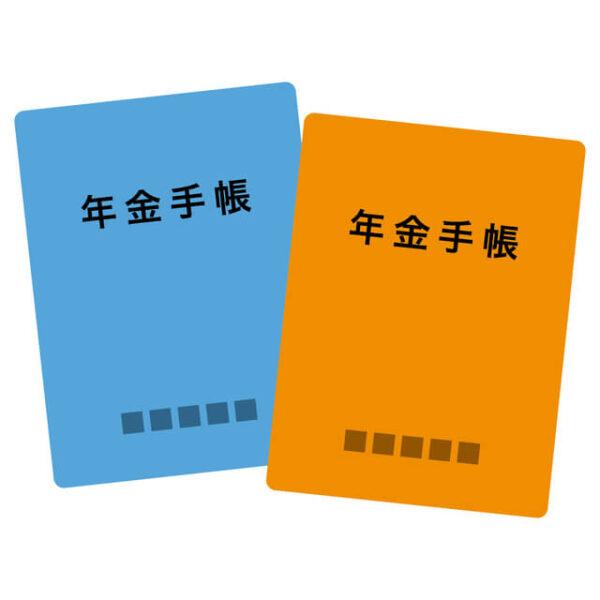
日本では20歳になると、国民年金への加入が義務付けられます。
また日本の公的年金制度には厚生年金もあります。ここではこれらの年金について詳しく説明します。
国民年金
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入が必要です。外国人であっても日本に住所を有していれば、国民年金の対象者になります。
つまり、20歳以上60歳未満であれば、学生でもなく、働いてもなく、働くための職業訓練も受けていない、ニートといわれる方も国民年金の対象です。
日本の公的年金制度は、国民年金と厚生年金による2階建てですが、1階部分を担う国民年金は「基礎年金」とも呼ばれます。なお令和6年度の国民年金保険料は、月額16,980円です。
参照:日本年金機構「国民年金保険料」
厚生年金
厚生年金は公的年金制度の2階部分にあたり、国民年金に上乗せされる年金です。厚生年金は公務員や会社員のみ加入できます。
厚生年金は、保険料を事業主と折半で支払う点が特徴です。なお厚生年金保険料の納付額には、国民年金の保険料も含まれています。
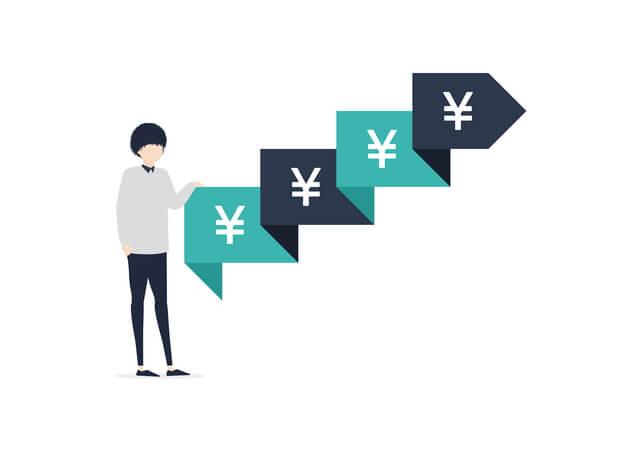
ニートの方必見!年金の納付が困難な場合に免除制度を利用できる条件

国民年金には、収入が少なく納付が困難な方に向けた免除制度があります。申請して利用が承認されると、以下の金額が免除されます。
- 全額
- 4分の3
- 半額
- 4分の1
なお免除制度の利用には、本人・配偶者・世帯主の合計所得額が以下の条件を満たす必要があります。
| 免除額 | 前年の合計所得額 |
|---|---|
| 全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
| 4分の3免除 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
| 半額免除 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
| 4分の1免除 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
ただし1月から6月に免除申請する場合は、前々年の所得が対象になるので注意してください。また、免除制度は、本人・配偶者・世帯主の合計所得が基準となるため、親が世帯主で所得が高ければ、免除制度の利用ができない可能性が高くなります。
免除制度の申請方法
国民年金の免除を申請する方法は、以下のとおりです。
- 居住地にある役所の国民年金担当窓口へ提出
- 年金事務所へ提出
- 郵送
- 電子申請
なお、申請の際は以下の書類を添付してください。
- 申請書類
- 基礎年金番号通知書のコピーまたは年金手帳(氏名の記載ページ)のコピー
申請書は日本年金機構のホームページからダウンロード可能です。
参考:日本年金機構「国民年金保険料 免除・納付猶予 の申請について」(PDFファイル)
年金の免除制度を利用するメリット

ニートの方が国民年金の免除制度を利用するメリットは、以下のとおりです。
- 年金の受け取りに必要な「受給資格期間」に算入される
- 障害年金や遺族年金を受け取れる
- 免除された保険料を追納できる
免除制度の申請前に、メリットについて正しく理解しましょう。
年金の受け取りに必要な「受給資格期間」に算入される
国民年金保険料の納付を免除された期間は、年金を受け取るために必要な「受給資格期間」に算入されます。
受給資格期間とは、将来年金を受け取るために必要な保険料納付済みの期間のことで、10年(120ヵ月)あると年金を受け取る資格が得られます。
保険料が未納の場合は受給資格期間に含まれませんが、免除を受けた期間は算入されます。そのため、保険料を未納のままにするよりも、免除を受けた方が将来年金を受け取れる可能性が高まります。
参照元:厚生労働省「年金を受けとるために必要な期間が10年になりました」
障害年金や遺族年金を受け取れる
年金の免除制度を利用した場合でも、障害年金や遺族年金の受給資格を得ることは可能です。
障害年金や遺族年金を受給するには、初診日がある月の前々月までの被保険者期間において、納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上必要です。そのため未納期間が長いと、障害年金や遺族年金を受け取れない可能性があります。
なお、直近1年間に未納がある場合は、納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上あっても障害年金や遺族年金を受け取れません。
参照元:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」「遺族基礎年金」
免除された保険料を追納できる
免除された保険料は、原則として過去10年間にさかのぼり追納可能です。なお、免除申請をしていない場合、追納できるのは過去2年までです。
保険料が免除された期間は受給資格期間に算入されますが、受け取れる年金額には反映されません。そのため免除されたままだと、将来の年金額が減ってしまいます。
金銭的に余裕ができた際は、受け取れる年金額の増加につながるため、追納するのがおすすめです。
参照元:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」
年金の免除制度を利用するデメリット
ニートの方が国民年金の免除制度を利用するデメリットは、以下のとおりです。
- 将来受け取れる年金額が減る
- 追納時に加算額が上乗せされるケースがある
- iDeCoに加入できない
免除制度はメリットだけではないため、デメリットについても理解しておきましょう。
将来受け取れる年金額が減る
年金の免除制度を利用して追納しなかった場合、将来受け取れる年金額が減ります。なお免除期間の減額割合は、以下のとおりです。
| 免除期間 | 減額割合(平成21年4月分以降) | 減額割合(平成21年3月分まで) |
|---|---|---|
| 全額免除 | 1/2 | 1/3 |
| 4分の3免除 | 5/8 | 1/2 |
| 半額免除 | 3/4 | 2/3 |
| 4分の1免除 | 7/8 | 5/6 |
例えば全額免除の期間が2ヵ月あった場合、通常は納付済期間が2ヵ月となるところ、半分の1ヵ月として計算されます。
将来受け取れる年金額を減らしたくない方は、追納して保険料を納めましょう。
参照元:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
追納時に加算額が上乗せされるケースがある
保険料の免除が認められると、原則として過去10年間にさかのぼり追納可能です。ただし、3年度目以降の分は加算額が上乗せされるので、通常納付よりも負担が増します。
例として令和6年度に追納する場合、令和3年以前の保険料には加算額が上乗せされます。加算後の追納額は、以下のとおりです。
| 全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 | |
|---|---|---|---|---|
| 令和元年度分 | 16,560円 | 12,420円 | 8,270円 | 4,140円 |
| 令和2年度分 | 16,670円 | 12,500円 | 8,340円 | 4,160円 |
| 令和3年度分 | 16,710円 | 12,530円 | 8,350円 | 4,170円 |
追納する予定の方は、加算額を考慮して早めの納付を検討してください。
参照元:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」
iDeCoに加入できない
国民年金の免除や猶予を受けている方は、iDeCo(イデコ)に加入できません。
iDeCoとは個人型確定拠出年金のことで、老後の資産形成を目的に作られた制度です。拠出金は全額所得控除の対象になるため、節税面でも大きなメリットがあります。
なお過去に免除を受けていても、すべて追納が完了している場合は、iDeCoに加入可能です。
年金の免除申請をせずに放置した場合に起こること
年金保険料の納付が難しいときは免除申請が可能ですが、放置して未納のままにしていると以下の事態が起こります。
- 最終催告状の送付
- 滞納を続けていると、最終催告状が送付されます。指定された期限までの納付が必要です。
- 督促状の送付
- 最終催告状の期限を過ぎても納付されない場合、督促状が送付されます。督促状も期限内の納付が必要です。
- 財産の差し押さえ
- 督促状の期限が過ぎても納付されない場合、財産を差し押さえられる可能性があります。
なお督促状の期限内に納付されない場合は、延滞金がかかります。令和6年1月1日から12月31日までに延滞した場合の延滞金の割合は以下のとおりです。
- 納付期限の翌日から3ヵ月を経過する日まで:2.4%
- 納付期限の翌日から3ヵ月を経過する日の翌日以降:8.7%
例えば納付期限が令和6年5月31日の保険料を、9月1日に納付した場合の延滞金の計算式は以下のとおりです。
- 16,980円(国民年金保険料) × 8.7%(延滞金の割合) × 92(延滞した日数) ÷ 365 = 約372円
延滞分全額の支払いとなれば、5月31日、6月31日、7月31日、8月31日の4カ月分の保険料合計と延滞金合計の支払が必要になります。
支払う負担を増やさないためにも、保険料は納付期限までに納めましょう。
年金の免除申請が却下されたときの対策

保険料の免除申請は、受理されずに却下されることもあります。却下されたときは、以下の方法で対処してみてください。
- 納付猶予を申請する
- 家族に納付を依頼する
免除申請が通らなくても未納のままにせず、他の方法を検討してみましょう。
納付猶予を申請する
免除申請した方が50歳未満であれば、条件を満たすことで納付猶予の制度を利用できます。
納付猶予を受けるには、本人と配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以内であることが条件です。なお金額は全額免除を受ける際の条件と同じです。
納付猶予された保険料は、免除されたときと同じく10年さかのぼって追納できます。ただし納付猶予された期間は、受給資格期間に算入されますが、将来受け取れる年金額には反映されないので注意してください。
参照元:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
家族に納付を依頼する
ニートの方や、学生・アルバイトなど収入が少ない方は、自分で支払えるようになるまでは、親への依頼も考えましょう。
子どもの国民年金を支払った親は、納付額の全額が社会保険料控除を受けられるため、所得税を抑えられます。
家族の保険料を支払った場合は、年末調整で忘れずに申告しましょう。
年金免除に関するQ&A

ここでは年金の免除に関するさまざまな疑問点を紹介します。ご自身の悩みが解決するケースもあるので、参考にしてください。
退職により国民年金の納付が困難な場合、特例免除を受けられるケースがあります。
通常の免除申請では申込者と配偶者、世帯主の合計所得が審査条件に入ります。しかし特例免除の場合は、申込者の前年所得はゼロとして計算され、通常の免除よりも条件が緩和されているのが特徴です。
なお免除される期間は、退職した月の前月から翌々年の6月までとなります。
特例免除は、自己都合退職のケースでも利用可能です。
なお特例免除は申込者本人だけではなく、世帯主や配偶者の退職も対象になります。
おわりに
日本の公的年金には「国民年金」と「厚生年金」の2種類があります。国民年金は、20歳以上60歳未満の方に納付義務があり、ニートの方でも支払いが必要です。
納付が困難な方は、免除や猶予が可能です。これらの制度を利用した期間は、将来年金を受け取るために必要な受給資格期間に算入されます。一方で免除と猶予には受給額が減るデメリットもあるため、申請前に十分な検討が必要です。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。