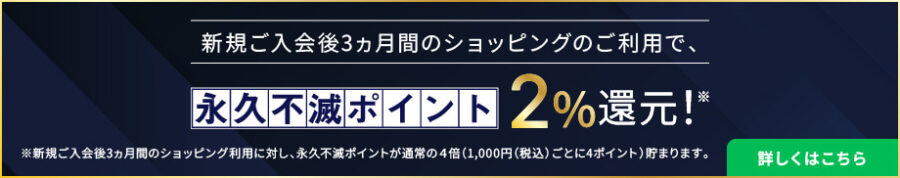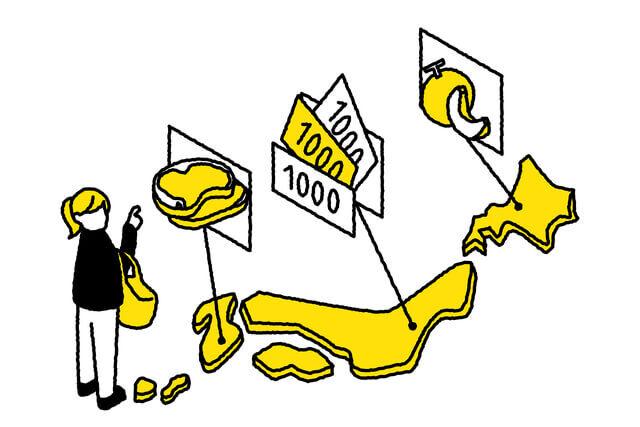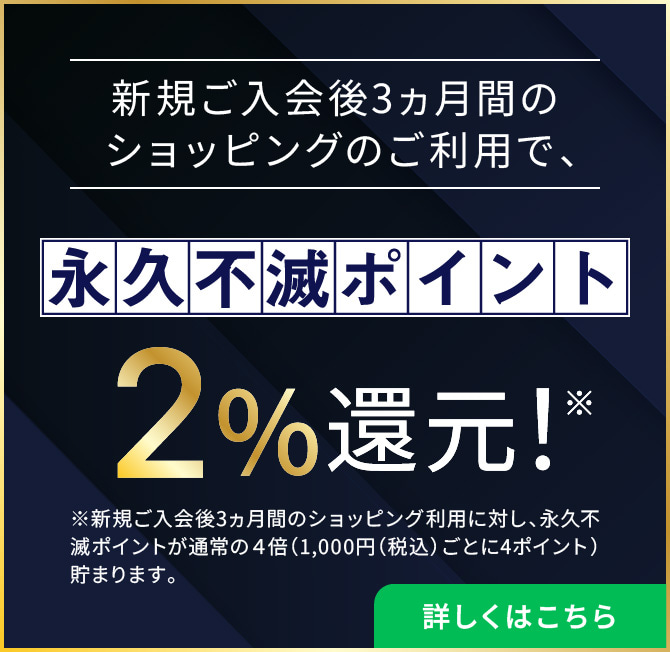確定申告の方法には、持参と郵送とe-Taxの3種類あります。e-Taxはネット環境があれば、パソコンやスマートフォンから利用可能です。そこで今回は、確定申告の方法のうち特にe-Taxについて解説していきます。e-Taxの利用方法やメリット、納税方法まで紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
この記事を読んでわかること
- e-Taxは還付までの期間が短く添付書類の省略もでき、青色申告特別控除として最高65万円の適用がある
- 事前に利用者識別番号を取得し、マイナンバーカードなど必要書類を揃えてから進めるとスムーズ
- 納税は現金や振込、振替、クレジットカード、電子マネーなどが利用できる
そもそも確定申告とは?

確定申告とは、1月から12月までを1年とし、その1年間の所得税を計算して翌年の所定期間内に税務署に申告する手続きのことです。ここからは、そもそも確定申告とは何なのかについて解説していきます。
- 確定申告が必要なケース
- 確定申告の提出方法は3種類
確定申告が必要なケース
確定申告は、主に個人事業主やフリーランス、年金所得者などで必要です。ただし、個人事業主やフリーランスで所得が48万円以下ならば申告の必要はありません。また、会社員やアルバイト・パートなど給与所得の場合は、勤務先で年末調整をしているので原則として確定申告は不要です。
ただし、給与所得が2,000万円を超える人や副業の所得が20万円を超える人、医療費控除や住宅ローン控除を受ける初年度の場合などは、会社員であっても確定申告が必要です。
確定申告の提出方法は3種類
確定申告の提出方法は、作成した申告書を窓口へ持参する方法と郵送、オンラインで完結するe-Taxの3種類があります。
窓口持参は、地域の税務署が確定申告の時期に専用会場を設けています。ほとんどの場合、確定申告時期には税務署に持参するのではなく、確定申告専用会場へ行くことになります。特に確定申告の締め切り期日前は混み合うため、早めに準備しましょう。
e-Taxとは?

e-Tax(国税電子申告・納税システム)とは、ネットを通じて所得税や消費税などの申請や届け出ができるシステムです。インターネット環境があれば、自宅や事務所から行政手続きが可能です。パソコンやスマートフォンから、マイナンバーカードを読み取ることでいつでも利用でき、利便性が高い申告方法です。
確定申告書の作成からオンライン申告まで、e-Taxで完結し、その後の進捗状況も逐一確認できます。還付が行われる場合、確定申告書を持参または郵送する手続きよりも、e-Taxの方が着金が早い傾向にあります。
e-Taxの確定申告はメリットが多い

e-Taxで確定申告するメリットについて、次の5つを紹介します。
- どこでも手続きできる
- 会計ソフトのデータを使える
- 還付までの期間が短い
- 添付書類を省略できる
- 控除額が増える可能性も
どこでも手続きできる
インターネット環境さえあれば、パソコンやスマートフォンでどこでも手続きが可能です。税務署窓口や郵便ポストまで出向く必要がありません。
会計ソフトのデータを使える
日々のお金の流れを会計ソフトへ入力している人は、そのデータを使ってe-Taxでの確定申告が可能です。e-Taxソフトに会計データを取り込むことができるため、確定申告書作成をイチから行う必要がありません。
還付までの期間が短い
前述したとおり、e-Taxは還付までの期間が短いのが特徴です。窓口持参や郵送では、還付金の振り込みまでに1~2カ月かかるところ、e-Taxでは2週間前後で振り込まれます。
添付書類を省略できる
e-Taxでは、確定申告の際に必要な添付書類を省略できます。ただし、全ての書類が省略できるわけではないため、事前に確認しておきましょう。省略可能な例として、生命保険料控除証明書や社会保険料控除証明書があります。
控除額が増える可能性も
確定申告は、帳簿の方式によって白色申告と青色申告が選べます。青色申告の場合、さらに簡易簿記と複式簿記に分かれており、複式簿記では最高55万円の青色申告特別控除額が発生します。さらにe-Taxで申告すると最高65万円まで差し引けることがe-Taxの大きなメリットであるといえます。
【事前準備】e-Taxで確定申告するやり方

e-Taxを使うための事前準備について、次の内容に沿って説明していきます。
- 事業の収支や所得控除の証明書をまとめておく
- 利用者識別番号の取得
- 電子証明書(マイナンバーカード)を取得する
- e-Taxの利用環境を整える
事業の収支や所得控除の証明書をまとめておく
個人事業をしている人は、日々のお金の流れを帳簿などで管理していることがほとんどでしょう。それ以外の人でも、確定申告の対象となる事業の収支内訳がわかる帳票や、所得控除に必要な証明書をあらかじめまとめておくと申告がスムーズです。
例えば、セゾンのふるさと納税なら、寄付ごとに自治体が発行していた寄付金受領証明書を1枚にまとめられるので便利です。
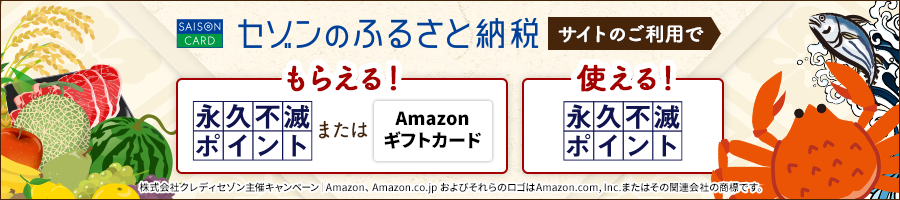
利用者識別番号の取得
利用者識別番号とは、e-Taxを利用するために必要な16桁の番号のことです。税務署で対面手続きを行い発行してもらうか、e-Taxから利用者情報を登録して取得可能です。
電子証明書(マイナンバーカード)を取得する
あらかじめマイナンバーカードを取得しておけば、パソコンにカードリーダーを接続することで情報を読み込んで確定申告が可能です。したがって、改めて電子証明書を取得する必要がありません。
e-Taxの利用環境を整える
事前に利用環境を整えておきましょう。パソコンを使う場合にはあらかじめe-Taxソフトをダウンロードしておきます。スマートフォンを使う場合には、専用アプリをダウンロードしておきましょう。
なお、e-Taxにログインするためにはマイナンバーカードを読み込む方法のほか、ログインIDとパスワードを入力する方法があります。パソコンでマイナンバーを読み込むためには、別途カードリーダーの準備が必要です。
【パソコンから】e-Taxで確定申告するやり方

パソコンからe-Taxを使って確定申告するやり方は次の通りです。まずe-Taxソフトをインストールし起動させておきましょう。
- 確定申告ソフトを用いて申告書を作成し提出する
- 確定申告ソフトをもとにデータ出力し、編集と提出をe-Taxで行う
- e-Tax上で申告書データを直接作成し提出する
- 国税庁ホームページ内「確定申告書等作成コーナー」で作成し、提出をe-Taxで行う
必ずしも確定申告ソフトを使う必要はありませんが、確定申告ソフトを使えば日々の帳簿管理がそのまま確定申告書作成につながるため手軽で良いでしょう。確定申告ソフトを使わない場合でも、e-Tax上や国税庁ホームページから申告書作成は可能です。自分にとって利便性の高い方法を選びましょう。
【スマホから】e-Taxで確定申告するやり方

スマートフォンからe-Taxを使って確定申告するやり方は次の通りです。
- マイナポータルアプリをダウンロードする
- マイナポータルとe-Taxを連携させる
- 連携後、自動的に必要データが確定申告書に反映される
注意点として、事前にマイナンバーカードや通知カードなど、マイナンバーのわかる書類の準備が必須である点です。IDパスワード方式のログインを選んだ場合でも、マイナンバーが必要となるためです。
また、スマートフォンにマイナンバーカードの読み取り機能がついていない場合は利用できません。あらかじめ、自分のスマートフォンが対応しているかどうか確認しておきましょう。
納税のやり方

確定申告で決められた税金の納税方法として、現金・振込・振替・クレジットカード・電子マネーなどがあります。ただし、自治体によって対象となるクレジットカードや電子マネーが違うため、利用可否も含めて事前に確認しておきましょう。
納税にはクレジットカードの「セゾンカード」がおすすめ!
クレジットカードでの納税は、ほとんどの自治体で導入されています。その際は、セゾンカードの利用がおすすめです。セゾンカードで納税すると、永久不滅ポイントが貯まります。時間や曜日に関係なく納税でき、一時的に手持ちの現金が不足していてもクレジットカードなら納税可能です。
これからセゾンカードを持つなら「セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード Digital」がおすすめです。申し込み方法はとても簡単で、スマートフォンから最短5分で手続きができ、ショッピングはもちろんキャッシングにも利用が可能です。
もちろん電子決済にも対応しているので、実店舗でもWEBサイトでもすぐお買い物ができます。アプリで簡単に利用明細の参照や利用停止手続きができるのも便利です。
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード Digitalの詳細はこちら
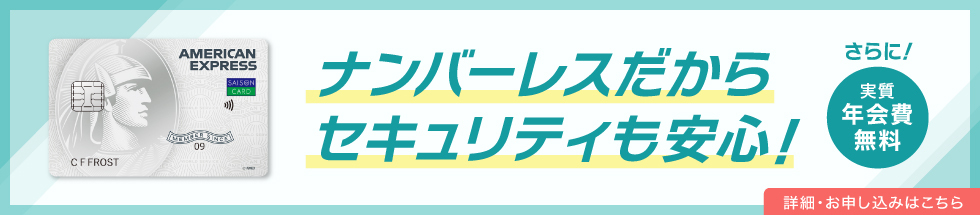
個人事業主の方におすすめのクレジットカード
個人事業主向けのクレジットカードとしておすすめなのが「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード」です。
プライベート用と仕事用でクレジットカードを分けることで経費管理が楽になります。
毎月利用明細で利用状況を確認できるため、都度現金の収支を出納帳などに記録する手間も省けるだけでなく、インターネット通販での注文が簡単になる点もメリットでしょう。
SAISON MILE CLUBを同時にご登録いただくと、JALのマイル還元率最大1.125%!
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードの詳細はこちら
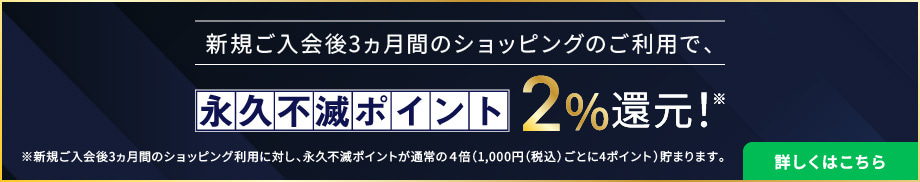
おわりに
確定申告は、個人事業主やフリーランスは毎年必要であり、要件を満たす会社員など給与所得者も対象となります。確定申告は所定の期間内に申告を終わらせる必要がありますが、確定申告会場での提出や郵送では還付金の振り込みに1~2カ月かかることがあります。
e-Taxを利用すると還付が2週間前後であり、処理が早いというメリットがあります。インターネット環境があれば、パソコンやスマートフォンからいつでもe-Taxの利用は可能です。e-Taxは、事前準備を行うことでスムーズな確定申告ができるためおすすめです。