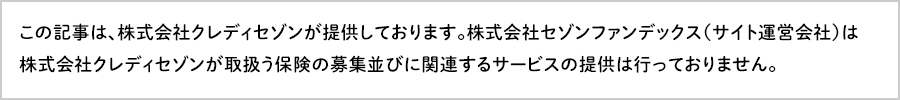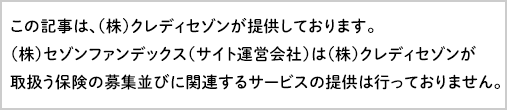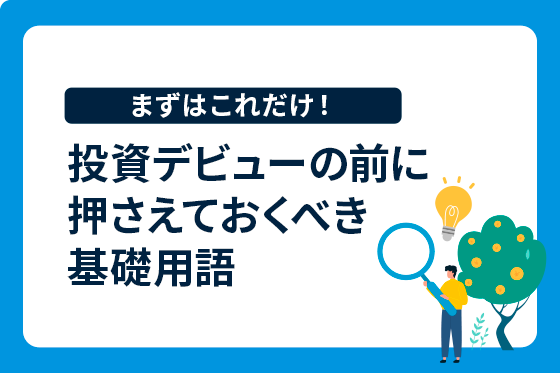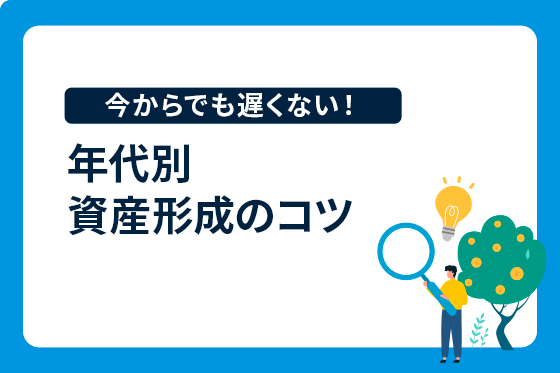住宅ローンの完済が近づくと、返済に使っていたお金をどうしようか考える人も多いでしょう。また、まだ返済が多く残っている人は、早く返したいかもしれません。住宅ローンの完済は喜ばしいことですが、人生100年時代を乗り切っていくには完済後の生活設計も重要です。
この記事では、住宅ローン完済を早めるための対策、完済後の手続き、完済後にもかかる費用や浮いたお金の使い道などを解説します。住宅ローンを早く完済したい人、完済が近い人は参考にしてください。
- 住宅ローンは、定年退職前の65歳までに完済できるのが理想
- 住宅ローンを完済したら速やかに抵当権抹消手続きをする
- 住宅ローン完済後は数百万円の修繕費用が必要な場合がある
- 住宅ローンを完済して浮いたお金は老後資金の準備に使うと良い
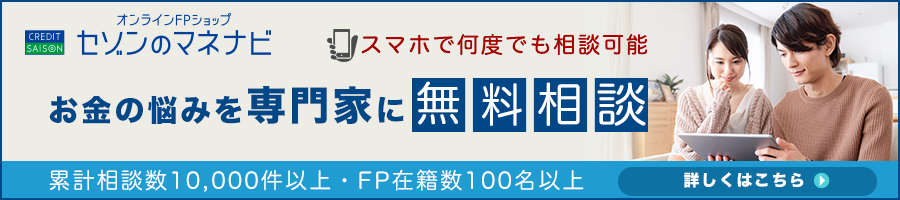
住宅ローンが完済した後の生活負担はどうなる?

住宅ローンが完済したときの喜びと安堵感は、長年の返済を終えた人にしかわからない特別な瞬間です。毎月の返済から解放され、家計に大きな余裕が生まれ、新たな人生のステージが始まります。
例えば、毎月10万円のローン返済をしていた家庭であれば、その分を自由に使えるようになり、貯蓄のペースも格段に上がります。また、完済によってマイホームが完全な自己資産となり、財産形成の大きな一歩となる点も喜ばしいポイントです。
しかし、人生100年時代において、ローンの完済はゴールではありません。完済後も固定資産税や住宅の修繕費など、一定の支出は継続して発生します。特に築年数が経過した住宅では屋根や外壁の塗り替え、設備の更新など、予想以上の費用がかかる場合もあります。
さらに、老後の生活設計も重要な課題となります。厚生労働省の「令和5年簡易生命表」によると、平均寿命は男性で81.09歳、女性で87.14歳まで延びており、老後の生活資金の十分な確保が不可欠です。そのため、完済後の余裕資金はセカンドライフに向けた資産形成に活用する必要があります。
住宅ローンは何歳までに完済するのが理想?

住宅ローンは、定年退職前の65歳までに完済できると理想的です。しかし、借入時の平均年齢は40歳前後で、完済年齢が70歳~75歳になるケースも少なくありません。
以下は、国土交通省のデータで住宅の一次取得者(初めて住宅を取得する人)の平均年齢と、住宅ローンの平均返済期間を住宅の種類別にまとめた表です。ここから、40歳前後で住宅ローンを組むと、65歳での完済は難しいとわかります。
【住宅の平均取得年齢と平均返済期間】
| 住宅の種類 | 一次取得者の平均年齢(歳) | 平均返済期間(年) |
|---|---|---|
| 注文住宅 | 40.1 | 32.7※ |
| 分譲戸建住宅 | 36.6 | 29.7 |
| 分譲集合住宅 | 39.9 | 28.0 |
| 既存(中古)戸建住宅 | 43.1 | 26.2 |
| 既存(中古)集合住宅 | 44.2 | 29.0 |
※住宅建築における借入金の返済期間
上記から、40歳前後で住宅ローンを組むと、65歳での完済は難しいとわかります。しかし、定年後の返済継続は、年金収入だけでは返済が厳しくなる可能性があるため注意が必要です。例えば、毎月の返済額が8万円の場合、年間96万円の支出となり、平均的な年金受給額から考えると、生活を圧迫する要因となるおそれもあるでしょう。
このため、住宅ローンの返済計画を立てる際は、将来の収入見込みや生活設計を踏まえた慎重な検討が求められます。特に、50代以降に借り入れる場合は、退職金での一部繰り上げ返済や、返済期間の調整など、柔軟な対応策を事前に考えておくようにしましょう。
住宅ローンの完済年齢を早めるためにできること

住宅ローンは65歳までに完済するのが理想です。
ここでは、少しでも完済年齢を早くする方法を紹介します。
繰り上げ返済
繰り上げ返済をすると住宅ローン残高が減り、住宅ローンの完済を早められます。繰り上げ返済とは通常の返済とは別にまとまった資金を用意して返済することで、総支払利息の軽減できる方法です。
繰り上げ返済には返済額軽減型と期間短縮型の2種類があり、返済額軽減型は毎月の返済額を減らし、期間短縮型は返済期間を短縮します。どちらを選択するかは、個人の生活設計に合わせて決めましょう。
繰り上げ返済を検討する際は必ずシミュレーションをして、具体的な効果の確認が必要です。また、金融機関によっては手数料がかかる場合もあるため、事前に確認しましょう。
借り換え
借り換えとは、現在返済中の住宅ローンを新たな住宅ローンを借り入れて一括返済する方法です。
借り換えのメリットは主に金利の低いローンに変更して、返済総額を減らせる点です。また、借り換え時には返済期間の短縮も可能で、完済年齢を早められます。
ただし、借り換えには保証料や事務手数料、登記費用といった諸費用が発生するため、金利の差による節約効果との比較が必要です。また、年齢や年収などの審査基準を満たす必要があるため、複数の金融機関に相談して自身に最適な商品を選ぶようにしましょう。
返済条件変更
返済条件変更は、現在の住宅ローンを組んでいる金融機関との契約内容を見直す方法です。完済年齢を早めたい場合、借入期間を短縮します。
返済条件変更は借り換えと比べて手続きが比較的簡単で、諸費用も抑えられる傾向にあります。ただし、増額した返済額を継続して支払える収入があるかどうかの審査は必要です。
全額繰り上げ返済
全額繰り上げ返済とは、住宅ローンの残高をすべて返済することです。住宅ローンを完済して毎月の返済がなくなるため、家計に余裕が生まれます。
しかし、必ずしも全額繰り上げ返済が最良の選択とはかぎりません。まとまった資金がある場合、資産運用をしたほうが有利なケースがあるためです。
例えば、手元に1,000万円の資金があり、借入残高が1,000万円、残りの返済期間が10年、住宅ローンの金利が1%の場合を考えてみましょう。
全額繰り上げ返済した場合、10年間で支払う利息は約51万円節約できます。しかし、1,000万円を年3%で運用した場合、10年間で得られる利益は約344万円になります。
このように、低金利環境下では全額繰り上げ返済よりも資産運用を選択するほうが有利になる可能性があります。ただし、資産運用にはリスクが伴うため、ご自身のリスク許容度や将来の資金計画を考慮したうえで判断するようにしましょう。
住宅ローン完済後に必要な手続き
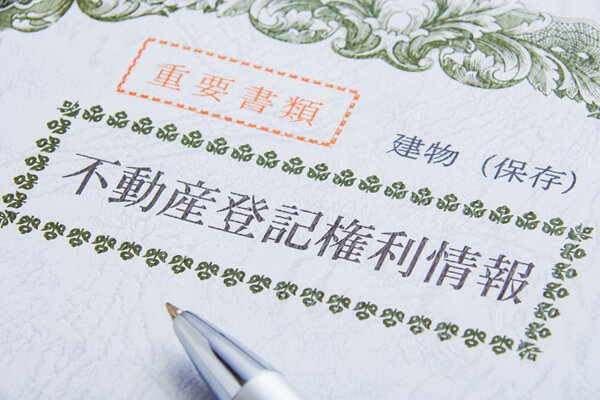
住宅ローンを完済したら、抵当権抹消手続きをします。抵当権抹消は法律上の義務ではありませんが、抵当権が残ったままだと将来の不動産売却などに支障が出る可能性があるためです。また、相続時のトラブルを防ぐためにも、完済後はできるだけ早めの手続きをおすすめします。
ここでは、抵当権についてと、抵当権抹消に必要な手続きの流れについて解説します。
抵当権とは?
抵当権とは住宅ローンを借りる際に、金融機関が土地や建物を担保として設定する権利です。返済が滞った場合に金融機関がその不動産を売却して、債権を回収できる権利を確保するために設定されます。
抵当権は不動産登記簿の権利部に記載され、完済後も自動的には消えません。そのため、住宅ローンを完済しても抵当権を抹消しないと将来的に不動産を売却する際の障害となる可能性があります。
住宅ローンの完済後は、速やかに抵当権の抹消手続きをすませましょう。
抵当権を抹消する手続きの流れ
抵当権の抹消手続きは以下の手順で進めていきます。
- 必要書類を準備
- 法務局に抵当権抹消登記の申請
- 登記完了後に書類を受け取る
まず、住宅ローン完済後1~2週間程度で金融機関から必要書類が郵送されてきます。次に、法務局のホームページから登記申請書をダウンロードし、必要事項を記入します。その後、自宅を管轄する法務局に書類を提出しましょう。申請の際には、不動産1件につき1,000円の登録免許税が必要です。
書類審査には1~10日程度かかり、不備があった場合は法務局から連絡が入ります。登記完了後、法務局で完了書類を受け取ると手続きは終了となります。なお、手続きに不安がある場合は、司法書士への依頼も可能です。
住宅ローン完済後にも引き続き支払いが必要な費用

住宅ローンが終わったらローンの支払いはなくなりますが、家の所有や維持管理について発生する費用があります。
ここでは、住宅ローン完済後にも支払いが必要な費用を解説します。
固定資産税
固定資産税は土地や建物を所有しているかぎり、毎年1月1日時点の所有者に課せられる地方税です。税額は固定資産税評価額に標準税率1.4%を掛けて算出されます。新築住宅の場合は3年間(長期優良住宅は5年)、建物部分の税額が半額になる軽減措置も適用されます。
納付は年4回の分割払いが原則で、毎年春頃に市区町村から送られてくる納税通知書に従って支払います。
住宅の修繕費
住宅の修繕は、快適な住環境を維持するために欠かせません。不動産情報サービスのアットホーム株式会社の「『一戸建て修繕』の実態調査 2023」によると、一戸建て修繕にかかった費用 平均615.1万円(築年数平均38年)となっています。
この金額をもとに修繕費用の準備をする場合、月あたりの積立額は約13,000円になります。外壁の塗り替えや水回りの設備の交換といった大規模な修繕が必要になる場合もあるため、計画的に資金を積み立てておきましょう。
火災保険料
住宅ローンを完済した場合でも、火災保険への加入は必要です。火災保険は火災だけでなく、風水害や落雷など、さまざまな自然災害による被害を補償するものです。
近年、自然災害の増加に伴い、火災保険料は上昇傾向にあります。火災保険料を節約するためには、補償内容を見直したり、長期契約を検討したりする方法があります。補償内容を見直す際は、必要な補償をしっかりと確認し、不要な補償は外すようにしましょう。また、火災保険は契約期間が長いほど保険料が割安になるため、できるだけ長期間の契約がおすすめです。
また、同じ補償内容でも保険会社によって保険料が異なるため、複数の保険会社を比較検討しましょう。
住宅ローン完済後の資金の使い道

住宅ローンの返済が終わると、返済に回していたお金が浮きます。一部は使ってしまわずに、人生100年時代の長い老後に向けての積み立てがおすすめです。
ここでは、積立定期預金、積立投資信託、個人年金保険、NISA(少額投資非課税制度)を紹介します。
| 運用方法 | 特徴 | リスク | リターン | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|
| 積立定期預金 | ・元本保証あり ・手続きが簡単 | ・インフレリスク | ・金利は非常に低い | ・安全性重視の人 ・元本割れを避けたい人 |
| 積立投資信託 | ・少額から始められる ・分散投資が可能 ・長期運用に適する | ・元本割れリスク ・価格変動リスク | ・中程度のリターン ・運用次第で変動 | ・長期投資志向の人 ・ある程度のリスクを許容できる人 |
| 個人年金保険 | ・老後の定期収入確保 ・受取時期を選択可 | ・インフレリスク ・途中解約で元本割れ | ・安定的 | ・計画的な資産形成をしたい人 ・将来の年金受取を重視する人 |
| NISA | ・非課税投資枠の活用 ・長期分散投資に適する ・株式 ・投資信託に投資可 | ・元本割れリスク ・価格変動リスク | ・高リターンの可能性 ・非課税の恩恵 | ・積極的な資産形成をしたい人 ・税制優遇を活用したい人 |
積立定期預金
積立定期預金は、毎月一定額を定期的に預け入れる定期預金の一種です。元本が保証されており、安全性が高い金融商品として知られています。
ただし、普通預金と同様に金利が低く、長期的なインフレリスクに対する備えとしては十分とはいえません。
積立定期預金は、セカンドライフで使う予定が具体的に決まっている資金の預け先としては適しています。例えば、数年後の大規模修繕や旅行資金といった、使用時期が明確な資金の管理に向いているでしょう。
積立投資信託
積立投資信託とは、毎月一定額の投資信託を積み立てていく投資方法です。投資信託は専門家が投資先を選んで分散投資をする金融商品ですが、元本は保証されていません。
積立投資信託は価格が変動する商品を、毎回異なる数量で買い付ける仕組みです。値上がり時は少なく、値下がり時は多く買えるため、購入単価が平均化され、価格変動リスクを抑える効果を期待できます。
また、老後に資産を取り崩す時期になったときに、全額を売却せずに運用を続けると、資産寿命を延ばせる可能性があります。例えば、1,000万円の資産があり、毎月5万円ずつ取り崩す場合、運用をしないと約17年で底をつきますが、年利2%で運用すれば20年以上枯渇しません。
投資信託のリスクは商品ごとの運用方針によって大きく異なります。株式中心の投資信託は値動きが大きく、債券中心の投資信託は比較的安定的です。そのため、自身のリスク許容度に合わせて、適切な投資信託を選択する必要があります。
個人年金保険
個人年金保険は、計画的な老後資金の準備に適した金融商品です。契約時に定めた年齢から年金を受け取ることができ、受取期間は10年確定や終身など、ニーズに応じて選択できます。
加入は65歳くらいまで可能で、毎月の積立型だけでなく、まとまった資金での一時払いも選べます。また、年金受取開始前に死亡した場合は、それまでの払込保険料相当額が死亡給付金として受け取れるタイプが多く、安心感があります。
現在の低金利環境では貯蓄性は高くありませんが、定額型を選べば将来の受取額が契約時に確定するため、老後の収入を確実に確保できます。
NISA
2024年から新しくなったNISA(少額投資非課税制度)は、住宅ローン完済後の資産形成に活用できる魅力的な制度です。つみたて投資枠(年間120万円)と成長投資枠(年間240万円)を併用でき、投資による利益が非課税となるため、効率的な資産形成が可能です。
つみたて投資枠では比較的リスクの低い投資信託も選べるほか、成長投資枠ではさまざまな金融商品に投資できるため、自分のリスク許容度に応じた運用ができます。また、非課税枠は無理に上限まで使う必要はありません。家計の状況や目標に合わせて、適切な投資計画を立てることが大切です。
住宅ローンの返済方針や返済後の資産の使い道に迷ったら「セゾンのマネナビ」にご相談ください

住宅ローンの返済方針や完済後の資金活用について専門家に相談したい方は、「セゾンのマネナビ」がおすすめです。「セゾンのマネナビ」は、お金に関する幅広い相談を無料でできるサービスです。生命保険や投資信託、住宅ローン、不動産売買といった、お金に関するさまざまな悩みを無料で相談できます。
豊富な知識と経験を持つFP(ファイナンシャルプランナー)があなたの状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれます。ご自宅からでも気軽に利用できるオンライン面談のほか、対面での相談も可能です。
まずは気になることを整理して、プロのアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。将来の不安を解消し、より良い資産形成の第一歩として、ぜひ「セゾンのマネナビ」をご活用ください。
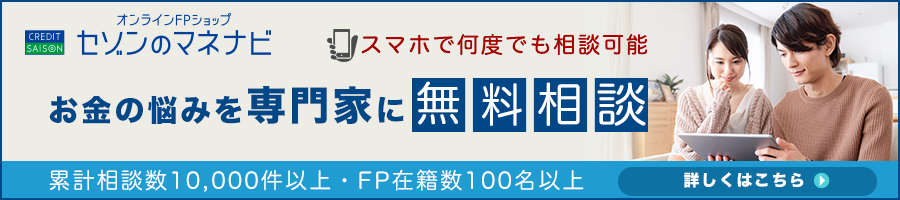
おわりに
住宅ローンの完済は長年の返済からの解放を意味する大きな節目ですが、これはゴールではなく新たなスタートと考えましょう。人生100年時代において、完済後も固定資産税や修繕費のような継続的な支出は発生します。
完済によって生まれた余裕資金は、老後の生活に向けた資産形成に活用することをおすすめします。自身のリスク許容度に合わせて運用方法を選択し、計画的な資産形成を心がけましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。