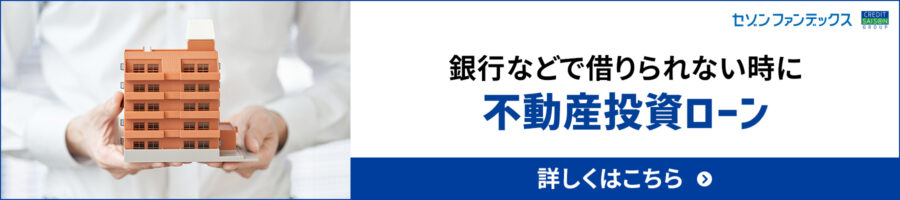会社員が副業で不動産投資するケースが増えています。しかし、初年度は物件の購入や賃貸の準備などで費用がかかるため、利益が出ないケースも少なくありません。
その際に「赤字なら確定申告は不要」と考える方もいますが、利益がないことを申告すると、翌年以降の税負担を抑えられる可能性があります。そのため、出費を抑えて不動産投資を有利に進めるならば、確定申告の知識は不可欠と言えるでしょう。
この記事では、不動産投資する場合の確定申告について解説します。申告方法や時期、節税ポイントなどを紹介するので、不動産投資を始めようとしている方や、すでに取り組んでいる方はぜひ参考にしてください。
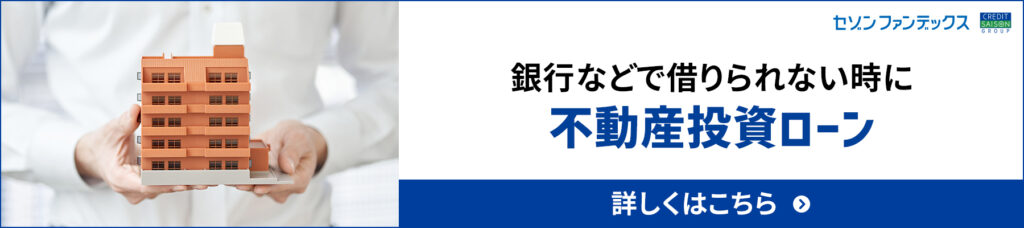
不動産投資を始めたら確定申告が必要

不動産投資を始めたら会社員であっても確定申告が必要です。ここでは、確定申告の概要を紹介します。
- 確定申告の内容と申告期限
- 不動産所得に該当するもの
- 所得税の計算方法
会社員の方は確定申告に触れる機会が少ないでしょう。まずは、正確な申告をするために確定申告について内容を把握してください。
確定申告の内容と申告期限
確定申告とは、1月1日から12月31日までに生じた所得を計算して所得税を確定させる手続きです。通常、申告期間は2月16日から3月15日ですが、年によっては土日祝の関係で変更となる場合があります。
多くの給与所得者は年末調整で所得税額が確定するため、確定申告の必要はありません。ただし、以下に該当する場合は申告が必要になります。
- 給与収入が2,000万円を超える場合
- 副業の所得(収入から経費を差し引いた額)が20万円を超える場合
- 2ヵ所以上から給与を受け取っている場合
- 医療費控除や住宅ローン控除などを適用する場合
上記に当てはまる方は、確定申告の申告期間を確認し、準備を進めましょう。
なお、赤字(損失)が発生した場合でも確定申告を行うことで、翌年以降の税負担を軽減できる場合があります(詳細は後述します)。
参照元:国税庁「確定申告が必要な方」
不動産所得に該当する収益
不動産収入とは、土地や建物などの不動産を貸し付けて得た収益を指し、主に以下のものが対象です。
- 土地や建物の貸付
- 不動産上の権利の設定や貸付(例:借地権等)
- 船舶や航空機の貸付
- 更新料や頭金などの名目で受け取るもの
- 保証金や敷金など返還の必要がないもの
- 共益費として受け取る水道光熱費(賃貸契約で家賃と一体の場合)
- ※家賃と分けて管理する場合は「雑所得」となることがあります。
- 駐車場収入(貸付契約に基づく場合)
これらの収入から必要経費を差し引いた金額が、不動産所得になります。
参照元:国税庁「不動産所得を受け取ったとき(不動産所得)」
所得税の計算方法
所得税は以下の流れで計算します。
- 収入 − 経費 = 所得
- 所得 − 所得控除 = 課税所得(1,000円未満切り捨て)
- 課税所得 × 税率 − 控除額 = 所得税
所得税は累進課税が適用されており、所得が増えると税率も上がります。以下の表に税率と控除額をまとめました。
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円〜1,949,000円 | 5% | なし |
| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
例えば、課税所得が200万円の場合、所得税額は102,500円(=200万円 × 10% − 97,500円)となります(※復興特別所得税2.1%は含まれていません)。なお、給与所得がある場合は不動産所得と合算した金額に対して所得税が計算されます。
参照元:国税庁「所得税の税率」
不動産投資した人が確定申告で税金を減らす3つの方法

確定申告する際は、以下の方法を実践すると税金を抑えられます。
- 経費を正確に計上する
- 青色申告を利用する
- 所得控除を申請する
正確な申告を心がけて税負担を減らしましょう。
経費を正確に計上する
不動産所得を得るための費用は経費として計上でき、税金を抑えることにつなげられます。経費として認められる費用の例は、以下のとおりです。
| 不動産投資ローンの利息 | 元本部分は不可 |
| 物件の管理費や修繕費 | 清掃費や補修にかかる費用など |
| 管理委託料 | 管理会社へ支払う費用 |
| 不動産投資にかかる税金 | 固定資産税や登録免許税 など |
| 火災保険や地震保険の保険料 | 物件にかかる保険料 |
| 減価償却費 | 建物や設備の購入費を耐用年数に応じて計上 |
| 税理士や司法書士への報酬 | 確定申告や契約書作成などで専門家に依頼した際の費用 |
| 交通費や交際費 | 物件管理に関するもの |
| 不動産の管理で使用する自動車にかかる費用 | ガソリン代や車両の維持費など |
修繕費は、その内容によって「資本的支出」とみなされる場合があり、この場合は経費として一度に計上できず、耐用年数に応じて減価償却で分割計上する必要があります。たとえば、増築やエレベーターの設置、屋根の全面葺き替えなどが該当します。特に内装工事や大規模なリフォームは、全額が修繕費として認められないケースも少なくありません。
経費として計上できる支出は税負担を軽減する効果が大きいため、正確に分類し、計上しましょう。なお、領収書やレシートは、青色申告の場合は7年間、白色申告の場合は5年間の保存が必要です。間違えて処分しないよう注意してください。
青色申告を利用する
確定申告で「青色申告制度」を利用すると、税金を抑えられます。青色申告制度とは、申告により以下の特典を受けられる制度です。主に個人事業主が利用しますが、給与所得者でも不動産所得がある場合には利用が可能です。
| 内容 | 条件や注意点 | |
|---|---|---|
| 青色申告特別控除 | ・所得控除を受けられる | ・最大65万円 |
| 貸倒引当金 | ・回収が危険な債権を費用計上できる | ・債権合計額の5.5%まで (金融業は3.3%) |
| 損益通算 | ・赤字が出た場合、3年間繰り越して税負担を軽減できる | ・本年度の赤字の繰戻しもできる |
| 青色事業専従者 | ・家族を従業員として雇う場合、支払う給与を経費にできる | ・生計を一にする15歳以上の家族 ・適用すると配偶者控除や扶養控除は利用できない |
| 少額減価償却資産の特例 | ・30万円未満の固定資産を一括で経費に計上可能 | ・1年での上限は300万円 |
特別控除は3種類あり、適用する際の条件は以下になります。
| 控除額 | 対象所得 | 記帳方法 | 貸借対照表の添付 | 損益計算書の添付 | e-Taxでの確定申告 |
| 65万円 | ・事業所得 ・不動産所得 (事業的規模) | 複式簿記 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 55万円 | 複式簿記 | 必要 | 必要 | 不要 | |
| 10万円 | ・事業所得 ・不動産所得 ・山林所得 | 単式簿記でも可 | 不要 | 必要 | 不要 |
なお、不動産所得の「事業的規模」とは、主に以下のいずれかに該当するケースを指します。
- 10室以上のマンションやアパート
- 5棟以上の一戸建て
ただし、税務署が賃料収入の規模(たとえば年500万円以上など)を基準に判断する場合もあります。物件の内容や地域によっても異なるため、詳しくは税理士などの専門家に確認することをおすすめします。
これらの要件を満たさない場合も不動産所得として扱われますが、「事業的規模」には該当せず、青色申告特別控除の65万円・55万円はいずれも受けられません。
また、複式簿記とは1つの取引を2箇所に記入する方法で、単式簿記と比べて手間がかかる一方、お金の流れが明確になるというメリットがあります。
加えて、貸借対照表は財政状態を示す財務諸表のひとつで、65万円・55万円の控除を受ける際は添付が必要です。
さらに65万円の控除を受けるには、e-Taxでの申告が必須です。e-Taxは税金の手続きをインターネット上で行えるシステムで、24時間利用できるため、青色申告を行う際には利用を検討してみてください。
青色申告制度を利用するためには、利用する年の3月15日まで、もしくは事業開始日から2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
なお、白色申告を利用した場合のメリットとデメリットは以下になります。
| メリット | ・記帳が簡易的 ・確定申告前の手続きが不要 |
| デメリット | ・特別な控除枠がない ・赤字を翌年以降に繰り越せない ・貸倒引当金を設定できない ・家族への給与を経費にできない |
上記の内容を理解して、両者の選択をしてみてください。
所得控除を申請する
確定申告する際は所得控除を申請すると課税所得を減らせるため、税金の減額につながります。所得控除の種類を、以下の表にまとめました。
| 主な適用条件 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 | |
| 基礎控除 | ・所得が2,500万円未満 | ・最高48万円 | ・最高43万円 |
| 社会保険料控除 | ・社会保険料を支払った方 ・家族の分も対象 | ・1年間で支払った社会保険料の全額 | ・1年間で支払った社会保険料の全額 |
| 配偶者控除・配偶者特別控除 | ・一定の要件を満たした配偶者 ・納税者本人の所得が1,000万円以下 | ・最高48万円 | ・最高33万円 |
| 扶養控除 | ・16歳以上の扶養親族 | ・最高63万円 | ・最高45万円 |
| 生命保険料控除 | ・生命保険や個人年金保険などを支払った方 | ・最高12万円 | ・最高7万円 |
| 地震保険料控除 | ・地震保険料を支払った方 | ・最高5万円 | ・最高25,000円 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | ・iDeCoや小規模企業共済へ拠出した方 | ・1年間で支払った掛金全額 | ・1年間で支払った掛金全額 |
| 勤労学生控除 | ・勤労学生の条件に該当する納税者 | ・最高27万円 | ・最高26万円 |
| 障害者控除 | ・納税者や家族が障害者 | ・最高75万円 | ・最高53万円 |
| 寡婦控除 | ・夫と離婚した扶養親族がいる女性 ・所得500万円以下 | ・27万円 | ・26万円 |
| ひとり親控除 | ・ひとりで子どもを育てる親 ・所得500万円以下 ・寡婦控除と併用は不可 | ・35万円 | ・30万円 |
| 寄附金控除 | ・特定の団体に寄付した方 | ・以下の金額の少ない方 − 2,000円 ・寄付金額・総所得金額等の40% | ・(以下の金額の少ない方 − 2,000円)× 10% ・寄付金額・総所得金額等の 40% |
| 医療費控除 | ・1年間の医療費が10万円を超える場合 | ・最高200万円 | ・最高200万円 |
| 雑損控除 | ・災害や盗難などで被害を受けた方 | いずれか多い方の金額 ・損失額 − 総所得金額× 10% ・災害関連の支出 − 5万円 | |
自分が対象になる控除がある場合は、忘れずに申請してください。
不動産投資したサラリーマンが自分で確定申告する方法

不動産投資により確定申告が必要になった場合は、以下の流れで行ってください。
- 必要書類を準備する
- 書類に記入する
- 書類を提出する
期限内に済ませられるように、確定申告の時期が近づいたら早めに準備しておきましょう。
1.必要書類を準備する
確定申告では、以下3種類の書類が必要です。
- 不動産収入に関する書類
- 経費がわかる書類
- 確定申告で必要な書類
それぞれの書類の内容を詳しく解説します。
不動産収入に関する書類
不動産所得を申告する際は、以下の収入がわかる書類を用意しましょう。
- 賃貸借契約書
- 敷金や更新料の管理表
- 家賃送金明細書
- 現金出納帳
- 収入が記載された通帳のコピー
収入を整理して正確な記帳を心がけてください。
経費がわかる書類
確定申告の際は、経費がわかる以下の書類を用意しましょう。
- 領収書
- 税金の納付書
- 年末借入金残高証明書
- 固定資産台帳
- 管理委託契約書
- 給与台帳
- 控除証明書
経費は課税所得を抑えられ所得税の減額につながるため、正確に計上してください。
確定申告で必要な書類
上記の書類が用意できたら、確定申告で必要になる以下の書類を準備しましょう。
- 確定申告書
- 本人確認書類
- 青色申告決算書もしくは収支内訳書
- 源泉徴収票(会社員の場合)
なお、所得税が還付される場合に備えて、口座番号がわかるものを用意しておくと後の手間が省けます。
自分で確定申告を行う時間がない場合は税理士に依頼するのもひとつ

不動産所得の確定申告は、収支の計算や経費の整理など手間がかかる作業が多く、本業が忙しい方や複数の物件を所有する方にとっては大きな負担となります。時間や手間を削減するためには、税理士への依頼も選択肢のひとつです。
確定申告を税理士に依頼する場合の費用は事務所ごとに異なりますが、一般的な相場は以下のとおりです。
| 申告区分 | 税理士費用の相場 |
|---|---|
| 白色申告 | 5〜10万円 |
| 青色申告 | 10万〜20万円 |
ただし、物件数や申告内容の複雑さによって費用が前後することがあります。依頼を検討する際は、事前に見積もりを確認しておくと安心です。
なお、青色申告は控除額が大きいため、節税効果を考慮すれと税理士に依頼するメリットも大きくなります。費用対効果を踏まえて、自分で対応するか税理士に依頼するかを判断しましょう。
費用はかかりますが、税金の知識に自信の無い方にとっては、経費の判断や書類の書き方などのハードルも高く、初年度の申告については税理士に依頼するのも良いかもしれません。
2.書類に記入する
確定申告書は4種類ありますが、すべての方が記入するのは「第一表」と「第二表」の2種類です。
確定申告書の第一表では、以下の情報を記入します。
- 住所
- 氏名
- マイナンバー
- 収入金額
- 所得金額
- 所得控除額
また、第二表での記入項目は以下です。
- 住所
- 氏名
- 控除に関する事項
- 配偶者や親族に関する事項
さらに、青色申告の場合は「青色申告決算書」白色申告の場合は「収支内訳書」を提出します。
3.確定申告書を提出する
確定申告書は以下3つの方法で提出します。
- 税務署に持参
- 郵送
- e-Tax
各提出方法について詳しく解説するので、参考にしてください。
税務署に持参
確定申告は、居住地を管轄する税務署へ持参することで提出できます。管轄の税務署がわからない場合は、国税庁の公式ページから郵便番号や住所を入力して検索もできます。
なお、税務署の開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時までです。開庁時間内に訪問できない場合は、時間外収受箱への投函でも提出可能です。
郵送
確定申告は郵送での提出も可能です。
ただし、確定申告書は「信書」に該当するため、荷物扱いでは送付できません。また、消印日が提出日になるため、申告期限内となるよう早めに送付しましょう。
e-Tax
国税電子申告・納税システム「e-Tax」を利用すれば、確定申告書の作成から提出までインターネット上で完結できます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、アカウント(利用者識別番号)の取得から申告書の作成・送信まで一連の手続きが可能です。
e-Taxは、マイナンバーカード対応のスマートフォンのほか、パソコン+ICカードリーダライタでも利用できます。ご自身に合った方法を選んで申告しましょう。
なお、青色申告特別控除を最大65万円適用するには、e-Taxでの申告が必要です。節税効果を高めるためにも、e-Taxの利用方法を押さえておきましょう。
不動産投資をした人が確定申告を怠った場合に発生する追徴課税

正しく確定申告しなかった場合は、以下の税金が課せられる可能性があります。
- 無申告加算税
- 過少申告加算税
- 重加算税
- 延滞税
余計な税負担を増やさないためにも、正確な申告を心がけましょう。
無申告加算税
無申告加算税は、期限内に確定申告しなかった場合にかかる税金です。
確定申告の期限は通常2月16日から3月15日までですが、この期間を過ぎて申告すると税額に対して以下の税率が課されます。
| 税務調査後に申告をした場合 | 調査の事前通知を受けて申告をした場合 | 自主的に申告をした場合 | |
|---|---|---|---|
| 50万円以下 | 15% | 10% | 5% |
| 50万円超300万円以下の部分 | 20% | 15% | |
| 300万円超の部分 | 30% | 20% |
例として無申告額が200万円の場合、以下の金額が追加で必要になります。
| 50万円まで | 50万円 × 15% = 75,000円 |
| 51万円から200万円の部分 | (200万-50万) × 20% = 300,000円 |
| 合計 | 375,000円 |
なお、無申告加算税は正当な理由がある場合や、期限内に申告の意思があったと認められた場合は課税対象になりません。
過少申告加算税
過少申告加算税は、申告した金額が実際の税額よりも少なかった場合に課される税金です。実際の税額と申告した金額の差額に対して、以下の税率が適用されます。
| 申告額と50万円のうち、多い方を超える部分 | 15% |
| 上記以外 | 10% |
以下の条件を例に、過少申告加算税を計算してみます。
- 申告額:100万円
- 実際の税額:300万円
- 差額:200万円
今回のケースでは申告額が100万円で、50万円よりも大きいため、差額の200万円のうち100万円を超える部分に15%の税率を適用します。
- (200万円-100万円) × 15% = 15万円
残りの100万円は10%の税率で計算します。
- 100万円 × 10% = 10万円
このケースでの過少申告加算税は25万円です。なお、税額が5,000円未満のときや税務調査で指摘を受ける前に自主的に修正した場合は、課税対象になりません。
重加算税
重加算税は意図的な隠蔽や不正などで税金を少なくした場合に課される税金です。通常の過少申告加算税や無申告加算税よりも税率が高く設定されています。
| 過少申告 | 35% |
| 無申告 | 40% |
例として実際の税金が50万円である場合、意図的に過小申告した場合は以下の重加算税が課されます。
- 50万円 × 35% = 175,000円
なお、重加算税は意図的な不正が対象のため、経理上のミスや計算間違いなどは対象外です。
延滞税
延滞税は、毎年3月15日の納付期限までに税金を納付しなかった場合に課せられます。期限日の翌日から実際に納付した日までの期間が課税対象になり、令和7年度は以下の税率が適用されます。
| 期限日の翌日から2ヵ月以内 | 年率2.4% |
| それ以降 | 年率8.7% |
【例】税金10万円を50日間滞納した場合
- 延滞税 = 10万円 × 2.4% ×(50日/365日)= 328円(1円未満切り捨て)
なお、延滞税が発生する場合は税務署から納付書が送付されるので、自分で計算する必要はありません。
参照元:国税庁「延滞税について」
不動産投資で確定申告する際に注意すべき3つのこと

確定申告する際は、以下の点に注意してください。
- 不動産投資の初年度が赤字でも確定申告する
- 会社に副業がバレる可能性がある
- 税負担が重い場合は法人化も検討する
いずれも不動産投資を始めたばかりの方が陥りやすい傾向があります。ひとつずつ見ていきましょう。
不動産投資の初年度が赤字でも確定申告する
不動産投資で赤字となった場合でも、確定申告を行うことをおすすめします。特に青色申告を選択していれば「損失の繰越控除」が利用でき、翌年以降に不動産所得が黒字化した際、最大3年間まで過去の赤字分を差し引いて課税所得を減らすことができるため、実質的な節税効果が期待できます(白色申告では繰越不可)。
なお、会社員の副業であっても、赤字が出た場合は確定申告をしておくことが大切です。
例として、以下の条件での所得税を比較します。
- 1年目:赤字50万円
- 2年目:黒字100万円
このケースでの2年目の所得税額は、以下になります。
| 繰越あり | 繰越なし | |
|---|---|---|
| 所得 | 100万円 | 100万円 |
| 赤字繰越 | −50万円 | なし |
| 課税所得 | 50万円 | 100万円 |
| 所得税 | 25,000円 (=50万円 × 5%) | 50,000円 (=100万円 × 5%) |
※基礎控除(48万円)など各種控除を適用すると、課税所得がさらに減少し、実際の所得税額はより少なくなる場合があります。
不動産投資の1年目は赤字になるケースも多いですが、繰越を適用すると翌年の課税所得が減り、税が軽減されます。その場合に備えて赤字でも確定申告しておきましょう。
会社に副業がバレる可能性がある
不動産投資で確定申告を行うと、「住民税」の金額から副業が発覚するケースがあります。
会社員の場合、給与から住民税が天引きされる「特別徴収」が一般的ですが、不動産投資により住民税額が増えた場合、会社側に給与以外の収入があることが知られ、副業を疑われることがあります。
なお、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」を選択すると、不動産所得にかかる住民税だけを自分で納付でき、会社に副業収入が伝わるリスクを低減できます。ただし、自治体によっては必ずしも反映されない場合もあるため、念のためご注意ください。
また、誤った申告などで税務調査が入った場合、会社に連絡が行く可能性もゼロではありません。こうしたリスクを避けるためにも、申告内容には十分に十分注意しましょう。
税負担が重い場合は法人化も検討する
不動産所得が増え、税負担が重いと感じたら法人化も視野に入れましょう。
個人が納める所得税は「累進課税」を採用するため、所得が増えるにつれ税率が上がります。一方、法人が納める「法人税」の税率は以下の2通りです(資本金1億円以下の場合)。
- 800万円以下:15%
- 800万円超:23.2%
例えば、課税所得が800万円(たとえば10室以上のアパートの賃料など)の場合、所得税と法人税の違いは以下になります。
| 所得税 | 1,204,000円(=800万円 × 23% − 636,000円)/復興特別所得税2.1%を除く |
| 法人税 | 1,200,000円(=800万円 × 15%) |
この結果から、一般的には課税所得800万円が法人化を検討する目安になります。
ただし、法人化は費用がかかるうえ、事務手続きや会計処理が複雑になるデメリットがあります。また、社会保険の負担が増す可能性や法人を維持する手間もかかるため、税額だけで判断するのはおすすめできません。
法人化を検討する際は、自分だけで判断せず、税理士や専門家などに相談してください。
おわりに
不動産投資を始めた方は、確定申告を忘れずに行いましょう。初年度は利益が出ないケースも多いですが、確定申告することで翌年度以降の税額を減らせる可能性があります。
また、確定申告の際は以下のポイントを意識すると節税につながります。
- 経費を正しく計上する
- 青色申告制度を利用する
- 所得控除を忘れずに申請する
確定申告は通常2月16日から3月15日までが期限になり、申告しない場合は以下の税金が加算されるおそれがあります。
- 無申告加算税
- 過少申告加算税
- 重加算税
- 延滞税
節税につなげることで浮かせたお金をさらに事業へ投資でき、売上向上の可能性も高まるため、できる限り正確に確定申告書を作成しましょう。
「不動産投資についてもっと知りたい」という方は、セゾンファンデックスの「不動産投資ローン」をチェックしてみてください。なかでもアパートローンは個人で投資用アパート・マンションを購入したい方や、銀行以外で不動産投資ローンを探している方などにおすすめです。
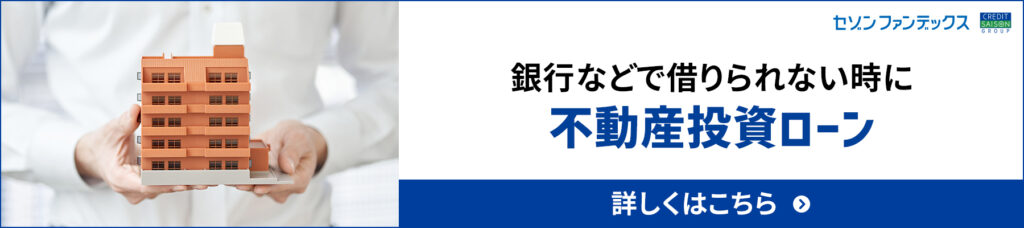
築古・狭小物件・借地権付き建物など、銀行では対応できない案件でも相談可能です。また、法人や個人事業主で投資用アパート・マンションを購入したい方におすすめの不動産投資ローンでは、ワンルームから1棟まで幅広い物件に対応しています。
不動産投資で安定した収入を得つつ、確定申告で正確な申告を心がけて税負担を抑えましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。