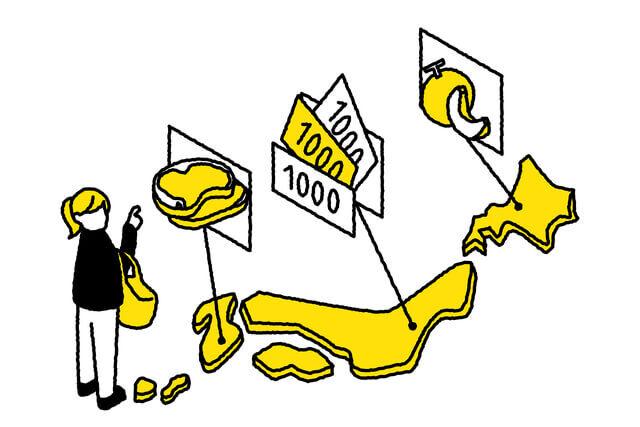自分で選んだ自治体へ寄付することができる「ふるさと納税」は、寄付額に応じて税金が控除され、実質2,000円の負担で返礼品がもらえるという特徴を持つ制度です。
しかし、控除に関する制度が複雑なため、ふるさと納税によって住民税が安くなっていると感じない方も多いのではないでしょうか。
このコラムでは、「返礼品は受け取ったけれど、住民税が控除されていない」「きちんと控除されているか分からない」という方に向けて、ふるさと納税で住民税が安くならない原因や、きちんと税金が控除されているかチェックする方法などをご紹介します。
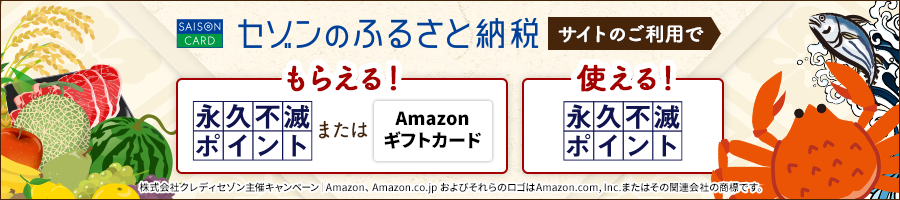
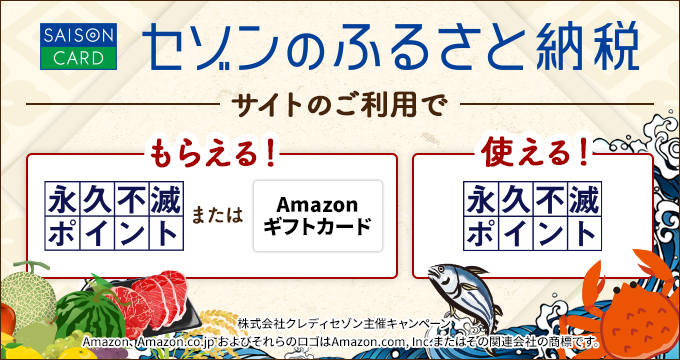
ふるさと納税と控除の仕組み

ふるさと納税は、返礼品を受け取りながら、税金の控除を受けられる便利な制度です。しかし、正しく手続きをしなければ、控除を受けられない点に注意が必要です。ここでは、ふるさと納税の基本的な考え方と、控除を受けるための手続き方法を解説します。
ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、自分の選択した自治体に寄付をした場合、寄付額のうち2,000円を越える部分が、所得税と住民税から還付・控除される制度です。
ふるさと納税という名前ですが、自分の生まれ故郷だけでなく、全国各地の自治体に寄付できます。
寄付金額に応じた返礼品を用意している自治体もあり、ネットショッピングの感覚でできるのもふるさと納税の魅力です。地元の特産品を返礼品に設定している自治体も多いため、全国の特産品を楽しみながら、税金を控除している方も多いでしょう。
また、寄付した自治体に対し寄付金の使い道を選択することも可能です。環境保全や子育て支援など、自分が支援したい分野に寄付金を使用してもらえます。
控除を受けるためには手続きが必要
ふるさと納税で控除を受けるには手続きが必要です。ふるさと納税の手続き方法は、確定申告を使った方法とワンストップ特例を使った方法の2通りがあり、それぞれ手続きの流れが異なります。
確定申告を行う
確定申告を利用してふるさと納税による控除を受ける際は、寄付先の自治体から受け取る書類と申告するタイミングに注意しましょう。
ふるさと納税を行うと、自治体からお礼の品と確定申告に必要な「寄附金受領証明書」という書類が送られてきます。寄附金受領証明書とは、ふるさと納税の寄付をしたことを自治体が証明する書類です。
確定申告は、原則として翌年の2月16日から3月15日までの期間に行われます。確定申告で、ふるさと納税の控除を受ける場合は、この期間中に手続きをしなければいけません。寄附金受領証明書と確定申告書等を用意して、住所地を所轄する税務署で確定申告を行いましょう。また、マイナンバーカードがあれば、税務署に行かなくても自宅でパソコンやスマートフォンなどからの申告が可能です。
寄附金受領証明書を紛失した場合は、寄付先の自治体窓口へ問い合わせて再発行してもらいましょう。また、利用したふるさと納税のサイトが国税庁指定の特定事業者であれば、寄附金控除に関する証明書を発行してくれます。
寄附金控除に関する証明書には、1年分のふるさと納税に関する情報が記載されているため、わざわざ寄付先の自治体に問い合わせる手間が省けます。ただし、寄附金控除に関する証明書の発行には数日かかるため、確定申告前に余裕を持って申請しましょう。
ワンストップ特例制度を利用する
ワンストップ特例制度を利用する場合、確定申告の手続きは不要ですが、代わりにワンストップ特例申請書の提出が必要です。申請書は、自治体から送付されてくることもあれば、ダウンロードできる場合もあります。
ワンストップ特例申請書に記入をしたら、ふるさと納税で寄付をした自治体へ郵送しましょう。なお、寄付した翌年の1月10日必着で送らなければなりません。また、一部の自治体やポータルサイトでは、オンラインでワンストップ特例の申請ができる場合もあります。詳しくは、ご利用のふるさと納税ポータルサイトを確認してみましょう。
ワンストップ特例の場合は、所得税からの還付はされず、ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除されます。
控除が受けられる金額は、確定申告を行った場合もワンストップ特例制度を利用した場合も同じです。
ワンストップ特例は、1年間に寄付した自治体が5団体以下である場合に利用できます。そのため、複数の自治体に対してワンストップ特例の申請書を提出しなければいけない手間が発生します。複数の自治体にふるさと納税を行った場合は、手続き漏れが発生しないように、すぐ郵送手続きをするなどの工夫が必要です。
あっ!控除を受けるには手続きが必要なのね。忘れないように早めにやらなきゃ。
ふるさと納税で住民税が安くならない原因

ふるさと納税を行った方の中には、実際に住民税が安くならない、安くなっているか分からないと悩んでいる方も多いでしょう。
場合によっては、ふるさと納税で寄付をしても税金が控除されないケースもあるため注意が必要です。ここでは、ふるさと納税をしても控除を受けられない原因について説明します。
確定申告をしていない
ふるさと納税をしても住民税が安くならない理由のひとつに、確定申告をしていない、もしくは正しく申告できていない可能性があります。返礼品を選んで寄付するだけでは、税金の還付・控除が受けられません。税金が控除されていない場合は、正しく確定申告ができているか確認しましょう。
なお、確定申告の手続きには、以下の書類が必要です。
- 寄附金受領証明書
- 源泉徴収票などの所得証明書類
- 還付金の受取口座番号
- マイナンバーがわかる書類
- その他、控除を受けるために必要な書類
必要書類を揃えたら、住所地所轄の税務署で確定申告を行いましょう。申請内容に誤りがあった場合でも、更正の請求をすることで正しい内容に訂正できます。
なお、マイナンバーカードがあれば、税務署に行かなくても手続きができるのでおすすめです。マイナンバーカードの申請手続きは『マイナンバーカード申請はスマホでできる!メリットや手順、よくある質問は?』で詳しく解説していますので参考にしてください。
ワンストップ特例制度に申し込みしていない
確定申告が不要な給与所得者で、ふるさと納税先が5団体以内の場合には、ワンストップ特例制度を利用できます。確定申告が不要な給与所得者とは、給与所得が2,000万円以下で1ヵ所のみから給与を受け取っている方や、雑所得が年間20万円以内の方などです。
ワンストップ特例制度を利用する場合は、返礼品を選び寄付する際にワンストップ特例制度の利用を選びます。申請書と必要書類を準備して、期日までにふるさと納税をした自治体へ提出しましょう。なお、申請書類の期日は寄付した翌年の1月10日までです。期日までに必着で送らなければ、控除の対象外となってしまうため忘れないようにしましょう。
無職・専業主婦(夫)の方が申請している
ふるさと納税による税金の還付・控除は、寄付する方の所得金額によって決まります。そのため、無職や専業主婦(夫)の方が申請した場合、そもそも所得が発生していないため、住民税と所得税が安くなることはありません。
仮に、収入がない方がふるさと納税を行った場合には、控除を受けられないため、全額自己負担の寄付として扱われてしまいます。
特に、結婚している専業主婦(夫)の方が、自分の名義でふるさと納税をしてしまうと、控除のメリットが受けられなくなってしまうので注意しましょう。親の扶養に入っている場合は親に、夫の扶養に入っている場合には夫に、ふるさと納税をしてもらうのがおすすめです。
住宅ローン控除を受けている
住宅ローンで住宅を購入する場合、住宅ローン控除を受けられます。住宅ローン控除は、ローン残高の0.7%が所得税と住民税から13年間控除される制度です。
住宅ローン控除は、控除額が非常に大きいため、住宅ローン控除を受けているとふるさと納税による寄附金税額控除ができないことがあります。住宅ローンがある場合は、住宅ローン控除額を確認して、ふるさと納税の控除が利用できるのか確認しておきましょう。
納税者の名義が異なっている
納税者と異なる名義でふるさと納税をしてしまうと、ふるさと納税の税金控除を受けられません。
名義の違いで控除を受けられないトラブルを避けるため、住民税を納めている納税者名義で寄付を行う必要があります。特に注意しなければいけないのは、クレジットカードの名義と納税者の名義が異なるケースです。
例えば、夫名義で寄付をする際に、妻名義のクレジットカードを使って決済したとします。この場合は、税金の控除を申請する名義が夫で、ふるさと納税の決済をした名義が妻になってしまうため、税金の控除を受けられません。
ふるさと納税を利用する際には、税金を納める方とふるさと納税を利用する方、決済するクレジットカードの名義という3者が同じ人物になっているか確認しましょう。
もし、誤って納税者と異なる名義のクレジットカードで決済してしまった場合でも、寄付先の自治体に問い合わせることで決済方法を変更できる可能性があります。できるだけ早めに自治体へ問い合わせて、対応方法を確認しましょう。
課税所得が増えている
住民税が安くならない原因のひとつとして、課税所得が増加していることが挙げられます。なぜなら、ふるさと納税によって住民税の控除を受けられたとしても、それを上回るほど所得が増えていれば、前年の住民税額より安くならないからです。
課税所得が増える要因
収入が増えたり、その他の所得控除額が減少すると、課税所得が増加します。例えば、以下のケースに該当すると、課税所得が増えて住民税が安くなっていないと感じる可能性があります。
- 株や不動産の売却(資産の売却で一時的に所得が増加)
- 昇給や賞与などで収入が増加した(年間の総所得が増加)
- 副業を始めて収入が増加した(雑収入が増えたことで所得が増加)
- 離婚した(配偶者控除が適用されなくなり、課税所得が増加)
- 子どもが扶養から外れた(扶養控除が適用されなくなり、課税所得が増加)
株などを売却した方や副業などで収入が増加した方は、年間の収入額が増加するため、課税所得が増加します。
一方、ライフステージの変化によって配偶者控除や扶養控除などが適用されなくなった方は、収入から差し引ける金額が減少するため、課税所得が増加します。
住民税が思ったように減らなかった場合は課税所得をチェック
ふるさと納税によって住民税が思ったほど安くならなかったと感じている方は、収入の増加だけでなく、所得控除額の減少により課税所得が増えていないか確認するとよいでしょう。課税所得が増加する原因は、収入の増加だけでなく、その他の控除額が減ってしまうことでも起こり得ます。
控除の上限額を超えている
ふるさと納税には、上限額があります。ふるさと納税額の年間上限を超えた金額は、控除の対象とならずに自己負担となります。上限額は寄附した年の所得や家族構成などによって異なるため、注意が必要です。ふるさと納税の各サイトに早見表や控除上限額シミュレーションがあるので、事前にチェックしておきましょう。
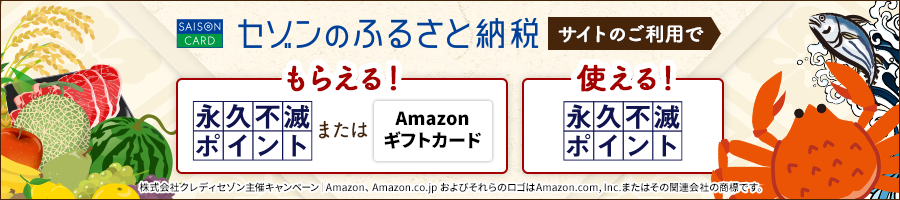
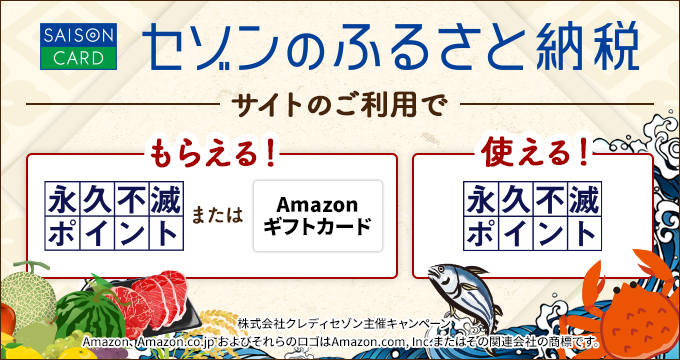
確定申告をした場合の住民税控除額は?住民税はいくら安くなる?
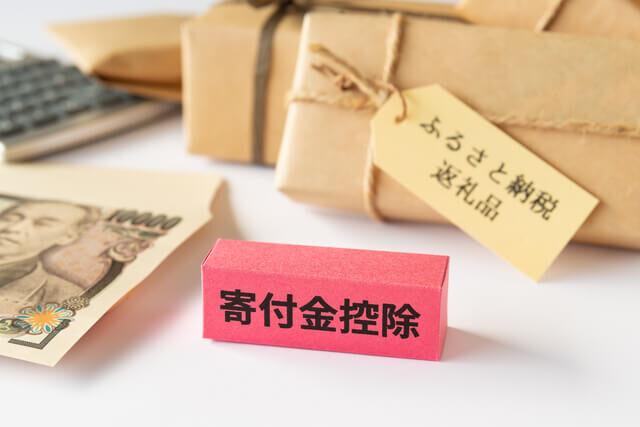
ふるさと納税を行った場合の控除額について、具体的な計算式を知りたい方も多いでしょう。ここでは、年収500万円(独身)で所得税率20%の場合を例に、確定申告をした際の所得税・住民税からの還付額・控除額の計算方法を解説します。
所得税からの還付額の計算方法
所得税からの還付額は、「(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率(復興等区別所得税を加算)」で決まります。なお、ふるさと納税に適用される所得税率には復興特別所得税(所得税率×2.1%)が加算されます。
復興特別所得税を加算した所得税率は、税率が5%の場合は5.105%、10%なら10.210%、20%なら20.420%となります。なお、所得税の還付の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
例えば、年収500万円で税率20%の方が50,000円のふるさと納税をすると、(50,000円-2,000円)×20.42%で所得税からの還付額は9,802円です。
住民税からの控除額(基本分)の計算方法
住民税からの控除には、「基本分」と「特例分」の2種類があります。まずは、基本分の計算方法を確認しましょう。
住民税からの控除額(基本分)は「(ふるさと納税額-2,000円)×10%」で求められます。控除の対象となる、ふるさと納税額には上限があり、上限額は総所得金額等の30%です。
例えば、50,000円ふるさと納税したとすると、(50,000円-2,000円)×10%で、4,800円の控除を受けられます。
住民税からの控除額(特例分1)の計算方法
住民税からの控除額(特例分)は、「(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率(復興等区別所得税を加算))」で求められます。
例えば、年収500万円で税率20%の方が50,000円のふるさと納税をした場合、(50,000円-2,000円)×(100%-10%-20.42%)で、33,398円の控除を受けられます。
ここで説明した住民税からの控除額(特例分1)は、この特例分が住民税所得割額の20%を超えない場合に限ります。
住民税からの控除額(特例分2)の計算方法
上記の計算方法で、住民税所得割額が20%を超えた場合、「(住民税所得割額)×20%」で、住民税からの控除額を求めることになります。つまり、20%を超えた部分については、差し引くものがないため住民税から控除されません。
控除額の合計額の計算方法
確定申告をした場合、所得税と住民税のそれぞれから税金の還付・控除が行われるため、それらの合計金額を求める必要があります。つまり、還付・控除の合計額の計算方法は、以下の計算式を合算して算出します。
・所得税の還付金:(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率(復興等区別所得税を加算)
・住民税控除額の基本分:(ふるさと納税額-2,000円)×10%
・住民税控除額の特例分(20%を超えない):(ふるさと納税額- 2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率(復興等区別所得税を加算))
・住民税控除額の特例分(20%を超える):(住民税所得割額)×20%
例えば、年収500万円で税率20%の方が50,000円のふるさと納税をした場合、控除額の合計は、「9,802円+4,800円+33,398円=48,000円」です。
ワンストップ特例を利用した場合の住民税控除額は?

ワンストップ特例制度を使った場合は、控除額の全額が住民税から控除される違いはあるものの、確定申告の場合と控除される金額は同じです。
確定申告の計算方法で示した事例と同じ、年収500万円(独身)で所得税率20%の方であれば、確定申告と同じ「4,800円+33,398円+9,802円=48,000円」の控除額となります。ただし、所得税からの還付がないため、この金額が全て住民税から控除される点は理解しておきましょう。
自分のも、計算してみよっと。
住民税が安くなっているか確認する方法は?

ふるさと納税をした方で、実際に控除されている金額を確認したい方も多いでしょう。ふるさと納税で控除される税金は、「住民税決定通知書」と「確定申告書の控え」で確認できます。ここでは、実際に控除されている税金の金額をチェックする方法について解説します。
確定申告で控除を受けた場合
確定申告で控除の申請を行った場合、所得税の還付金を受け取れます。所得税の還付金額は、確定申告書の控えにある「還付される税金」欄に記載されている金額を確認しましょう。
所得税の還付金は、確定申告をしてから1ヵ月〜2ヵ月後に指定の口座へ振り込まれます。念の為、実際に振り込まれた金額も確認しておきましょう。
一方、住民税の控除は、ふるさと納税を行った翌年6月の支払い分から1年間適用されます。所得税の還付とは別に、翌年の住民税に対して適用されるため注意しましょう。
なお、住宅ローン控除など他にも受けている控除がある場合には、それらも合算された控除額が確定申告書に記載されています。記載されている金額が、全てふるさと納税による控除額ではない点は理解しておきましょう。
住民税の控除は、住民税決定通知書を確認します。住民税決定通知書とは、住民税額が記載された書類です。会社勤めの場合は5月〜6月頃に勤務先から、自営業の場合は6月に市区町村から郵送されてきます。
住民税の控除額を知るためには、住民税決定通知書の左下にある「摘要」という欄を確認しましょう。摘要の欄に「寄附金税額控除額」として記載されています。この寄附金税額控除額と、所得税の還付額を合計した金額が、「ふるさと納税で寄付した金額-2,000円」と同額になっていれば、正しく控除が行われています。
ワンストップ特例制度で控除を受けた場合
ワンストップ特例制度では、全額が住民税から控除されるため、所得税の還付はありません。住民税の控除は、確定申告をした場合と同様に、ふるさと納税をした翌年の6月の支払い分から1年間適用されます。
控除が正しく行われているか確認するためには、住民税決定通知書をチェックしましょう。住民税決定通知書の摘要欄にある「寄附金税額控除額」を確認し、「ふるさと納税で寄付した金額-2,000円」となっていれば、正しく控除が行われています。
住民税の控除額の正確な数値は、次の年にならないと分からないのね。知らなかったわ。
住民税控除の手続きを忘れてしまった、控除額に誤りがあった場合は?

ふるさと納税をする際に、控除の手続きを忘れたり、控除額が誤っていた場合は、5年以内であれば税金控除の手続き、更正が間に合います。ここでは、手続きを忘れた場合や、控除額に誤りがあった場合の対処方法について詳しく解説します。
確定申告なら申告期限は5年
ふるさと納税で税金控除の手続きを忘れた場合、ふるさと納税を行った翌年1月1日から、原則として5年以内に確定申告を行うことで、税金控除の手続きができます。
仮に、ワンストップ特例制度の申請を期限内にできなかった場合でも、確定申告を行うことで控除を受けられるため、諦めずに確定申告を行いましょう。
確定申告なら5年以内に更正の請求ができる
確定申告をしたけれど「税金が控除されていない」「控除額に誤りがある」といった場合には、更正の請求が可能です。控除が正しく行われているか不安な場合は、所轄の税務署に問い合わせてみましょう。
ただし、更正を請求する場合には、「更正の請求書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。更正の請求内容が正当と認められれば、減額更正が行われて、納め過ぎた税金が還付されます。
ふるさと納税に関するよくある悩みや質問

ふるさと納税はルールが複雑で、初めて利用する方は慣れない手続きに時間がかかってしまいます。スムーズに手続きを進めるためには、多くの方が疑問に思うポイントを先回りをして、対策を知っておくことが重要です。ここでは、ふるさと納税でよくある質問について詳しく解説します。
申請者の名義を間違えた場合は、速やかに寄付先の自治体に連絡して、名義変更の手続きを依頼しましょう。
ふるさと納税を利用する際、申請者の名義と控除を受ける納税者の名義、支払ったクレジットカードの名義は、すべて同一である必要があります。そのため、名義を間違ってしまうと、住民税や所得税の控除を受けられません。
もし、申請者の名義を間違えたことに気づいた場合は、寄付先の自治体に連絡することで、申請者名義が変更できる可能性があります。
確定申告をする方は、自治体に名義変更を依頼したうえで、確定申告時に正しい氏名と住所で申請を行いましょう。また、確定申告後に気付いた場合でも、申告期限から5年以内であれば所轄税務署で「更正の請求」によって税額を修正できます。
ワンストップ特例制度を利用している方も、寄付先の自治体に名義変更の連絡をすることで、翌年度以降から住民税が控除されます。ただし、過去に名義の間違いで控除されなかった住民税は、遡って控除されることはなく、還付もされません。
ふるさと納税の寄付金額には上限がありません。ただし、税金の控除額には、個人の所得や他の控除の状況に応じて、年間の上限額が決められます。
控除上限額を超えて寄付をした場合、超過分の寄付金は自己負担となります。そのため、寄付金額を決める際には、控除上限額に注意しながら決定しましょう。
例えば、年間の控除上限額が5万円の方が、ふるさと納税で7万円分の寄付をしたとします。寄付金の5万円分は所得税や住民税から控除されますが、残りの2万円は自己負担の寄付金として扱われます。
個人の控除上限額を調べる際には、ふるさと納税ポータルサイトなどが提供している「控除上限額シミュレーション」が便利です。今すぐに自分の控除上限額を知りたい方は、セゾンの控除上限額シミュレーションでチェックしましょう。
ふるさと納税を行う際、勤務先で特別な手続きを行う必要はありません。なぜなら、ふるさと納税の手続きは、個人でワンストップ特例制度の申請をするか、確定申告をすることで完結するからです。
多くの会社は、特別徴収によって給料から住民税を天引きし、従業員の代わりに支払っています。そのため、ふるさと納税によって給料から天引きされる住民税の金額が変更になることがあります。しかし、この変更は税額の計算に伴うものなので、勤務先の会社が関与するものではありません。
これからふるさと納税を始める方は、勤務先のことを気にせずに手続きを進めましょう。
ふるさと納税による所得税と住民税の控除は、それぞれ適用されるタイミングが異なります。
所得税の控除が適用されるのは、寄付をした年の確定申告を実施したタイミングです。例えば、2024年にふるさと納税をした場合、2025年の2〜3月に確定申告を行い、その1〜2ヵ月後に還付金として受け取れます。
一方で、住民税の控除が適用されるタイミングは、ふるさと納税を行った年の翌年度です。例えば、2024年にふるさと納税を行った場合、2025年6月以降の住民税が減額される形で適用されます。
ワンストップ特例制度を利用している方は、所得税の還付は受けられないため、翌年度の住民税控除のみを受けられます。
所得税と住民税の控除は、それぞれ適用される時期が異なります。ふるさと納税を利用する方は、各控除が適用されるタイミングを正しく理解しておきましょう。
おわりに
この記事では、ふるさと納税で住民税が安くならない原因や、税金が控除されているかチェックする方法などをご紹介しました。
ふるさと納税は、所得税や住民税の控除を受けつつ、実質2,000円の負担で全国の特産物を楽しめる点が魅力的な制度です。
しかし、正しい手続きをしなければ税金が控除されない点には、注意しなければいけません。ふるさと納税の仕組みや正しい手続きの方法を理解して、メリットを最大限に活用しましょう。
ふるさと納税をする際には、ポイント還元も嬉しい、セゾンのふるさと納税もおすすめです。セゾンのふるさと納税では、確定申告が面倒な方に便利なワンストップ特例制度も利用できます。正しい手続きを行って、ふるさと納税を賢く活用しましょう。
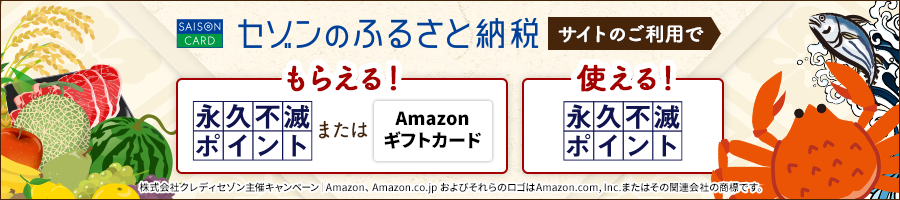
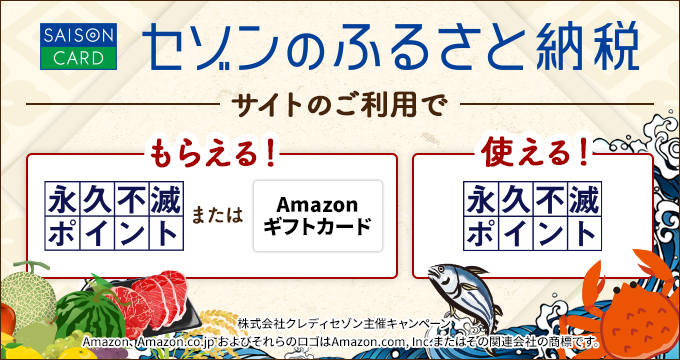
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。