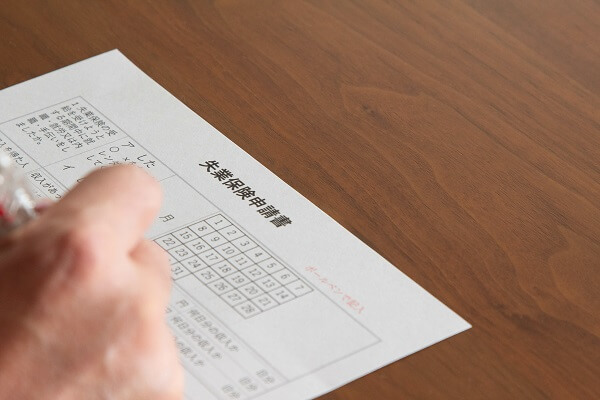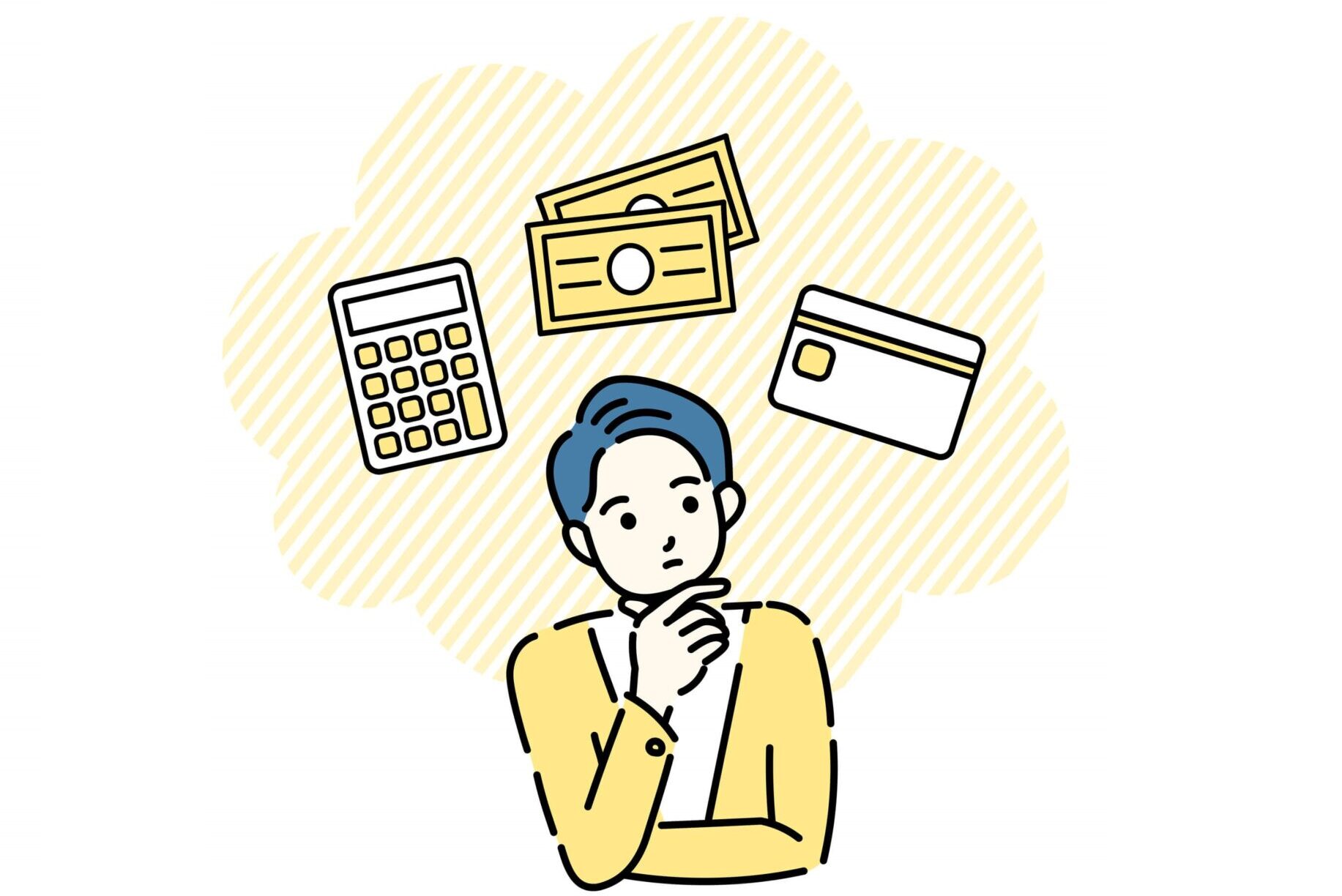物価が上昇傾向にある中、大学の受験料がいくらかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。
複数の大学を併願する場合、受験料だけでも高額になります。また、試験会場への交通費や宿泊費、さらには入学金など、大学受験にはさまざまな費用が発生します。そこでこの記事では、大学受験にかかる費用をわかりやすく整理し、その金銭的負担を軽くする方法を紹介します。
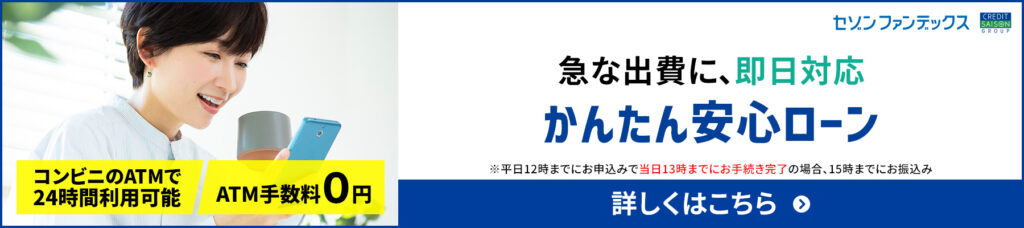

大学受験料はどのくらい?
受験料は国公立大学と私立大学で異なります。国公立大学の受験料は比較的安く見えますが、このほかに大学入学共通テストの受験料も必要です。国公立大学だけでも数万円が必要になり、私立大学を複数併願するとなると10万円を超えることも珍しくありません。2025年度の受験料は以下のとおりです。なお、私立大学の受験料は大学によって異なるため、ここでは目安となる金額を記しています。
| 受験の種類 | 受験料 |
|---|---|
| 大学入学共通テスト | 3教科以上:18,000円 2教科以下:12,000円 成績通知を希望する場合は追加料金:800円 |
| 国公立大学(2次試験) | 多くの大学で17,000円 |
| 私立大学一般方式 (医歯学部等を除く) | 約35,000円 |
参照元:公益財団法人生命保険文化センター|大学受験から入学までにかかる費用はどのくらい?
大学の受験料以外に必要な進学にかかる費用
大学受験では受験料だけでなく、試験会場に行くための交通費・宿泊費なども必要です。また、併願する大学に納める入学金も予定に入れておく必要があります。まとまった金額となるため、いくらになるのか把握しておきましょう。ここでは、受験料以外の費用について解説します。
- 願書代
- 受験当日の交通費や宿泊費
- 入学金
- 併願する大学の入学金(滑り止め)
- ひとり当たりの大学入学費用まとめ
願書代
大学受験は手続きの段階から費用がかかります。受験する大学の願書は国公立大学の場合は無料ですが、一部の私立大学では300~1,500円程度の費用がかかる場合があります。取り寄せる場合には郵送料も負担しなければなりません。インターネット出願の場合は願書の郵送は不要ですが、高校が作成する調査書や各種証明書などの提出は郵送となるため、その送料はかかります。
受験当日の交通費や宿泊費
受験当日は受験会場までの交通費も必要です。受験する大学が遠方の場合、交通費が高額になり、宿泊を伴う場合は宿泊費も用意しなければなりません。食費など滞在費も含めると、まとまった金額となります。例としては以下のようなイメージです。
広島県から東京へ向かうケース(合計:約66,000円)
- 交通費:約37,000円(新幹線往復 広島~東京)
- 宿泊費:約20,000円(1泊×10,000円×2泊)
- 食費など:約9,000円(1日あたり3,000円×3日分)
入学金
文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移」によると、国立・公立・私立大学の入学金は以下のとおりです。
| 国立大学 | 282,000円(2024年4月1日施行) |
| 公立大学 | 374,371円(2023年度、地域外からの入学者の平均) |
| 私立大学 | 240,806円(2023年度の平均) |
参照元:文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移」、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令
これらのうち、国立大学の入学金は省令で定められており、2002年から変動はありません。
公立大学の入学金は基本的に国立大学の学費と同様の水準に設定されますが、地域内の学生の入学料を地域外の学生に比べて優遇しているケースが多くみられます。
表中の公立大学の入学金は地域外からの入学者の平均値であるため、国立・私立より高くなっています。
併願する大学の入学金(滑り止め)
本命の大学以外に「滑り止め」としていくつかの大学を受験する方は、最初に合格した併願校の入学金が必要になることも把握しておきましょう。
入学金の支払期限を過ぎると入学資格がなくなるため、それまでに本命校の結果が判明しない場合には入学金を支払っておかなければなりません。
志望校に合格した場合には無駄な支払いとなる可能性もあますが、「滑り止め」として受験した併願校の入学金納付期限と志望校の合格発表の日を確認し、どちらの入学金も用意しておくと安心です。
ひとり当たりの大学進学費用まとめ
日本政策金融公庫の「教育費負担の実態調査結果(令和3年度)」によると、子どもひとりあたりの「大学入学費用」は国公立67.2万円、私立文系81.8万円、私立理系88.8万円です。これらの金額は、受験費用や入学しなかった大学への納付金、入学する大学への入学金、寄付金などの合計額です。
(単位:万円)
| 国公立大学 | 私立大学文系 | 私立大学理系 | |
|---|---|---|---|
| 学校納付金(入学金など) | 28.6 | 40.6 | 46.6 |
| 受験費用 | 27.7 | 31.3 | 32.2 |
| 入学しなかった学校への納付金 | 10.8 | 9.9 | 10.0 |
| 入学費用計 | 67.2 | 81.8 | 88.8 |
参照元:日本政策金融公庫「令和3年度教育費負担の実態調査結果 P.5」
大学生活の初期費用と在学にかかる費用
入学金を支払って進学の準備が整ったあとも、大学生活を送るためには以下のような費用がかかります。
- 自宅外通学の初期費用
- 年間授業料
- ひとり当たりの大学在学費用
いくらかかるのか、ひとつずつ見ていきましょう。
自宅外通学の初期費用
日本政策金融公庫の2021年の調査によれば、大学生が自宅外通学を始めるための費用は、ひとり当たり平均38.7万円です(参照元:「教育費負担の実態調査結果」2021年12月20日 P.13)
ひとり暮らしを始めるにあたっては、下表のような費用がかかります。
| 項目 | 具体例 |
|---|---|
| 住居関連費用 | 住まい探しのための交通費や宿泊費新居の敷金・礼金、仲介手数料、前払い分の家賃など |
| 生活用品購入費 | 家具、家電、寝具、日用雑貨など |
| その他 | 引っ越し費用、4月分の生活費など |
年間授業料
| 国立大学 | 535,800円(2024年4月1日施行) |
| 公立大学 | 536,191円(2023年度の平均) |
| 私立大学 | 959,205円(2023年度の平均) |
参照元:文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移」、e-Gov法令検索「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令」
国立大学の授業料は長年据え置かれているのに対して、私立大学の授業料は年々上昇しており、進学先によっては大きな負担となります。
ひとり当たりの大学在学費用
日本政策金融公庫が2021年に実施した「高校生以上の子どもを持つ64歳以下の男女」を対象とする調査によると、「1年間で世帯の子ども全員にかかる高校以上の在学費用」が世帯年収に占める割合は14.9%です(参照元:日本政策金融公庫「教育費負担の実態調査結果」2021年12月20日)。
また、日本学生支援機構が全国の大学学部、短期大学および大学院の学生を対象に実施した「令和2年度学生生活調査」によると、学生のひとり当たりの年間平均生活費は以下のとおりです。
居住形態別・学生生活費(大学各部・昼間部) (単位:円)
| 自宅通学 | 自宅外通学 | 平均 | |||
| 国立 | 私立 | 国立 | 私立 | ||
| 学費 | 657,200 | 1,305,700 | 582,400 | 1,338,100 | 1,147,300 |
| 生活費 | 425,400 | 426,100 | 1,099,400 | 1,065,700 | 677,400 |
| 計 | 1,082,600 | 1,731,800 | 1,681,800 | 2,403,800 | 1,824,700 |
参照元:独立行政法人日本学生支援機構「令和4年度 学生生活調査結果」(2024年3月)
1-1表「居住形態別・収入平均額及び学生生活費の内訳(大学学部・昼間部)」より一部抜粋。平均には公立も含む
学費には授業料やその他の学校納付金、修学費、課外活動費、通学費を含みます。
私立大学の学費は国立大学の約2倍と高額です。自宅外通学の場合、生活費が自宅通学の約2.5倍になるため、全体の費用も大きく増加します。
受験費用を抑える工夫
大学受験は「子どもの将来のため」とつい出費を惜しまない傾向にありますが、費用が重なる時期だからこそ節約できるところはしていきましょう。
ここでは、大学の受験費用を抑える方法を紹介します。
大学入学共通テスト利用入試を活用する
あらためて別の試験を受けず、大学入学共通テストの結果で合否を判定する「共通テスト利用入試」は、一般選抜より受験料が安い傾向にあります。また、共通テストは全国各地で実施されるため、交通費や宿泊費が大幅に抑えられます。うまく活用すれば、受験費用の節約につながるでしょう。
受験料の割引制度を利用する
私立大学の受験料は1校あたり約35,000円と高額で、複数校を受験すると大きな出費です。しかし、大学によっては複数学部を併願して受験する場合に受験料が割引になる制度があります。
割引内容や割引率は大学ごとに異なりますが、他大学を併願するよりも受験料が抑えられるため、志望大学に割引制度があるか確認してみましょう。
また、インターネット出願をすると受験料が割引になる大学もあります。インターネット出願は願書の購入が不要な点もメリットです。
地方会場で受験する
大学によっては各地方の中心都市に試験会場を設けるところがあります。最寄りの会場を利用すれば、交通費や宿泊費が節約できるだけでなく、遠征による体力の消耗も避けられます。離れた場所にある大学を志望している場合、地方会場があるかどうか確認しておくと良いでしょう。
旅費を節約する
地方会場がない、あるいは地方会場も遠方にある場合は、学割や早期購入による割引を積極的に利用して交通費を安く抑えることが大切です。志望校や受験日が確定したら、早めに手配すると良いでしょう。
旅行代理店の受験生向け宿泊パックには、駅や試験会場に近いホテルと交通手段がセットになっている商品や、試験会場までの送迎がついている商品があります。うまく活用すれば旅費の節約になるかもしれません。また、併願する大学が遠方に分散していると移動コストが増えるため、受験校を選ぶ際にエリアや受験日が近い大学を組み合わせると効率的です。これにより、移動時間を短縮し、費用負担も軽減できます。
受験費用の不足に備える方法

日本政策金融公庫が実施した2021年の調査結果によると、高校生以上の子どもを持つ保護者のうち、教育費を捻出するための対策を特に行っていない方の比率は約35%に上ります。
複数回答で、対策として上位にあるのは節約(28.6%)、2位以下が子どものアルバイト(21.5%)、奨学金(19.2%)、預貯金や保険の取り崩し(18.8%)と続きます。
ここでは、この調査で下位にある手段も含めて、教育費の不足に備える方法を紹介します。
参照元:日本政策金融公庫「令和3年度教育費負担の実態調査結果 P.12」
学資保険
子どもが小さいうちから対策を立てるなら、教育資金の準備手段として学資保険という選択肢があります。学資保険は、満期のほか入学時にも祝い金としてお金を受け取れる貯蓄としての機能と、保護者の死亡保障に子どもの医療保障を加えた保障機能を備えています。
特に、契約者である保護者に万が一のことがあった場合に、それ以降の保険料を支払わなくても契約どおりの満期保険金を受け取れる点が学資保険の特徴です。
日本学生支援機構の奨学金
経済的な理由で修学が困難な意欲ある学生が安心して学ぶための制度として、独立行政法人日本学生支援機構が運営する奨学金があります。
この奨学金には返済不要の給付奨学金と、返済を要する貸与奨学金の2種類があります。給付奨学金のほうは2020年度から授業料・入学金の減免とセットとなった「高等教育の修学支援新制度」として実施されています。
貸与奨学金には無利子の第1種奨学金と有利子の第2種奨学金があります。 通常の借入金と同じように、延滞すると信用情報に登録されますが、減額返還や返還期限猶予などの救済制度が利用可能です。
日本学生支援機構の貸与奨学金の種類と概要
| 項目 | 第1種奨学金(無利子) | 第2種奨学金(有利子) |
|---|---|---|
| 利息 | 無利子 | 有利子(在学中は無利子) |
| 貸与月額 | 国公立・私立、自宅・自宅外通学により異なる。自宅外通学者は自宅通学の金額を選択可能。 | 原則として20,000円から120,000円までの間で選択(10,000円単位で設定可能) |
| 学力基準 | 原則として 高校等での成績が5段階評価で3.5以上 | 学習意欲等を評価 |
| 家計基準 | 厳しめの所得制限あり | 第1種より緩やかな所得制限あり |
| 募集時期 | 主に高校3年生時の予約採用(在学採用もあり) | |
| 返還開始時期 | 貸与が終了した月の翌月から数えて7ヵ月目の27日から返還開始 | |
なお、2018年度以降に大学へ入学した方の第1種奨学金(無利子)の貸与月額は、以下のとおりとなっています(単位:円)。
| 区分 | 自宅 | 自宅外 |
|---|---|---|
| 国公立 | 20,000 30,000 45,000 | 20,000 30,000 40,000 51,000 |
| 私立 | 20,000 30,000 40,000 54,000 | 20,000 30,000 40,000 50,000 64,000 |
参照元:独立行政法人日本学生支援機構「平成30年度以降入学者の貸与月額」「第二種奨学金の貸与月額」「【高校生等対象】給付奨学金の選考について」「進学前(予約採用)の第二種奨学金の学力基準」「定額返還方式(月々の返還額が一定の返還方式)」
国の教育ローン
「国の教育ローン」とは、日本政策金融公庫の「教育一般貸付」の別名です。一般に借り入れする場合は一定以上の収入が求められますが、国の教育ローンでは、世帯年収が一定基準以下の保護者を対象としています。
- 融資限度額:学生1人あたり350万円(自宅外通学や海外留学などの場合は450万円)
- 資金の使途:1年以内に必要となる教育資金
- 借入方法:融資限度額内で一括借入または複数回に分けて借入可能
- 保証:連帯保証人または教育資金融資保証基金による保証のいずれかを選択
- 返済期間:最長20年
- 金利:固定金利 年2.95%(保証料別途必要)
※一定条件を満たす場合、さらに0.4%低い金利での借入が可能(2025年4月1日現在)
※民間金融機関と比べて低めの金利設定
通常、10月から3月までの入学シーズンは申込件数が多くなるため、早めの申し込みが必要です。日本政策金融公庫では、資金が必要となる時期の2~3ヵ月前に申し込むことを勧めています。
民間金融機関の各種ローン
民間の教育ローンの金利は年2.0~5.0%程度で、変動金利の商品が多い傾向です。
「国の教育ローン」には申し込み可能な世帯年収に上限がありますが、民間の教育ローンの場合は年収が低いと審査に通りにくくなります。
教育にかかる費用に幅広く利用できる場合が多いものの、金融機関によっては資金使途が学校納付金に限られていることもあるため、事前に確認しておきましょう。
原則として保証人は不要です。金融機関によって異なりますが、一般に民間のローンは国のローンに比べて短期間で借りられますが、それでも融資が完了するまでには2週間から1か月弱かかるといわれています。余裕をもって申し込みをすることをおすすめします。
また、急な出費の備えとして、セゾンファンデックスの「かんたん安心ローン」を検討してはいかがでしょうか。80歳まで利用できるローンで、一時的に必要な費用の借り入れができます。相談してから申し込みたい方は、電話によるサポートを受けることも可能です。ぜひ、詳細を確認してみてください。
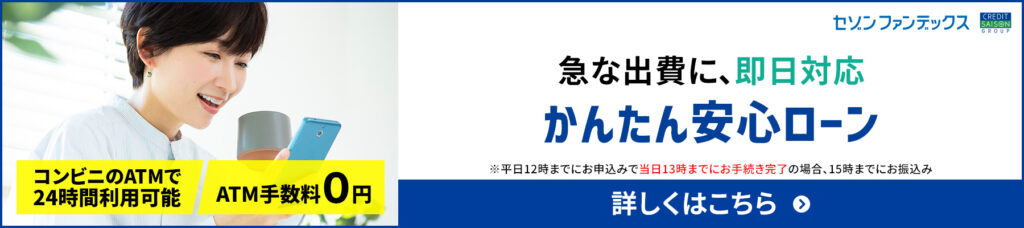

大学無償化の新制度
2020年度から、家庭の経済状況に関わらず意欲ある子どもたちの進学を支援するため、授業料・入学金の減免と給付型奨学金の支給による「高等教育の修学支援制度」がスタートしています。
支援の対象となるのは、住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生です。生計維持者やご自身の資産額が一定水準を超えないことや学修意欲があることも要件とされています。
また、2023年12月に閣議決定された「こども未来戦略」に基づき、2025年度からは、子どもを3人以上扶養している家庭に対し、一定の条件を満たす場合、大学等の授業料・入学金が所得制限なしで一定額まで無償になることも決定しました。
参照元:内閣官房「こども未来戦略」令和5年12月22日 P.15
おわりに
大学進学は、将来の選択肢を広げる大切な一歩です。しかし、受験料や進学にかかる費用は思った以上に負担が大きく、早めの準備が欠かせません。
しかも、すべての支払いタイミングが集中するため、計画的な資金準備が重要です。もし十分な資金が用意できない場合は、奨学金やローンなどの利用も検討してみてください。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。