死後事務委任契約には、さまざまな費用が発生します。死後事務委任契約の利用を検討している場合、どのような費用がいくらかかるのかを把握しておくことが大切です。本記事では、死後事務委任契約とその費用相場、費用を安くするコツを解説しています。
(本記事は2024年1月26日時点の情報です)
- 死後事務委任契約は、成年後見制度や遺言書と組み合わせて準備することがおすすめ
- 死後事務委任契約の費用相場は50万〜200万円と、事業者やサービス内容によって異なる
- 死後事務委任契約の費用を抑えるコツは、預託金や入会金が不要なサービスを利用したり、事前に親戚に相談してみること
死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の手続きを、元気なうちに代理人に依頼する契約のことです。
死後事務委任契約で依頼できること
死後事務委任契約で依頼できることは、大きく分けて5つあります。
- 葬儀や埋葬にまつわる手続き
- 行政手続きに関する対応
- 契約やお金の精算・解約にまつわる手続き
- 遺品整理にまつわる手続き
死後事務委任契約は幅広い事務手続きに対応できますが、遺言書と異なり相続にまつわる手続きには対応できません。そのため、相続財産の分割方法や遺言執行者を指定したい場合には、遺言書を作成する必要があります。
なお、死後事務委任契約や遺言書の検討はいつから始めても構いません。しかし、認知症などで判断能力が低下した場合には契約できないため、早いうちに検討・契約しておくと安心でしょう。
死後事務委任契約の主な依頼先
死後事務委任契約の主な依頼先は、下記のとおりです。
- 友人や知人・親戚
- 弁護士や司法書士
- 社会福祉協議会
- 民間企業
死後事務委任契約は誰に委任しなければという決まりはありません。口頭でも契約が成り立つため、信頼できる友人や知人と口約束で依頼してもよいですが、口頭の場合は約束した証拠が残らないという点に注意してください。
トラブルを防ぎ、スムーズに各種手続きを行なってもらうためにも、契約は公正証書を作成することが一般的です。
死後事務委任契約の手続きの流れ
死後事務委任契約の手続きの大まかな流れは以下のとおりです。
- 依頼内容を決める
- 代理人を決める
- 見積書を確認する
- 契約書・公正証書の作成
- 支払い方法を決めて支払う
死後事務委任契約は、誰に何を委任したいのかを自由に決められます。葬儀の手配や遺品整理など依頼内容は多岐にわたるため、誰に何を委任したいのか慎重に検討しましょう。
依頼内容と代理人が決まったら、見積書を確認し、契約書・公正証書を作成します。契約を締結したら、決められた方法で費用を支払います。
死後事務委任契約と一緒に検討すべきこと
死後事務委任契約と一緒に、遺言書や成年後見制度についても検討しましょう。死後事務委任契約は亡くなったあとの事務手続きを委任するものであり、生前の財産管理や介護、相続にまつわる手続きには対応できません。
財産管理や介護サポートを依頼したい場合には、成年後見制度が活用できます。成年後見制度は判断力が低下した本人の権利と利益を守るために、契約などの法律行為についてのサポート役を選任する制度です。
相続に関しては遺言書を用意する必要があります。遺言書は記載しても確実に実現してもらえるとは限りません。そのため、死後事務委任契約や遺言書、成年後見制度を組み合わせて生前準備しておくと安心です。
死後事務委任契約の費用相場
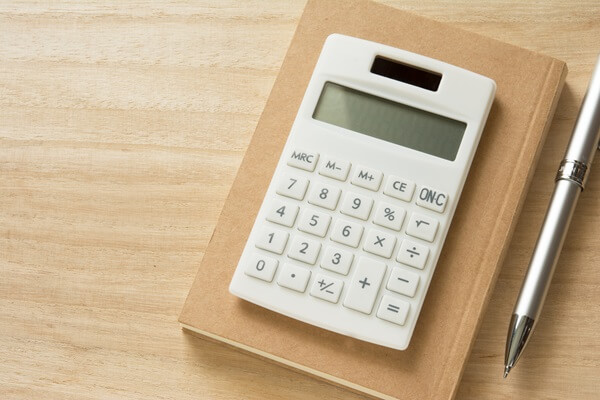
死後事務委任契約の費用は委任する業務によって異なりますが、大体100万円〜200万円程度です。契約内容が決まっているセットプランもあれば、必要に応じて選べるものもあり、事業者によってサービス内容は異なります。
死後事務委任契約にかかる費用の内訳は、公正証書等の作成費用、契約内容の費用、預託金の3つです。それぞれ順番に解説します。
公正証書等の作成費用
公正証書は公証人が作成する文書で、公的な文書として証拠の力が強くなるだけでなく、紛失や改ざんを防止できます。死後事務委任契約の締結で公正証書を作成するときの費用は、公証人に支払う手数料が11,000円程度、謄本手数料などで3,000円程度です。
公正証書作成の手続きを専門家に依頼した場合には、別途専門家へ50万円〜300万円程度の報酬を支払うことが多いですが、依頼先やプランにより設定されている金額には差があります。
委任する内容の費用
死後事務委任契約のサービス料の相場は、以下の表を参考にしてください。あくまで相場であるため、事業者によって異なる点に留意しましょう。
| 死後事務 | 費用項目 | 費用(目安) |
| 葬儀・埋葬・遺品整理 | 葬儀・埋葬の手続き・手配 | 10〜30万円~(希望内容による) |
| 遺品整理 | 2〜5万円~(整頓内容による) | |
| 施設・賃貸物件の手続き等 | 病院・介護施設の諸手続き | 2〜5万円 |
| 賃貸住宅明け渡しの手続き | 2〜5万円 | |
| 行政機関への届出・納税 | 市町村役場への諸届出 | 1〜10万円 |
| 住民税・所得税の納税手続き | 2〜5万円 | |
| その他 | 公共料金精算・解約手続き | 1〜6万円 |
| デジタル遺品の整理・消去 | 1〜5万円 | |
| 勤務先企業・機関の退職手続き | 5万円 | |
| 関係者への死亡通知 | 1,000円/件 | |
| 銀行や携帯電話回線の解約手続き | 2万円 |
預託金
預託金とは、葬儀費用や病院への精算費用など死後事務を行う際にかかる費用を、生前に代理人に預けておくことです。スムーズに死後の事務手続きを行うための金額だけでなく、報酬も含めた額を預けることが一般的です。
預託金の金額は、葬儀の規模や委任する業務の範囲によって大きく変わりますが、一般的には100万円〜200万円程度を預けるケースが多くなっています。
死後の事務手続きを行なったあと、預託金が余った場合には相続財産に返還されるため、事務手続きに支障をきたさないよう十分な額を用意しておく必要があります。事業者によっては預託金が不要なところもあるため、まとまった金額を用意するのが難しい方でも安心です。
死後事務委任契約の費用を支払う方法

死後事務委任契約費用の支払いには、預託金で支払う、遺産で支払う、保険を使用して支払うといった方法があります。
預託金で支払う
預託金は、代理人へ前もってまとまったお金を預けておく方法です。事前に死後手続きに必要なお金を預けているため、あとから支払いに関するトラブルが起きにくいことがメリットです。
しかし、代理人が預託金を使い込んでしまうといったトラブルも起こりうるため、個人に預ける場合は十分注意しましょう。
遺産で支払う
死後事務委任契約の締結とともに、遺言書に遺産の一部を死後事務委任契約の代理人に渡す旨を明記しておくと、遺産から死後事務委任契約費用を支払えます。
契約時のまとまった出費を抑えられる一方で、遺言書作成には別途費用がかかることもある点に注意が必要です。
保険を利用して支払う
生命保険を契約している場合には、保険金を使って死後事務委任契約の費用を支払えます。
契約時のまとまった出費を抑えられますが、生命保険の加入には条件があるため、年齢や病歴によっては契約できない可能性もあります。
死後事務委任契約の費用を安くするコツ

死後事務委任契約を依頼したいけれど、できるだけ費用を抑えたいという方に、費用を安くする3つのコツを解説します。
社会福祉協議会のサービスを利用する
社会福祉協議会は、社会福祉活動の推進を目的とする民間組織です。すべての市町村にある組織ですが、死後事務を取り扱っている社会福祉協議会は一部です。営利を目的としない組織のため、死後事務の費用は低い金額に抑えられています。
死後事務を取り扱っていなくても、別の事業者などを紹介してくれる場合もあるため、近くに相談できる方がいない場合には、社会福祉協議会に相談してみるとよいでしょう。
社会福祉協議会で取り扱っている死後事務サービスには、一般的に次のようなものがあります。
- 葬儀や納骨の手配
- 家財道具の処分
- 市区町村役場への届け出 など
サービスの内容は地域によって異なります。また、サービスの利用には年齢制限や所得制限が設けられていることが多く、誰でも利用できるとは限らない点に注意が必要です。
預託金や入会金が不要なサービスを利用する
死後事務委任契約時の負担を減らすためには、預託金や入会金、月額費がかからないサービスを選ぶことも重要です。
死後事務委任契約の費用には決まりがないため、各事業者によって設定しているサービス内容や料金体系が異なります。そのため、複数の事業者で比較・検討し、対応やサービス内容をしっかり確認することが大切です。
親戚や相続人などに事前に相談する
自分では頼れる人がいないと思っている方でも、親族や親戚がいる場合には事前に相談することで、死後の事務手続きをお願いできる可能性もあります。
疎遠であっても親族が葬儀をするつもりだったとトラブルになるケースもあるため、死後事務委任契約を結ぶ前に、できる限り親族へ相談することが大切です。
おわりに
おひとりさまが増えている中で、終活について考える方も増えています。
おひとりさまが増加する昨今、死後に自身の意向を反映したい、周囲に迷惑をかけたくないなどの理由で契約を検討する方が増えています。
死後事務委任契約の締結には、最短1か月、状況によっては3か月程度の期間を要します。不備なく少しでもスムーズに契約を締結するためにも、どのような流れで手続きを進めるのか、どのくらいの費用がかかるのかを事前に確認しておきましょう。

































