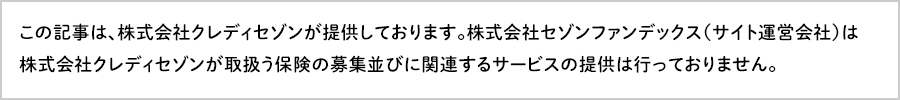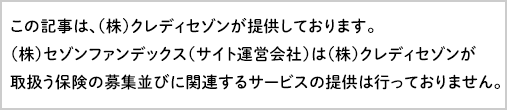子どもの成長に比例した活発な行動が、思わぬ近隣トラブルに発展することがあります。足音や大きな声などの生活音、外でのボール遊び、いたずらなど、子どもの行動が原因となるトラブル事例は少なくありません。本記事では、子どもに関する近隣トラブルの特徴を解説するとともに、家族ができる効果的な対策方法や相談先を紹介します。子どもがトラブルを起こすリスクを下げながら近隣との良好な関係を保つためのポイントを押さえ、トラブルに発展する可能性を下げる方法を学びましょう。
- 子どもの近隣トラブルは「生活音・騒音」「外遊び」「いたずら」が主な原因となっている
- 子どもに関する近隣トラブルは、悪気がなかったり指摘しにくかったりするため解決が難しい特徴がある
- 防音対策やルール決め、近所との交流など、家族が実践できる具体的なトラブル予防をしていく事が大切

近隣トラブルになりやすい子どもの行動

子どもの成長に合わせた活発な行動は健やかな発達のために必要なものですが、それが近隣とのトラブルの原因になってしまうケースは少なくありません。特に集合住宅では、他の住民との生活空間が近いため、子どもの行動がそのまま騒音問題につながりやすい傾向があります。
株式会社ヴァンガードスミスの調査によれば、子どもに関する近隣トラブルのうち、最も多かったのは「足音」で21.2%、次いで「話し声」18.2%、「親が叱る声」17.8%、「泣き声」17.0%、「喧嘩等の声」15.8%と声や音に関連するトラブルが多い傾向にあります。
また、「外遊び関連(ボール)」20.2%や「たむろしている」15.6%、「いたずら」14.3%といったトラブルも発生しているようです。
同調査内で実際には近隣トラブルの解決へ向かうために行動したことは何か、またその行動が解決につながったのかについてもアンケートをとっており「管理会社への相談」25.8%、「警察への連絡」12.3%、「学校への連絡」7.1%と約半数が第三者に相談しています。しかし、その解決率は「管理会社への相談」12.9%、「警察への連絡」8.1%、「学校への連絡」3.9%と約半分ほどしか解決に至らなかったという結果になっています。
それでは、子どもに関する近隣トラブルとして特に多い「生活音・騒音」「外遊び」「いたずらの3つについて、具体的な事例とともに詳しく見ていきましょう。
生活音・騒音
子どもの発する足音や大きな話し声、泣き声、けんかの声などは、近隣の方が不快だと感じるケースが少なくありません。
特に集合住宅では、子どものジャンプや走り回る音が周囲に響き、トラブルの原因になりやすい傾向があります。また、夏場には庭やベランダでプール遊びするときの騒ぎ声も、周囲の方にとって気になる音となってしまうことがあります。
こういった生活音・騒音に関するトラブル事例は数多く報告されています。マンションに住む40代女性は、賃貸の隣室住人から子どもの足音について指摘を受け、菓子折りを持って謝罪に行きましたが、問題解決には至りませんでした。
別のケースでは「毎晩、隣の子どもが全速力で廊下を走り回る足音に悩まされ、寝るのも苦労する」という40代女性の訴えにより管理会社が騒音を注意する貼り紙を掲示をしたものの状況は改善されず、最終的に女性自らが引っ越すことを選択したといいます。
外遊び
「かくれんぼで私有地に入ってしまう」「蹴ったボールが原因で物を壊してしまう」「道路で遊んでいて危険」といった外遊びによるトラブルも多く発生しています。公園が近くにない住宅地では、子どもたちが道路や駐車場を遊び場にすることも多く、、周囲の住民とのトラブルに発展するケースがあります。
外遊びによるトラブルの事例では、隣に住む小学生兄弟が蹴り合うサッカーボールを何度も自宅の壁にぶつけられたという50代男性。隣小学生兄弟の親に注意しても「すみません」と言うだけで改善されず、子どもが中学生になるまで問題が継続したそうです。
また、向かいのマンションの子どもが道路でボール遊びをしていることに悩んだ40代女性は、管理会社へ連絡して頻度を減らすことはできたものの、道路でのボール遊びを完全に止めさせることはできなかったと報告しています。
いたずら
「花壇にゴミを埋められる」など、子どものいたずらがトラブルの発端となることもあります。
子どものいたずらに関するトラブル事例として、近所の小学生たちが敷地内に侵入して花壇にゴミを埋めるなどのいたずらを受けた女性の体験があります。彼女は「下手に注意してしまうと自分の子どもが同じ学校に入った時、仲間外れにされるのでは」と懸念し、注意の仕方に悩んだといいます。
子どもに関する近隣トラブルの特徴

子どもが原因となる近隣トラブルには、大人同士のトラブルとは異なる特有の難しさがあります。トラブルの当事者が子どもであることから、親が対応することになり、これが別の形の大人同士のトラブルへと発展するケースも少なくありません。
特に子どもの問題に対して、どのように対応すべきか悩む親も多いのではないでしょうか。以下では子どもに関する近隣トラブルの主な特徴として、株式会社ヴァンガードスミスの調査を基に「悪気がないケースが多い」「指摘しにくいと感じやすい」「解決が難しいケースがある」という3つの観点から解説します。
悪気がないケースが多い
子どもが起こす近隣トラブルの最大の特徴は、子ども自身に悪意がないことが多い点です。成長過程の子どもは、自分の行動が周囲にどのような影響を与えるのかを十分に理解できていないケースがほとんどです。
ヴァンガードスミスでは近隣トラブルは「感情によるトラブル」と捉えており、子どもの出す音を「うるさい」と感じるか「元気だ」と感じるかといった価値観の違いや、親が子どもにきちんと注意しているのか、わざと音を出しているのではないか。などの相手への不信感・嫌悪感からトラブルが発生するケースが多いと考えています。
同じ行動でも受け取る側の許容範囲によって問題視されるかどうかが変わってくるため、こじれやすい傾向があるのです。
指摘しにくいと感じやすい
隣人の子どもの行動で不快に思うことがあっても、どのように指摘すればよいか悩むケースは少なくありません。
その理由として、「つっぱねられそう」「逆恨みが怖い」といった声があります。また、「相談するべきところがどこかわからなかった」という意見もあり、改善したいと思っていても解決方法がわからないまま問題を抱え込んでいるケースも多いようです。
株式会社ヴァンガードスミスの調査によれば、子ども関連のトラブルの相談先として、「管理会社への相談」25.8%、「警察への連絡」12.3%、「学校への連絡」7.1%と、全体の45.2%が第三者への相談を選んでいることが明らかになっています。
解決が難しいケースも
子どもに関する近隣トラブルは、第三者に相談したとしても解決が難しいケースも少なくありません。株式会社ヴァンガードスミスの調査によれば、管理会社に相談した場合での解決率は12.9%、警察への連絡では8.1%、学校への連絡では3.9%と、解決率はかなり低いという結果が出ています。
「住民同士で話し合ってくれと言われた」「管理会社は直接指導することを避けていた」「相談した相手が、加害者寄りのスタンスで、中立の立場の人間がいなかった」「相手が明らかに悪くても、内容によっては法的処置をとれない場合が多い」「長年住んでいる人のほうを優先された」といった意見が見られます。
警察に相談した場合も、事件性や緊急性が低いと判断された場合、すぐに対応してもらえないことがあります。このような状況から、近隣トラブルの解決には、早期に中立な立場の第三者を間に入れ、お互いの譲歩・妥協点を見つけることが重要となります。
近隣トラブルに子どもが巻き込まれないよう家族ができる対策

近隣トラブルのリスクを下げるためには、保護者や家族が積極的に対策を講じることが重要です。子どもの行動が原因でトラブルに発展する前に、家庭内で取り組める対策もいくつかあります。
音を軽減するための防音対策、子どもへ適切に注意を促す、近隣住民との良好な関係構築など、さまざまな角度からのアプローチが考えられます。また、トラブルが発生してしまった場合の適切な相談先についても知っておくと安心です。
つづいて具体的な対策について詳しく見ていきましょう。
防音対策を講じる
子どもの生活音によるトラブルを防ぐには、効果的な防音対策が欠かせません。特に集合住宅では、周囲への騒音対策として、厚手のカーペットやマット、ラグを床に敷くことが有効です。これらは厚い方が効果的で、防音専用のカーペットやジョイントマットを活用すると、より衝撃音を和らげることができます。
また壁際に家具を配置するのも効果的な方法です。本棚やタンスなどを壁に沿って置くことで、音の伝わりや漏れを軽減できます。ただし、子どもがぶつかっても倒れないように固定することが大切です。
さらに騒音を外部に漏らさないために、窓を閉める、厚手のカーテンを使用するといった対策も有効です。また、頻繁に開閉するドアには、勢いよく閉まる音を軽減するためのドアクローザーや隙間テープを取り付けるといった工夫も役立ちます。しかし、防音対策をしたからといって音がなくなるわけではないことを念頭に置いて、周囲への配慮をおこたらないようにしましょう。
子どもに注意を促す・ルールを決める
子どもが原因となる近隣トラブルを防ぐには、家族間でのルール作りが重要です。外遊びに関しては、公共のスペースでのルールとマナーを子どもに説明し、私有地に入らない、壁や窓を汚さないといった基本的なルールを理解させましょう。
ピアノなどの楽器演奏については、夜間を避けたり窓を閉めたりするなど、演奏する時間帯や音量に配慮するルールを設けることが大切です。また、集合住宅の場合は、そもそも物件の規約で禁止されていることもあるため、規約を正しく把握しておくことも重要です。
他にも子ども同士のトラブルに発展しないよう、他人の家や持ち物を大切にすることの意味を教え、なぜ自宅のような振る舞いをしてはいけないのかをしっかり伝えることも重要です。
ご近所と積極的に交流を図る
日頃から近隣の方とコミュニケーションを取り、良好な関係を築くこともトラブル予防の一助となります。弁護士の畠山慎市さんも「日頃から付き合いがあれば『うちの子が何か迷惑を掛けていませんか?』ということも気軽に聞けるのですが、交流がないと突然裁判になってしまったり、大ごとになりかねません」と指摘しています。
出産を控えていたり、引っ越しをしたりするなど、今後大きな音が発生するかもしれない場合には、事前にあいさつに伺うことも効果的です。一言事前にあいさつがある状況とない状況では、相手の受け取り方や感じ方も変わってくることもあります。
また、すれ違った際にはあいさつを交わすなど、ご近所との関係性を良好に保つこともトラブルのリスク軽減に有効です。
「子どもだから仕方がない」と思わない
子どもの行動に対して「子どもだから仕方ない」と考えがちですが、その判断をしてよいのは何かしらの不快感や被害を受けた相手だけであることを忘れてはなりません。
親が子どもの行動を容認する姿勢を見せると、「危険な遊びをしているのに保護者が見ていない」「騒いでいるのに注意しない」といったマイナスな印象を与え、より大きな問題に発展する可能性があります。
トラブルが起きた際は、後回しにせず誠意をもって対応することがトラブル解決への近道となるでしょう。
近隣トラブル解決支援サービスの利用を検討する
近隣トラブルは実害がともなわないことも多いため、法令で対応できないケースであることも多く、対応できる機関がないのが現状です。当事者同士での話し合いでは感情が高まってトラブルがエスカレートする可能性が高いため、中立な立場の第三者を間に入れることが穏便な解決につながります。
例えば、株式会社ヴァンガードスミスが提供する近隣トラブル解決支援サービスを利用すれば専門的な知識と豊富な経験を持つ相談員が対応してくれます。同社では、全員元警察官の専門相談員が、騒音や迷惑行為、つきまとい行為など、「事件未満のトラブル」の解決をサポートしています。
子どもが絡むトラブルは親同士でヒートアップしやすい傾向にあるため、第三者の客観的な立場からの介入は非常に有効です。サブスクサービスのため、「ちょっと気になる」という段階から何度でも相談ができ、成功報酬や追加請求が一切かからない点も安心です。もしもの場合にそなえて、こうしたサービスに加入しておくのも一つの手段でしょう。
近隣トラブルに子どもが巻き込まれた際の相談先

近隣トラブルは、当事者間での解決が難しく感情的になりやすい特徴があります。そのような場合、適切な第三者に相談することで、客観的な立場からアドバイスをしてもらうことで解決につながる可能性が高まります。
警察
子どもに関する近隣トラブルが悪化した場合、警察に相談するという選択肢もあります。警察相談専用電話「#9110」では、近隣トラブルについての相談を受け付けています。
ただし、警察は事件性がない・緊急性が低いと判断した場合、対応することが難しい場合があります。子どもの騒音など、事件ではない案件では対応が限られることもあります。それでも、「どうすればよいかわからない」というときには、まず#9110に相談してみることで問題解決のきっかけになることがあります。
管理会社
集合住宅やマンション内での近隣トラブルは、まず管理会社に相談しましょう。
管理会社に相談すると、掲示物で注意喚起してもらえるケースがあります。また、管理会社とケースによりますが、トラブルの相手方に注意してくれることもあります。この方法は、当事者同士で直接話し合うより角が立ちにくく、穏便に問題解決へ話が進むでしょう。
学校
子ども同士のトラブルや近隣の子どもの行動で困っている場合、その子どもが通う学校に相談するという方法もあります。特に、外遊びでのトラブルや子ども同士のけんかなど、学校外でも児童・生徒間で発生する問題については、学校が介入することで改善が期待できます。
ある掲示板では「僕たちが子どもの頃にいたずらをしたとき、地域の人より学校の先生からの注意が心に響きました」という意見もあり、子どもたちに対する学校からの指導は効果的な場合があります。
学校に通っている子どもであれば、学校に相談し改善がみられるケースもあります。文書などで保護者に連絡してもらうことで、理解を得られやすくなるでしょう。
Pサポで近隣トラブルを解決しましょう

近隣トラブルは、早期解決が重要です。保護者として日頃から子どもを見守り、適切な対応を心がけることはもちろん、専門家のサポートを受けられる体制を整えておくことで、トラブルの深刻化を防ぐことができます。
そんなとき頼りになるのが、元警察官による近隣トラブル解決支援サービス「Pサポ」です。
「Pサポ」は警察官時代に培われた専門的な知識と豊富な現場経験を持つ専門相談員が、騒音や迷惑行為など事件未満のトラブルの解決支援を行うサービスです。
トラブルの芽を摘むため、「気になる」の段階から何度でも相談ができる少額の定額制を取り入れており、成功報酬や追加請求は一切かかりません。お電話にて一次ヒアリングから収束まで対応しています。

おわりに
子どもが関わる近隣トラブルは、適切な対策でリスクを下げることが可能です。生活音や外遊びなどのトラブルに関しては、防音対策の実施や明確なルール設定、近所との良好な関係づくりが重要となります。トラブルが発生した場合は、警察や管理会社、学校などへの早めの相談が効果的です。また、Pサポなどのサービスを活用することで、より円滑な解決が期待できるでしょう。子どもの健全な成長と周囲との調和を両立させるため、日頃からの備えと適切な対応を心がけましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。