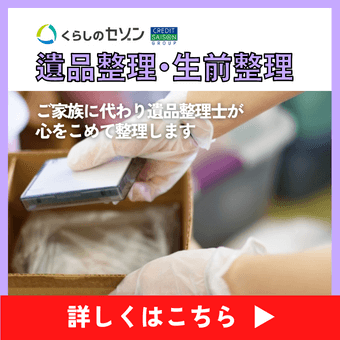物が多くて家が散らかっていると、探し物に時間を取られたり、日々の生活でストレスを感じやすくなります。しかし、正しい手順で片付けを進めれば、リバウンドせず快適な住環境を手に入れることが可能です。
本記事では、「物が多くても片付けられる3ステップの手順」と、「散らからない状態を保つためのコツ」をわかりやすく解説します。
- 散らかった部屋が心理的ストレスや集中力低下を引き起こす一方で、片付けによって探し物の時間短縮や経済的メリットが得られる
- 片付けを成功させるには、目標設定と道具準備、「いつか使うかも」を卒業する心構え、家族との役割分担という3つの事前準備が重要
- 片付けは「物を全て出す」「必要か不要かで仕分ける」「使用頻度で定位置を決める」という3ステップで進めると効果的
- リバウンドを防ぐためには「1つ買ったら1つ捨てる」ルールの実践と、物を元の場所に戻す習慣化が必要
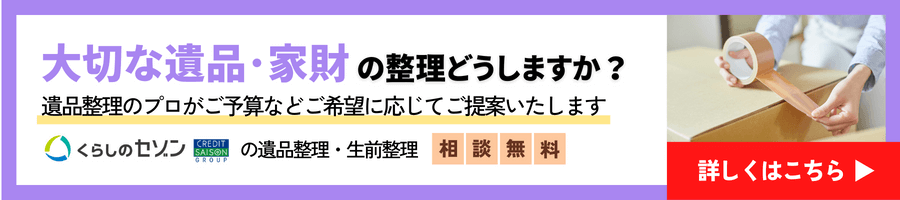
物が多い家の共通点と片付けによるメリット

物が多い家では、郵便物や書類を「後で片付ける」と後回しにするくせや、買い物好きによって物が増え続ける傾向があります。また、散らかった環境で暮らしていると、気分が散漫になり心理的なストレスも蓄積されます。
一方、片付けによって物理的な空間が整うと、精神的な満足感も得られるでしょう。探し物にかかる時間が減り、無駄な買い物も抑えられるため経済的なメリットも生まれます。家が整うことで快適な生活環境が実現し、日常生活の質が向上します。
散らかった部屋がもたらす問題点とストレス
乱雑な部屋ででは集中力が散漫になり、仕事や勉強の効率低下につながります。
散らかった部屋で暮らすことによる主な問題点は以下の通りです。
【生活におけるデメリット】
- 必要な物を探すのに時間がかかる
- ホコリがたまりやすく掃除が行き届かない
- 衛生面の悪化により健康リスクが高まる
郵便物や書類の整理の後回しや、趣味や買い物で物が増えることも片付かない原因になります。
片付けによって得られる時間的・経済的なメリット
片付けを行うことで、探し物にかける時間が大幅に減少します。物量を把握できるようになるため、同じ物を重複して購入する無駄も防げます。整理された環境では、物の管理がしやすくなり、生活効率が向上します。
快適な空間で家族との時間も充実し、精神的な安定も得られるでしょう。
物が多い家の片付けを成功させる3つの準備

片付けは、事前の準備をしっかりと行うことが成功の鍵で、以下の3つが欠かせません。。
- 道具の準備
- 断舎離マインド
- 家族との協力体制
これらの準備を怠らずに行うことで、片付けがスムーズに進み、リバウンドしない整理収納を実現できます。
まずは目標設定と道具の準備から
片付けを始める前に、片付ける範囲・期限・具体的な目標を決めましょう。たとえば「リビングの収納家具の1段目の引き出し」など小さな範囲から始めると、達成感が得られモチベーションが高まります。
仕分け用の段ボールは、「必要」「不要」「保留」の3種類を用意。収納グッズは整理後に必要な分だけ買い足すと無駄がありません。
片付けを楽しむ工夫として、好きな音楽をかけて気分を上げながら作業を進めたり、片付けが終わった後のご褒美を用意しておくとやる気が持続するでしょう。
「いつか使うかも」を卒業する断捨離の心構え
物を持つことが必ずしも幸福につながるわけではありません。私たちは「所有すること=満足感」と思い込みがちですが、実際には不要な物を抱え込むことで、かえってストレスや負担が増えてしまいます。まずは「物を持つことにとらわれない」マインドセットを身につけることが大切です。
断捨離が苦手な人がよく口にするのが「いつか使うかも」という考え方です。この思い込みを手放し、「今の暮らしで本当に必要か」を基準に冷静に見極めるクセをつけましょう。使用頻度が低い物は、「1年以内に使う予定があるか」といった具体的な期限を設けて判断するのがおすすめです。
また、思い出の品など処分に迷う物は、一時保管ボックスを用意し、期限を決めて置いておく方法も有効です。無理にすべてを捨てる必要はありません。
家族と協力するための役割分担
家族全員で片付けに取り組むと、負担を分散できるため非常に効果的です。役割分担を明確にすれば、作業がスムーズに進むだけでなく、協力意識も高まります。
具体的には、子どもはおもちゃや学用品、子ども部屋を担当し、大人は共用スペースやワークスペースを受け持つといった方法です。さらに、定期的に「片付けの日」を設けて一緒に作業することで、片付けの習慣が自然と身につきます。
ただし、家族の持ち物を勝手に捨てたり整理したりするのはトラブルのもと。必ず本人の合意を得てから行動することが、円滑に片付けを進める大原則です。
【実践】物が多い家の片付けを3ステップで進める手順

物が多い家を効率的に片付けるには、以下の正しいステップで進めることが重要です。
【片付けの手順】
- ステップ①:物を全て出して全体量を把握する
- ステップ②:「必要か不要か」で仕分ける
- ステップ③:使用頻度で物の定位置を決める
この順番に沿って進めることで、物が多い家でも挫折することなく、効率的に片付けることができます。
ここからは具体的な片付けの手順を解説します。
ステップ①:物を全て出して全体量を把握する
片付けの第一歩は、物をすべて出して「何がどれくらいあるのか」を把握することです。まず、家の中で1つのスペースを決め、その場所にある物を一つずつ取り出しましょう。
いきなり大きな範囲に手をつけるのではなく、たとえば「リビングの収納家具の1段目の引き出し」など、小さな範囲から始めることがポイント。
すべての物を一度出すことで、現在持っている物を正確に確認でき、整理や収納の次のステップがスムーズになります。同じ物が複数あるなどの無駄も発見できるため、物の全体量を視覚的に把握することが可能です。
ステップ②:「必要か不要か」で物を仕分ける
決めた範囲の物をすべて出し終わったら、「必要」「不要」「保留」の3つの段ボールに仕分けします。判断に迷う場合は、以下の基準を参考にしてください。
| 分類 | 判断基準 | 具体例 |
|---|---|---|
| 必要 | ・日常で頻繁に使っている ・今後も使う予定が明確 など | ・毎日使う食器や調理器具 ・よく着る服 ・日用品 など |
| 不要 | ・「1年以上」使っていない ・壊れている・同じ機能の物が複数ある など | ・サイズが合わなくなった服 ・古い雑誌 ・重複している調理器具 など |
| 保留 | ・捨てるかどうか判断に迷う ・思い出の品 など | ・思い出の品(写真、手紙、子どもの作品など) ・季節物 ・趣味のコレクション など |
不要な物は、ゴミとして処分するだけでなく、フリーマーケットで売る、家族や友人に譲る、寄付するといった選択肢もあります。ただ単に「まだ使えるから」といった理由で残すのは避け、明確な基準で判断することが大切です。
ステップ③:使用頻度を考えて物の定位置を決める
物の仕分けが終わったら、次は「必要」と判断した物の定位置を決めましょう。物を配置する際は、使用頻度を考慮することが重要です。
- 毎日使う物は、手の届きやすい場所に置く
- 年に数回しか使わない物は、クローゼットや押し入れの奥に収納する
高さのある収納スペースを使う場合は、使用頻度の高い物を中段や下段に、低い物を上段に置くと取り出しやすくなります。また、収納は、スペースの8割程度に留める「8割収納」を意識しましょう。物を詰め込みすぎると出し入れが大変になるだけでなく、通気性が悪くなりカビの原因にもなります。
散らからない家にするためのリバウンド防止策

一度片付けても元の散らかった状態に戻ってしまう「リバウンド」を防ぐには、継続的な習慣づくりとルール設定が欠かせません。物を増やさない明確なルールと、散らかりにくい収納方法を両面から実践することで、整理された状態を長く維持できます。
日々のルーティンに整理整頓を組み込み、物の定位置を守る習慣を身につけることが重要です。自力での片付けが難しい場合は、専門業者のサービスを活用するのも有効な選択肢です。
「1つ買ったら1つ捨てる」ルールと収納の工夫
物の量を管理するには、「新しい物を購入したら古い物を手放す」というルールが効果的です。これにより、必要な物だけを持つ習慣が身につき、物が増えすぎるのを防げます。
整理整頓を習慣化するには、使った物を必ず元の場所に戻すことも大切です。家のデッドスペースには、S字フックやスタッキング可能な収納ボックスなどを活用し、収納スペースを効率的に使いましょう。
こうした工夫を日々積み重ねることで、すっきりとした生活空間を維持できます。
片付けが難しいと感じたら|プロへの相談も検討
片付けの手順やリバウンド防止策を実践しても、どうしても自力で進められない場合があります。たとえば以下のようなケースです。
- 実家が遠く、片付けにまとまった時間を割けない
- 重い物や大量の荷物をを一人で運び出せない
- 家全体の荷物が多すぎて手に負えない
このような場合は、無理に自分だけで片付けようとせず、専門業者に相談するのも有効な選択肢です。プロに依頼すれば、時間や体力の負担を軽減しつつ、効率よく整理を進められます。
たとえば、くらしのセゾンの「家財整理・生前整理」サービスでは、専門スタッフが、物が多い家でも丁寧に整理・仕分けを行います。
- 料金例:1K(作業員2名)38,500円(税込)~、2LDK(作業員4名)154,000円(税込)~
- サービス内容:貴重品捜索、不用品の仕分け・搬出、簡易清掃まで一括対応
- 見積もり:専門スタッフが現地訪問し、予算や状況に応じて無料で提案。
大規模な片付けや短期間での整理、心理的負担の軽減にも便利です。自力での作業が困難な場合は、専門家に依頼することも検討しましょう。
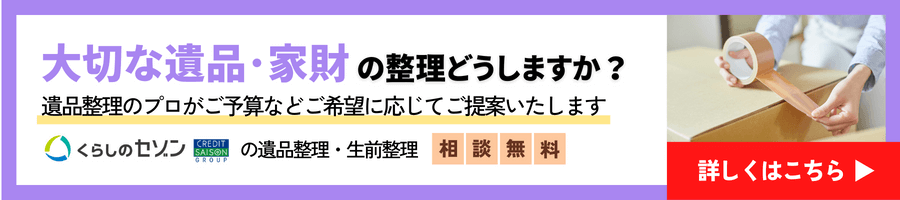
おわりに
物が多い家の片付けを成功させるには、事前の準備と正しい手順が重要です。まず目標設定と道具の準備を行い、「いつか使うかも」を卒業して断捨離のマインドセットを身につけましょう。家族との役割分担を明確にすることで、負担を軽減できます。
実際の片付けは「出す」「分ける」「収める」の3ステップで進めます。小さなスペースから物を全て出して全体量を把握し、「必要か不要か」で仕分けを行い、使用頻度に応じて定位置を決めます。リバウンドを防ぐには、「1つ買ったら1つ捨てる」ルールと、物を元の場所に戻す習慣化が欠かせません。自力での片付けが困難な場合は、専門業者への相談も検討してみると良いでしょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。