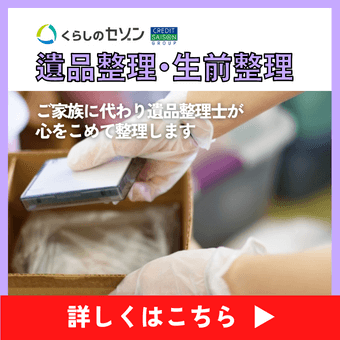大切な方が亡くなった後、遺品整理の費用がどのくらいかかるのか、誰が支払うべきなのか悩んでいませんか。遺品整理の費用は、部屋の広さや荷物の量によって大きく変動します。1Kなら数万円程度ですが、4LDK以上では数十万円に及ぶこともあるでしょう。この記事では、遺品整理の料金相場を間取り別に詳しく解説し、費用が変動する要因や支払い義務者、信頼できる業者の選び方まで幅広くご紹介します。
- 遺品整理の費用相場は間取りによって異なり、1R・1Kで2.5~10万円、4LDK以上では22〜69万円程度かかる
- 同じ間取りでも荷物の量、建物の構造(エレベーターの有無)、特殊清掃の必要性などで費用が大幅に変動する
- 遺品整理費用の支払い義務は原則として法定相続人にあるが、相続放棄した場合は次順位の相続人や連帯保証人に移行する
- 遺品整理業者への依頼の流れと信頼できる優良業者の見極め方
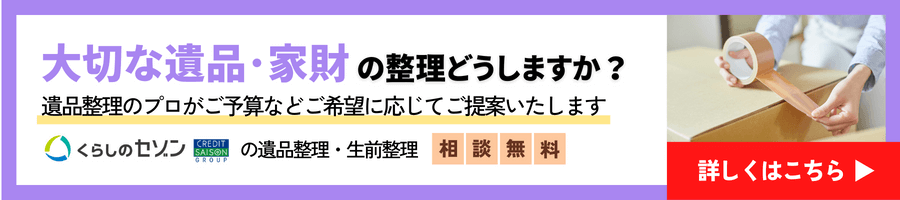
遺品整理にかかる費用の全体像

遺品整理の費用は、間取りの広さだけでなく、オプションサービスの有無によっても大きく変わります。まずは基本的な料金体系と、追加で必要になる可能性のあるサービスについて見ていきましょう。
間取り別の料金相場一覧
遺品整理の費用は、部屋の間取り、作業にあたる人数、そして作業にかかる時間によって決まります。一般的に、部屋が広くなるほど整理すべき物品が増え、より多くの人手と時間が必要になるため、費用も高くなる傾向にあります。
| 間取り | 料金相場 |
|---|---|
| 1R・1K | 25,000円~100,000円 |
| 1DK | 50,000円~120,000円 |
| 1LDK | 70,000円~200,000円 |
| 2K | 50,000円~120,000円 |
| 2DK | 70,000円~250,000円 |
| 2LDK | 120,000円~450,000円 |
| 3DK | 120,000円~400,000円 |
| 3LDK | 170,000円~500,000円 |
| 4LDK以上 | 220,000円~690,000円 |
ただし、これらの金額はあくまで目安であり、実際の費用は状況によって異なります。特にゴミ屋敷のような状態になっている場合や、孤独死などで特殊清掃が必要な場合には、表の金額を大幅に超える可能性があることを念頭に置いておきましょう。
オプションサービスの料金目安
基本的な遺品整理サービスには、必要品と不用品の仕分けや搬出作業が含まれていますが、それ以外の専門的な作業については別途料金が発生することが一般的です。以下に主なオプションサービスとその費用相場をまとめました。
| サービス内容 | 費用相場 | 備考 |
|---|---|---|
| エアコンの取り外し | 無料~20,000円 | 業者によって料金に幅があります。 |
| お焚き上げ・遺品供養 | 3,000円~80,000円 | 自宅での供養か、お焚き上げか、また合同供養か個別供養かによって料金が変動します。 |
| ハウスクリーニング | 15,000円~60,000円 | 部屋の広さや清掃内容によって料金は異なります。1Rで15,000円から、部屋全体では30,000円からが目安です。 |
| 特殊清掃 | 30,000円~ | 孤独死などの現場で必要となる専門的な清掃です。状況によって費用は大きく変動し、見積もりが必要です。 |
| 消臭・消毒作業 | 10,000円~60,000円 | 部屋の状況や臭いの原因によって料金が変わります。 |
| 害虫駆除 | 10,000円~50,000円 | 害虫の種類や範囲によって費用が異なります。 |
| 自動車・バイクの廃車手続き代行 | 自動車: 6,000円~15,000円バイク: 8,000円~ | 車種や手続き内容によって変動します。 |
| 畳の撤去 | 3,000円~(1枚あたり) | 畳の状態や枚数によって総額が変わります。 |
| 風呂釜の取り外し | 10,000円~ | 設置状況により料金が変動します。 |
| 形見分けの梱包・配送 | 無料~数千円 | 配送する量や距離によって料金が決まります。 |
| 原状回復リフォーム | 要見積もり | 部屋の状態によって費用が大きく異なるため、現地での見積もりが必要です。 |
| 家屋の解体 | 1坪あたり20,000円~ | 建物の構造や立地条件によって変動します。 |
なお、クレジットカード決済への対応や女性スタッフの指名、立ち会いなしでの作業、オンライン見積もりなどは、多くの業者で無料サービスとして提供されています。業者を選ぶ際には、これらの無料オプションの有無も確認しておくとよいでしょう。
遺品整理の費用が変動する主な要因

遺品整理の費用は、単純に間取りの広さだけで決まるわけではありません。さまざまな要因が複雑に絡み合って最終的な金額が決定されます。ここでは、費用に影響を与える主な3つの要因について詳しく解説します。
部屋の広さと遺品の物量
同じ2DKの部屋でも、遺品の量によって費用は大きく変わります。たとえば、ミニマリストのような生活をしていた方の部屋と、長年にわたって物を溜め込んでいた方の部屋では、作業にかかる時間や必要な人員数が異なります。
実際の事例では、2DKの部屋でも遺品が少ない場合は3名のスタッフで半日程度で作業が完了し、費用も10万円前後で済むケースがあります。一方、同じ広さでも2トントラック2台分の荷物があった場合、8名のスタッフで丸一日かかり、費用も30万円近くになることもあるのです。
費用を抑えるためには、事前に自分で処分できるものは処分しておくことが効果的です。たとえば、明らかなゴミや不要な雑誌、着なくなった衣類などを自治体の回収に出しておけば、業者の作業量が減り、結果として費用を節約できるでしょう。
建物の構造と周辺環境
建物の構造や立地条件も、遺品整理の費用に大きな影響を与えます。エレベーターのない4階建てアパートの最上階と、エレベーター付きマンションの2階では、同じ荷物量でも搬出にかかる労力が異なります。
階段での搬出作業は、エレベーターを使う場合と比べて時間も体力も必要です。そのため、追加の人員が必要になったり、作業時間が延長されたりすることで、費用が上乗せされることがあります。
また、建物の前にトラックを駐車できるかどうかも重要な要因です。狭い路地にある家や、駐車禁止区域にある物件では、離れた場所にトラックを停めて台車で何度も往復する必要があります。たとえば、家からトラックまでの距離が100メートル以上あるようなケースでは、通常以上の時間がかかるため、費用も相応に増加することもあるでしょう。
さらに、東京や大阪などの都市部から離れた地方での作業を依頼する場合、スタッフの交通費や、場合によっては宿泊費が加算されることもあるため、事前に確認しておくことが大切です。
特殊清掃やハウスクリーニングの必要性
故人が亡くなってから発見されるまでに時間が経過していた場合、特殊清掃が必要になることがあります。このような状況では、通常の清掃では対応できない体液や臭いの除去のため、専門的な薬剤や機材を使用する必要があります。
特殊清掃の費用は、汚染の程度や範囲によって変動しますが、最低でも3万円以上、重度の場合は数十万円に及ぶこともあります。専門業者は、人体に無害でありながら効果的な薬剤を使用し、臭いの元から徹底的に除去してくれます。
また、長年の生活で蓄積されたフローリングのシミ、壁や天井に染み付いたタバコのヤニ、ペットの臭いなどがある場合も、通常の清掃では対応できません。このような場合は、プロによるハウスクリーニングが必要となり、キッチンで1万円程度、浴室で1万円程度、部屋全体では1Rでも1万5千円以上の追加費用が発生します。
さらに深刻なケースでは、床や壁の張り替えなどの原状回復リフォームが必要になることもあります。また、ゴキブリやダニなどの害虫が大量に発生している場合は、専門的な害虫駆除も必要となり、これらすべてが追加費用として計上されることになります。
遺品整理の費用は誰が支払うべきか

遺品整理の費用負担については、法律で定められたルールがあります。しかし、相続放棄や身寄りのない方のケースなど、状況によって誰が支払うかは変わってきます。ここでは、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
原則として法定相続人が負担する義務
遺品整理の費用は、原則として法定相続人が支払う義務があります。法定相続人とは、民法で定められた相続の権利を持つ人のことで、配偶者は常に相続人となり、それ以外は次の順位で決まります。
第一順位は子ども(子どもが亡くなっている場合は孫)、第二順位は両親(両親が亡くなっている場合は祖父母)、第三順位は兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)となります。
相続人が複数いる場合は、法定相続分に応じて費用を分担することが一般的ですが、話し合いによって特定の相続人が全額負担することも可能です。ただし、遺言書で特別な指定がある場合は、その内容に従うことになります。
重要なのは、遺品整理の費用も相続財産の一部として扱われるという点です。つまり、故人の預貯金や不動産などの財産から支払うことも可能ですが、その場合は相続を承認したものとみなされるため、後から相続放棄をすることはできなくなります。
相続放棄した場合の支払い義務の移行
相続人が家庭裁判所に相続放棄の申述をして認められた場合、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。したがって、相続放棄をした人には遺品整理費用の支払い義務はありません。
しかし、ここで注意が必要なのは、相続放棄をすると支払い義務が次の順位の相続人に移るという点です。たとえば、子ども全員が相続放棄をした場合、支払い義務は第二順位の両親に、両親も相続放棄をすれば第三順位の兄弟姉妹に移ります。
賃貸物件の場合は、さらに複雑になることがあります。相続人全員が相続放棄をしても、連帯保証人がいる場合は、その人が原状回復の義務を負うことになります。連帯保証人は、賃借人(故人)と同等の責任を負っているため、大家から遺品整理と原状回復を求められれば、それに応じなければなりません。
また、相続放棄を考えている場合は、絶対に避けなければならない行為があります。故人の財産から遺品整理費用を支払ったり、価値のある遺品を売却したりすると、相続を承認したとみなされ(単純承認)、相続放棄ができなくなってしまいます。このような事態を避けるためにも、相続放棄を検討している場合は、まず専門家に相談することをおすすめします。
身寄りがない場合の費用負担者
相続人が全員相続放棄をした場合や、そもそも法定相続人がいない場合、遺品整理の費用は誰が負担するのでしょうか。このような場合の対応は、故人の住居形態によって異なります。
賃貸物件の場合、まず連帯保証人に費用負担が求められます。連帯保証人も既に亡くなっているなど、連帯保証人がいない場合は、物件のオーナーや管理会社が費用を負担して遺品整理を行うことになります。ただし、この場合でもオーナーは故人の財産から費用を回収する権利があるため、後から相続財産管理人を通じて請求される可能性があります。
持ち家の場合で相続人がいないときは、最終的に国庫に帰属することになりますが、その前に利害関係者(債権者など)の申し立てにより、家庭裁判所が相続財産管理人を選任することがあります。相続財産管理人は、故人の財産を管理・清算する役割を担い、その過程で遺品整理も行います。
また、生活保護を受けていた方など、経済的に困窮していた方が亡くなった場合は、自治体が葬祭扶助として遺品整理の一部を負担することもあります。このような制度の適用については、各自治体の福祉事務所に相談することで詳しい情報を得ることができます。
いずれにしても、身寄りのない方の遺品整理は複雑な問題を含んでいるため、行政や専門家のアドバイスを受けながら進めることが重要です。
遺品整理業者のサービス内容と依頼の流れ

遺品整理を専門業者に依頼する場合、どのようなサービスが受けられ、どのような手順で進むのかを事前に知っておくことで、スムーズな作業が可能になります。ここでは、基本的なサービス内容と依頼から完了までの流れを詳しく解説します。
基本サービスに含まれる作業の範囲
多くの遺品整理業者の基本料金には、次のような作業が含まれています。
- 遺品の仕分け作業
残すべき大切な品物と処分する品物を丁寧に分類する作業です。写真や手紙、貴重品などの思い出の品は、ご遺族の意向を確認しながら慎重に扱われます。 - 不用品の梱包と搬出作業
処分が決まった品物は適切に梱包され、建物から運び出されます。大型家具や家電製品も、プロの技術で安全に搬出されるため、建物を傷つける心配もありません。 - 作業後の簡易清掃
搬出作業で出たホコリや汚れを掃除機で吸い取ったり、床を拭き掃除したりする程度の清掃です。本格的なハウスクリーニングとは異なりますが、次の入居者や売却のための最低限の清潔さは確保されます。 - 作業に必要な車両費用
ただし、トラックの手配や燃料代などを別途請求されることはありません。
注意すべき点として、不用品の処分費用や家電リサイクル法対象品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機など)のリサイクル料金は、基本料金に含まれない場合が多いです。これらは品目や量に応じて別途費用が発生するため、見積もり時に必ず確認しておきましょう。
問い合わせから作業完了までのステップ
遺品整理を業者に依頼する際の一般的な流れを、5つのステップで説明します。
- STEP1:問い合わせ
電話やウェブサイトの問い合わせフォームから連絡します。この段階で、大まかな状況(間取り、場所、希望時期など)を伝え、現地調査の日程を調整します。多くの業者が土日祝日も対応しているため、仕事を休む必要はありません。 - STEP2:現地調査・見積もり
業者のスタッフが実際に現地を訪問し、部屋の状況や荷物の量を確認します。この調査は通常無料で行われ、30分から1時間程度で終了します。調査後、詳細な見積書が提示されるので、内容をしっかり確認しましょう。不明な点があれば、遠慮なく質問することが大切です。 - STEP3:作業当日打ち合わせ
契約後、作業当日には改めて作業内容の確認が行われます。特に残してほしい品物がある場合は、この時点で必ず伝えておきましょう。作業責任者から作業手順や予定時間の説明を受け、最終的な確認を行います。 - STEP4:作業実施
打ち合わせに基づいて、実際の遺品整理作業が始まります。まず貴重品や重要書類の捜索が行われ、その後、残すものと処分するものの仕分けが進められます。作業中に新たに貴重品が見つかった場合は、その都度報告されます。すべての搬出が完了したら、簡易清掃を行い、お客様に最終確認をしていただきます。 - STEP5:支払い
作業完了後、料金の支払いを行います。多くの業者では、作業前に半額、作業後に残額を支払う方式や、作業完了後に一括払いする方式があります。現金払いのほか、クレジットカードや銀行振込に対応している業者も増えています。領収書は相続関連の手続きで必要になることがあるため、必ず受け取って保管しておきましょう。
なお、遠方にお住まいで立ち会いが難しい場合は、鍵を預けて作業を任せることも可能です。その場合は、作業の進捗を写真で報告してもらえる業者を選ぶと安心でしょう。
失敗しない遺品整理業者の選び方

遺品整理は故人との最後のお別れの場でもあり、大切な思い出の品を扱う繊細な作業です。信頼できる業者を選ぶことは、後悔のない遺品整理を行うために非常に重要です。ここでは、優良業者を見極めるポイントと、トラブルを避けるための注意点を解説します。
相見積もりで比較すべき項目のリスト化
遺品整理業者を選ぶ際は、必ず複数の業者から見積もりを取ることが大切です。これを相見積もりといい、3社程度から取ることで、適正な価格やサービス内容を比較検討できます。
見積書を確認する際は、まず料金の総額だけでなく、その内訳を細かくチェックしましょう。作業費、人件費、車両費、処分費など、それぞれの項目がどのように計算されているかを確認します。
特に注意したいのが「一式料金」という曖昧な表記です。この表記では具体的に何が含まれているのかが不明確なため、後から追加料金を請求される可能性があります。必ず「一式」の内容を詳しく説明してもらい、書面に残してもらうことが重要です。
また、追加料金が発生する可能性のある作業は何か、キャンセル料はいつから発生するのか、作業日時の変更は可能か、損害保険に加入しているか、作業後のアフターフォローはあるか、支払い方法と時期はどうなっているかといった項目も必ず確認しておきましょう。これらの情報を各社で比較することで、最適な業者を選ぶことができます。
見積もりの際は、安さだけで決めるのではなく、サービス内容と価格のバランスを総合的に判断することが大切です。極端に安い見積もりを出す業者は、後から高額な追加請求をしてくる可能性があるため注意が必要です。
悪質な業者に共通する手口と対策
残念ながら、遺品整理業界には悪質な業者も存在します。よくある手口を知っておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
まず気をつけたいのが、価値のある遺品を不当に安く買い取ろうとする業者です。「これは価値がないから処分料がかかる」と言いながら、実際には高値で転売するケースがあります。貴金属や骨董品など、価値がありそうな品物については、別途専門の買取業者に査定してもらうことも検討しましょう。
次に多いのが、作業開始後に「予想以上に荷物が多い」「特殊な作業が必要」などと理由をつけて、高額な追加料金を請求するケースです。このような事態を避けるためには、必ず事前に現地調査をしてもらい、追加料金が発生する条件を明確にしておくことが重要です。
現地調査をせずに電話だけで見積もりを出す業者は要注意です。実際の状況を見ずに正確な見積もりができるはずがなく、後から追加請求される可能性が高いでしょう。
契約を急かす業者にも注意が必要です。「今日中に決めれば割引する」「他の予約で埋まってしまう」などと煽ってくる場合は、冷静に断りましょう。大切な遺品整理だからこそ、じっくりと検討する時間が必要です。
また、不用品回収には「一般廃棄物収集運搬業」の許可が必要ですが、この資格を持たない業者が違法に営業していることがあります。無資格業者に依頼すると、不適切な処分により、依頼者も法的責任を問われる可能性があります。必ず許可証の確認をしましょう。
信頼できる優良業者の見極め方
では、どのような業者を選べば安心なのでしょうか。信頼できる業者にはいくつかの共通点があります。
まず重要なのが、遺品整理士などの専門資格を持つスタッフが在籍していることです。遺品整理士は、遺品整理の専門知識だけでなく、遺族への接し方や法令順守についても学んでいるプロフェッショナルです。資格の有無は、その業者の専門性と信頼性を示す重要な指標となります。
問い合わせへの対応も重要な判断基準です。電話やメールでの問い合わせに対して、丁寧で分かりやすい説明をしてくれる業者は信頼できます。専門用語を使わず、お客様の立場に立って説明してくれるかどうかをチェックしましょう。
見積もりの内容についても、詳しく説明してくれることが大切です。なぜその金額になるのか、どのような作業が含まれているのかを、納得いくまで説明してくれる業者を選びましょう。質問を嫌がったり、曖昧な回答しかしない業者は避けるべきです。
遺品の買取や不用品回収において、自社で全てを行うのではなく、それぞれの専門業者と提携している業者も信頼できます。餅は餅屋というように、各分野のプロフェッショナルと連携することで、より適切なサービスを提供できるからです。
また、地域に根ざして長年営業している業者は、それだけ地域の信頼を得ている証拠です。ホームページで過去の実績や、お客様の声を確認することも参考になります。ただし、極端に良い評価ばかりの場合は、逆に注意が必要かもしれません。
最後に、見積もりから作業完了まで、同じ担当者が一貫して対応してくれる業者は安心感があります。担当者が変わると伝達ミスが起きやすくなるため、できるだけ同じ人が最後まで責任を持って対応してくれる業者を選ぶとよいでしょう。
くらしのセゾンの遺品整理サービスで不安を解消

遺品整理は、大切な方との最後のお別れの場であり、心の整理をつける大切な時間です。しかし、実際には体力的・精神的な負担が大きく、どこから手をつけてよいかわからないという方も多いのではないでしょうか。そんなときは、専門会社のサポートを活用することで、安心して作業を進めることができます。
くらしのセゾンの「遺品整理・生前整理」サービスでは、片付けに精通した専門スタッフが、お客様の大切な家財を心を込めて整理・仕分けします。単に物を片付けるだけでなく、故人様への敬意とご遺族の気持ちに寄り添いながら、丁寧に作業を進めることを大切にしています。
サービスの大きな特徴は、現地での無料調査・無料見積りを実施している点です。専門スタッフが実際に現場を訪問し、お客様のご希望やご予算に合わせた最適なプランをご提案します。見積もり内容に納得いただいてから契約となるため、後から予想外の費用を請求される心配もありません。
作業内容は、貴重品の捜索から不用品の仕分け・搬出まで、一貫して対応します。特に重要なのは、書類などの個人情報を含むものは適切に処理し、家財についても無断で売却・転売することは一切ないという点です。必ずご依頼主の意向を確認したうえで、大切な思い出の品々を丁寧に取り扱います。
遠方にお住まいで作業に立ち会えない場合でも、事前の打ち合わせ内容に基づいて整理作業を代行することが可能です。仕事や育児で忙しい方、実家が遠く頻繁に通えない方でも、安心してご利用いただけます。
さらに、遺品整理だけでなく、生前整理や空き家整理、リフォームにも対応しています。高齢の親御様の施設入居に伴う家財整理や、将来の相続に備えた財産整理のアドバイスも含めて、トータルでサポートいたします。
大切な方の遺品整理は、誰にとっても難しい作業です。思い出に浸りながらも、現実的な片付けを進めなければならない葛藤があります。くらしのセゾンは、そんなお客様の気持ちに寄り添い、故人様との思い出を大切にしながら、新たな一歩を踏み出すお手伝いをいたします。
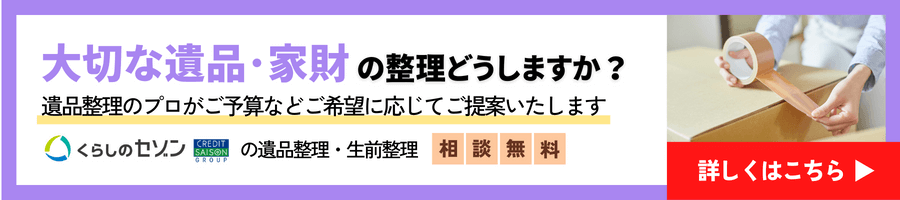
おわりに
遺品整理の費用は、1Kで3万円程度から4LDK以上で60万円を超えることもあり、間取りや荷物の量、建物の状況によって大きく変動します。費用の支払い義務は基本的に法定相続人にありますが、相続放棄や身寄りがない場合など、状況に応じて異なることも理解しておく必要があります。
業者選びでは、必ず複数社から相見積もりを取り、料金だけでなくサービス内容や対応の丁寧さも比較検討することが重要です。悪質な業者を避け、遺品整理士などの資格を持つ信頼できる業者を選ぶことで、故人を偲びながら心のこもった遺品整理ができるでしょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。