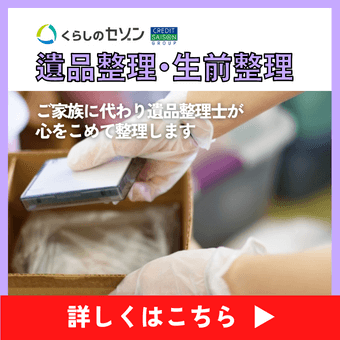「部屋を片付けたいのに、どうしても手が動かない」「何度も片付けようと決意するのに、結局できずに自己嫌悪に陥ってしまう」。そんな苦しい思いを抱えていませんか。
もしかすると、その「片付けられない」状態は、単なる性格の問題ではなく、医学的な背景が関係しているかもしれません。この記事では、片付けが困難になる病気や障害について詳しく解説し、その原因と具体的な対処法をお伝えします。
- 片付けられない背景にはADHD、うつ病、ためこみ症などの医学的要因が潜んでいる可能性がある
- 散らかった部屋は害虫発生や火災リスク、精神的ストレスの増大など深刻な健康被害をもたらす
- 「1日1つ手放す」「引き出し1つから始める」など、今日から実践できる改善ステップがある
- 専門機関への相談や片付け業者の活用により、一人で悩まず適切なサポートを受けられる
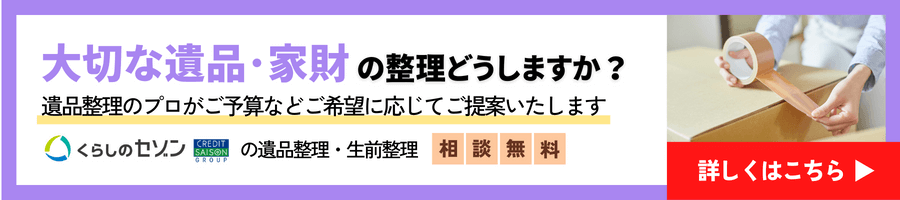
「片付けられない」のは性格ではなく”背景”がある

片付けができないことに悩む多くの人が、「自分の意志が弱いから」「だらしないから」と自己批判に陥りがちです。しかし、その背景には医学的な要因が隠れている可能性があります。ここでは、片付けられない状態の真の原因と、放置することのリスクについて詳しく見ていきましょう。
単なる性格や怠慢ではない3つの背景
「片付けたいのにできない」という苦しい状況は、決して意志の弱さだけが原因ではありません。実は、医学的な背景が関係している可能性があるのです。
代表的な要因として、ADHD(注意欠如・多動症)が挙げられます。この発達障害を持つ人は、注意力の持続や計画立案が苦手なため、片付けの途中で別のことに気を取られてしまいやすいという特性があります。
また、うつ病による意欲低下も大きな要因となります。何もかもが億劫になり、片付けどころか日常生活さえままならなくなることがあるのです。
さらに、ためこみ症(ホーディング障害)という、物を捨てることに強い苦痛を感じる精神疾患も存在します。これらは本人の努力だけでは解決が難しく、適切な支援が必要となります。
「もしかして自分も?」と感じたとしても、決して自分を責める必要はありません。まずは自分の状態を正しく理解することから始めていきましょう。
散らかった部屋が心身に与える深刻なリスク
ゴミが溢れた部屋は、単に見た目が悪いだけではなく、住む人の健康と生活に深刻な影響を及ぼします。
衛生面では、食べ残しや生ゴミが放置されることで、ゴキブリやネズミなどの害虫・害獣が発生しやすくなります。これらは感染症の原因となり、健康被害につながる恐れがあります。また、悪臭が発生し、カビやダニの温床となることで、アレルギー症状を引き起こすケースも少なくありません。
精神的な影響も見過ごせません。散らかった状態を見るたびに「また片付けられなかった」と自己嫌悪に陥り、ストレスが増大していきます。この負のスパイラルは自己肯定感を著しく低下させ、うつ病の悪化につながることもあるのです。
社会的な問題も深刻です。悪臭や害虫の発生により近隣から苦情が寄せられたり、友人や家族を家に招けなくなったりすることで、人間関係が悪化し、社会的な孤立を深めてしまう危険性があります。
さらに、物が積み重なった状態は火災のリスクを高め、災害時の避難経路を塞いでしまう可能性もあるため、生命の危険にもつながりかねません。
片付けられない原因となる主な病気とその特徴

片付けが困難になる背景には、さまざまな病気や障害が関係していることがあります。それぞれの特性を理解することで、適切な対処法を見つけることができるでしょう。ここでは、代表的な3つのカテゴリーについて詳しく解説していきます。
発達障害(ADHD・ASD)の特性が整理整頓を妨げる仕組み
ADHDを持つ人の場合、「不注意」という特性が片付けを困難にさせる大きな要因となります。作業を始めても、途中で別のことに注意が向いてしまい、最後まで完了できないことが多いのです。たとえば、クローゼットを整理している最中に古い写真を見つけて見入ってしまい、気づけば何時間も経っていた、というようなことが頻繁に起こります。
計画性の欠如も特徴的です。「どこから手をつけて良いか分からない」「優先順位がつけられない」といった悩みを抱えやすく、結果として作業が進まないまま挫折してしまうことがあります。
一方、ASD(自閉スペクトラム症)の人は、「強いこだわり」という特性が影響します。特定の物に対する愛着が強く、他人には不要に見える物でも手放すことができません。また、「変化への抵抗」も強く、物の配置を変えることに不安を感じるため、新しい収納方法を取り入れることが困難になります。
これらの特性は、本人がどれだけ努力しても克服が難しい場合が多く、特性に合わせた工夫やサポートが必要不可欠となります。無理に一般的な片付け方法を押し付けるのではなく、その人に合ったアプローチを見つけることが大切です。
精神疾患(うつ病・統合失調症など)が気力を奪うプロセス
うつ病になると、脳内の神経伝達物質のバランスが崩れ、意欲や思考力が著しく低下します。朝起きることすら困難になり、食事や入浴といった基本的な生活行動さえ億劫になってしまうのです。このような状態で片付けをすることは、健康な人が想像する以上に困難なことなのです。
思考力の低下により、「何をどこに片付ければ良いか」という判断ができなくなることもあります。簡単な分別作業でさえ、大きな負担となってしまうのです。
統合失調症の場合は、思考のまとまりが低下するという症状が現れます。物事を順序立てて考えることが難しくなり、ゴミの分別や物の整理といった、複数の判断を必要とする作業が困難になります。また、現実認識が曖昧になることで、ゴミとそうでない物の区別がつかなくなることもあるでしょう。
これらの精神疾患を抱えている場合、まずは適切な治療を受けることが最優先となります。無理に片付けようとすることは、かえって症状を悪化させる可能性があるため、医師の指導のもとで、体調に合わせた生活を送ることが大切です。
参考:国立精神・神経医療研究センター こころの情報サイト|うつ病
国立精神・神経医療研究センター こころの情報サイト|統合失調症
モノへの過剰な執着心を生む「ためこみ症」の実態
ためこみ症(ホーディング障害)は、単に「もったいない」という気持ちとは質的に異なる精神疾患です。物を手放すことに対して、まるで自分の体の一部を失うような強い苦痛を感じるという特徴があります。
以下のような症状が複数当てはまる場合、ためこみ症の可能性があります。
- チラシや空き箱、コンビニの袋など、一般的に価値がないと思われるものでも大量に集めてしまう。
- 「いつか使うかもしれない」「もったいない」という気持ちが強く、物を手放すことができない。
- 物を捨てることに対して、まるで自分の体の一部を失うような、強い不安や苦痛を感じる。
- 集めた物によって生活スペースが著しく狭くなり、ベッドやテーブルの上、床などが物で埋まっている。
- 物が多すぎて、どこから手を付けて良いか分からず、結果として部屋がさらに散らかってしまう。
- 部屋の状況が原因で、友人や家族を家に招くことができない。
- 物を溜め込んでしまう自分を責めたり、罪悪感や孤独感に苛まれたりすることがある。
- 収納が限界を超えても物を処分できず、住環境が悪化している。
ためこみ症の原因として、過去のトラウマ体験が関係している場合があります。大切な人を失った経験や、貧困を経験したことで、物を失うことへの恐怖が強くなることがあるのです。
また、脳の機能的な要因も指摘されています。意思決定を司る脳の部位に何らかの問題があり、物の価値を適切に判断できなくなっている可能性があります。このような場合、専門的な治療アプローチが必要となるでしょう。
状況を改善するために今日からできる具体的な行動

片付けられない状況を改善するには、自分の状態を正しく理解し、無理のない範囲で少しずつ行動を起こすことが大切です。ここでは、今日から実践できる具体的なステップをご紹介します。
まずは専門機関で自分の状態を正しく知る
専門機関への相談を検討すべきタイミングには、いくつかの目安があります。日常生活に支障が出ている場合、たとえば「床が見えないほど物があふれている」「悪臭が発生している」「家族や友人を家に招けない」といった状況が続いているなら、早めの受診をおすすめします。
また、片付けようと思っても体が動かない、何から手をつけて良いか全く分からない、物を捨てることを考えただけで強い不安に襲われるといった症状がある場合も、専門家の助けが必要なサインです。
心療内科や精神科での診察を受けることで、自分の状態に適した診断が得られます。発達障害の専門外来や、ためこみ症の治療に詳しい医療機関もありますので、事前に調べてから受診すると良いでしょう。
専門家に相談することで、薬物療法や認知行動療法など、自分に合った治療法が見つかります。また、症状に応じた具体的な対処法のアドバイスを受けることができ、一人で悩むよりもはるかに効果的な改善が期待できるのです。
受診先は、診療内科・精神科・発達障害専門外来などが適しています。地域によっては自治体の「発達障害支援センター」や「精神保健福祉センター」でも相談できます。
小さな達成感を得るための目標を設定する
片付けを始める際、部屋全体を一気にきれいにしようとすると、その膨大な作業量に圧倒されて挫折してしまいます。そこで重要なのが、ごく小さな範囲から始めることです。
「引き出し一つだけ」「机の上の一角だけ」といった、15分程度で完了できる範囲から始めてみましょう。小さな成功体験を積み重ねることで、「自分にもできる」という自信が生まれ、次の行動へのモチベーションにつながります。
継続しやすい目標の例として、「1日1つ手放す」というルールもおすすめです。使わなくなったペン1本、読み終わった雑誌1冊など、本当に小さなものから始めて構いません。大切なのは、毎日続けることで習慣化することです。
完璧を目指さないことも重要なポイントです。「今日はここまで」と決めて、それ以上は無理をしない。そして、少しでも進んだ自分を褒めることを忘れないでください。自己肯定感を高めることが、継続的な改善につながる鍵となります。
リバウンドを防ぐためにモノの管理ルールを作る
せっかく片付けても、すぐに元の状態に戻ってしまっては意味がありません。リバウンドを防ぐためには、物の管理ルールを作ることが効果的です。
まず重要なのは、物の「入り口」を管理することです。「1つ買ったら1つ手放す」というルールを設けることで、物の総量が増えることを防げます。新しい服を買ったら、着なくなった服を1枚処分する。新しい本を買ったら、読み終わった本を1冊手放す。このシンプルなルールが、部屋の状態を維持する大きな力となります。
次に、物の「出口」を確保する習慣も大切です。月に1回「不用品チェックの日」を設けて、使わなくなった物がないか見直す時間を作りましょう。リサイクルショップやフリマアプリを活用すれば、物を手放すことへの抵抗感も和らぐかもしれません。
すべての物に「定位置」を決めることも、部屋が散らかりにくくなる重要なポイントです。使ったら必ず元の場所に戻すという習慣をつけることで、物を探す時間も減り、生活がスムーズになります。ラベリングを活用したり、透明な収納ボックスを使ったりすることで、どこに何があるか一目で分かるようにすると良いでしょう。
一人では困難な時、頼れるサポートとサービスの選び方

片付けられない状況を一人で解決しようとすると、かえって状況を悪化させてしまうことがあります。適切なサポートを受けることは、決して恥ずかしいことではありません。ここでは、さまざまな支援の形について詳しく見ていきましょう。
家族や身近な人が片付けられない場合の適切な接し方
家族が片付けられない状況にある時、つい「なぜ片付けないの?」「だらしない」と責めてしまいがちです。しかし、このような言葉は本人の自己肯定感をさらに下げ、片付けへの意欲を完全に奪ってしまう危険性があります。
大切なのは、「片付けられないのは意志の弱さではない」と理解することです。病気や障害が原因である可能性を考慮し、本人の困りごとに寄り添う姿勢を持つことが重要となります。「片付けたいけどできない」という苦しい気持ちを受け止め、一緒に解決策を探していく姿勢が必要です。
具体的な協力方法として、まず医療機関の受診を優しく勧めることから始めましょう。「最近、体調はどう?」「何か困っていることはない?」といった形で、自然に話を聞き出すことができれば、受診へのハードルも下がります。
また、片付けを手伝う際は、本人の意向を尊重することが大切です。勝手に物を捨てるのではなく、一つ一つ確認しながら進めていくことで、信頼関係を保ちながらサポートすることができます。
専門業者の利用を提案する際も、「プロに頼むことで楽になるよ」「一緒に業者を探そう」といった前向きな声かけを心がけましょう。第三者の力を借りることは、家族関係を良好に保ちながら問題を解決する有効な手段となります。
こうした「片付けられない悩み」は、実は年齢を重ねたご家族にも多く見られます。特に高齢の親が物をため込みやすくなっている場合、本人だけで片付けることは難しく、家族のサポートが欠かせません。
そこで次に、親の家を片付ける際に役立つ「生前整理」という考え方をご紹介します。
高齢の親の家を片付ける「生前整理」の重要性
親の家を片付ける際、元気なうちから少しずつ家財を整理しておく「生前整理」は、将来の負担を減らすためにとても大切です。施設への入居や病気などで急に片付けが必要になるケースも多く、事前に整理しておくことで、慌ただしい対応を避けられます。また、相続時に「誰が何を引き継ぐか」で家族間でのトラブルを防ぐ効果もあります。
とはいえ、遠方に住んでいて頻繁に実家に帰れなかったり、重い家具や家電の整理が体力的に難しかったりと、思うように進まないことも少なくありません。そんな時は、専門サービスの力を借りるのがおすすめです。
くらしのセゾンの「遺品整理・生前整理」では、経験豊富なスタッフがご自宅に伺い、家財の仕分けから搬出までを丁寧にサポート。単に不用品を処分するだけでなく、思い出の品や大切な書類なども一つひとつ確認しながら整理します。
また、近年はパソコンやスマートフォンの中に残る「デジタル遺品」も重要な整理対象です。写真データや、ネットバンキング情報など、デジタル資産の扱いについてもアドバイスが受けられます。財産整理に関する相談も含め、総合的にサポートできるのがくらしのセゾンの強みです。
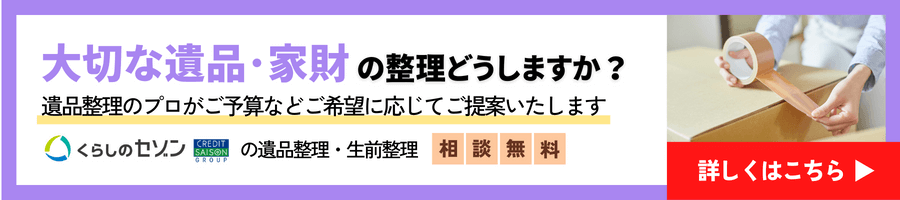
安心して任せられる片付け専門業者の見極め方
大量の不用品に囲まれて身動きが取れない状況では、専門業者への依頼が最も効率的な解決策となります。プロの手を借りることで、最短即日で部屋が片付き、物理的・精神的な負担から解放されるという大きなメリットがあります。
信頼できる業者を選ぶ際のポイントとして、まずプライバシーへの配慮が挙げられます。片付けられない状況を周囲に知られたくないという気持ちは当然のことです。秘密厳守を徹底し、近隣への配慮ある作業を行ってくれる業者を選びましょう。
女性の一人暮らしの場合、男性スタッフだけでは不安を感じることもあるでしょう。女性スタッフが在籍している業者なら、より安心して依頼することができます。事前に相談すれば、女性スタッフのみでの対応も可能な場合があります。
サービス内容の充実度も重要な判断基準です。不用品の回収だけでなく、床や壁の清掃、トイレやキッチンなど水回りのハウスクリーニング、さらには消臭・消毒といった専門的な清掃まで一括で依頼できる業者を選ぶことで、手間を大幅に削減できます。
料金体系が明確であることも大切です。見積もり時に詳細な内訳を提示し、追加料金が発生する可能性についても事前に説明してくれる業者なら、安心して依頼することができるでしょう。
おわりに
片付けられない状態には、さまざまな原因があることをお伝えしてきました。ADHD、ASD、うつ病、統合失調症、ためこみ症など、医学的な背景が関係している可能性があることを理解いただけたでしょうか。
大切なのは、自分を責めず、適切なサポートを求めることです。専門機関での診断、小さな目標設定から始める改善方法、そして必要に応じてプロのサービスを活用することで、必ず状況は良い方向に向かいます。
一人で抱え込まず、家族や専門家、そして片付けのプロフェッショナルの力を借りながら、あなたらしい快適な生活空間を取り戻していきましょう。今日の小さな一歩が、明日の大きな変化につながることを信じて、できることから始めてみてください。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。