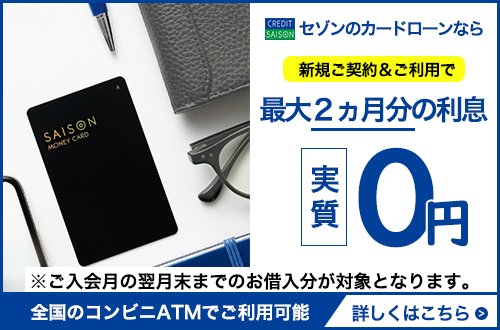健康診断で「再検査」や「要精密検査」と書かれて、費用や会社負担がどうなるのか不安に感じている方もいるのではないでしょうか。この記事では、再検査・精密検査にかかる費用はいくらなのか、健康保険は適用されるのか、会社は負担してくれるのかといった疑問にお答えします。この記事を読めば、再検査・精密検査の費用相場や、いざという時に利用できる制度が分かります。
- 健康診断の再検査や精密検査の費用がいくらか、健康保険は適用されるか
- 再検査や精密検査の費用を会社が負担する義務がない理由と、会社や健康保険組合に確認すべきポイント
- 再検査・要精密検査と言われ、を無視することのリスク
- 高額な医療費に備えるための公的制度(高額療養費制度・医療費控除)や、急な出費に対応するための手段


健康診断の再検査・精密検査にかかる費用はいくら?

健康診断の費用は、企業が全額負担するため、あなたの自己負担はありません。
しかし、健康診断で再検査や精密検査が必要になった場合、その費用は原則として自己負担となります。この再検査・精密検査の費用は、通常、健康保険が適用され、自己負担は3割です。ただし、具体的な費用は検査項目によって大きく異なります。
再検査・精密検査の費用相場一覧
| 検査項目 | 費用相場(保険適用・3割負担) | 主な検査内容・目的 |
|---|---|---|
| 血液検査 | 2,500円~3,000円程度 | 貧血、肝機能、腎機能、脂質異常、血糖値などを詳しく調べる |
| 尿検査 | 1,000円~2,000円程度 | 尿中の糖やタンパク、潜血などを再評価し、腎臓や尿路系の疾患を調べる |
| 心電図検査 | 400円~1,000円程度 | 不整脈や狭心症、心筋梗塞などの心疾患の可能性を調べる |
| 胃カメラ(上部消化管内視鏡) | 3,500円~5,000円程度 | 食道・胃・十二指腸を直接観察し、がんやポリープ、潰瘍などを調べる(※1) |
| 大腸カメラ(下部消化管内視鏡検査) | 5,000円~10,000円程度 | 大腸を直接観察し、がんやポリープ、炎症などを調べる(※1) |
| CT検査 | 5,000円~13,000円程度 | X線で体の断面を撮影し、胸部や腹部の臓器のがんや血管の異常などを調べる |
| MRI検査 | 5,000円~20,000円程度 | 磁気を利用して体の断面を撮影し、脳や脊椎、関節などの異常を調べる |
| 超音波 | 1,000円~3,000円程度 | 超音波を発生させる器械を身体の表面に当て、体内の臓器から跳ね返る超音波で、腫瘍や結石、炎症の有無などを調べる |
| ホルター心電図 | 約5,000円 | 携帯型心電計を使用して、日常生活を送りながら心電図を記録する検査で、動悸や息切れ、めまい、不整脈などの原因を調べる |
※ 表記の料金に加え、以下の場合には追加の費用がかかります。
・生検や鎮静などが必要な場合:数千円~数万円程度
・紹介状なしで大病院を初診で受診する場合:7,000円以上の定額負担金(2022年10月1日から)
※1 胃カメラや大腸カメラで、疑わしい組織を採取して調べる「生検(病理組織検査)」を行った場合、追加で費用がかかることがあります。
正確な費用については、必ず受診を検討している医療機関に直接問い合わせる必要があります。また、健康保険の自己負担割合は年齢によって異なり、原則、70〜74歳は2割、75歳以上は1割となります。
2025年10月から、現役並みの所得はないが「一定の所得」がある方の、外来で医療機関窓口に支払う自己負担割合が1割から2割に引き上げられました。これまで、「一定の所得」がある方は1割負担になる軽減措置がありましたが、それが撤廃された形です。
再検査費用は基本的に保険適用
健康診断や人間ドックは、病気の予防や早期発見を目的として行われるため、健康保険が適用されません。しかし、健康診断の結果、病気の疑いがあるとして行われる再検査や精密検査は、病気の治療のために必要な「診療行為」とみなされるため、健康保険が適用されます。
ただし、例外として、人間ドックで追加した任意検査や、医師の指示によらない本人の希望による検査、そして先進医療の技術料に該当する部分などは、健康保険の適用外となり、自費診療(自己負担)となります。
再検査の費用は会社負担にならない
労働安全衛生法第66条に基づき、事業者は従業員に健康診断を実施する義務がありますが、再検査の費用負担までは義務付けられていません。
健康診断(一次健診)は事業者の義務なので、従業員の費用負担がないことが一般的ですが、再検査は個人の健康管理の一環と見なされるためです。
ただし、会社の福利厚生として再検査費用を補助してくれるケースや、健康保険組合が補助金を出しているケースもあります。まずは会社の総務・人事担当者や、加入している健康保険組合に確認してみましょう。
参照:厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」
健康診断の再検査を受ける場所

健康診断で再検査が必要になった場合、どこで受診すればよいか迷うかもしれません。再検査はどこで受けても健康保険は適用されますが、利便性や追加費用に差が出る場合があります。選択肢としては、主に以下の3つが考えられます。
- 健康診断を受けた医療機関
- かかりつけ医
- 自分で探した専門の医療機関
それぞれのメリットとデメリットを理解し、ご自身の状況に合った場所を選びましょう。
健康診断を受けた医療機関
健康診断を受けた医療機関で再検査を受ける場合、これまでの検査データが残っているため、スムーズに手続きが進みます。医師も過去のデータと比較して診断できるため、より正確な判断につながります。
しかし、健康診断シーズンは予約が混み合い、すぐに受診できない可能性がある点に注意が必要です。
かかりつけ医
普段から通っているかかりつけ医で再検査を受ける場合、既往歴や健康状態を把握しているため、より自身にあったアドバイスが期待できます。
一方で、高度な検査設備がないクリニックの場合、改めて別の医療機関を紹介されるケースがあるため、二度手間になる可能性があります。
自分で探した専門の医療機関
「要精密検査」と診断された場合、その分野を専門とする医療機関を自分で探して受診することも可能です。専門性の高い医療機関では、高度な検査から診断までを一つの場所で完結できるため、より正確で迅速な診断が期待できます。
ただし2022年10月以降、紹介状なしで大病院を受診する場合、初診時特定療養費として7,000円以上の追加費用がかかる可能性があるため注意が必要です。
「要精密検査」の紹介状は”やばい”サイン?
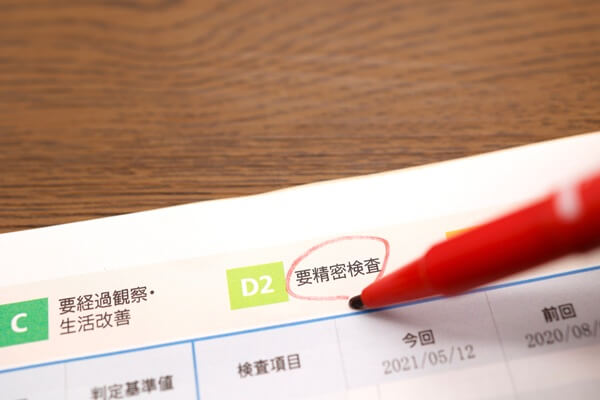
健康診断の結果、要精密検査の結果を受け取ると、「もしかして重い病気なのでは?」と不安になるかもしれません。しかし、結論から言うと、直ちに重篤な病気を意味するわけではありません。
医師の見解では、要精密検査はあくまで「より詳しく調べる必要がある」という段階であり、検査の結果、異常なしと診断されるケースもあります。
要精密検査と判定されるよくあるケースとしては、検査当日の体調による一時的な数値の変動(脱水、飲酒、睡眠不足など)や、体質的なものが挙げられます。
しかし、もちろん重大な病気の早期発見に繋がる重要なサインであることも事実です。決して無視せず、必ず指定された期間内に受診してください。早期に発見できれば、治療の選択肢も増え、医療費の負担も抑えられることが多いです。
健康診断の結果を無視するとどうなる?
再検査や精密検査の指示を無視した場合、重大な疾患の発見が遅れて、初期段階で治療できた病気がより深刻な状態に進行してしまう可能性があります。
病状が進行すれば、治療が長期化したり高額な治療が必要になったりして、結果的に医療費が増大するリスクも高まります。
さらに、会社員の場合、労働安全衛生法に基づき事業者が医師の意見を求め、就業上の措置を講じることがあります。再検査を無視すると、産業医の意見書が作成され、業務内容の変更や、最悪の場合には就業制限を言い渡されることもあります。
費用の支払いが不安な時のための選択肢

再検査や精密検査の費用が数万円に及ぶ可能性を考えると、「もし高額になったら払えるだろうか」と不安に感じるかもしれません。そのような時のために、利用できる選択肢を知っておきましょう。
①高額療養費制度
この制度は、1ヶ月の医療費の自己負担額が上限を超えた場合、超えた分が払い戻される制度です。所得に応じて上限額が定められており、一般的な所得の方であれば、おおよそ数万円〜10万円程度が上限となります。 高額療養費制度は、医療費を支払った後で払い戻されるため、一時的な立て替えが必要になります。
②医療費控除
1年間に支払った医療費の合計が一定額を超えた場合、所得控除を受けられる制度です。支払った医療費の金額に応じて所得税が軽減されます。ただし、医療費控除の還付申告は早くても翌年以降なので、所得控除により還付金を受け取る時期がかなり先になる場合があります。
③カードローン
急な出費で手元に現金がない場合や、公的制度の払い戻しを待てない場合には、カードローンが選択肢の一つになります。カードローンは、審査が通れば即日融資が可能で、担保を用意したり保証人を立てたりする必要もなく、使い道も自由なのが特徴です。
公的制度の払い戻しまで待てない…そんな時の一時的な備えに
再検査や精密検査を早く受けたいけれど、費用が不安で公的制度の払い戻しまで待てないときは、カードローンの利用を検討しましょう。セゾンのカードローン「MONEY CARD GOLD」は最短即日審査なので、再検査や精密検査などの急な出費にも安心です。
また、土日や夜間でも提携ATMから出金できるため、仮に再検査や精密検査の結果、緊急で入院や手術が必要になった場合でも、すぐに医療費を準備できます。※お取扱時間は設置場所により異なります。
MONEY CARD GOLDは、2つのコースから選択いただくことができ、20歳から75歳までの安定した収入のある方がお申し込みいただけます。
- 300万円コース(実質年率6.62%)
- 200万円コース(実質年率8.62%)
ただし、実際の利用可能額は、収入などの申込内容をもとに個別に設定されます。また、貸金業法の総量規制により、年収の3分の1を超える借り入れはできません。
利用する場合は、毎月決まった金額の返済があるため計画的な利用を心がけてください。


おわりに
健康診断の再検査や精密検査で不安を感じたとしても、その費用は数千円から数万円が目安です。そして、多くの場合、健康保険が適用されるため、過度な心配は不要です。
万が一、医療費が高額になったとしても、高額療養費制度や医療費控除といった公的な制度を利用して備えることができます。また、急な出費で手元に現金がない場合でも、一時的な立て替え手段としてカードローンなどの選択肢があることも知っておくと安心です。
最も大切なのは、再検査や要精密検査の指示を無視しないことです。費用の不安から受診をためらわず、ご自身の健康を守るために必ず医療機関を受診しましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。