最近よく耳にする「時間制限食」。
食べる量を減らすのではなく、「食べる時間を決める」というシンプルなルールだけで、ダイエットや体調改善につながると話題です。
「難しそう」「本当に効果あるの?」と思う方もいるかもしれませんが、実は生活リズムに合わせて柔軟に取り入れられるのがこの食事法の魅力。
特に、食べ過ぎや運動不足が気になる方にとっては、身体を無理なく整える方法として注目されています。
本記事では、時間制限食の基本とその効果、始め方などを広島大学 大学院医系科学研究科 公衆衛生学教室 田原 優(たはら ゆう)准教授にわかりやすくご紹介いただきました。
毎日の食習慣を見直すヒントとして、ぜひ参考にしてください。
時間制限食とは?

近年、健康やダイエットの分野で注目を集めている「時間制限食」。
従来の食事法とは少し異なる視点からアプローチするこの考え方は、国内外の研究者によって多くの効果が報告されつつあります。
では、時間制限食とは具体的にどういったものなのでしょうか?
食事の「時間」を制限する食習慣
「時間制限食」とは、1日の中で食事をとる時間をあらかじめ決めて、それ以外の時間は食べないようにする食事法のこと。世間では「8時間ダイエット」「オートファジーダイエット」「ファスティングダイエット」といった呼び方でも浸透しています。
たとえば、「朝10時〜夜6時」の8時間だけ食べるという方法がよく知られています。このスタイルでは、残りの16時間は水やお茶などのカロリーのない飲み物のみで過ごします。
「断食」というと厳しそうなイメージがありますが、時間制限食は毎日の生活リズムに取り入れやすいのが特徴です。朝食を少し遅らせるだけで実践できるため、忙しい現代人にも人気が広がっています。
空腹時間(ファスティング)が肝
人間の身体には、24時間のリズムで働く体内時計(概日リズム)が備わっており、消化・代謝・ホルモン分泌などの機能もこのリズムに沿って動いています。
私たちの身体は本来、“昼に活動し、夜は休む”ようにできています。ところが現代人は、夜遅くまで食べたり、朝早くから食べ始めたりと、身体のリズムに合わないタイミングで食事をとってしまうことも。
時間制限食では、食べる時間帯を制限することで、体内時計の乱れを整え、代謝の効率を高めることが期待されます。
また、重要なのは“食べる時間”だけではなく、食べない時間=空腹時間(ファスティング)にあります。16時間以上の食間(ファスティング時間)をとると、身体は“休息と修復”のモードに切り替わります。この時間こそが、内臓や細胞にとって必要なメンテナンス時間になるのです。
時間制限食の魅力と効果とは?

近年、欧米を中心にこの食事法が注目されている背景には、体重管理だけでなく、生活習慣病予防や体内時計との深い関わりがあることが、科学的にも明らかになってきたからです。
一見シンプルな方法ですが、私たちの健康に与える影響は意外に大きい。その理由をひも解いてみましょう。
無理なく続けやすい!
時間制限食は、「〇〇を食べてはいけない」といった厳しいルールはありません。最初は12時間の枠から始めて、少し慣れてきたら10時間にしていく、といった具合に、無理のない範囲で取り組むことが大切です。
たとえば朝10時に最初の食事をとったら、夜8時までに食事を終える。この10時間の間であれば食事の内容に制限はなく、2〜3回に分けて食べるのが理想です。特に「1日1食」「短時間に詰め込む食事」は血糖値が急上昇しやすく、かえって健康を損ねる可能性があるため、分食しながら制限時間内で収めるスタイルが推奨されています。
体重や体脂肪の減少が期待できる
時間制限食は、自然と間食や夜食が減ることで、1日の摂取量や食欲が抑えられることから、体重や体脂肪の減少に効果があるとされています。
欧米では10時間以内に食事を終えたグループの方が、そうでないグループに比べて明らかに体重が落ちたという報告が多くあり、脂肪が蓄積されにくい時間帯をうまく使って、痩せやすい身体づくりができるのだそうです。
日々の食事リズムを見直すだけで、ダイエット効果が得られる、それがこの食習慣の大きな魅力です。
血糖値や中性脂肪の改善
もうひとつの注目点は、代謝指標の改善効果です。特に血糖値や中性脂肪など、生活習慣病に関連する数値への好影響が期待されています。1日1食のようなスタイルでは、食べたときに血糖値が一気に上がってしまう。しかし、時間制限食で1日3回を基本に分けて食べることで、血糖値の乱高下が抑えられ、代謝が安定します。
血糖や脂質の数値が気になる方にとっても、薬に頼らずにできる実践的な生活改善法として注目されています。
生活リズム改善
時間制限食の効果は、体重や血糖値だけにとどまらず、毎日の生活リズムを整えるきっかけにもなります。“朝はこの時間に食べる”“夜はこの時間までに済ませる”というルールができることで、自然と生活全体が整っていくようになります。
たとえば、夕食を18時までに終えると、就寝前に胃が空になり、睡眠の質が向上したり、翌朝すっきり目覚めやすくなるといった変化を感じる人も少なくありません。
また、規則正しい時間帯で食事をとることは、「今日は何時から食べるか」を自覚的に意識することにもつながり、1日の過ごし方全体を見直す機会になります。食べる時間を決めることで、“食べない時間”の過ごし方も変わってくる。
ダラダラ夜更かししてお酒やお菓子に手が伸びる…という習慣が減っていくという効果も期待できるのです。
アンチエイジング効果も
近年では、時間制限食が持つアンチエイジング効果にも期待が寄せられています。
空腹時間(ファスティング)を設けることで、細胞の修復や老廃物の除去を促す「オートファジー」の活性化が見込まれるため、加齢による身体の劣化を緩やかにする可能性があるのです。
重要なのは“食べない時間”をきちんと確保すること。16時間以上のファスティング時間があって初めて、体は修復モードに入れます。ここを安定させることが、アンチエイジングにもつながるのです。
初心者におすすめの時間制限食の始め方
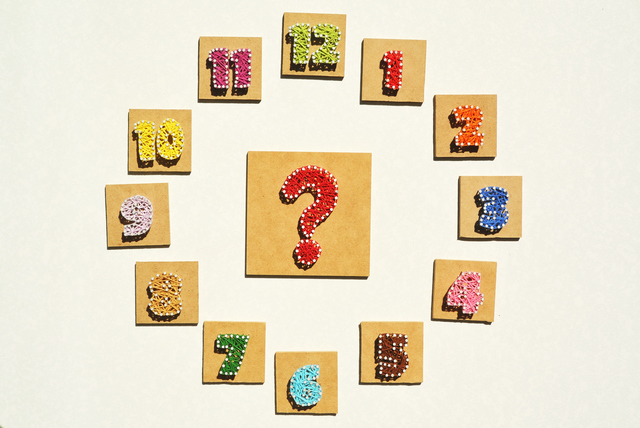
時間制限食はシンプルで始めやすい一方、急に食事時間を大きく変えると身体に負担がかかることもあります。大切なのは、無理なく、生活リズムに合った方法で始めること。
ここでは、これから時間制限食を取り入れたいと考えている方に向けて、実践しやすいポイントをご紹介します。
いきなり厳しくしないのが長続きのコツ
時間制限食は、「朝10時から夜6時まで」といったように、食事の時間帯を制限することで健康効果を得る方法ですが、いきなり8時間など短い枠で始めるのは、ハードルが高く、挫折しやすくなってしまう可能性があります。
最初は12時間から始め、10~8時間を目指すようにしましょう。たとえば、朝10時に1回目の食事をとり、夜8時までに夕食を終えるといったように、日常生活に無理なく組み込める時間帯を選ぶことが大切です。 それに慣れてきたら、徐々に8時間に移行するなど、段階的に短くしていくのが理想的な取り組み方です。
食事内容や回数の改善にも目を向けて
時間制限食は「いつ食べるか」に注目したアプローチですが、「何を食べるか」もなおざりにはできません。特に最初の食事で血糖値が急上昇するような食べ方をすると、かえって健康に悪影響を及ぼす可能性もあります。
また、1日1食や極端に短い時間での食事は、食べた瞬間に血糖値がスパッと上がってしまう恐れも。2~3回に分けて食べる“分食”が基本です。そのうえで、食事の質にも目を向けてください。
多くの研究で、3ヶ月程度で体重や代謝に明確な変化が現れることが報告されています。毎日ダラダラと食事時間が長くなりがちな方にとって、短期的に実践しやすい方法として注目されているのが時間制限食。
ただし、この食べ方を長期間続けることが目的ではありません。あくまで短期的なダイエット法や、生活習慣を見直す“きっかけ”として活用することが推奨されています。
時間制限食のポイントと注意点とは?

時間を区切るだけで始められる時間制限食は、実践しやすい反面、正しい知識と工夫がなければ思うような効果が得られない場合もあります。
ここでは、時間制限食を効果的かつ安全に続けるために知っておきたい基本のポイントと注意点を紹介します。
空腹時間のサイクルを守る
今日は16時間空けられたけど、次の日は食間が短くなってしまった…。そうした不規則なサイクルでは、効果が2日に1回しか得られていないかもしれません。時間制限食の効果をきちんと得るには、ある程度の規則性が必要です。
たとえば、「今日は10時から18時」「明日は13時から21時」などと日によってバラバラになると、体内時計も乱れてしまい、食事のリズムが安定しません。そのため、まずは毎日同じような時間帯に食事をとることを心がけることが、継続と効果のカギとなります。
ライフスタイルの合わせて柔軟に
時間制限食には、「この時間でなければならない」という厳格なルールはなく、何時に食事を始めるかは、自分のライフスタイルに合わせて調整して構いません。ただし、就寝の2時間前には食事を終えることが、睡眠の質を高め、脂肪の蓄積を防ぐうえでも推奨されています。
特に夜勤がある方は注意が必要です。昼夜逆転しやすい生活では、一般的な時間帯に合わせるのがかえって負担になることも。
その場合は、普段の食生活をベースに、夜勤明けに朝食をとってから眠るといったスタイルが望ましいとされています。
また、朝型・夜型など生活リズムが人それぞれ異なることを前提に、自分に合った時間帯で取り組むことが重要です。
「この時間に食べなければならない」と決めつけるのではなく、体調や生活に合わせて調整していく柔軟さこそ、時間制限食を続けるためのコツです。
高齢者は注意が必要
時間制限食は比較的若年〜中年層の健康維持やダイエットには有効とされる一方で、高齢者(65歳以上)には慎重な判断が求められます。
高齢者の場合、体重を減らすことよりも、むしろ“維持する”ことのほうが健康上重要です。加齢にともなって筋肉量が減少するサルコペニア(加齢性筋肉減少症)のリスクが高まりやすく、過度な空腹時間を設けることで食事量の低下や栄養不足を引き起こす可能性もあるため、注意が必要です。
まとめ:無理なく続ける時間制限食で、日々の体調を整えよう

時間制限食は、「何を食べるか」よりも「いつ食べるか」に注目するシンプルな食習慣。食事内容の厳しい制限がなく、時間を意識するだけで始められるため、ダイエットや生活改善の「入り口」として非常に取り組みやすい方法です。
ただし、体質や生活リズムとの相性もあるため、自分に合うかどうかを試しながら、無理のない範囲で取り組むことが大切です。
また、長期的な健康を見据えるなら、やはり3食をバランス良く、規則正しくとる食習慣が理想的。時間制限食は、その理想に近づくための“きっかけ”として活用するアプローチとして考えてみてください。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。





























