引っ越しや買い替えで不要になった家電。「捨てたいけど、どうすればいいの?」「無料で処分できる方法はある?」と悩んでいませんか?家電には法律で決まったルールがあり、正しく手放すには知っておきたいポイントがあります。
この記事では、一般財団法人 家電製品協会監修のもと、家電を賢く、安全に処分するための方法を、わかりやすく解説します。迷いや手間を減らして、スッキリ手放しましょう。
家電は簡単に捨てられない?

私たちの暮らしに欠かせない冷蔵庫や洗濯機といった家電製品。実は、その多くは通常のゴミとして簡単に処分することはできません。
特に大型家電や主要な電化製品は、法律で処分方法が定められており、自治体や指定の回収ルートを通す必要があります。
誤った方法で捨ててしまうと、環境への悪影響だけでなく、思わぬトラブルや罰則の対象になることも。まずは「家電を捨てるのは簡単ではない」という前提を理解しておきましょう。
「燃えないゴミ」では出せない理由
家電製品の多くは、自治体の粗大ごみや不燃ごみの区分には含まれません。その理由として、家電には内部に金属やプラスチック、ガラス、さらには有害物質やフロンガスなどが含まれている場合があり、適切に分解・処理しないと環境汚染の原因になるためです。
そのため、家電ごとに定められた特別な回収ルールを守る必要があります。
処分方法を間違えると法律違反になることも
特に、テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機などは「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」の対象であり、勝手に廃棄したり、許可のない業者に渡したりすると法律違反にあたる可能性があります。
さらに、個人情報が残っている機器を適切に処分しないと情報漏えいのリスクも。安全で正しい処分のためにも、必ず自治体や認定業者の案内に沿った方法を選びましょう。
処分にはルールがある!「家電リサイクル法」と「小型家電リサイクル法」

家電を手放すとき、ただゴミに出せばいい…というわけではありません。日本では資源を無駄にせず、環境を守るために、処分のルールが法律でしっかり決められています。
特に「家電リサイクル法」と「小型家電リサイクル法」は、私たちが守るべき代表的な制度。知らずに違反してしまうことがないよう、基本をおさえておきましょう。
知っておきたい「家電リサイクル法」とは?
2001年に施行された「特定家庭用機器再商品化法」の通称で、家電製品に含まれる金属やプラスチックをリサイクルし、廃棄物を減らすことを目的としています。メーカー・販売店・消費者それぞれに役割があり、「正しい回収ルートで処分する」ことが義務づけられています。
家電リサイクル法の対象となる家電製品は以下の4品目です。
- テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)
- エアコン
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
これらは資源の有効利用や廃棄物削減、社会的コスト低減の観点から対象になっています。適切に分解しないと環境負荷が大きいため、一般ゴミとしては処分できません。
2024年度における指定引取場所での家電4品目の引取台数は約1,458万台にのぼりました。また、同年度のリサイクル処理台数は約1,445万台で、ほぼ引き取った全ての製品が適切に処理されています。
家電4品目の素材別の再商品化重量は約49.3万トンで、全体の再商品化率は約87%に達しています。多くの家電が資源として有効活用され、環境負荷の軽減に貢献しています。
リサイクルにかかる費用は誰が負担する?

リサイクルにかかる費用は、基本的に捨てる人(排出者)が負担します。リサイクル料金は、メーカーが実施する再資源化にかかる費用で、メーカーや品目ごとに金額が異なります。
例えば、家電リサイクル法の対象家電を販売店に引き取ってもらう際は、「リサイクル料金」と「収集・運搬料金」の二つが必要になります。
リサイクル料金の支払いは「家電リサイクル券」を使って行います。一方、収集・運搬料金は販売店が家電を指定引取場所まで運ぶための費用で、金額は各販売店が設定しています。
合計額はメーカー・製品・販売店によって変わるため、処分を依頼する前に販売店やメーカーに料金を確認しておくと安心です。
家電リサイクル法で使われるリサイクル券(特定家庭用機器廃棄物管理票)には、固有の「お問い合わせ管理票番号」が付いており、この番号で家電の処理状況を追跡できます。
排出者は控えを保管し、回収やリサイクルの状況は小売業者やリサイクル業者によって記録・管理されます。このシステムにより、廃棄物の適正な管理と流通が確実に行われる仕組みとなっています。
金属資源をムダにしない!「小型家電リサイクル法」とは?
小型家電リサイクル法は2013年に施行され、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」が正式名称です。スマホ、デジカメ、ゲーム機、ドライヤーなど、小型家電に含まれる金・銀・銅などの貴重な金属を回収・再利用するための制度です。
日本で1年間に使用済みとなる小型家電は65万トン、そのうち有用な金属は28万トン(金額にして年間約844億円分)といわれています。これが、いわゆる「都市鉱山」と呼ばれるもので、有用な資源のリサイクルが期待されています。
小型家電の回収方法は自治体や認定業者によって異なり、回収ボックス設置や窓口での受付などがあります。対象製品も自治体によって異なるため、事前確認が重要です。
どうやって捨てるか迷った時は「正しい捨て方・回収依頼の方法」を確認
「これって粗大ごみ?それともリサイクル?」と家電の処分に迷ったときは、一般財団法人 家電製品協会が提供する「3秒でえらべる家電の捨て方・回収依頼の方法」のページが便利です。簡単な質問に答えるだけで、正しい処分方法がわかるので、家電の処分方法に困った際には、チェックしてみましょう。
参照元:一般社団法人家電製品協会|3秒でえらべる家電の捨て方・回収依頼の方法
プロに聞く、家電の正しい処分方法

家電の処分には処分する家電によってルールがあり、処分方法にも複数の選択肢があります。
そして、自治体、販売店、メーカー指定の回収場所、不用品回収業者などそれぞれにメリット・デメリットがあります。買い替え・単独処分・運搬の可否など、自分の状況に合った方法を選ぶことが大切です。
ここからは、家電の代表的な処分方法と注意点を分かりやすく解説します。
家電量販店で引き取ってもらう
新しい家電を購入する際、同時に古い製品を有料で引き取ってくれる店舗が多くあります。買い替え時の手間が少なく確実なのがメリットですが、引取手数料や収集運搬費が別途かかる場合があるため、事前に料金と作業内容を確認してください。
指定取引場所への持ち込み
メーカーやリサイクル事業者が指定する回収・リサイクル拠点に直接持ち込む方法です。家電リサイクル法のルールに沿った最も確実な処分方法で、リサイクル券(リサイクル料)の手続きが必要になります。運搬手段がある場合や、確実にリサイクルしたいときにおすすめです。
市町村の回収サービスを利用する
購入した店舗が不明なときや買い替えではなく単独で処分したいときは、お住まいの自治体の回収サービスを確認してみましょう。対象品目や申込み方法、料金は自治体ごとに異なるため、自治体のホームページや環境窓口で事前に申し込み手順や搬入場所、収集日を確認してから手配しましょう。
不用品回収業者に回収を依頼する
自宅まで回収に来てくれるなど便利ですが、無許可業者や法外な料金を請求する業者も存在します。
一般廃棄物処理業の許可を持っているか、見積りは書面でもらい、追加費用の有無や取り扱い品目・キャンセル規定・領収書の発行可否を確認しましょう。信頼できる業者選びがトラブル回避の鍵です。
メーカーやリサイクル業者による家電回収は通常1~2週間かかります。比較的予約が取りやすいのは10月から2月の冬季で、引っ越しや転勤が多い3月や9月は特に忙しくなります。回収をスムーズに進めるには、早めに業者へ連絡して予約状況を確認することが大切です。
捨てる以外の選択肢もある
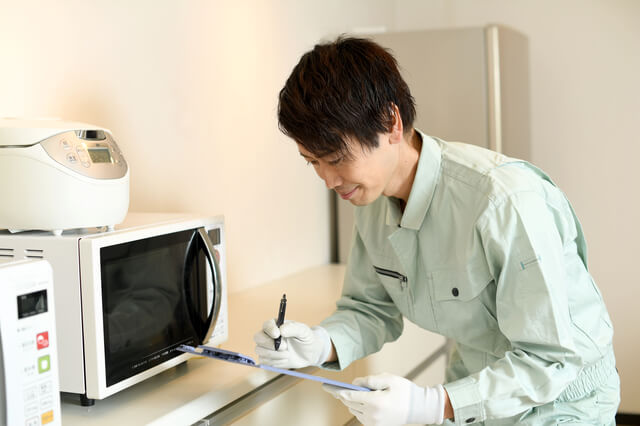
まだ新しい家電なら、ただ「捨てる」のではなく、「活用する」方法もあります。リユースやリサイクルは環境にやさしいだけでなく、経済的にもメリットがあります。
さらに、福祉団体やNPOに寄付すれば、社会貢献にもつながります。ただし、個人間での売買には注意が必要です。掲示板やフリマアプリでの取引でも、実際には業者が関与している場合があることを覚えておきましょう。
また、一般財団法人 家電製品協会によると、発売から7年以内の家電はリユースに向いているとされています。この「7年」という目安は、メーカーが修理部品を保有している期間に基づくもので、7年以上経過した製品は修理が難しくなるため、リサイクルでの処分が推奨されます。
まとめ:家電を正しく処分して、安心・スッキリな暮らしへ

家電の処分は、法律やルールを守ることがとても重要です。特にテレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機などの主要な家電は「家電リサイクル法」の対象であり、正しい回収ルートで処分しなければなりません。
自治体や販売店、メーカー指定の取引場所、認可された回収業者など、処分方法にはさまざまな選択肢がありますが、それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分の状況に合った方法を選びましょう。
また、まだ使える家電は「捨てる」だけでなく、リユースや寄付といった活かす方法もあります。正しい知識をもって適切に処分すれば、不要な家電も安心して手放せ、環境負荷の軽減にも貢献できます。この記事を参考に、賢く安全な家電の処分で、スッキリ快適な暮らしを実現しましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。






























