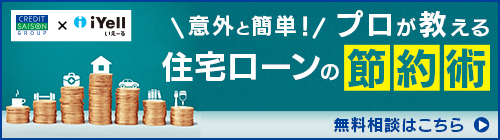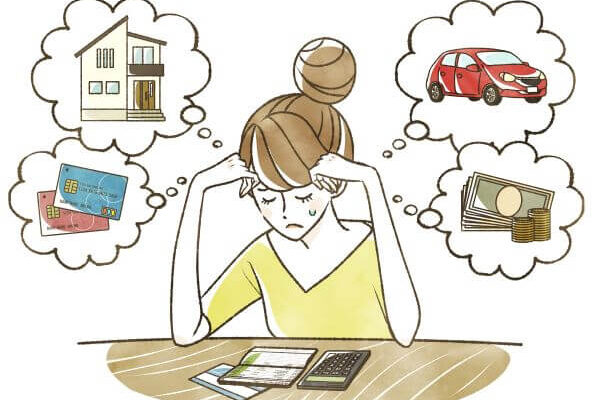分譲マンションの購入を検討する際、メリットだけではなくデメリットも知りたい方は多いのではないでしょうか。この記事では、戸建てと比べた分譲マンションのメリット・デメリットを詳しく解説します。
最後まで読んでいただくことで、分譲マンションの魅力や、どんな方に向いているのかがわかります。戸建てと分譲マンションのどちらを購入するか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
分譲マンションのデメリットには、騒音トラブルが発生しやすいこと、修繕積立金や管理費が必要なこと、リフォームをしづらいことなどがあります。
一方で分譲マンションには、立地やセキュリティの良さ、耐久年数の長さ、断熱性・気密性の高さといった多くのメリットがあります。設備や利便性を重視したい方、手間をかけずに長く住みたい方には、戸建てより分譲マンションが向いている可能性があります。
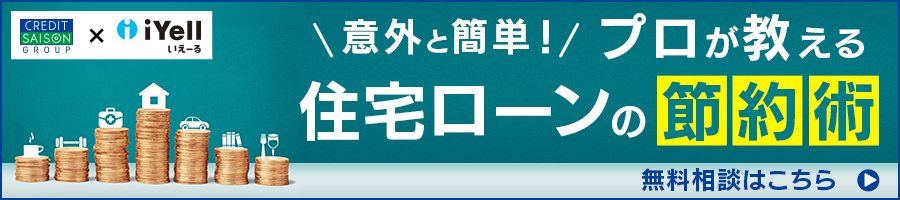

分譲マンションとは?種類や分譲賃貸マンションとの違いを知ろう

はじめに分譲マンションの概要を解説します。新築・新古・中古と分けられる他、分譲賃貸マンションとも明確な違いがあります。
分譲マンションとは
「分譲」とは、土地や建物を分割して譲渡することをいいます。分譲マンションは、1棟の建物と敷地を区分して売り渡された住戸です。分割した建物の所有権(区分所有権)と敷地利用権を売買契約で移転する方法で譲渡されます。以下で分譲マンションの種類を説明します。
新築マンション
新築マンションは、竣工から1年未満のマンションを指します(住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条2項)。だれも入居したことがなければ、竣工から1年に満たないうちは「新築」として打ち出せるため、購入を検討している方にアピールしやすい利点があります。
参照元:国土交通省「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年六月二十三日法律第八十一号)」
新古マンション
新古マンションは、一般的に誰も入居することがないまま、竣工から1年以上経過した物件を指します。法律上、販売する際に「新築」と打ち出すことはできませんが、だれも住んだことがない新しいマンションが新築よりも割安で販売されます。
中古マンション
一度でも誰かが入居したことのあるマンションは、中古マンション扱いとなります。不動産業界では「建築後1年以上経過し、または居住の用に供されたことがあるマンション」は中古マンションに該当するとされています(「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」第3条10号)。
参照元:不動産公正取引協議会連合会「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」
分譲マンションと分譲賃貸マンションの違い
分譲マンションと分譲賃貸マンションには、さまざまな違いがあります。分譲マンションは自ら購入して所有する物件であり、分譲賃貸マンションは、本来分譲マンションとして購入した方が転勤に伴う引っ越しなど何らかの理由で住めなくなり、賃貸として提供している物件です。家賃収入を目的に分譲マンションを購入する方もいます。
分譲マンションは購入者の資産となりますが、分譲賃貸マンションに入居する方は家賃を払って一定期間利用するだけです。マンションを購入した方なら好みに合わせてリフォームできますが、賃貸マンションの入居者がリフォームをする際はオーナーの許可が必要となります。
分譲マンションは戸建てと比べてデメリットが多い?
分譲マンションは、戸建てと比べてデメリットが多いといわれることもあります。ここでは騒音問題や修繕積立金の負担など、具体的なデメリットを解説します。
騒音によるトラブルが発生しやすい
分譲マンションには、上下階や両隣の住民との間で、騒音によるトラブルが発生しやすいデメリットがあります。戸建ては隣家との間に距離があるのに対し、他人の部屋が近接していることが多いためです。
大音量で音楽を聴いたり、子どもが走り回ったりすると、トラブルの原因となる可能性があります。壁や床に防音性の高い素材を使ったマンションを選ぶことや、住民同士のあいさつを欠かさず隣人と良好な関係を築くなど、トラブルに発展する心配を和らげる工夫が大切です。
修繕積立金や管理費が必要
分譲マンションを購入すると、修繕積立金や管理費の支払いが必要になります。国土交通省の「令和5年度マンション総合調査」によると、1戸当たりの修繕積立金は平均月13,378円、管理費は平均月17,103円となっています。住宅ローンに加えて毎月30,000円前後の支出を求められることは、家計の大きな負担となる可能性があります。
管理費は、マンションのエントランスや階段といった共有部分の管理や設備の維持管理などに必要です。戸建てにはない支出ですが、管理費が設備の改善に充てられたり、清掃が行き届いたりするなど快適な住環境が得られます。
修繕積立金は、外壁の塗り替えや設備の更新に必要な費用を、管理組合の取り決めに従って積み立てておくものです。戸建ての場合は、毎月積み立てる必要はありませんが、定期的なメンテナンスに備えて資金を用意しておく必要はあります。
リフォームやリノベーションをしづらい
分譲マンションのデメリットとして、リフォームやリノベーションをしづらいことが挙げられます。マンションの構造上の制約などで管理組合が決めたルールに従う必要があるためです。
専有部分である居室をリフォームしたいと考えても、玄関ドアや窓、バルコニーなどは区分所有者に専用使用権がありますが、共用部分として定められており、自由に現状の変更などはできません。分譲マンションを購入する際は、リフォームやリノベーションについて管理組合の規則を確認するのが重要です。
リフォーム費用でお困りの方は「セゾンのリフォームローン」へご相談ください。


ペット飼育やゴミ出しなどのルールがある

ペット飼育やゴミ出しなどのルールがあることも、分譲マンションのデメリットといえるでしょう。多くの住民が共同で暮らすマンションでは、他の住民に対する配慮や共用部分の適切な管理のため、詳細なルールが管理規約で定められているケースがほとんどです。
飼育可能なペットの種類や飼育数、演奏できる楽器や時間などが決められている場合があり、戸建てに比べて生活に一定の制限が生じます。ゴミ出しに関しても、指定された曜日や時間に出すよう求められるのが一般的です。
広さが限られる
分譲マンションは広さが限られることもデメリットです。戸建てのように2階建てや3階建ての構造は難しいため、部屋数を多くしづらい傾向があります。
マンションは土地の面積に対して多くの区分所有者がいるため、1戸当たりの広さは限られます。住宅金融支援機構の「2023年度フラット35利用者調査」によると、住宅面積の全国平均は、マンションが66.2平方メートルだったのに対して、戸建て(注文住宅)は119.5平方メートルでした。広さがないため間取りの自由度が限られる上、庭を設けられないこともデメリットに感じる方もいるでしょう。
参照元:住宅金融支援機構「2023年度 フラット35利用者調査」
駐車場代が別途必要な場合も
分譲マンションの場合、駐車場代が別途必要なことがデメリットとなります。戸建てなら敷地内に駐車場を用意すれば自由に使えますが、マンションの場合は、管理組合に駐車場代を支払わなければならないケースが多く、なかには駐車場代込みで管理費の金額が設定されている場合もあります。
また、機械式駐車場の場合は車の移動に時間がかかることもあり、戸建てと比べて手間に感じる方もいるでしょう。敷地内の駐車場不足で、マンションから離れた場所にご自身で駐車場を借りなければならないケースもあります。
分譲マンションにはメリットも!
分譲マンションにはデメリットだけでなく、メリットも豊富にあります。立地やセキュリティ、耐久年数など戸建てを上回る利点を詳しく解説していきます。
立地が良い物件が多い
分譲マンションの大きなメリットは、立地が良い物件が多いことです。マンションは建物に多くの住戸を造れるため、資金を確保しやすい特徴があります。これにより駅近や商業施設が集まる場所に建設されるのが一般的で、通勤通学や買い物、通院など毎日の暮らしで優れた利便性を享受できるでしょう。
国土交通省の「令和5年度 住宅市場動向調査報告書」によると、分譲マンションを取得した世帯が住宅を選んだ理由は「立地環境が良かった」が54.0%と半数以上を占めています。立地が良い物件は資産価値が落ちにくいので、売却する際にも有利になります。
セキュリティが整っている
セキュリティが整っていることも分譲マンションのメリットです。分譲マンションにはエントランスにオートロックや防犯カメラを設置することが多く、不審者の侵入対策などで戸建てより高い安心感があります。
管理人に常駐してもらったり、宅配ボックスや利用キーが必要なエレベーターを設置したりすることで、防犯力をさらに引き上げることも可能です。
ワンフロアのため暮らしやすい
分譲マンションは、2階建てや3階建ての戸建てのように室内階段がなく、ワンフロアで暮らしやすいのが利点です。階段の上り下りによる負担がないため、体力が低下する高齢になっても快適に暮らしやすくなります。
ワンフロアのため部屋数は限られますが、間取りをシンプルにできることから生活動線を確保しやすいのもメリットです。リビング、寝室、キッチンなどが同じフロアにあるため、家族が接する機会が増えます。子どもがいる家庭にとっては目が届きやすい点も魅力です。
耐久年数が長い

耐久年数が戸建てに比べて長いことも、分譲マンションのメリットです。耐久年数は、住宅メーカーなどが独自テストなどを通して判断した住宅として使用できる期間です。期間は各社の判断で異なりますが、国土交通省の資料で、鉄筋コンクリート造の建物の物理的な寿命は100年を超えるとの推定が紹介されたこともあります。
減価償却費を計算する際に使う固定資産の耐用年数を示した国税庁の耐用年数表でも、分譲マンションの優位性が確認できます。戸建てに多い木造住宅の耐用年数は22年であるのに対し、分譲マンションのような鉄骨鉄筋コンクリート造や鉄筋コンクリート造の住宅は47年と定められています。
参照元:国税庁「耐用年数表」
断熱性・気密性が高い傾向にある
分譲マンションは、断熱性・気密性が高い傾向にあります。分譲マンションはコンクリートで一体的に躯体を造るため、隙間ができにくい構造です。特に近年は省エネ性能を重視した建材や工法が採用されており、断熱性や気密性に優れた物件が増えています。
断熱性・気密性が高い建物は外気の影響を受けにくいため冷暖房が効きやすく、温度変化の少なさから冷暖房費の上昇を抑えることも可能です。高い気密性で室内の湿度調整もしやすく、カビやダニの発生を防ぐ効果も期待できます。
眺望や日当たりが良い傾向にある
分譲マンションは、2階建てや3階建てが多い戸建てに比べて高さがあるため、眺望や日当たりが良い傾向にあります。
上層階になるほどその可能性は高まり、周囲から覗かれにくい点もメリットになるでしょう。日当たりが良い部屋は室内が明るく、温かくなるため、光熱費を抑える効果も期待できます。
将来的に売却しやすい
将来的に売却しやすい点も分譲マンションのメリットです。設計段階では購入者が決まっていないため、万人にとって住みやすい間取りが採用されることがほとんどです。
このため、住んでから売却することになっても、間取りを理由に購入を敬遠される確率が下がります。この他、駅や商業施設に近い立地が多いことや、セキュリティが優れていることなど、戸建てに比べて買い手が見つかりやすい理由が多くあります。
便利な共有スペースが設置されている場合もある
分譲マンションには便利な共有スペースが設置されている場合があることも、メリットのひとつといえます。ゲストルームやキッズルーム、プール、ジムなどの共有スペースを備えたマンションもあります。
維持管理のコストは必要になりますが、こうした便利なスペースを利用することで、戸建てにはないラグジュアリーな暮らしや、住民同士の活発な交流も期待できるでしょう。
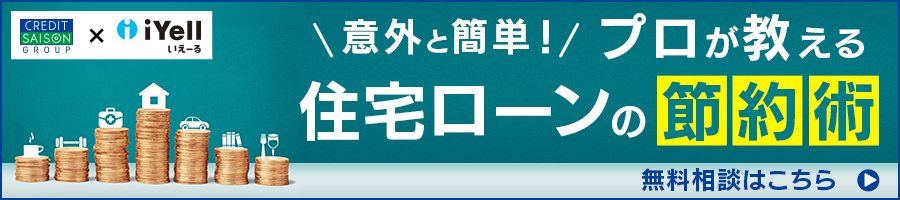

分譲マンション購入に向いている方は?

分譲マンションのメリットとデメリットを踏まえ、分譲マンション購入に向いている方の特徴を解説します。
設備や利便性を重視したい
分譲マンションは、駅近などの好立地にあるケースが多いことや、新築時点でジムやゲストルームなどの便利な共有スペースを備えていることがあるため、設備や利便性を重視して住宅探しをしている方におすすめです。
省エネや環境対策が施された物件も増えており、光熱費が上昇する状況では大きなメリットとなるでしょう。IoTを活用したスマートホームシステムの導入も進み、利便性はさらに高まっています。
新しい技術や設備を活用した快適な生活を送りたい方、生活に必要な施設へのアクセスを重視する方は、分譲マンションが向いています。
手間をかけずに長く住みたい
手間をかけずに長く住みたい方も、戸建てより分譲マンションが向いています。分譲マンションの強みのひとつは、共有スペースの維持管理を管理組合や管理会社が担ってくれることです。
戸建ての場合も定期的な屋根・外壁の修繕、庭の手入れなどが必要になりますが、基本的にご自身で管理する必要があります。一方で分譲マンションの場合は、修繕積立金や管理費がかかるものの、専門会社との折衝やスケジュール管理などは管理会社が行ってくれるため、手間を大幅に軽減できます。
分譲マンションの選び方

分譲マンションを選ぶ際は、新築と中古のメリット・デメリットを知り、立地条件や管理状況をよく確認して選ぶことが大切です。ここでは、分譲マンションの選び方を解説します。
新築と中古のメリット・デメリットを知る
分譲マンションには新築と中古があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。以下の表で確認しましょう。
| 新築分譲マンション | 中古分譲マンション | |
|---|---|---|
| メリット | ・セキュリティや設備が最新 ・最初の居住者になれる ・共用施設が充実している ・修繕リスクが少ない ・長期保証が付くことが多い ・中古に比べて住宅ローン控除が手厚い | ・新築と比べて価格が安い ・資産価値を維持しやすい ・事前に管理体制を確認できる ・購入前に物件を確認できる ・すぐに入居できる ・リノベーションしやすい |
| デメリット | ・購入費用が高額になりがち ・購入前に物件を確認できない ・建設中だと引き渡しまでに時間がかかる ・購入後に資産価値が下がりやすい | ・セキュリティや設備が古い可能性がある ・修繕リスクが高い ・保証が終了しているか、限定的な場合が多い ・新築に比べて住宅ローン控除の借入限度額が少なく、控除期間が短い |
新築マンションはセキュリティや設備が最新で、共用施設も充実しているケースが多いですが、その分購入費用が高くなります。一方、中古マンションは新築に比べて価格が安い傾向にありますが、設備が古いと修繕費用がかかる可能性があります。
また、保証やアフターサービスの有無、資産価値の維持のしやすさなど、それぞれにメリット・デメリットがある点を理解しておきましょう。なお中古マンションに関しては、資産価値を維持しやすい傾向があるものの、実際は立地条件や管理状態によって左右される点に注意が必要です。
立地条件を確認する
分譲マンションを選ぶ際は、所在地の立地条件を確認することが重要です。例えば、以下のような点に注目して立地条件を見極めましょう。
- 交通機関へのアクセスは良好か
- 商業施設、教育施設、医療施設、公園などが近くにあるか
- 治安が良いか
- 災害リスクが高くないか
- 再開発などにより資産価値の向上が見込めるエリアか
交通機関へのアクセスに関しては、最寄駅からの距離だけではなく、複数の路線や駅が利用できるか、駅から自宅までの道のりが安全かどうかの確認も重要です。また、徒歩圏内に商業施設があるなど、周辺施設が充実していると利便性がさらに高まります。普段の買い物を想定し、営業時間や品揃えなども確認しておくとよいでしょう。
さらに、犯罪率が低く治安の良いエリアや、災害リスクの少ないエリアであれば、より安心して暮らせます。所在地の犯罪率をインターネットで調べたり、ハザードマップを利用して災害リスクを確認したりして、安心して暮らせるエリアかどうかを確認しましょう。マンション自体のセキュリティや耐震性能も確認しておくと、より安心です。
再開発が予定されているエリアなど、周辺環境の将来性が高い地域であれば資産価値の向上も期待できます。
マンションの管理状況を確認する
特に中古マンションの場合は、清掃が行き届いているか、植栽が適切に管理されているか、ゴミ置き場が清潔かどうかなど、管理状況を確認することが大切です。また、過去に計画通りに修繕工事が実施されているか、今後の修繕予定がどうなっているかについても、管理組合の総会議事録や長期修繕計画で確認しましょう。
さらに、マンションの床面積や全戸数、機械駐車場の有無などから、修繕積立金が適切に積み立てられているかを確認することも大切です。将来的に修繕積立金が不足するリスクや、値上がりのリスクがある点も念頭に置いておきましょう。
分譲マンションの費用相場はどのくらい?
国土交通省の「住宅市場動向調査」によると、三大都市圏における分譲マンションの購入資金は、新築が平均4,716万円、中古が平均2,793万円となっています。また、同省が公表している「不動産価格指数」によれば、2010年の平均値を100とした場合のマンション(区分所有)の不動産価格指数は201.4です。つまり、2010年と比較して、マンションの価格は2倍以上に上昇しています。
一方、戸建て住宅の不動産価格指数は119.2であることから比較すると、マンション価格の高騰が顕著であるとわかります。マンション価格上昇の背景には、建築資材の価格高騰や建設業界の人手不足、円安による海外投資家の購入が活発化に加えて、都市部への人口集中による需要の増加や、長期にわたる低金利政策で住宅ローンを組みやすい環境が続いていることなど、さまざまな要因が影響しています。
分譲マンションの購入を検討している方におすすめのサービス
分譲マンションを購入する際、ほとんどの方は住宅ローンを利用します。ただ、多くの金融機関があるため、どの商品がご自身に合うのかを調べるのには手間がかかるでしょう。
クレディセゾングループが提携しているiYell(いえーる)の「住宅ローンの相談窓口」では、新規の借り入れに関する相談を幅広く受け付けています。
年齢や職業といった情報を基にそれぞれの考えに沿った住宅ローンを提案できます。金利タイプや返済年数、団体信用生命保険など、さまざまな条件で商品を選べるうえ、相談は無料です。マイホーム購入を検討している方は、相談してみてはいかがでしょうか。
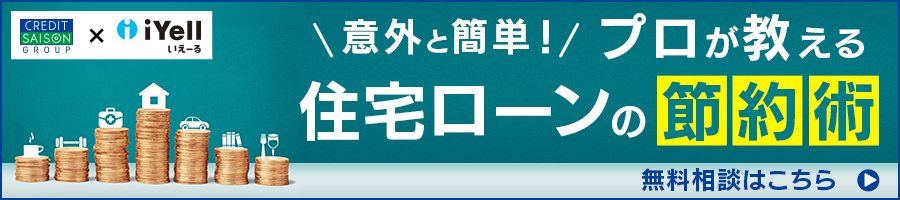

おわりに
分譲マンションのデメリットについて解説してきました。分譲マンションには、騒音トラブルや、修繕積立金・管理費の支払い、リフォームしづらいといったデメリットがある一方で、立地の良さやセキュリティ面での強みがあります。
ご自身のライフスタイルや価値観に合った住まいを選ぶことが大切です。設備や利便性を重視し、手間をかけずに長く住みたいと考える方には、分譲マンションが適しているでしょう。ご自身やご家族の考えを整理しながら、理想の住まい探しを楽しんでください。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。