アパート経営は安定した収入源を期待できる不動産投資の一つですが、すべてが順調に進むとは限らず、失敗するケースもあります。予想外の修繕費に資金を圧迫されたり、空室率の増加で家賃収入が激減したりと、一度の誤算が経営を困難にするリスクも存在します。
このような経営上の落とし穴を回避するためには、どのような注意点が必要なのでしょうか?この記事では、アパート経営における具体的な失敗例と対処法について解説します。
【資金面】アパート経営に失敗する4つの理由
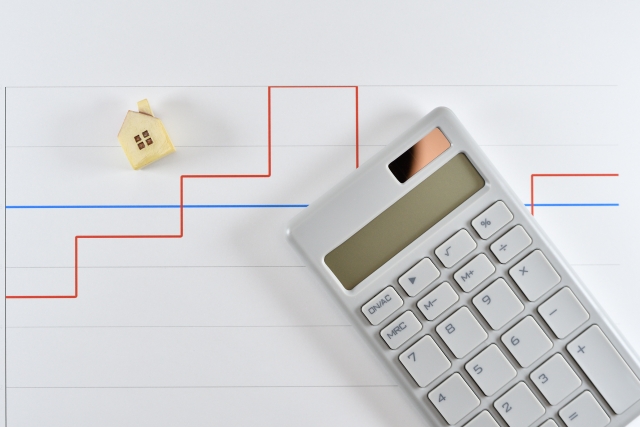
アパート経営は、収支の試算や資金計画が不十分だと、事業に失敗するだけでなく生活さえも脅かす危険があります。資金面での主な失敗理由は、以下の4つです。
- 借り入れが返済できない
- 利回りが想定を下回る
- サブリースの手数料が高い
- 老朽化で空室が増え、家賃を下げざるを得なくなる
それぞれ順に解説します。
借り入れが返済できない
アパート経営を始める際には、土地や建物の購入、相続した建物のリフォームに銀行の融資を利用するケースが多いです。しかし、返済能力以上の借り入れを行ってしまい、手元資金がなくなり苦しむ失敗例が多く見られます。
公務員や大企業の会社員は社会的な信用度が高く、高額なローンでも審査に通りやすい傾向があります。また、夫婦共働きで融資申し込みを行うと、借入限度額が大きくなることも。
しかし、物件に多額の投資ができる一方で、家賃収入が減少した際に返済できなくなる懸念があります。
例えば、利率3%、返済期間30年の条件で借り入れた場合の利息の総額と毎月の返済額は以下のとおりです。
| 借入額 | 利息の総額 | 毎月の返済額 |
|---|---|---|
| 4,000万円 | 2,072万円 | 16.9 万円 |
| 8,000万円 | 4,143万円 | 33.8 万円 |
表面上は4,000万円の借入でも、利息の総額は2,072万円と決して小さい額ではありません。8,000万円の借り入れでは、利息を含めると返済総額は約1億2,000万円となり、後から返済が負担になるケースがあります。
また、必ずしも安定的に家賃収入が得られるとは限りません。経営状況が悪化する前に、一部繰り上げ返済など計画の見直しを行いましょう。
利回りが想定を下回る
アパート経営において利回りとは、家賃収入を物件の購入費用などで割った指標で、数字が大きいほど収益性が高いと判断できます。ただし、利回りには「表面利回り」と「実質利回り」の2つがあり、しっかりと違いを理解していないと、収支が予想を下回る可能性があります。
- 表面利回り:年間家賃収入÷物件価格×100
- 実質利回り:(年間家賃収入-年間経費)÷(物件価格+購入時の諸費用)×100
表面利回りは、年間家賃収入と物件価格で算出しており、仲介手数料や保険料などの経費や諸費用を含んでいません。物件選びの参考にはなるものの、実際の利回りがシミュレーションより低くなる場合が多いため、試算時には経費を含んだ「実質利回り」で判断することが重要です。
物件の購入時には、初期費用として仲介手数料や登記費用、アパートローン手数料などがかかります。利回り計算の際には、物件の購入価格に初期費用を上乗せし、実質利回りで想定しましょう。
年間経費には税金や管理会社への委託費、保険料・借入金利息・広告宣伝費などが含まれます。シミュレーションする際は、一定の年数ごとに修繕費の計上も必要です。
当初の試算から融資金利や賃料などの状況が変わったときにも、改めてシミュレーションを行い、現在の経営状況を把握しておきましょう。ローンが変動金利の場合には金利上昇リスク、築年数が経過すると家賃下落リスクがあります。悪い状況から目を背けると適切な対処ができず、さらに利回りが想定を下回る懸念があります。
サブリースの手数料が高い
本業が忙しいサラリーマンや公務員がアパート経営を行う際は、サブリースの利用や管理業務を管理会社に委託するケースが多いです。しかし中には、手数料の負担からサブリースや管理会社の選択を失敗したと感じるオーナーもいます。
サブリースと管理会社への委託時の一般的な手数料相場は以下のとおりです。
| サブリース | 家賃の10〜20% |
| 管理会社 | 家賃の5% |
サブリース契約は空室リスクを引き受けてくれる反面、家賃の80〜90%しか手元に入りません。一方、管理会社に管理業務の一部または全部を委託する場合は、差し引かれる手数料は家賃の5%前後です。
手数料の負担が大きいと感じたら、契約内容の見直しや他の業者との比較検討を行いましょう。
老朽化で空室が増え、家賃を下げざるを得なくなる
アパート経営の失敗要因には、物件の老朽化による空室発生や家賃下落のリスクが挙げられます。経営を始めた当初は順調でも、年数が経過するごとに空室が目立ち、収支が悪化するケースは珍しくありません。
住宅の構造別の法定耐用年数は以下のとおりです。なお、実務上は20年を過ぎるころから屋根・外壁などの修繕が必要になるケースが多いとされています。
- 木造、合成樹脂造:22年
- 鉄骨造:19~34年
出典:国税庁 「主な減価償却資産の耐用年数表」
木造住宅は、20年経っても建物そのものは使用できますが、安定して収益を上げ続けるには適切な修繕が必要です。築古アパートは内・外装や屋根、共用部分などの劣化や性能の低下が見られます。ライフスタイルにそぐわない間取りや、古さを感じるデザインも空室リスクを高める原因です。
経年劣化を放置すると、さらに空室率や賃貸収入の水準は悪化し、入居者が入らないのに経費だけがかかり続ける「負動産」になる可能性もあります。
修繕やリフォームで収益改善の見込みが立たない場合、売却を検討するのも一つの方法です。セゾンファンデックスでは、老朽化した投資用不動産の買取提案を行っています。
セゾンファンデックス 投資用不動産の売却・改修サポートの詳細はこちら
【運営面】アパート経営に失敗する4つの理由

アパート経営を始める際、万全な資金計画やシミュレーションを行っていたとしても、運営面で失敗する事例もあります。具体的な要因は、主に以下の4つです。
- 立地が悪い
- 入居者トラブルに対応できない
- 時間が確保できない
- 入居者のニーズを把握できていない
順番に見ていきましょう。
立地が悪い
アパート経営の失敗例で多いのは、立地が悪く入居者が集まらなかったケースです。アパートの立地において、生活利便性と周辺環境は特に重視されます。
利便性の面では、最寄り駅までの距離が短いほど価値が高く、徒歩10分以内が理想です。また、複数路線が使えるターミナル駅や急行の停車駅、主要駅まで乗り換えなしなど、通勤・通学に便利なアパートは人気があります。
周辺環境として、スーパーや学校、病院などが徒歩圏内に多数あると「住みよい街」と言えます。また、近くにゴミ処理場や騒音が気になる施設がない立地が好まれ、治安の良さも選ばれやすい要因です。入居者によっては、日当たりを重視して物件を選ぶケースもあります。
すでに土地を所有している場合でも、アパート経営の観点で立地に問題がないかリサーチが必要です。周辺のライバルとなりうる物件の賃料や空室状況を参考に、収支を想定しておくと失敗が少なくなるでしょう。
入居者トラブルに対応できない
アパート経営では、入居者トラブルの対応は避けて通れません。契約内容やマナーが守られない状態が続き、当事者や他の居住者からのクレームにつながることもあります。
| 契約違反 | 家賃の滞納 無断転貸など |
| マナー違反 | 騒音やゴミの問題 入居者間のトラブル |
| 設備の不備 | 雨漏り エアコンなど付帯設備の故障 |
家賃が思うように回収できなかったり、騒音やゴミなどのマナー違反に悩まされたり、アパート経営では思わぬトラブルに見舞われることがあります。またトラブルから退去者が出るリスクも考えられます。
入居者対応に不安がある場合は、管理会社に委託範囲を広げるなどの対策を検討しましょう。
時間が確保できない
会社員がアパート経営を行う場合、本業とアパート経営の時間配分が課題です。仕事が忙しいと、アパート経営の現状把握が疎かになり、問題への対策が遅れることがあります。
一方で、アパート経営に注力しすぎて、本業や家庭に影響が出ている状態も望ましくありまません。本業とアパート経営の両立で、ストレスが増えることも想定されます。アパート経営が負担になっているなら、両方が上手く回らなくなる前に売却を考えるのも一つの方法です。
入居者のニーズを把握できていない
アパート経営では、予想される入居者に合わせた間取りや設備を選ぶことが大切です。ニーズの把握を怠ると、空室が増えて失敗につながります。
周辺施設別に、具体的な立地とニーズの例を見ていきましょう。
| 周辺施設 | 主なニーズ |
|---|---|
| 大学や大学院 | ・1Kや1DKなど単身向け ・オートロックなどセキュリティ |
| 保育所や小学校 | ・2LDK以上のファミリー向け ・駐車スペース |
予想される入居者が単身かファミリーかによって、求められる間取りや設備が変わってきます。他にも「トイレ・バスが別」「キッチン設備が充実」「収納スペースが豊富」など、入居者が求めるニーズを把握することが重要です。
築古物件で収益向上を目指すならリフォームを行うか、思い切って売却して別の物件への投資を検討するのも良いでしょう。
セゾンファンデックス 投資用不動産の売却・改修サポートの詳細はこちら
アパート経営に失敗しやすい3つのケース

アパートオーナーや物件の特性によって、アパート経営に失敗しやすいケースがあります。具体的には以下の3つです。
- 利回り計算や資金計画、収支の把握が苦手
- 親からアパートを相続した
- 新耐震基準を満たしていない
それぞれ順番に確認していきましょう。
利回り計算や資金計画、収支の把握が苦手
アパート経営において、利回り計算や資金計画は経営方針を決める上で重要です。不動産会社から提示された利回りの数字を鵜呑みにして投資してしまう方は、アパートオーナーには向いていないかもしれません。
一方で、会社員が資金計画や収支の把握のための学習に時間をかけすぎると、本業に影響を及ぼすリスクがあります。管理会社を活用したり、税理士などの専門家と連携したりしながら、効率的な経営を行うことも大切です。
親からアパートを相続した
親からアパートを相続した場合、知識がない状態からアパート経営を始めるケースが多く見られます。相続してすぐは何もせずに賃貸収入が得られても、長続きするとは限りません。
すでに築年数が経過しているアパートであれば、空室リスクが高まるだけでなく、定期的にリフォームや修繕が必要です。アパートをただ保有し続けているだけでは、近隣の物件に対する競争力が低下し、家賃収入の下落を招きます。
新耐震基準を満たしていない
新耐震基準は1981年6月1日より施行された法律で、以前よりも耐震性の規定が厳格化され、安全面で優れています。
新耐震基準を満たしていない物件は、入居者が集まりにくい、火災保険料が高額になるなどのデメリットがあります。さらに、基準を満たすアパートよりも修繕費が高くなる傾向にあり、建て替えや売却も視野に入れる必要があるでしょう。
「アパート経営に失敗した」と悩んだら売却相談を

アパート経営は必ずしも成功するとは限らず、失敗して行き詰まるケースも珍しくありません。苦しい思いをして保有し続けるより、売却してしまうのも有効な手段です。値段が付かないと思っていた築古アパートでも、うまく買い手が見つかれば利益が残せるケースもあります。
セゾンファンデックスでは、投資用不動産の売却のサポートが可能です。セゾンファンデックスまたは提携不動産会社が買取提案を行うため、個人間売買と違い売却後の売主責任もありません。アパートの売却をお考えの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
セゾンファンデックス 投資用不動産の売却・改修サポートの詳細はこちら
おわりに
アパート経営の失敗には、資金面や運営面といった複数の原因があります。当初は順調に進んでいても、修繕費やトラブルの発生で経営が困難になる事態が発生する可能性があります。あらかじめ失敗しやすい事例を予想しておくと、万が一の際に適切な対処ができるでしょう。
まずは今のアパートの現状把握をして、経営状況を見直すことをおすすめします。経営を続けるのが難しいと感じたときには、売却も見据えた出口戦略を検討しましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。
























