相続税対策、なにから始めればいいかわからない…。そんな初心者の方に向けて、今回は「不動産」を活用した基本的な対策について、不動産と相続を専門に取り扱う山村暢彦弁護士がわかりやすく解説します。
なぜ現金を不動産に変えることで相続税が抑えられる可能性があるのでしょうか?その仕組みから、知っておくべきメリット・デメリット、そして注意点まで、丁寧に紐解いていきます。賢く資産を守るための第一歩、一緒に踏み出してみましょう。
「節税」の基本的な考え方

資産を相続する際に相続税が生じるのは、基本的に避けようがありません。相続税をゼロにするような極端なものがあった場合、それは「節税」という名の「脱税」に近いようなスキームである場合が多いので、注意が必要です。
では、「節税」とはなにか? 基本的なところからお話ししていきたいと思います。
相続が発生した時点で、現金3億円を有していた場合、当たり前ですが「3億円」の資産に対して税金が生じます。一方、相続が発生した時点で「3億円で買った不動産」を保有していた場合、どうなるでしょうか?
土地の値段も日々動いていくものですが、ここでは非常にシンプルに考えていきます。仮に更地の土地を3億円で買っていた場合、時価3億円の土地であっても、相続税の算定の際には、路線価と呼ばれる時価の8割程度の基準値によって相続税を算出します。すなわち、3億円で買った土地を2億4,000万円で評価してくれる可能性があるのです。
これが基本的な節税の考え方です。現金で有していればその現金の額面自体の評価が避けられないのに対して、不動産やほかのモノに代えていれば時価評価よりも低い評価が受けられる可能性がある――これが節税の一番基本的な考え方でしょう。
さて、さらに発展させてみましょう。たとえば5,000万円の現金を保有していたとして、このまま相続が発生すれば、5,000万円の資産と評価されます。では、5,000万円を頭金として1億5,000万円の銀行融資を受け、土地1億円、上物の建物1億円の合計2億円の収益アパートを購入していた場合、どのようになるでしょうか? 今回はあくまでシミュレーションなので、概括的な数字で説明します。
1億円の土地については、路線価評価により時価の約8割なので、8,000万円として評価されます。1億円の建物については、固定資産税評価により時価の約7割とすると、7,000万円として評価されます。もっとも、融資を1億5,000万円受けているので借金1億5,000万円です。
土地8,000万円、建物7,000万円の合計1億5,000万円に対して、借金1億5,000万円なので、差し引きで評価額がゼロ円となります。すると……不思議ですね。頭金5,000万円のキャッシュがあったはずなのに、収益不動産を購入することで、形式的な相続税評価額がゼロ円になってしまうという“バグ”のような現象が生じています。
このような効果があるので、先祖代々の土地を承継しているような家庭や資産家の方は、増やす目的というよりも、
・相続時に目減りしないようにするため
こうした理由から収益不動産を購入していくというケースが多いように思います。
増やそうとすれば、利回りを高くすることが必要です。しかし相続税により目減りを減らそうという考え方の場合、利回りが高いことよりも、将来的な時価の低下を避けたいとの心理が働きます。
そのため、このような発想で収益不動産を買う方は、利回り3%を切ってもよいからと、名の通った大手の不動産会社で収益アパートを建築して、安定した資産を次世代に承継させるような傾向があります。
不動産による節税を考えるなら…必ず知っておくべき「令和4年最高裁判決」
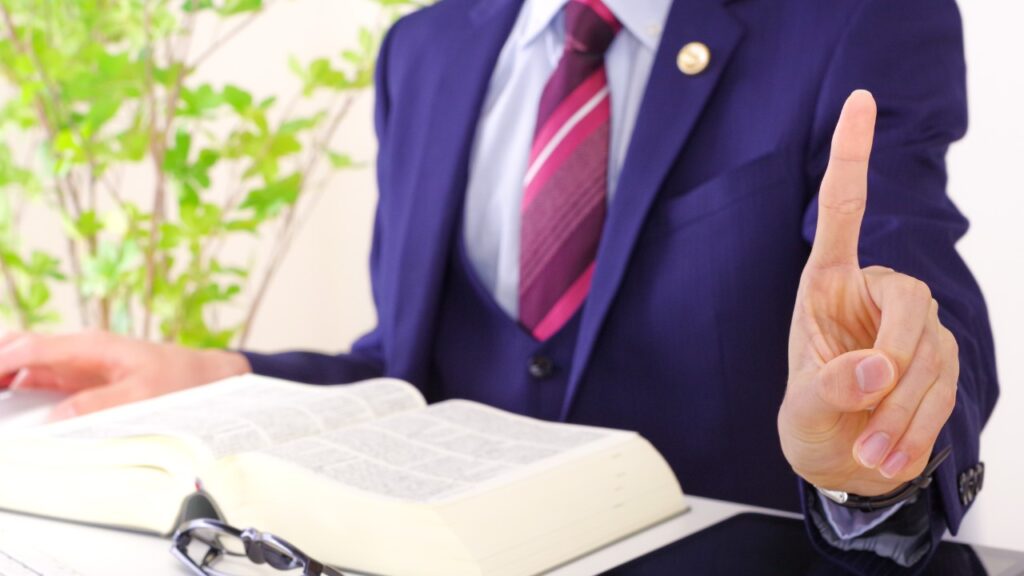
さて、このような節税が実際にできるのかについてです。
基本的に「できる」というのが解答です。しかし、これまではできていた節税の度合いであっても、誰かがやりすぎてしまうと、できなくなってしまうこともあります。過去にも、あまりにも節税をやりすぎてしまった例では、最高裁判決で修正が命じられました。それが、最高裁令和4年4月19日相続税更正処分等取消請求事件の最高裁判決(最高裁判所民事判例集76巻4号411頁)です。
この例では、約13億円にものぼる収益物件を購入していましたが、それを3億円強の評価額を前提として相続税申告。税務署側の不動産鑑定によれば、約12億円の評価は免れないとして、追徴課税3億円を課したという内容です。
確かに表面的にみれば、路線価等によって、おかしいとは言い切れない理屈から相続税申告していました。しかしあまりにも度が過ぎていたので、税務署が追徴課税を課し、最高裁まで争いになりましたが、税務署側の勝訴により決着がつきました。
追徴課税を課された側は、「みんな路線価で評価してやっているのに、うちだけ不動産鑑定で評価されるのは平等原則違反だ!」と争いました。
最高裁は、
として税務署側を勝訴としました。難しい言葉ですが、要は「税負担の観点から、あまりにも度が過ぎている場合には一般的な評価方法と異なる基準で税を課してもよい」という意味合いで、とりあえずの理解はよいでしょう。
もっとも、この事例に関しては90歳近くの高齢な方が、明らかに短期的な節税目的で不動産を購入している点や、金融機関の融資審査書類に「相続対策のため不動産購入を計画」などと記載されていた点等、明らかにやりすぎな事情も散見された特殊な例だと思います。
過度な節税は制度の歪み、ほどほどの恩恵を意識すべき

不動産による節税を考える方は、必ず令和4年最高裁判決のことを押さえておくべきです。しかし、この最高裁判決があるからといって完全に節税対策ができなくなったわけではありません。
筆者の私見ですが、本来、多少の節税は制度としても予定しているところ、その歪みを利用しすぎて明らかに誰がどう見ても不公平なほどの「節税」をやりすぎたがために、この最高裁の事案では税務署が動いたのだと思います。
そのため、節税については「徹底的にやり抜く」ではなく、あくまでほどほどに、多少恩恵を受ければよいな、という感覚で臨むほうがよいのではないでしょうか。細かな事案の詳細を知らない立場からですが、まともな税理士の方がアドバイスしていれば、ここまで極端なことはやらなかったのではないかと思います。
おわりに…節税対策による注意点

さて、本記事では節税そのものについての考え方を基本にお話ししましたが、もう一つ注意してほしいことがあります。それは、節税対策を行う際に紛争が発生するとそのスキームが崩れてしまう危険性がある、ということです。
節税というのはあくまで不動産の形態で資産を保有することにより、相続税評価額を下げることが基本的な節税の考え方です。一方で、不動産の相続というのは紛争が生じる危険性もあります。その際に「保有する前提で節税を考えていたのに、揉めたから売らなければならない」となってしまうと、前提が崩れてしまい、トータルで次世代に残す資産が少なくなってしまう可能性もあるのです。
筆者のもとへ相談に来られた方の言葉で、非常に印象に残っているものがあります。ある相談者の方が複雑な遺産分割や節税対策について話されたときのものでした。「こんな複雑な分け方、節税対策を考えた人が儲かるだけで、結局、揉めて相続人は苦労するし、手残りも少なくなっているだけだ」と、痛切な思いを語られていました。
節税と揉めない相続という観点は、どちらも欠かせない両輪であることを、改めて認識していただきたいと思います。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。


























