身内の方が亡くなった直後は、悲しみに暮れる間もなくさまざまな手続きに追われます。特に不動産が関わる相続においては、不動産の状況確認や必要書類の収集、名義変更に向けた準備など、専門的な知識と煩雑な手続きが伴い、なにから手を付ければよいのか戸惑う人も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、不動産相続をスムーズに進めるための第一歩として、死亡届の提出から遺産分割協議に至るまでの一連の流れを必要書類リストとともに、不動産と相続を専門に取り扱う山村暢彦弁護士が解説していきます。
相続はいつ始まる?相続開始の定義を知らないと…

相続は法律上、「被相続人(亡くなった方)が死亡した瞬間」に始まります。民法第882条には、「相続は死亡によって開始する」と明記されており、多くのケースでは病院で死亡診断書が作成されたその時点が、法的な「相続開始日」となります。
(相続開始の原因)
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。
一方、死亡届の提出や住民票の抹消などの行政手続きは、相続の開始とは別に行われます。これらは相続手続きのきっかけにはなりますが、開始の条件ではありません。
つまり、「死亡届を出していないから相続は始まっていない」ということにはならないのです。この相続開始日を基準として相続放棄や限定承認など、さまざまな期限がカウントされていくため、正確に認識をしておきましょう。
また、このタイミング以降、相続人は被相続人の財産(資産も負債も含む)を引き継ぐ立場に置かれます。今後のすべての相続手続きにおいて、戸籍謄本や住民票などの被相続人と相続人をつなぐ公的書類が重要になります。相続人を確定するためにも、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めることは、避けて通れない相続の最初のステップです。
死亡後すぐに行う手続きと必要書類

被相続人が亡くなった直後、遺族が最初に直面するのが「死亡後の初期手続き」です。ここでは相続の前提となる法的・行政的な作業が求められます。手続きを怠ると、葬儀が進まなかったり、のちの相続手続きが滞ったりするため、正確な対応が必要です。
①死亡届の提出(7日以内)
人が亡くなると、医師により死亡診断書が発行されます。この診断書と一体になっている死亡届を、死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません。
提出先は、亡くなった方の本籍地・住所・死亡地のいずれかの市区町村役場です。提出者は親族や同居人などに限られており、一般的には遺族が行います。
②火葬許可書の取得と葬儀の実施
死亡届の提出により火葬許可書が交付されます。これをもとに葬儀社と連携して火葬・葬儀を実施します。葬儀は感情的な負担も大きいですが、同時並行で今後の相続手続きに必要な書類も準備しておくとスムーズです。
③住民票の除票と戸籍の収集
次に行うべきは、住民票の除票の取得と、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)の収集です。これらは、相続人の確定や各種名義変更に欠かせません。特に戸籍は、結婚・転籍・離婚・養子縁組などの変遷がある場合、複数の自治体から取得する必要があります。
死亡直後に行う手続きとして、①~③を挙げました。行政が関わる手続きも多く、加えて年金の停止手続きや保険証の返還なども必要になります。
これらの「死亡直後」の手続きについては、葬儀社がサポートしてくれる場合もあるため、葬儀社や各自治体に相談しながら進めていくとよいでしょう。
また、③の戸籍収集などは、この後に行う「遺産継承」手続きの前提となる重要な準備です。内容が比較的単純であれば相続人自身で対応できますが、複雑なケースでは司法書士、行政書士、弁護士といった士業に依頼したほうが「早い」ケースも少なくありません。
これは、各種士業が「職権請求」という手続きを利用して行うことができるためです。
遺産の内容を把握するための調査

相続手続きを適切に進めるためには、まず「遺産の全体像」を正確に把握することが不可欠です。相続の対象となるのは、預貯金や不動産、株式・投資信託などの有価証券だけでなく、借金や保証債務などのマイナス財産も含まれます。プラスの財産だけで判断してしまうと、後に想定外の債務を相続してしまうリスクがあるため、慎重な調査が必要です。
金融資産の調査と口座の凍結
被相続人が取引していた金融機関を調べ、各口座の残高や契約内容を確認します。金融機関は死亡の事実を把握すると口座を凍結するため、相続人でも勝手に出金することはできなくなります。凍結解除・解約には、相続人全員の戸籍謄本、印鑑登録証明書、遺産分割協議書などの提出が必要です。
一般的には、残された通帳や証券会社からの郵便物などを手がかりに、取引のあった金融機関を把握していきます。手掛かりが全くない場合は、逆に未払い債務が残っていないかを確認して、取引先金融機関等を探っていくという手段も考えられます。
もっとも、こうした調査が難航するケースでは、早期に専門家に相談するのがよいでしょう。
また、こうした事態を防ぐためにも、遺す側としては生前に通帳や証券口座の情報をしっかり整理して、相続人の方がわかるようにしておくことが重要だといえます。
不動産調査と評価
不動産がある場合は、法務局で「登記簿謄本(全部事項証明書)」を取得し、所有者や権利関係、抵当権の有無を確認します。不動産の価値を把握するには、役所で「固定資産評価証明書」を取得する必要があります。これは相続税の申告や不動産登記の際にも使用されます。
不動産調査が複雑になる場合、役所で名寄帳や固定資産税台帳などを確認して調査を進めます。
特に共有名義や私道部分などは見落としが生じやすく、士業が関与しても慎重な確認が必要です。このようなケースでは、発見漏れの可能性も踏まえ、遺産分割協議書の条項作成に工夫が求められます。
債務や保証の有無の確認
借入金やローンの有無も重要な確認事項です。通帳の履歴、郵便物、契約書類、信用情報などから債務の有無を調査します。特に
収益不動産を保有していた場合は、金融機関からの融資を受けているケースが多く、融資返済表や登記情報からも確認できます。
また、細かな借り入れ、保証債務の確認には、指定信用情報機関である「(株) シー・アイ・シー(CIC)」「日本信用情報機構(JICC)」または「全国銀行個人信用情報センター」への情報開示請求も可能です。ただし、手続きの内容検討や費用も伴うため、必要性を含め専門家に相談しながら進めるのが無難です。
相続放棄の判断と期限
調査の結果、明らかに債務超過の場合は「相続放棄」も選択肢となります。相続放棄は、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
「知った日」からなのですが、疑義が生じるのを避けるため、筆者としては基本的に「死亡日から3ヵ月以内」を目途に行動するよう伝えています。判断がつかない場合は、検討期間の延長申請も可能です。
なお、法人を運営していた場合やリース契約が多いケースなどは、相続放棄後の権利関係が複雑になりやすく、弁護士に相談しながら方針を決めることをおすすめします。
シンプルな相続放棄であれば家庭裁判所で比較的容易に手続き可能ですが、判断が難しいケースでは専門家の関与が安心です。
やっと遺産分割協議へ
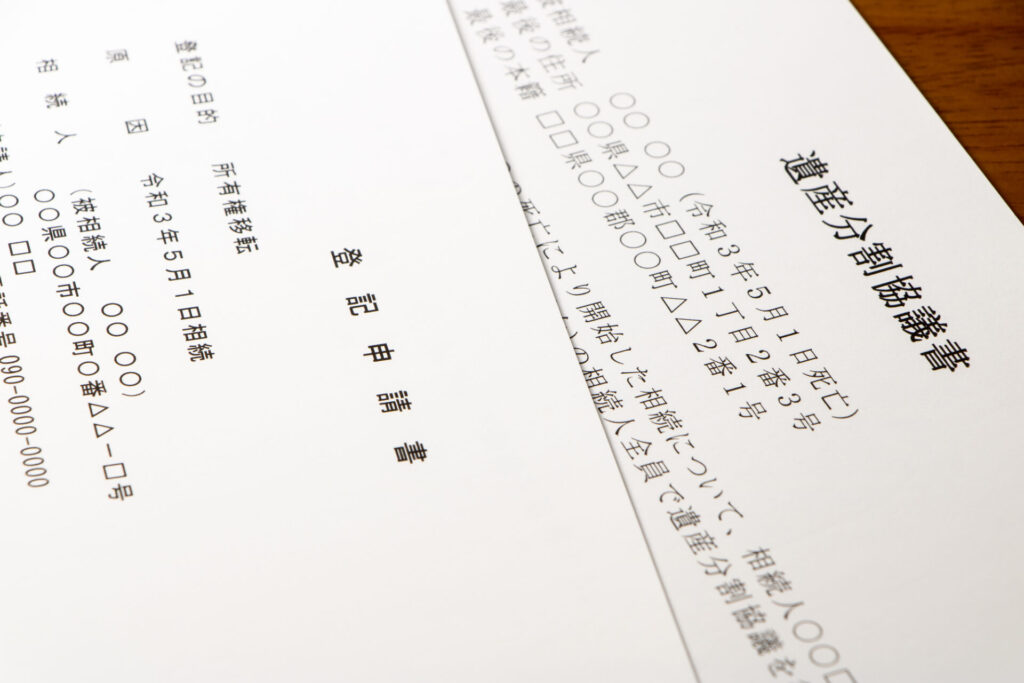
財産調査と必要書類が揃って、ようやく相続人間でどのように相続財産をわけるのかを話し合う「遺産分割協議」に進みます。
ここでもトラブルは生じやすく、不動産が絡む相続では評価や分割方法を巡って意見が対立しやすい傾向にあります。協議開始まで半年程度かかることも珍しくありません。
相続が発生すると、悲しみに暮れる間もなく行政手続きや相続手続きを日常生活をこなしながら進めていく必要があります。
特に不動産相続は複雑で専門的な知識が必要になるため、適切な準備と対応が不可欠です。負担が大きく大変だとは思いますが、本記事が一人でも多くの方の参考になれば幸いです。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。


























