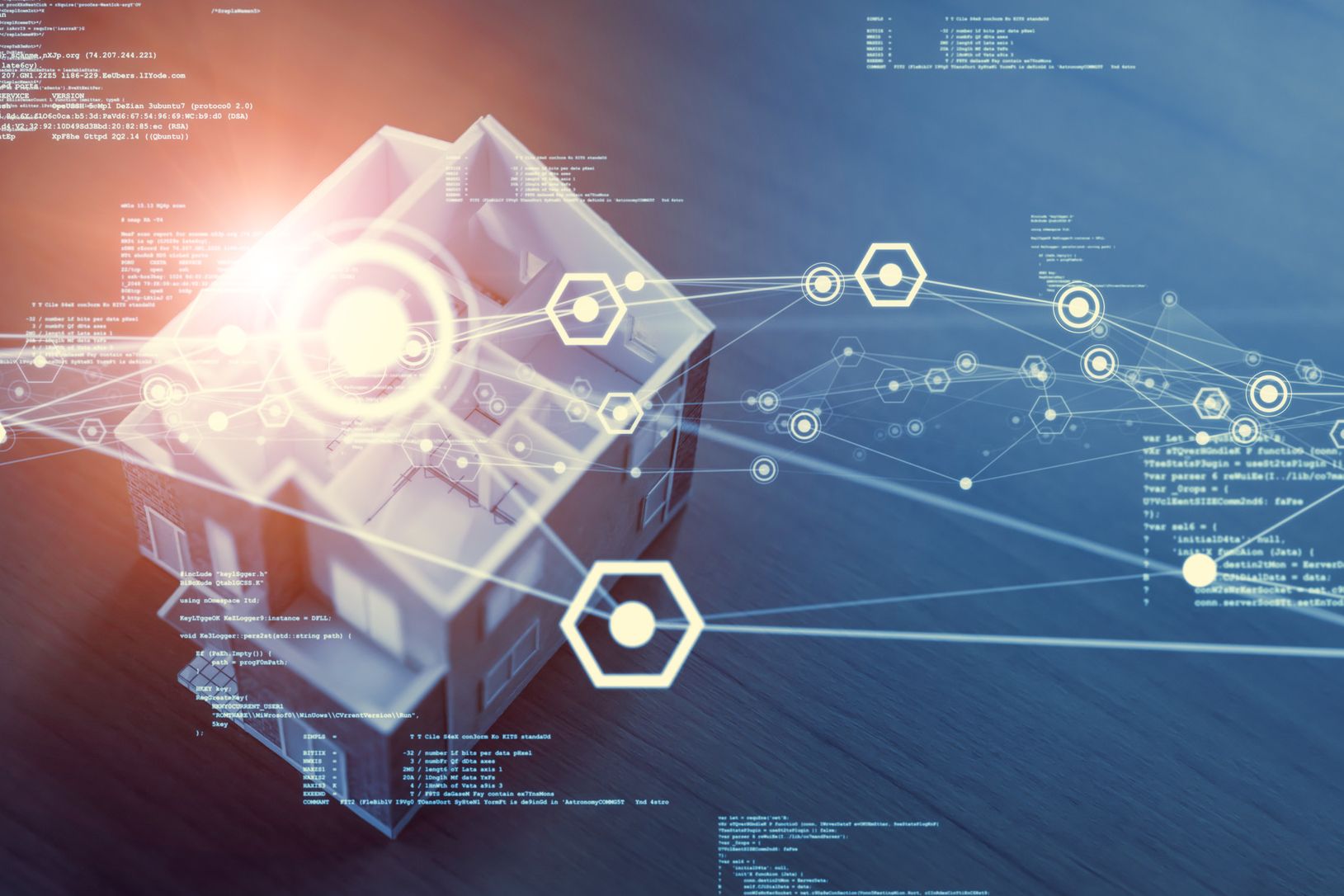不動産の相続は、土地や建物そのものだけでなく、それに付随する売買契約書や登記情報、重要書類などの「情報の引き継ぎ」も重要です。
これまで紙で保管していた書類も、昨今では、パソコンやクラウドで保存することが一般的になりつつあります。
本記事では、不動産相続に必要なデジタル書類の管理方法やクラウドサービスの活用、トラブルを防ぐためのデジタル遺品対策について、フジ相続税理士法人・代表社員の髙原誠税理士がわかりやすく解説します。
相続人が気づきにくい「不動産のデジタル情報」とそのリスク

近年、契約書類や重要な不動産情報をデジタルデータで管理するケースが増えています。デジタル書類は紙書類とは異なり、パソコンやクラウド上で管理されるため、相続人が気づきにくいのが特徴です。
もし故人が不動産に関するデジタル情報を残したまま亡くなると、「なにを所有していたのか」「どこに重要な書類が保存されているのか」が把握できず、相続手続きが滞ったり、不動産の名義変更や売却の対応が遅れたりする原因となります。
相続に関する重要なデジタル情報の具体例は、以下のとおりです。
- 不動産売買契約書のPDFデータ
- 賃貸借契約書(オーナーの場合)
- 登記簿謄本のスキャンデータ
- 土地測量図/建物図面のデジタルデータ
- 相続に関するメール(弁護士、税理士、不動産業者とのやりとり)
- クラウドストレージに保存されたファイル(Google Drive、OneDrive、Dropboxなど)
- 不動産管理アプリのアカウント情報
- 賃貸物件の家賃管理システムのログイン情報 など
これらの情報は、不動産の権利や利用状況を正確に把握するために不可欠です。しかし、相続人がデジタル情報を発見しなければ、存在しないのと同じリスクを伴います。
主な問題点は以下のとおりです。
1.相続手続き後に資産を発見した場合の負担
遺産分割協議が完了したあとにデジタル資産を発見した場合、遺産分割の再協議が必要となり、相続人にとって大きな負担となります。場合によっては、すべての手続きを最初からやり直すケースも想定されます。
2.固定費・利用料の引き落としが継続するリスク
サブスクリプション契約やクラウドストレージ、有料のデジタルサービスは、解約や利用停止の手続きをしない限り、自動的に故人の口座やクレジットカードから料金の引き落としが続く可能性があります。
3.税申告の遅延・過少申告
相続税の申告期限は「相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」です。デジタル資産を見落として期限内に申告できなかった場合、延滞税のほか、意図的な隠蔽等があると重加算税などの罰則が課される可能性もあります。相続財産の全体把握には特に注意してください。
4.負の遺産の可能性
デジタル資産には、プラスの財産だけでなく、インターネットで契約した借金(例:オンライン申込みの不動産担保ローン)、FXや仮想通貨取引で発生した負債(追加証拠金など)、マイナスの財産も含まれます。こうした負債も相続の対象となるため、注意が必要です。
【生前対策】デジタル不動産情報の整理・保管と引き継ぎ準備

デジタル遺品とは、亡くなった人が所有していたパソコンやスマホ、クラウドストレージ内のデータ、アカウント情報など、デジタルに関するすべての資産を指します。
不動産に関するデジタル遺品は相続時に見落とされがちですが、生前に適切に整理し、引き継ぎの準備をしておくことで、将来のトラブルを防ぐことができます。
1.まずは情報を一元化する(整理・保管)
不動産に関するデジタル書類は膨大な量になることが多く、管理が煩雑になりやすいのが特徴です。
しかし、適切に整理や保管を行っておけば、相続が発生した際、非常に役に立ちます。不動産に関するデジタル書類を安全かつ効率的に管理するためには、以下のポイントを押さえましょう。
- ファイルの一元管理
不動産ごとにフォルダをわけ、ファイル名には「物件名」「作成年月日」「書類の種類」を明記しておきましょう。
例:〇〇マンション_2023年3月5日_売買契約書.pdf - クラウドストレージの活用
Google DriveやDropboxなどのクラウドサービスを活用し、パソコンが故障した場合でもデータを保護できるようにしておきます。また、家族にもアクセス権を設定する(共有フォルダを作成する)ことを忘れないようにしましょう。 - パスワード管理
各種サービスのログインIDやパスワードは、暗号化されたパスワード管理アプリなどで一元管理することが可能です。 - 紙とデジタルの両面で保存
契約書などの重要書類はスキャンしてデータ化すると同時に、原本を紙でも保管。紙とデジタル両方の所在がわかる一覧表を作成して管理しておくと万全です。
2.次に引き継ぎ方を決める(相続準備)
整理した情報を相続人が確実に受け取れるよう、具体的な準備を進めます。デジタル遺品の相続対策の具体例は、以下のとおりです。
- 財産目録にデジタル資産を明記
不動産のデジタル書類の保存場所、ログイン情報、利用しているクラウドサービスの詳細などを財産目録に記載しておきます。 - パスワードの引き継ぎ方法を明確化
IDやパスワードの管理については、紙のエンディングノートに直接書き込む方法は盗難や流出リスクがあるため、厳重な管理が必要です。
可能であれば、暗号化されたパスワード管理アプリや、相続専用のサービス等を利用し、信頼できる家族だけが緊急時に確認できる体制を作ることを推奨します。 - 遺言書によるデジタル資産の言及
遺言書には、デジタルデータの取り扱い方や相続の方法も明記しておくと、よりスムーズな引き継ぎが可能になります。 - 「死後事務委任契約」の活用
「死後事務委任契約」とは、本人が死亡した後の各種手続きを第三者に委任できる民事上の契約です。デジタルデータの整理や解約なども委任事項に含めることができますが、遺言の効力とは異なるため、遺言書と併用することが望ましい点に注意してください。
おわりに…被相続人もデジタルに強い世代へ

不動産相続において、デジタル情報の存在を見過ごしてしまうと致命的なトラブルに繋がりかねません。
特に最近では、契約書や管理情報が紙ではなく、データのみで残されているケースも急増しており、もし家族がデジタル情報を見つけられなければ、不動産を適切に相続し、売却することが難しくなる可能性があります。
これからの不動産相続の対策において重要となるポイントは、次の3つです。
1.生前整理の徹底
紙とデジタルの資産を把握し、財産目録に記載しておきましょう。クラウドの共有設定を活用し、家族がいつでも確認できるようにすることをお勧めします。
2.専門家との連携
弁護士や行政書士と連携し、デジタル資産も含めた遺言書の作成が有効です。必要に応じて、死後事務委任契約の活用も早めに検討しましょう。
3.相続税のリスクに備える
相続税の課税対象となるデジタル資産の評価や把握は、専門的な知識を要します。申告漏れや延滞税のリスクを避けるために、税理士などの専門家に相談すると安心です。
これまで相続といえば、「土地」「建物」「預金」といった目に見える財産の引き継ぎが中心でした。しかし、これからの時代は「どこに情報があるか」を伝える「情報の相続」こそが、円満な資産承継の鍵を握ります。
デジタル情報は便利である一方、適切に整理されなければ相続人にとって“見えない財産”となり、手続きが遅れるなどの大きな負担になり得ます。
仮に不動産の存在が判明しても、その権利書や登記情報が見つからない場合、名義変更や土地の売却に多くの時間と労力を費やすことも少なくありません。
そのため、不動産相続においてデジタル書類を適切に管理することは、相続対策に欠かせない準備のひとつといえます。
また、今後は、パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器に積極的に関わってきた世代が被相続人となる時代が訪れます。
被相続人がデジタルに強い世代となると、個人情報の漏えいや流出防止に対する意識が一層高まり、セキュリティがさらに複雑化することが考えられます。
相続の際にいざ個人情報(=資産)を引き出そうとしてもアクセスすること自体が困難になるリスクが想定されるのです。
遺言書やエンディングノートに個人情報(=資産)の手がかりを記載しておくことは重要です。
現時点では多くのサービスが「ID・パスワード管理」に依存していますが、将来的には生体認証や信託型管理など新しい仕組みも広がる可能性があります。
現状は、法的に有効な手段(遺言・委任契約)と厳重なパスワード管理を併用するのが現実的です。
いずれにしても、大切なご家族が困らないよう、早い段階から整理を始めることが重要です。デジタル書類の整理や生前対策、相続税申告に不安のある方は、税理士や弁護士などの有資格者を含む、不動産相続に強い専門家へ早めにご相談ください。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。