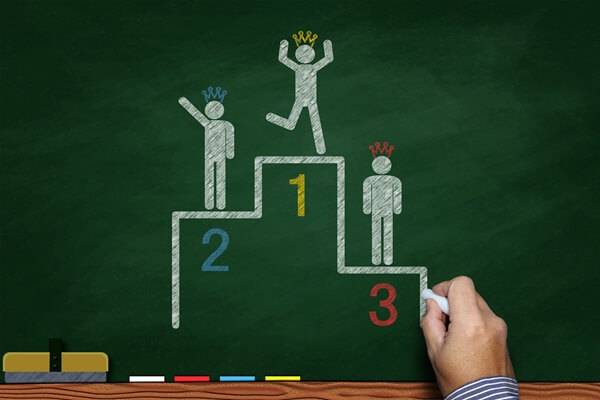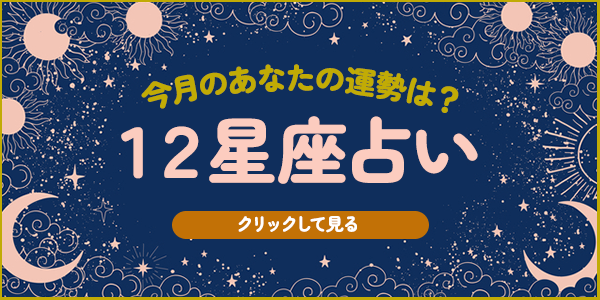建築基準法の条件を満たせず、建て替えができない「再建築不可物件」。もし相続した実家がこれに該当した場合、資産価値が周辺相場の3~5割に下落することもあり、相続人は大きな岐路に立たされます。
本記事では、一級建築士の三澤智史氏が、再建築不可物件を相続した際の選択肢(「専門業者への売却」や「大規模リフォームによる活用」)について、それぞれのメリット・デメリットを整理。
さらに、再建築を可能にするための実践的なアプローチも詳しく解説します。
「再建築不可物件」とは?

再建築不可物件とは、一度建物を取り壊すと、新たに家を建て替えることができない物件を指します。
これは主に、建築基準法が定める「敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」という、接道義務を果たしていないことが原因です。戦後すぐのころに建てられた古い物件に多い傾向があります。
再建築不可物件の例として、周囲の土地に囲まれてまったく道路に接していない「袋地」や、旗竿地と呼ばれる細長い路地で接道部が2m未満の土地、または道路の幅員自体が4mに満たない土地に建つ住宅などが挙げられます。
また、接道要件を満たしていても、都市計画法による開発制限がある「市街化調整区域」や、建築基準法上の規制が強化される「土砂災害特別警戒区域」に位置する物件は、用途や構造、自治体の運用によっては建て替えに制限が生じる場合があります。
このような接道要件や地域の規制の問題により、建物を建て替えできない物件を再建築不可物件といいます。
「既存不適格建築物」という言葉と混同する人も散見されますが、この場合は現行の建築基準法に遵守した建物であれば立て替えすることが可能です。この2つの違いは、誤解しないよう注意しましょう。
資産価値への深刻な影響と、「固定資産税」の罠

再建築不可物件は、建て替えができないため需要が極めて限られ、資産価値が大幅に低下します。売却価格は通常の3~5割程度にまで下落することも珍しくありません。
相続したからといって、いいことばかりではありません。固定資産税や都市計画税といった維持費はかかり続けます。
「再建築不可なのだから、土地の固定資産税も大幅に安くなるはずだ」と考えがちですが、現実はそうなりません。
税法上、利用価値が低い分、一定の減額(補正)は行われます。しかし、その減額幅は、市場価値(売値)の下落に比べ、はるかに小さいことがほとんどです。
さらに注意すべきは、建物にかかる税金がなくなるからといって安易に取り壊して更地にすると、住宅用地に適用されている「課税標準の軽減(1/6)」が外れるため、結果として固定資産税が大幅に上昇する場合があることです。
参照:国土交通省「土地の保有に係る税制」
資産価値の下落と維持費の負担。この二重苦を避けるために相続放棄も手段の一つですが、その際は預金などほかの財産も放棄することになるため、慎重に判断しなければなりません。
売却は可能なのか?主な売却先と注意点

再建築不可物件は、売却が不可能というわけではありません。しかし、通常の物件とは異なる方法で買い手をみつける必要があります。
再建築不可物件の売却先
再建築不可物件を専門に扱っている不動産買取業者が存在します。こうした業者は、物件をそのまま買い取り、自社でリノベーションして再販するノウハウを持っています。早期に現金化できる可能性も高く、売主が大規模な修繕をする必要もありません。
業者探しには、その業者のウェブサイトをみれば再建築不可物件の買取実績が豊富かどうか確認できます。お客様の声などがあれば、それを参考にするのもよいでしょう。
また、隣地の所有者に買い取ってもらう方法もあります。再建築不可物件の土地と隣地を一体化して接道要件を改善することで、隣地の所有者は将来の建て替えなどに備えるメリットなどがあるからです。
不動産買取業者よりも高値で売却できる可能性も。しかし、当然ながら必ず買い取ってくれるとは限らず、交渉には手間や時間がかかる点に注意が必要です。
売却時の注意点
複数の相続人がいる場合、売却益の分配や、1人が再建築不可物件を相続する代わりにほかの相続人に代償金を支払う「代償分割」といった手法など、事前に十分な話し合いを行い、全員の合意を得ておくことが重要です。
感情的な対立を避けるためにも、第三者である弁護士や司法書士、不動産コンサルタントを交えて話し合うのもいいでしょう。
また、買主と最もトラブルになりやすいのは、「再建築不可物件であること」の説明不足です。買主に対して、口頭での説明だけでなく、重要事項説明書を用いて再建築不可である旨を詳細に説明する必要があります。
宅建業法第35条では、取引士が「再建築不可であること」およびその理由(接道要件の不備など)を明確に説明する義務が定められており、この手続きを怠ると後日の紛争につながりかねません。
家を相続する人のように売主が個人の場合、契約不適合責任を免責にすることが一般的で、契約後に物件の不具合が見つかっても売主が責任を負わない扱いとされることが多いです。
しかし、再建築不可である事実やその根拠を告知しなかった場合、買主が「契約の目的を達成できない」と判断すれば、契約不適合責任に基づいて契約解除や損害賠償を請求される可能性があります。
リフォームやリノベーションによる活用方法とその限界

再建築不可物件は建て替えができないものの、リフォーム・リノベーションすることは可能です。耐震補強や内装のリフォームを行えば、そのまま住み続けたり、賃貸に出したりする道が残されています。
好立地エリアでは、相場以下の価格で購入した再建築不可物件を大規模リノベーションして賃貸物件に再生し、その賃料収入で購入費用を回収する事例もあります。
しかし、リフォームには大きなハードルもあります。2025年4月の建築基準法改正により、住宅に関する審査は従来より厳格化されました。
具体的には、4号建築物に対する構造審査の範囲見直しや、省エネ基準適合の義務化が段階的に進められている点が挙げられます。
再建築不可物件のリフォームでは、増改築の規模や構造補強の内容によっては「確認申請」が必要となり、その際に確認検査機関から耐震性能や断熱性能について、現在基準への適合を求められるケースが多くなります。
特に、旧耐震基準の建物も多いため、大規模な耐震補強が必要となり、コストは高額になりがちです。
つまり、リフォームは可能ですが、法規や技術上の豊富なノウハウと多額の工事費用がかかるため、住み続けたり賃貸に出したりする費用対効果があるかどうか、冷静に検討する必要があります。
おわりに…一級建築士からの助言

再建築不可物件を相続した場合、相続・売却・リフォームといった各局面で、早い段階から専門家に相談しながら進めることが重要です。まずは相続人間で方針を共有し、感情的な対立を避けながら、全体の方向性を固めていきましょう。
リフォームして住み続けたり賃貸に出したりする場合には、住宅の安全性を最優先に考える必要があります。十分な耐震性能を確保し、安心して暮らせる状態にすることが、建物を将来にわたって活かすうえで欠かせません。
費用対効果だけを重視して工事範囲を極端に縮小すると、安全性が損なわれ、結果的に資産としての価値も低下しかねません。リフォームでは、コストと安全性のバランスを冷静に判断し、長期的に見て最適な選択をすることが大切です。
相続した再建築不可物件には、売却・活用・改善と複数の選択肢があります。本記事の内容を参考に、専門家の助言を得ながら、将来の安心につながる最良の道を見極めてください。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。