長いあいだ続いた「低金利時代」と「デフレ」が終わり、不動産投資をめぐる常識も大きく変化しつつあります。
では、こうした環境下で不動産投資をはじめる場合、「新築物件」と「中古物件」どちらに投資すべきなのでしょうか。
メガバンク出身の不動産鑑定士である小俣年穂氏が、不動産投資市場の現状をおさえたうえで、新築・中古それぞれのメリット・デメリットを解説します。
不動産投資家たちの“好み”

不動産投資を行うにあたって「新築」に投資すべきか「中古」に投資すべきか迷う人は多いものです。筆者が銀行員として融資をしていた際には、顧客によって明確に好みが分かれていました。
「新築物件」にしか投資しない人、「中古物件」ばかりを探している人……。銀行では審査においてすべての資産を把握するため、資産の構成を見ると好みが如実に表れていました。
また、新築投資のなかでもタイプが分かれています。自ら土地を取得して建築会社を選んだうえで開発するケースと、完成している新築の土地建物を購入するケースとがありますが、この場合、投資上級者は前者の戦略を取る傾向があったように思います。
目利きが問われ手間はかかるものの、自ら開発するほうが、不動産業者が開発したものを買うよりも一般的には安く仕上がるためです。
さらに、なかには希少性の高い物件を一般公開前に優先的に紹介を受けて購入している個人もいました。こうした特別な物件の紹介を受けられるかどうかは、投資家自身のネットワークや信頼、そしてこれまでの経験や実績が大きく関係してきます。。
“新築プレミアム”で高賃料が期待できる…初心者向けの「新築物件」

新築物件の強みは、主に以下の点にあります。
- ローン期間が長く取れる
- 賃料が高く取れる
- 修繕にかかるコストが低い
ローン期間が長く取れる
金融機関では法定耐用年数(住宅用:鉄筋コンクリート造47年、重量鉄骨造34年、木造22年)あるいは金融機関独自の基準で建物使用可能期間を定め、築年数を控除したうえでローン期間を算出しています。
〈例〉木造30年(金融機関の基準)-0年(新築)=30年(融資期間)
賃料が高く取れる
賃料についても、新築時はいわゆる“新築プレミアム”が存在しており、新築建物を好む入居者が相場より高い賃料で借りてくれるため、賃料が高く取れる可能性が高いです。
ただし、エリアや物件タイプによっては、新築プレミアムの継続期間や賃料の維持力に差が出る場合もあります。
一方で、竣工の時期によっては全部屋が満室になるまで時間を要することもあり、その場合には「空室損」が発生することもあります。
修繕にかかるコストが低い
また、新築物件は修繕にかかるコストが低いというメリットもあります。新築時は、通常管理業務(清掃やメンテナンス)や入退去にともなう原状回復工事が発生する程度で、大きな修繕工事は不要であることから、収支が安定しており不測の費用が発生しにくいです。
したがって、新たに不動産投資に参入する場合には新築物件のほうがリスクは低めです。
ただし、利回りが低い(不動産価格が高い)、募集賃料が実際の賃料と乖離している(募集賃料が高い)、経費が実際にかかるものより低く見積もられている……など、未稼働がゆえに判断を間違えるケースもあるため留意が必要です。
また、新築といえども、将来的な賃料の下落や稼働率の悪化リスクがゼロというわけではありません。購入時は、楽観的なシミュレーションに頼らず、数年後の賃料下落や空室リスクも織り込んだうえで収支計画を立てることが重要です。
したがって、実際に投資を行う場合には、現地への視察を行うとともに周辺の不動産会社へのヒアリングなども行い、賃料が妥当か否か、そもそも賃貸需要があるのか否かを確認しておくことをおすすめします。
「販売用資料」の過信はNG…周辺業者にも調査を
数年前、新築のシェアハウスで不動産投資家が大きな損害を被った事件がありました。
これは、不動産業者が作成した販売用資料を投資家が過信してしまったために、賃料が想定どおりに入らず(正しくはサブリース契約の解除後に、収入がほとんどなかったことが判明)、ローン返済ができず窮地に陥った事例です。
販売用資料には、利回りを高く見せるための手法(主に賃料を高く設定する)があるため、特に注意が必要です。決して鵜吞みにせず、地元の不動産業者へのヒアリングが不可欠です。
収入のブレが少なく、利回りが高い…中級者以上向けの「中古物件」

他方、中古物件の強みは、主に以下の点にあります。
- 収入のブレが少ない
- 空室リスクの発生期間が少ない
- 新築に比べて利回りが高い(不動産価格が安い)
収入のブレが少ない
中古物件は、新築物件とは反対に、すでに入居者が入っており “新築プレミアム”もないことから、比較的収入が安定しているというメリットがあります。
ただし、現入居者の契約条件や賃料水準が市場より低く設定されている場合、今後の賃料増加が難しいケースもあります。
空室損の発生期間が少ない
また、すでに稼働中であることから、空室損が発生する可能性も低いです。
ただし、同時期に複数の部屋で退去が発生する可能性もあることから、現入居者の入居期間や滞納の発生状況について精査することが重要です。
この点、長いあいだ滞納なく住んでいる人は、継続して入居する可能性が高いです。
新築に比べて利回りが高い(不動産価格が安い)
また、価格についてはいわずもがな、中古は新築よりも安いです。
ただし、中古の場合は購入後数年内に大規模修繕が必要となるケースもあり、外壁や屋上、鉄部の塗装、配管の更新などを実施する場合には数千万円単位で費用がかかることもあります。そのため、事前調査や大規模修繕の見積もりを取得しておくことが望ましいです。
特に大規模修繕にかかる費用は、ローン返済や日々のキャッシュフローに大きく影響します。購入判断時には必ず「直近10年の修繕履歴」や今後必要となる修繕費の見積もりを確認し、将来の資金繰り悪化リスクに備えておきましょう。
また、こうした問題を解消するために、体力のある不動産会社では自社で安価に中古物件を取得し、大規模修繕を実施したうえで再販しているケースもあります。
したがって、修繕履歴の確認が重要であるとともに、将来的に売却することを想定して購入するのであれば、物件購入後も修繕履歴をきちんと残しておきたいところです。
中古物件が安価なもうひとつの理由
中古物件が安価な理由としては、ローンの問題もあります。
以下の例のとおり、築年数によってはローン期間が長く取れないため、ローン調達が困難になるケースがあります。仮にローンの審査が通ったとしても、金融機関から多額の自己資金を求められるため、不動産投資のハードルが上がってしまいます。
〈例〉
木造30年(金融機関の基準)-15年(築年数)=15年(融資期間)
中古物件は新築に比べて安価ではあるものの、上記のとおりさまざまなリスクも含んでいることから、資金計画・修繕計画・入居状況の把握が必須であり、不動産投資を何度か経験している中級者以上に適しているといえるでしょう。
建築費の高騰が顕著…“目利き力”が試される不動産市場
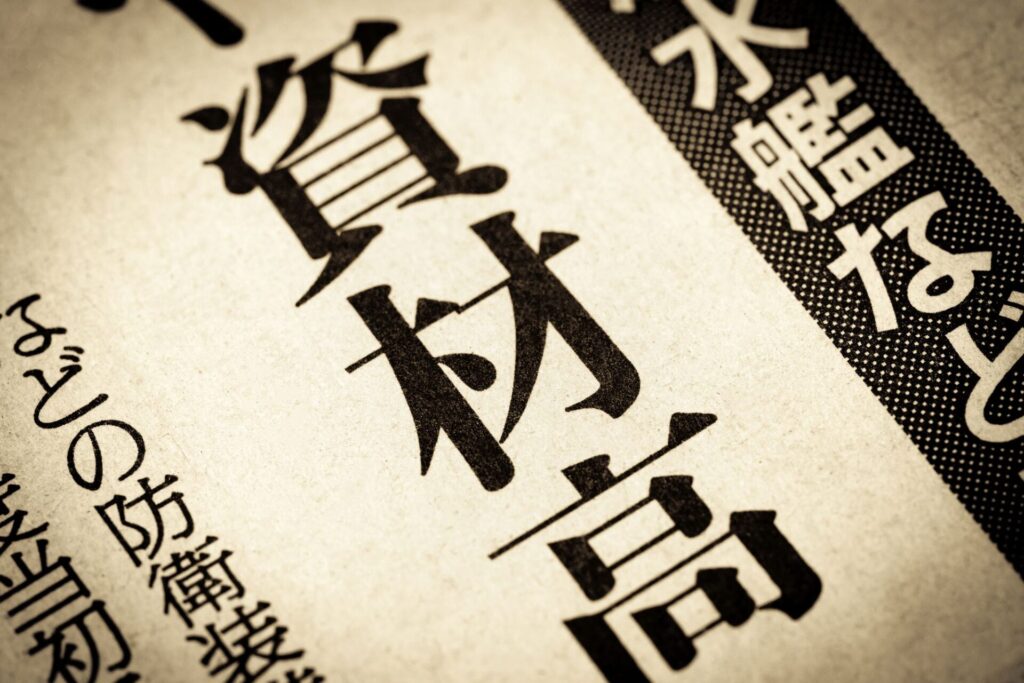
2020年代以降、建築費は右肩上がりで上昇しており、新築投資を取り巻く環境も大きく変化しています。
特に最近は、建築費の高騰が一段と顕著です。一般財団法人建設物価調査会の調査によると、集合住宅の「建設物価建築費指数」は下図のとおりで、2021年頃から右肩上がりで上昇しています。
![[図表]2025年5月の建設物価建築費指数:集合住宅(RC造)](https://life.saisoncard.co.jp/wp-content/uploads/2025/08/032c38e181bdcbbc76090480c9fae1e9-1024x484.jpg)
※ 東京:2015年平均=100
出典:一般財団法人建設物価調査会総合研究所「建設物価 建築費指数【2025年5月分】」)
筆者が日頃取引しているハウスメーカーにヒアリングを行うと、「今後上がることはあっても下がることはまずない」との回答が多いです。
主な理由としては、人件費の高騰(建設業の2024年問題、人手不足、担い手不足など)や建築資材の高騰などが挙げられます。
建設費が一定の水準にあったひと昔前においては、建築費をすべてローンで調達することが当たり前にできていました。
しかし昨今では、たとえ土地を所有していても全額ローンで調達することは困難となっており、建築費の一部に自己資金を求められるケースが増えてきているという状況です。
投資用不動産の場合、建築費の高騰に対して賃料が上昇していない場合は、自己資金の捻出が必要になります。
つまり、賃料が上昇している地域においては、いままでどおり建築費をすべて資金調達できますが、賃料が上昇していない地域では資金調達ができず、建築が困難となってるのです。ハウスメーカーによると、年々建築可能な地域が狭くなっているという話も聞かれます。
このように、新築建物の建築費高騰に対する対策として、投資用不動産デベロッパーは比較的安価な木造建築を増やすなど、工夫を凝らしています。
ただし、販売しやすくするために利回りを維持しようとすると、賃料を高くするか、性能を落として安く建物を仕上げるかのどちらかしかありません。したがって、表面利回りや募集賃料だけで判断せず「構造・設備・管理内容」まで精査することが“目利き”の第一歩です。
また、資材高騰の影響を受けるのは、新築物件だけではありません。中古物件についても、修繕費が以前より高騰しています。
建物を長期間良好に利用し続けるためには修繕が不可欠であり、10~15年スパンなどで継続的に実施していくことが肝要です。
しかし、施工会社は資材不足や人手不足などから、受注件数を制限しているところも多いのが現状です。さらに、いざ工事を行おうと思ってもすぐに着工できない、予算内に収まらないなどの問題もあります。
また、先述のとおり新築建物の建築費が高騰していることから、解体して建て替えという選択肢もハードルが高くなっています。
したがって、安定的な賃貸経営を続けるためには、賃料の上昇も図りながら適切な事業計画を策定することが重要になっています。
いまが“目利き力”を鍛えるチャンスといえるワケ
不動産投資にあたっては、購入前の事前調査がとても重要です。新築・中古それぞれのリスクを十分に理解したうえで投資判断を行うことが望ましいでしょう。
また、「市場環境の変化=参入チャンス」と単純化せず、手元資金やリスク許容度、自分自身の投資目的を明確化したうえで計画的な資産形成を意識したいところです。
今回見てきたように、ひと昔前に比べて、建築費の高騰やローン金利の高騰などの影響により不動産投資のハードルは上がっています。しかし、こうした環境だからこそ知識と経験を深め、自身の投資スタンスを確立するいい機会にもなります。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、最新情報は各サービスのホームページ等でご確認ください。
























