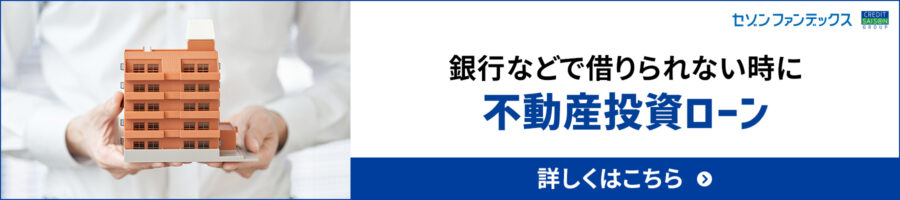不動産投資に興味はあるものの、「どれくらいの利回りを目指せばいいのか分からない」「この物件の利回りは適切なの?」と悩む方も多いのではないでしょうか。
利回りは高いほうが収益を得られるものの、他の観点を見落とさないように注意が必要です。実際に、適切な利回りは物件のエリアや投資目的、リスク許容度によって異なります。
本記事では、自信を持って投資先物件を選べるようになりたい方に向けて、利回りの基本的な考え方や計算方法について解説します。エリアや物件の種類による利回りの相場も紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。
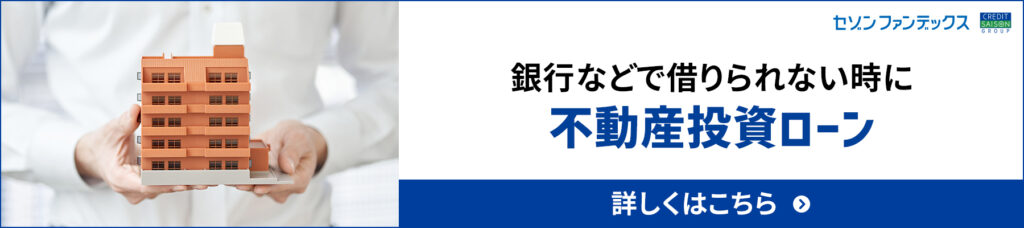

不動産投資における利回りの理想ライン・最低ラインは?

不動産投資において、一律の理想的な利回りや最低ラインは存在しません。
前提として、投資するエリアや物件の種類によって利回りの目安が大きく異なります。また、投資家自身が不動産投資にかけられる時間や労力、リスク許容度などによっても、理想的な利回りの水準は変わります。
さまざまな情報を総合的に判断し、自分にとって理想的な利回りを考えてみましょう。
投資するエリアや物件によって利回りの目安は異なる
不動産投資では、エリアや物件の種類によって期待できる利回りは大きく変動します。平均的な利回りを把握しておくことは、適切な投資判断を下すうえで重要です。
例えば、平均より利回りが低い場合はリスクが少ない反面、収益性が乏しい可能性があります。一方、利回りが極端に高い物件には「満室になりにくい」「直近で大規模な修繕が必要」といった、隠れたリスクが存在する場合も少なくありません。
一般財団法人日本不動産研究所「第51回不動産投資家調査」が公表している物件タイプごとの期待利回りは、以下のとおりです。
物件の種類と期待利回り
| 物件の種類 | 期待利回り |
|---|---|
| 賃貸住宅一棟 | 3.8〜5.2% |
| 商業施設 | 3.3〜6.2% |
| 物流施設 | 3.8〜4.5% |
| 宿泊特化型ホテル | 4.2〜5.3% |
また、同調査ではワンルームマンション(一棟)の地域別利回りも発表されており、同じタイプの物件でも地域によって利回りに違いがあることがわかります。
地域別の期待利回り(ワンルームマンション一棟)
| 地区 | 期待利回り |
|---|---|
| 札幌 | 5.0% |
| 仙台 | 5.0% |
| さいたま | 4.6% |
| 千葉 | 4.6% |
| 東京(城南地区) | 3.8% |
| 東京(城東地区) | 3.9% |
| 横浜 | 4.3% |
| 名古屋 | 4.5% |
| 京都 | 4.6% |
| 大阪 | 4.3% |
| 神戸 | 4.7% |
| 広島 | 5.0% |
| 福岡 | 4.5% |
投資目的やリスク許容度などによって目指すべき利回りは異なる
不動産投資で目標とすべき利回りは、投資目的やリスク許容度などによって異なります。リスク許容度とは、損失を受け入れられる度合いのことです。リスク許容度が高いほど大きな損失にも耐えられるといえます。
副業として不動産投資を始める場合は、高利回りを追求するよりも、リスクが少なくなるべく手間のかからない物件を選んだほうがよいでしょう。
例えば、都心部や利便性の高いエリアにある区分マンションは、多少利回りが低くても安定した需要が期待できるうえ、空室リスクや修繕リスクを最小限に抑えられます。
一方、本業で不動産投資に取り組む場合は、低価格で購入できる物件を活用して高い利回りを狙うのもひとつの方法です。
例えば、地方の物件や修繕が必要な物件をあえて選び、リフォームや修繕工事を施して価値を高めるといった戦略が考えられます。このような物件は空室リスクがある一方で、購入価格が抑えられるため、高い利回りが期待できるでしょう。
また、不動産会社や工務店と積極的に連携することで、収益性をさらに向上させられる可能性もあります。
不動産投資をする際は、物件ごとに利回りをシミュレーションし、それが自身の投資目的に合致しているかを確認しましょう。
不動産投資における利回りとは?

不動産投資において、利回りは物件の収益性を測るための基本的な指標です。ここからは、利回りについて以下の内容を解説します。
- 基本的な意味
- 主な種類
- 計算方法
利回りについての理解が曖昧な方は、ぜひ参考にしてみてください。
利回りの基本的な意味
利回りとは、物件購入価格に対する年間収益の割合のことです。利回りを確認することで、その物件が生み出す収益を把握でき、投資資金を何年で回収できるかといった目安もわかります。
ただし、投資全般にいえることとして、リスクとリターンは相関性があるため、利回りが高い場合はリスクも高くなることがほとんどです。反対に、リスクが低い場合は利回りも低くなる傾向があります。
利回りは投資先を選ぶうえで重要な指標のひとつですが、利回り以外の面も考慮して総合的に投資判断を下しましょう。
利回りの主な種類2つとそれぞれの計算方法・シミュレーション
利回りには「表面利回り(グロス利回り)」と「実質利回り(ネット利回り)」の2種類があります。それぞれの計算方法や特徴を理解することで、投資物件の収益性をより正確に把握できます。
表面利回り
表面利回りは、物件購入価格に対する年間家賃収入の割合を示す指標です。表面利回りの計算式は以下のとおりです。
表面利回り(%)=(年間家賃収入÷物件購入価格)×100
例えば、年間家賃収入が100万円、物件購入価格が2,000万円の場合、表面利回りは5.0%(=100万円÷2,000万円×100)です。
多くの不動産投資サイトでは「満室時の想定利回り=表面利回り」として記載しています。しかし、実際には空室が発生したり運用コストがかかったりするため、実際の利回り(実質利回り)は表面利回りを下回ることが一般的です。
実質利回り
実質利回りは、家賃収入から維持費を差し引いた正味の収益を、物件購入価格と購入時の諸経費の合計額で割った値です。
実質利回りはの計算式は以下のとおりです。
実質利回り(%)=(年間収入-年間維持費)÷(物件購入価格+購入時諸経費)×100
年間維持費や購入時諸経費の一般的な内訳は、以下のとおりです。
| 年間維持費 | 購入時諸経費 |
|---|---|
| ・固定資産税 ・都市計画税 ・所得税・住民税 ・管理会社への委託料 ・修繕費 ・修繕積立金 ・共用部の水道光熱費 ・火災保険料 ・地震保険料 ・入居者募集費用 | ・不動産会社への仲介手数料 ・融資手数料 ・登録免許税 ・不動産取得税 ・印紙税 ・司法書士報酬 |
年間維持費は家賃の20〜30%程度、購入時諸経費は物件価格の7〜15%程度が一般的とされています。
例えば、年間家賃収入が100万円、物件購入価格が2,000万円、年間維持費が20万円、購入時諸経費が200万円の場合、実質利回りは約4.4%となります。
計算式は以下のとおりです。
実質利回り(%)=(100万円−20万円)÷(2,000万円+200万円)×100 ≈ 4.4%
実質利回りは運用コストを反映した利回りであるため、上述した表面利回りよりも投資先の収益性を正確に把握できます。
不動産投資の利回りについて知っておきたい考え方

利回りは投資物件を選ぶ際の重要な指標ですが、それだけで投資先を決めるのはおすすめできません。利回りに関する注意点や考え方について、以下の2つは理解しておきましょう。
- 利回りだけで投資先を判断しない
- 利回りが高すぎる物件は訳アリの可能性がある
ひとつずつ解説します。
利回りだけで投資先を判断しない
利回りは物件価格と家賃収入のバランスを示す指標ですが、それだけで投資先の優劣を判断するのは避けましょう。物件価格が高い場合は利回りが低く、逆に安い場合は利回りが高くなる傾向があるからです。
例えば、物件価格1,000万円で家賃が5万円の立地条件が悪いワンルームマンションAと、物件価格5,000万円で家賃が10万円の好立地のワンルームマンションBを比較した場合を考えてみましょう。この場合、Aの表面利回りは6.0%、Bは2.4%です。
- Aの年間家賃収入:5万円 × 12ヶ月 = 60万円
- Aの表面利回り:(60万円 ÷ 1,000万円)× 100 = 6.0%
- Bの年間家賃収入:10万円 × 12ヶ月 = 120万円
- Bの表面利回り:(120万円 ÷ 5,000万円)× 100 = 2.4%
一見するとAのほうが収益性が高く見えるかもしれません。しかし、実際には立地が悪く賃貸需要の低いAは空室率が高くなるリスクが存在し、期待どおりの収益を得られないことがあります。
一方で、賃貸需要が高いBのほうが空室リスクが低く、安定した収益を得られるケースは十分に考えられます。
投資する価値が高い物件でも、利回りだけをみると低くなっていることもあるので注意しましょう。
さらに、建物の老朽化や周辺エリア環境の変化によって、利回りが変化するリスクも無視できません。当初想定していた実質利回りを維持するには、定期的なメンテナンスが必要となり、それにかけられる時間や費用についても考慮する必要があります。
また、周辺環境が変化するリスクを見越して、人口増加や賃貸需要の増加が見込まれる地域で物件を選ぶことも重要です。
利回りだけを投資判断の根拠にするのはおすすめできません。他の要素も総合的に検討し、リスクを見極めましょう。
利回りが高すぎる物件は訳アリの可能性がある
利回りが高すぎる物件に出会った場合、その理由を確認することが重要です。
考えられるケースは、以下のとおりです。
- 旧耐震基準で建てられている
- 老朽化が進んでおり将来的に大規模な修繕が必要になる
- 周辺環境に問題がある
- 家賃が相場とかけ離れている
- 過去に事件や事故が起きている
こうした問題点が見つかると空室リスクが高まり、想定した収益を得られなくなります。また、売却しようとしても買い手が見つかるまでに時間がかかることもあるでしょう。
利回りの高い物件に投資する際には、「なぜ高利回りなのか?」を不動産会社に確認することが大切です。
利回り以外で投資物件を選ぶ時のチェックポイント

投資物件を選ぶときは利回りだけではなく、以下の項目もチェックしましょう。
- 立地条件
- 築年数
- 告知事項の有無
- 耐震基準への適合性
上述したとおり、利回りだけに囚われているとさまざまなリスクにより、思うような収益を得られない可能性があります。これらの要素を加味して、中長期的にどのくらいの収益が見込めるのかをシミュレーションすることが大切です。
立地条件
投資物件を選ぶ際は、利回りだけでなく立地条件を確認することが重要です。
例えば、都心部の物件は地方よりも利回りが低い傾向があるものの、賃貸需要は高いため空室リスクが少なく、安定した収益が見込めます。また、都心部の物件は流動性が高く現金化しやすいうえ、資産価値も比較的落ちにくいため、最終的に売却する場面でも有利になるでしょう。
公益財団法人東日本不動産流通機構の「首都圏不動産流通市場の動向(2023年)」によると、首都圏の中古マンションや中古戸建ての価格は2013年から継続的に上昇しており、安定した需要があることがわかります。
実際に投資する際は、内見時に以下の項目をチェックし、居住者にとっての利便性を把握しておきましょう。
- 最寄り駅および物件までの距離
- 商業施設の有無
- 学校や医療機関の有無
- 治安の良し悪し
- 災害リスク
災害リスクはハザードマップなどで調べられます。ハザードマップとは自然災害による被害を軽減するために、被災想定区域や避難経路などをまとめた地図のことで、各自治体のホームページや窓口などで入手できます。災害リスクが低いエリアであれば、安定した賃貸需要が期待できるでしょう。
築年数
不動産の収益力を評価する際、築年数は重要なチェックポイントのひとつです。
実質利回りに加え、NOI(Net Operating Income)率も参考にすることで、より現実的な収益性を把握できます。NOI率とは、満室賃料を100%とした場合に、実際の収入(賃料)から経費(管理費、固定資産税など)を差し引いた収益の割合を示したものです。この指標からは、投資物件が生み出す純粋な収益の水準を把握できます。
公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会「第11回(2023年版)全国賃貸住宅実態調査 報告書」によると、築年数が経過するほどNOI率は下がる傾向があるとのことです。
主な要因として、修繕費などのメンテナンス費用が増加することが考えられます。築年数が古い物件を購入する場合は、将来的な修繕費や運営コストを見込んだ収益計画を立てる必要が出てくるでしょう。
築年数は、登記簿謄本(全部事項証明書)や物件購入時の重要事項説明書などで確認できます。
告知事項の有無
投資物件を選ぶ際には、物件が瑕疵(かし)物件でないか確認することも重要です。瑕疵物件とは、通常備えるべき品質や性能を欠いている、つまり何らかの欠陥がある不動産のことを指します。
瑕疵物件は主に以下の4種類に分けられます。
- 物理的瑕疵物件
⇒建物の構造や設備に欠陥がある物件。雨漏りやシロアリ被害、基礎のひび割れなどがある場合などが該当する。 - 法的瑕疵物件
⇒建物や土地が法的に問題を抱えている物件。建築基準法違反で増改築が行われている物件や再建築不可物件などが当てはまる。 - 環境的瑕疵物件
⇒周辺環境に問題がある物件。近隣の工場やゴミ処理施設からの悪臭に悩まされる物件や、近隣に高層マンションが建築されたことによって眺望や日当たりが悪くなった物件などが該当する。 - 心理的瑕疵物件
⇒居住者に心理的な抵抗感や嫌悪感を与える物件。過去に事件や事故、自殺があった物件などが該当する。
上記に該当する場合は、広告で「告知事項あり」と記載しなければならないと定められています。売買契約書や重要事項説明書には瑕疵に関する記載や説明が必ず含まれているため、これらの書類を細かく確認し、疑問点があれば不動産会社や売主に直接問い合わせましょう。
耐震基準への適合性
建築物が地震の揺れに耐えられるかを判断する基準である「耐震基準」を満たしているかどうかも、物件選びにおける重要な要素です。耐震基準は建築基準法や同法施行令によって定められており、旧耐震基準と新耐震基準の2種類があります。より安全性の高い新耐震基準を満たしている物件を選ぶと、投資のリスクを抑えられます。
- 旧耐震基準:1950年から施行され、1981年5月31日までに建築確認を行った建物に適用された耐震基準です。この基準では、震度5強程度の地震で建物が倒壊せず、仮に破損したとしても補修することで生活できることを前提としています。
- 新耐震基準:1981年6月1日から適用されている基準で、震度6強~7レベルの揺れでも、建物が倒壊しないような構造基準が設定されています。
旧耐震基準で建設されている物件は耐久性に不安があるため、入居者が集まりにくく、空室リスクを伴うでしょう。また、地震リスクが高いエリアでは修繕費や保険料が高くなる可能性があるため、注意が必要です。
物件が新耐震基準を満たしているかどうかは、建築確認通知書(確認済証)を確認するとわかります。建築確認日が1981年6月1日以降であれば新耐震基準に適合している可能性が高いといえます。建築確認通知書がない場合は「建築確認概要書」や「建築確認台帳記載事項証明」を自治体の窓口で閲覧・発行してもらうことで確認が可能です。
【参考】
「不動産投資ローン」を活用して希望に合った物件に投資しよう

不動産投資では、理想的な条件が揃った物件を見つけても、資金不足が原因で諦めざるを得ないケースがあります。そんなときは、不動産投資ローンの活用を検討してみてください。
不動産投資ローンを活用すれば、自己資金が少なくても投資の選択肢が広がり、自分の希望に合った物件に手が届きやすくなります。
セゾンファンデックスの「不動産投資ローン」なら、収入や借入枠などの問題で銀行の融資条件に当てはまらない場合も、柔軟に対応可能です。
また、自宅やすでに所有している収益用不動産を共同担保にすることで、自己資金が少なくても頭金0円でローンを組める可能性があります。
これから不動産投資を始める方は、セゾンファンデックスの「不動産投資ローン」をぜひご検討ください。
利回りの考え方を理解して不動産投資を成功させよう

不動産投資では立地や築年数などによって状況が大きく異なるため、理想の利回りや目指すべき利回りの最低ラインは一概には語れません。しかし、自分の投資目的を達成できる適切な利回りであり、かつ市場の相場から大きく外れていない物件を選ぶことで、理想に近い投資を実現できる可能性があります。
実際に物件を選ぶ際は、利回りだけに囚われず、以下のようなさまざまな要素に目を向けることが大切です。
- 立地条件
- 築年数
- 耐震基準
- 告知事項の有無 など
理想の物件が見つかったら、資金計画を立てることをおすすめします。不動産投資ローンをうまく活用することで、希望する物件に投資するチャンスが広がるでしょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。