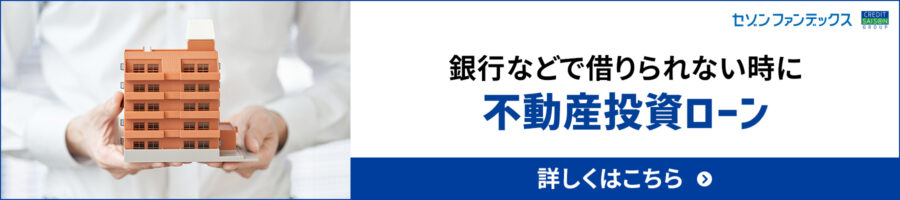不動産投資を検討している方の中には、近年注目を集める「民泊投資」に興味を持っている方も多いのではないでしょうか?
賃貸経営と比べて高い利回りが期待できるといわれる一方で「リスクはないのか?」と不安に感じる方もいるはずです。実際、物件選びや法規制への理解が不十分だと、思わぬ失敗につながることもあります。
この記事では、民泊投資の基本的な仕組みやメリット・デメリットを詳しく解説します。成功するために押さえておくべきポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
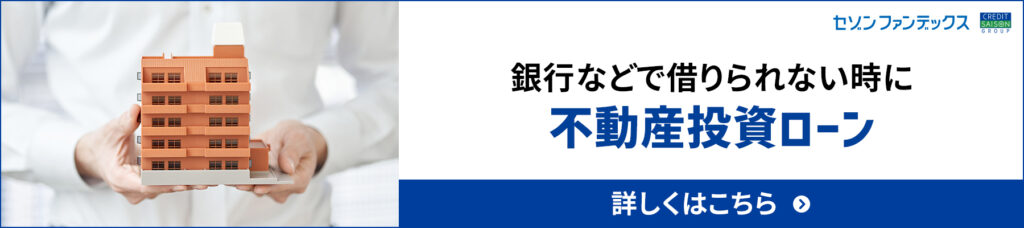

民泊投資とは?

民泊投資とは、一軒家や区分マンションなどを貸し出し、宿泊料を収益として得る不動産投資の一種です。
ここでは、民泊投資が注目されている理由や、一般的な不動産投資との違いについて詳しく解説します。
注目されている理由
民泊投資が近年注目を集めている背景には、シェアリングエコノミー(個人が所有するモノや場所を、必要とする人と共有すること)の浸透やインバウンド(訪日観光客)の増加が挙げられます。
政府も宿泊施設の不足を補う手段として民泊ビジネスを推進しており、国土交通省が民泊のポータルサイトを運営しているくらいです。
また、空き家問題の解決策としても注目されており、空き家を民泊として活用することで、建物の劣化を防ぎながら収益を得られる可能性があります。
さらにワーケーションの広まりやインバウンドの回復など、民泊需要は今後も増加する見込みです。特に大阪万博では約350万人の外国人観光客の訪日が予想され、ホテルの不足を補う手段として民泊の活用が一層加速すると考えられています。
一般的な不動産投資(賃貸経営)との違い
一般的な不動産投資(賃貸経営)と民泊投資の主な違いは、以下のとおりです。
| 賃貸経営 | 民泊投資 | |
|---|---|---|
| 収入源 | 家賃+売却益 | 宿泊料金 ※所有物件で民泊経営する場合は売却益も得られる |
| 契約期間 | 長期契約(1年以上) | 短期間(1泊~数週間) |
| 料金設定 | 契約期間中は固定 | シーズンや需要に応じて柔軟に変更可能 |
| 設備投資 | 基本的に不要(リフォーム程度) | 家具・家電・リネン類の購入が必要 |
一般的な不動産投資では家賃収入と売却益が主な収入源であり、長期間の契約による安定収入が特徴です。一方、民泊投資は短期間の宿泊料から収益を得るビジネスモデルであり、高単価を狙える一方で収入が不安定になりやすいという特徴があります。
また、民泊投資は宿泊料金を柔軟に設定できることも、事業における大きなメリットとなりえます。繁忙期には高めに、閑散期には割引の適用など料金を調整することで、収益の最大化を狙えるでしょう。
しかし、宿泊者が頻繁に入れ替わるため、管理の手間がかかる点や家具・家電の購入やリネン類の定期交換などの費用がかかる点には注意すべきです。
民泊投資の種類

民泊投資は、大きく分けて以下の3種類があります。
- 所有物件を活用する
- 賃貸物件を転貸(サブリース)する
- 民泊事業者に物件を貸し出す
投資方法によって初期費用の負担や運営の手間が異なるため、自分に合った方法を選びましょう。
所有物件を活用する
セカンドハウスを含め、すでに物件を所有している場合は物件購入費用が不要なため、初期投資を最小限に抑えて民泊経営を始められます。
ただしマンションの場合、管理規約で民泊営業が禁止されていると、所有物件であっても民泊経営はできません。そのため、民泊を始める前に管理規約を確認しておきましょう。
運営方法には、自分で管理する方法と専門会社に委託する方法があります。
自分で管理する
宿泊者とのやりとりや鍵の受け渡し、清掃などの運営をすべて自分で行う方法です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・業者への委託料が不要なため、収益が大きくなりやすい ・民泊の管理・運営を全て自分でコントロールできる | ・清掃や宿泊者対応の手間がかかる ・トラブル発生時も自分で対応が必要 |
なお、住宅宿泊事業法に基づいて家主不在型の民泊を経営する場合、住宅宿泊管理業者への委託が義務付けられています。そのため、自己管理はできません。
専門会社に管理を委託する
管理の負担を減らしたい場合は、専門会社に運営を委託する方法もあります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・運営の手間を大幅に削減できる ・プロによる運営で、集客力やサービスの向上に期待できる | ・手数料が発生する |
すべてを任せる「完全代行」と、清掃のような一部の業務のみ依頼する「部分代行」があります。
一般的に、手数料は完全代行の場合、毎月の売上の約20〜30%程度です。一方、部分代行の場合は1回あたりの相場は1〜2万円程度となっています。
賃貸物件を転貸(サブリース)する
賃貸物件を借りて民泊サービスを提供する方法を「サブリース(転貸)」といいます。サブリースのメリット・デメリットは、以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・物件購入の必要がないため、初期投資を抑えられる ・立地の良いエリアで民泊経営ができる可能性がある | ・契約上、転貸禁止の物件では運営できない ・毎月の家賃や転貸料が発生するため、固定費の負担が大きい |
物件を購入する必要がないため、初期費用を抑えて民泊経営を始められるのが大きなメリットです。不動産価格が高騰している人気観光エリアや都市部でも、サブリースなら比較的少ない資金で民泊を始めやすいでしょう。
一方で、サブリースを行うためには、契約上で転貸が許可されているか事前の確認が必要です。オーナーや管理会社の許可なしに民泊を運営すると契約違反となり、最悪の場合は契約解除や損害賠償を請求されるリスクがあります。
特にマンションの場合は、管理組合の規定によって運営できない場合もあるため、事前の確認が必須です。
また、サブリースでは毎月の家賃や転貸料が発生するため、固定費の負担が大きくなります。民泊の稼働率が低下した場合でも、家賃の支払いは継続しなければならず、閑散期には収益が減少しやすい点に注意が必要です。そのため、事前に収益シミュレーションを行い、長期的に利益が見込めるかを慎重に検討しましょう。
民泊事業者に物件を貸し出す
自らが民泊を運営するのではなく、所有する不動産を民泊事業者向けに貸し出すことで、家賃収入を得る方法もあります。
民泊事業者に物件を貸し出すメリット・デメリットは、以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・一般的な民泊よりも安定した収益を得やすい ・通常の賃貸経営よりも高い利回りを狙える ・民泊運営の手間がかからない | ・民泊事業者の経営状況に収益が左右される可能性がある ・必ず借り手が見つかるとは限らない |
民泊向けに賃貸する最大のメリットは、一般的な賃貸契約と同じように毎月の家賃が安定して入るため、民泊経営特有の収益変動リスクを避けながら収益を確保できることです。
さらに、転貸を許可することで通常の賃貸よりも高い賃料で貸し出せる可能性があります。民泊事業者にとっては、好立地の物件を確保できることがビジネスの成功に直結するため、高額な家賃を支払ってでも契約したいと考えるケースが多く、オーナー側は民泊向けの物件として貸し出すことで、より高い利回りの実現が期待できるでしょう。
また、実際に民泊運営をするわけではないため、オーナー自身が手間をかけずに家賃収入を得られる点も大きな魅力です。
ただし、民泊事業者が必ず見つかるとは限らず、エリアによっては需要が少ない場合もあるため注意が必要です。
一般的な住宅賃貸と異なり、民泊用途での貸し出しを希望する事業者は限られており、不動産会社が民泊物件の仲介業務に対応していないケースもあるため、一般的な賃貸物件よりも成約までに時間がかかることも考えなければなりません。
民泊投資のメリット3つ

所有物件やサブリースを活用した民泊投資には、以下のようなメリットがあります。
- 高い利回りに期待できる
- 築年数の影響を受けにくい
- 用途変更がしやすい
一般的な賃貸経営と比べてどのような点が優れているのか、確認していきましょう。
高い利回りに期待できる
民泊投資の魅力は、一般的な不動産投資よりも高い利回りを狙える可能性があることです。利回りが高くなりやすい理由は、以下のとおりです。
- 宿泊料金を柔軟に設定できる
- 原状回復費用が低く済む
- 売却時の評価が高くなりやすい
通常の賃貸経営では、契約期間中にオーナーの一方的な都合で料金の変更はできません。しかし、民泊では季節やイベントの有無などに応じて、宿泊料金を柔軟に調整できます。
例えば、観光シーズンや大型イベントの際には宿泊料金を高めに設定し、閑散期には割引を行うことで稼働率を安定させ、収益を最大化できる可能性があります。
また、民泊は短期滞在が中心のため、入居者が退去する際の原状回復費用が低く済むケースが多いのも特徴です。
通常の賃貸経営では、長期間の入居後にリフォームが必要になることがあります。しかし、民泊では定期的な清掃やメンテナンスが行われるため、修繕はほとんどの場合で不要です。
さらに、民泊として一定の稼働実績がある物件は、投資家にとって魅力的に映るため、売却時に高値がつく可能性もあります。すでに安定した収益を上げている物件は、一般的な住宅よりも投資対象としての評価が高まりやすいためです
実際に、民泊投資は一般的な不動産投資よりも高い利回りを実現できるケースが多いです。
一般財団法人日本不動産研究所の「第51回不動産投資家調査」によると、賃貸住宅一棟の期待投資利回りは約4〜5%とされています。
一方、観光庁の「住宅宿泊事業の実態調査」によると、民泊投資の年間利益率は平均で15.9%というデータもあります。
算出基礎が異なるため単純比較はできないものの、民泊投資は一般的な不動産投資よりも高い収益を狙いやすい手法であることは確かだといえるでしょう。
築年数の影響を受けにくい
一般的な賃貸物件では、新築や築浅の物件のほうが選ばれやすく、築古物件は家賃を下げざるを得ないこともあります。
しかし、民泊の場合は築年数が古くてもアクセスが良く、内装が魅力的であれば十分な需要が見込める点がメリットです。例えば、古民家をリノベーションして和の雰囲気を活かした宿泊施設として運営することで、外国人観光客から人気を集めている民泊もあります。
築年数が理由で敬遠されがちな物件も、民泊として運営することで、新たな価値を生み出せる可能性があります。
用途変更がしやすい
市場の変化に応じて用途を変更しやすい点も、民泊投資のメリットのひとつです。
一般的な賃貸経営では入居者と長期契約を結ぶため、一度貸してしまうとオーナーの都合で契約の解除は簡単にはできません。
一方で、民泊投資の場合は短期間の賃貸が基本となるため、需要が変化した場合は柔軟に運用方法の変更が可能です。
例えば観光需要が減少した場合には民泊運営を停止し、シェアハウスやマンスリーマンションなどに切り替えることで、安定した収益を確保できます。
用途変更により空室リスクを最小限に抑えられるのは、民泊投資ならではのメリットといえるでしょう。
民泊投資は失敗しやすい?デメリット4つ
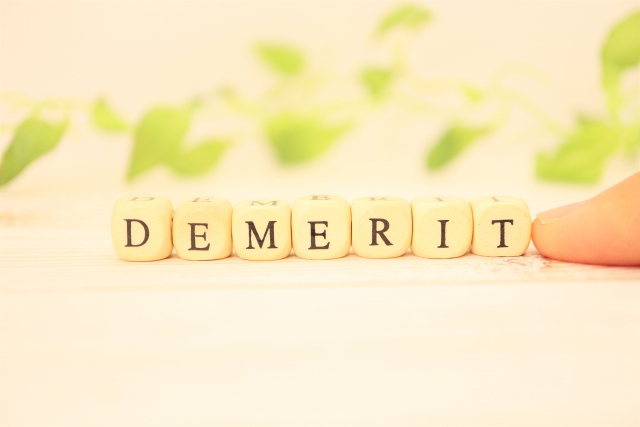
高い収益が期待できる民泊投資ですが、安易に参入すると思わぬリスクに直面し、失敗する可能性があります。民泊投資の代表的なデメリットは、以下のとおりです。
- 設備投資のコストがかかる
- 運営方法によっては営業日数が制限される
- 時勢の影響を受けやすい
- 近隣トラブルが起きる可能性がある
デメリットを元に民泊投資で失敗しやすいポイントや、リスクを抑えるための方法を紹介します。
設備投資のコストがかかる
民泊を運営するためには、一定の設備要件を満たす必要があります。物件によっては、設備を揃えるために初期費用がかさみます。
また、物件の規模や用途によっては、自動火災報知設備や消火器、誘導灯などの消防用設備の設置が求められ、工事費用が発生することがあります。
特に空き家や築年数の古い物件を活用する場合は、内装リフォームや水回りの改修、家具・家電の購入など、設備投資に多額の費用がかかる可能性がある点に注意が必要です。
実際に、観光庁の「住宅宿泊事業の実態調査」によると、65.5%の民泊事業者が500万円未満の初期費用で開業している一方、5,000万円以上の費用をかけた事業者も13.4%いるというデータがあります。
民泊では「快適に宿泊できるか」が重要視されるため、設備投資を怠ると口コミ評価が下がり、稼働率が低下するリスクも考えられます。そのため、他の宿泊施設との差別化を図るためにも、以下のような設備投資が必要になるでしょう。
例えば、民泊新法(住宅宿泊事業法)に基づいて民泊を運営する場合、建物内に以下4つの設備が必要です。
- 台所
- 浴室
- 便所
- 洗面設備
また、建物の規模や用途によっては消防用設備(自動火災報知設備や消火器、誘導灯など)の設置が求められ、工事費用が発生することがあります。
特に空き家や築年数の古い物件を活用する場合は、内装のリフォームや水回りの改修、家具・家電の購入など、設備投資に多額の費用がかかる可能性がある点に注意が必要です。
実際に、観光庁の「住宅宿泊事業の実態調査」によると、65.5%の民泊事業者が500万円未満の初期費用で開業している一方で、5,000万円以上の費用をかけた事業者が13.4%いるというデータがあります。
民泊では「快適に宿泊できるか」が重要視されるため、設備投資を怠ると口コミ評価が下がり、稼働率が低下するリスクがあります。そのため、他の宿泊施設との差別化を図るためにも、以下のような設備投資も必要となるでしょう。
- 壁や床のリノベーション
- 機能性の高い家具や家電の設置
- スマートロックや防犯カメラの導入
- 高品質なマットレスや枕の用意
- タオル、シャンプー、歯ブラシ、ドライヤーなどアメニティの用意
- Wi-Fi設備の整備
とはいえ、すべての設備を一気に導入するのは費用面で負担が大きいため、以下のような方法でコストを抑える工夫も有効です。
- 中古家具・家電を活用する
- DIYや簡易リノベーションを自分で行う
- 必要最低限の設備で運営を開始し、稼働率を見ながら追加投資を検討する
初期費用がどうしても大きくなる場合、民泊事業向けのローンを利用するのもひとつの選択肢です。物件購入費用だけでなく、リフォーム費用や家具・家電の購入資金にも使えるため、資金計画の一助となるでしょう。
運営方法によっては営業日数が制限される
民泊は運営形態によって営業日数が制限されるため、収益が安定しにくいデメリットがあります。民泊の運営形態は、大きく分けると以下の3種類です。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく民泊 | ・届出のみで開業できるため、手続きが比較的簡単 ・住宅専用地域でも営業が可能なので、比較的自由に物件を選べる | ・営業日数が180日以内に制限されるため、収益が頭打ちになる可能性がある |
| 国家戦略特別区域法に基づく特区民泊 | 年間営業日数の制限がないため、安定した収益が見込める | 最低宿泊日数の制約(2泊3日以上)がある |
| 旅館業法に基づく民泊(簡易宿所) | 年間営業日数の制限がないため、安定した収益が見込める | 構造設備基準や用途地域などの基準を満たす必要があり、許認可を受けるためのハードルが比較的高い |
住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく民泊は、営業日数が180日以内に制限されるため、収益面での課題が生じる可能性があります。この制限の影響を最小限に抑え、収益を向上させるために、以下のような対策が有効です。
- 繁忙期の料金を引き上げ、収益を最大化する
- 365日営業が可能な運営形態への変更を検討する
- 民泊利用以外の期間にマンスリーマンションとして活用する
これらの対策を組み合わせることで、営業日数制限のデメリットを補いながら、効率的な収益運営が可能となります。
時勢の影響を受けやすい
民泊投資は、外部環境の変化で収益が大きく変動するリスクがあります。収益を左右する主な外部要因は、以下のとおりです。
- パンデミック
⇒2020年の新型コロナウイルス感染症の流行では、観光業全体が大打撃を受け、多くの民泊事業者が撤退を余儀なくされた - 季節的な変動
⇒観光地によっては、オフシーズンに宿泊者が大幅に減ることもある - 景気の悪化
⇒不況になると旅行を控える人が増え、稼働率が低下する可能性がある - 法規制の変更
⇒ 国や自治体が民泊の規制を強化することで、営業が制限されるリスクがある
外部環境による影響を抑え、安定した収益を確保するためには、以下のような対策が有効です。
- 国内旅行者やビジネス需要を取り込む:海外からのインバウンド需要が減少した場合でも、稼働率を維持しやすくなります。
- 複数の物件を異なるエリアで運営する:特定のエリアの市場環境が悪化した際に大きな影響を受けるリスクを分散できます。
これらの対策を講じることで、市場の変動に強い運営体制を構築し、安定的な収益を確保しやすくなります。
近隣トラブルが起きる可能性がある
民泊は不特定多数の宿泊者が出入りするため、近隣住民とのトラブルが発生しやすい傾向があります。
よくあるケースとして、ゴミ出しのルール違反や深夜の騒音、建物の共用部分の利用マナーの問題などが挙げられます。
特に宿泊者が外国人観光客が多いエリアでは、日本の生活ルールやマナーに不慣れな方も多いため、トラブルが発生しやすい点に注意が必要です。
こうしたトラブルを未然に防ぐためには、以下のような対策が有効です。
- ルールの明確化と案内の充実
外国語対応の「ウェルカムガイド」を用意し、注意事項を明確に伝えましょう。- 夜間(22時以降)は会話や音楽の音量を控える
- ゴミ出しのルールを守る(指定の時間・場所を厳守)
- 監視体制の強化
防犯カメラやスマートロックを導入し、トラブルが発生した際に迅速に対応できるようにします。 - 近隣住民とのコミュニケーション
民泊運営を始める前に事前説明を行い、近隣住民と良好な関係を築いておくことが重要です。また、緊急時の連絡先を共有し、苦情が発生した際に迅速に対応できる体制を整えましょう。
これらの対策を講じることで、近隣トラブルを抑えながら円滑に民泊を運営することができます。
民泊投資を成功に導くためのポイント

民泊投資で安定した収益を得るために、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 収益シミュレーションをする
- 立地を重視して物件を選ぶ
- 差別化を狙う
これらのポイントを理解し、戦略的に投資・運用することが重要です。
収益シミュレーションをする
民泊投資で安定した収益を得るためには、事前にシミュレーションを行い、投資額の回収期間や中長期的な収支を計算しましょう。
シミュレーションの際に考慮すべき主な要素は、以下のとおりです。
- 初期費用
- ランニングコスト
- 宿泊料金
- 稼働率・営業日数
各要素について解説します。
初期費用
初期費用によって、民泊の運営を開始するまでの難易度が大きく変わります。以下の項目は、初期費用として見込んでおきましょう。
- 物件購入費または賃貸契約の初期費用
- リノベーション・内装工事費
- 家具・家電・アメニティの購入費(ベッド・冷蔵庫・洗濯機など)
- 消防設備の設置費用
- 広告宣伝費(民泊サイト掲載料、写真撮影代など)
これらの投資額をどのくらいの期間で回収できるのか、計算してみてください。
ランニングコスト
一般的な民泊経営では、以下のような費用が定期的に発生します。
- 水道光熱費・Wi-Fiなどの通信費
- リネン交換・清掃費
- 固定資産税
- 火災保険料
- 予約サイトの手数料
- 専門会社への委託費用
ランニングコストを事前に把握しておくことで、最低限必要な収益の目安がわかります。
宿泊料金
宿泊料金を決める際のポイントは、以下のとおりです。
- 周辺の民泊の価格を調査し、相場を把握する
- ターゲット層(観光客・ビジネス客など)に合わせた料金設定を行う
- 平日と週末、繁忙期と閑散期の価格調整を考慮する
宿泊料金を設定する際には価格競争に巻き込まれないように、設備やサービスの差別化も意識するとよいでしょう。
稼働率・営業日数
民泊の売上は「1室あたりの宿泊料金 × 部屋数 × 稼働率 × 営業日数」の計算式で、おおよその数字を予測できます。
稼働率とは、全体の客室数に対して客室が実際に利用されている割合のことです。エリアやターゲット層によって、稼働率は大きく変わります。
また、民泊の営業日数は運営形態によって法律で決められており、新法民泊では最大180日間の制約があります。
| 運営形態 | 年間最大営業日数 |
|---|---|
| 新法民泊(住宅宿泊事業法) | 180日 |
| 特区民泊(国家戦略特区) | 365日 |
| 簡易宿所(旅館業法) | 365日 |
立地を重視して物件を選ぶ
民泊投資では物件の立地が収益に直結するため、慎重に選びましょう。どれだけ魅力的な物件であっても、需要が少ないエリアでは稼働率が低下し、想定した収益を得られない可能性があります。
民泊の稼働率を上げるためには、観光客やビジネス客など、宿泊需要が高いエリアを選ぶことが重要です。
| 観光需要が高いエリア | ビジネス需要が高いエリア |
|---|---|
| ・外国人観光客が多い地域 (北海道・京都・大阪・沖縄など) ・大型観光施設の周辺 (東京ディズニーリゾートやUSJなど) ・季節によって人気が変わる地域 (温泉地やスキーリゾートなど) | ・大都市圏のオフィス街周辺 (東京・大阪・名古屋など) ・展示会 ・国際会議が頻繁に開催されるエリア (幕張・福岡など) ・新幹線や空港へのアクセスが良い地域 |
また、交通アクセスや周辺環境も確認しておきましょう。以下のような条件を満たしている場合、稼働率が高くなる可能性があります。
- 最寄りの駅から5〜10分以内
- 繁華街や観光スポットが近い
- 周辺にコンビニ・飲食店・スーパーが多い
差別化を狙う
競合が多いエリアの場合、ありきたりな物件だと選ばれにくく、収益化が難しくなります。以下のような工夫をして、競合との差別化を狙いましょう。
- 設備を新しくし、快適性を向上させる
⇒最新設備やサウナ、プロジェクターなどの快適な滞在環境を整備することで、宿泊者の満足度向上とリピーター獲得につなげる - コンセプトを明確にし、ターゲットを絞る
⇒子連れやペット同伴などの具体的なテーマに沿った内装やサービスを提供することで、民泊の差別化を図りやすくなる - 民泊の少ない地域を狙う
⇒観光地から少し離れたエリアで利便性と独自性を両立させることで、競争を避けながら高い稼働率を確保できる可能性がある
差別化を図れれば運営する民泊物件が利用者から選ばれやすくなり、収益につながります。中には費用がかかる施策もあるため、予算を決めたうえで取り組むと良いでしょう。
民泊投資の始め方

民泊経営は、以下の手順で始められます。
- 運営形態を選択する
運営形態によって営業日数や許認可要件が異なるため、営業日数の制限や立地条件などを考慮し、自分に合った運営形態を選択する - 民泊経営をする物件を選ぶ
立地や競合を考慮して物件を選ぶ - 開業資金を調達する
物件取得費やリフォーム費用などの初期費用がかかる。自己資金が不足する場合は、不動産投資ローンや民泊専用ローンの活用も検討する - 物件の設備工事・リノベーションをする
消防設備の設置やターゲットに合わせた内装デザインにするために、工事やリノベーションが必要になる場合もある - 運営形態に合わせて許可申請・届出をする
運営するために、法律に基づいた届出や許可申請を行う - 備品の整備や規約の作成などを行う
宿泊者が快適に過ごせるよう、寝具・アメニティ・キッチン用品などを用意する。またハウスルールを作成し、騒音やゴミ出しのルールを明確にしておく - 民泊サイトに登録する
AirbnbやBooking.comなどの予約サイトに登録し、物件の魅力が伝わる写真と説明文を掲載する - 運用・管理をする
清掃やチェックイン対応、宿泊者からの問い合わせ対応などの運営管理を行う
実際に運営してみると、業務の負担が多く手が回らないと感じることもあるでしょう。負担が大きいと感じたときは、民泊管理代行サービスの活用も検討してみてください。
民泊投資を検討している方は不動産投資ローンも活用しよう

民泊投資は、宿泊料金を自由に設定できることや用途変更がしやすい点など、一般的な不動産投資と比べて柔軟に運用できます。そのため、高い利回りを期待できるのが大きな魅力です。
一方で、営業日数の制限や設備投資の負担といったデメリットもあるため、安定した収益を得るためには事前のシミュレーションが欠かせません。
また、民泊投資を成功させるためには、需要のあるエリアで物件を選ぶことが重要です。しかし、資金が不足していると、好条件の物件を購入する選択肢が限られてしまいます。
物件の購入代金だけでなく、運営を開始するまでに設備投資の資金も必要となります。資金面に不安がある方は、不動産投資ローンの活用を検討してみてください。
セゾンファンデックスの「不動産投資ローン」で資金調達をサポート
セゾンファンデックスの「不動産投資ローン」は、通常の銀行融資よりも柔軟な審査で民泊投資の資金調達をサポートします。
- 自宅やすでに所有している収益不動産を担保にすることで、頭金0円でローンを組むことも可能
- 築古・狭小物件、借地権付き建物など、銀行では対応が難しい物件にも対応可能な場合あり
民泊投資を始めたいが資金面で悩んでいる方は、ぜひ一度ご相談ください。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。