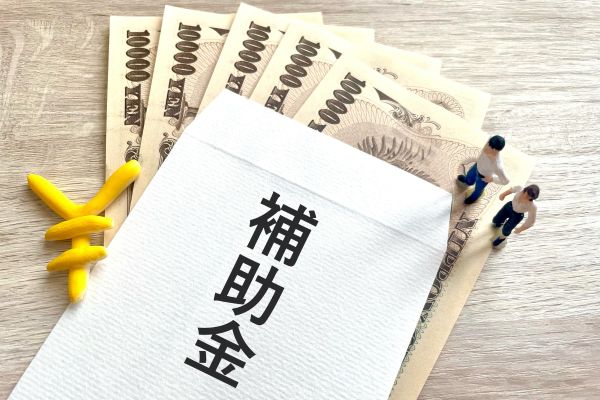事業継続や成長のために資金確保は欠かせませんが、銀行融資や自己資金だけが選択肢ではありません。返済不要で活用できる補助金・助成金は、国や自治体が支給する有力な公的支援資金のひとつです。ただし、制度ごとに内容や要件が異なるため、適切な選択と事前準備が不可欠です。本記事では、公認会計士・税理士の視点から、補助金・助成金の違いや代表的な制度、活用のポイントをわかりやすく解説します。
補助金・助成金による資金調達とは?

まずは、補助金や助成金とはどのような資金なのか、その特徴を正しく理解しておきましょう。
返済不要の「公的支援資金」
補助金や助成金とは、
・地方自治体(都道府県・市区町村)
・各種公的機関(商工会議所・中小企業支援機関など)
こうした公的機関が、特定の政策目的や地域活性化、雇用促進などを目的に実施している「公的支援資金」です。
最大の特徴は返済義務がないこと
調達した資金は返済や利息の支払いが不要で、自己資金や借り入れに頼らず事業投資や経営強化に活用できます。
この「返済不要」という特性は、資金繰りの負担を軽減し、攻めの投資を後押しする大きなメリットといえるでしょう。
採択・受給には「条件」や「手続き」が必要
ただし、補助金・助成金は、誰でも簡単にもらえる「無条件の資金」ではありません。
以下のようなルールや制約があることを理解しておく必要があります。
・審査や書類手続きが必要で、必ずしも受給できるとは限らない
・採択後も、実施報告や経費証憑の提出など、細かな手続きが求められる
このように、制度ごとに内容や要件は大きく異なります。「準備不足」や「要件不適合」により受給できないケースも多いため注意が必要です。
とはいえ、条件に合致し、しっかり準備を整えれば、返済不要で活用できる資金です。
「使えるものなら積極的に使うべき」ですが、情報収集・制度理解・事前準備を怠らないことが成功のカギとなります。
補助金と助成金の違い

補助金と助成金は似ているようで、実は大きく異なります。
簡単にまとめると以下の通りです。
| 補助金 | 助成金 | |
|---|---|---|
| 実施主体 | 経済産業省・中小企業庁など | 厚生労働省・自治体など |
| 目的 | 事業成長・地域振興・イノベーション支援 | 雇用促進・人材育成・労働環境改善 |
| 採択方式 | 審査・競争あり(採択率に限りがある) | 要件を満たせば原則受給可能(審査は形式的) |
| 募集時期 | 年数回の公募、期限あり | 通年・随時申請可能なものが多い |
| 代表例 | ものづくり補助金、IT導入補助金など | キャリアアップ助成金、雇用調整助成金など |
補助金は「競争型」、助成金は「条件クリア型」
補助金は、事業計画書や財務状況などを基に「審査」され、優れた取り組みが「採択」される仕組みです。
このため、募集枠や予算が限られ、応募しても不採択となる場合があります。一方、助成金は、法律や制度で定められた要件を満たせば、原則として受給できます。
ただし、申請書類の不備や手続きミスがあると不支給になることもあるため、正確な運用管理が重要です。
主な補助金・助成金の例

ここでは、代表的な補助金・助成金を紹介します。
<主な補助金>
・新製品開発や生産設備導入、サービス革新などを支援
・中小企業・小規模事業者が対象
・補助率1/2~2/3、最大1,250万円程度
(2) IT導入補助金
・業務効率化やDX(デジタルトランスフォーメーション)推進を支援
・ソフトウェア・ITツール導入費用を補助
・補助率1/2~3/4、数十万円~数百万円規模
(3) 中小企業新事業進出補助金
・既存事業からの転換、新分野進出、ビジネスモデル変革などポストコロナ時代の挑戦を支援
・中小企業・小規模事業者向け(地域経済の再活性化を重視)
・上限2,000万円程度(事業規模や類型により異なる)の補助金を交付予定
・設備投資、販路開拓、デジタル化、グリーン分野など幅広い取り組みを対象
<主な助成金>
・非正規雇用労働者の正社員化、処遇改善を支援
・雇用形態転換や賃金引き上げに対して一定額を支給
(2) 雇用調整助成金
・景気悪化や災害時に、雇用維持を図るための休業補償を支援
・休業手当や教育訓練費用などを一部助成
(3) 人材開発支援助成金
・従業員の職業訓練・スキルアップを支援
・中小企業・小規模事業者向け(地域経済の再活性化を重視)
・訓練費用や賃金助成を通じて人材育成を後押し
補助金・助成金活用の注意点と成功のポイント

(1) 情報収集を怠らない
補助金・助成金は毎年制度が見直され、新設・廃止・変更が繰り返されています。
情報を得ているかどうかが大きな差となるため、
・商工会議所・支援機関のセミナー
・税理士・社会保険労務士など専門家の情報提供
などを活用し、最新情報をキャッチアップし続けることが重要です。
(2) 申請要件・手続きの理解
補助金・助成金は、要件を満たさなければ受給できません。
また、「実施後の報告・証憑提出」など煩雑な手続きも求められます。
・記録・証憑の保管体制
・実績報告や経費精算の正確さ
これらを徹底しないと採択されても支給されないリスクもあるため、事前に制度要件をしっかり理解しておきましょう。
(3) 事業計画との整合性を重視
補助金・助成金は「もらえるから使う」のではなく、「自社の事業戦略に合致しているか」を最優先に判断するべきです。
補助金目当ての投資や、助成金狙いの雇用・制度変更は、本来の経営方針を損なうリスクがあります。資金調達はあくまで「目的ではなく手段」であることを忘れず、本当に必要な投資・施策に絞って活用することが、持続的な成長につながります。
制度の活用で追い風に

補助金・助成金は、企業にとって返済不要という非常に大きな魅力を持つ公的支援制度です。
うまく活用できれば、資金繰りの改善だけでなく、これまで踏み出せなかった新たな事業投資や人材育成に大きな追い風をもたらします。
・雇用調整助成金やキャリアアップ助成金で、雇用維持や人材確保など「守りの経営」を支援
経営課題や事業フェーズに応じて、これらを適切に使い分けることが求められます。
一方で、「すべての制度に申請すればよい」というわけではありません。
補助金・助成金には、制度ごとに目的・趣旨・要件があり、自社に合わない施策を無理に合わせてしまうと、かえって事業の軸をぶらしかねません。
だからこそ、「本当に自社に必要な制度を見極めること」「適切な申請と運用で効果を最大化すること」が、補助金・助成金活用の成功のポイントです。
公認会計士・税理士として、多くの企業の補助金・助成金活用を支援してきた立場からも、「制度を知り、経営戦略に組み込み、資金を経営に活かす力」が、企業の財務基盤や成長力を高める原動力になると考えています。
ぜひ補助金・助成金を「知っているだけ」で終わらせず、「自社の成長を後押しする武器」として戦略的に活用してください。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。