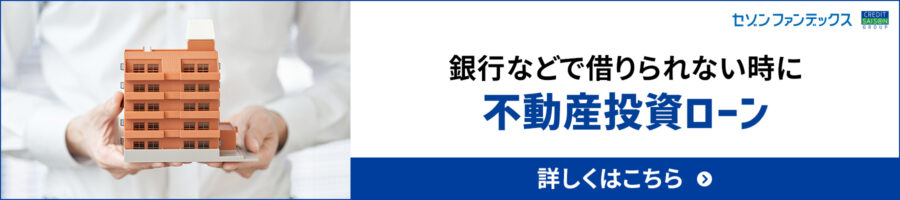都市部で民泊の競争が激化する中、田舎での民泊経営に注目する方が増えています。しかし「観光客が少ない地方でも本当に採算が取れるのか」「副業として成り立つほどの収益は期待できるのか」など、不安に感じている方もいるでしょう。
実は、田舎の民泊には都会にはない強みがあり、適切な戦略を取ることで安定した収益を得られる可能性があります。実際に成功している事例もあり、工夫次第で年収アップを狙うことも夢ではありません。
本記事では、田舎の民泊が注目される3つの理由や、成功するためのポイントを詳しく解説します。収益シミュレーションや開業前に押さえておくべき注意点も紹介しているため、田舎での民泊経営を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
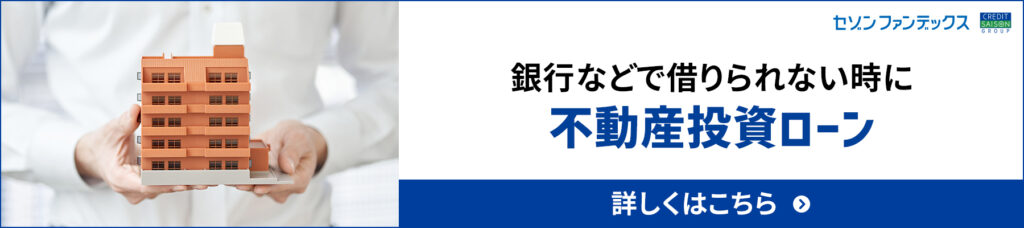

田舎の民泊が儲かるといわれる3つの理由

田舎の民泊は都市部に比べて観光客の数は少ない傾向にあります。しかし、以下の理由から、田舎の民泊は収益を上げやすい環境にあると考えられています。
- 低コストで運営できる
- 競合が少ない
- インバウンド需要を取り込みやすい
特徴を理解し、経営をスタートする際の判断材料にしましょう。
低コストで運営できる
田舎の民泊は運営コストが低いため、都市部の民泊に比べて利益を出しやすい状況といえます。
民泊の運営コストは、経営を始める際にかかる「初期投資」と、毎月発生する「ランニングコスト」の2つに分かれます。
初期投資を抑えやすい
初期投資のうち、大部分を占めるのは「物件購入費用」です。田舎では土地や物件の価格が都市部よりも安く、物件取得コストを大幅に削減できる可能性があります。
以下は、県庁所在地における住宅地の平均価格を比較した表です。
| 1㎡あたりの平均価格 | |
|---|---|
| 東京都23区 | 69万6,400円 |
| 大阪市 | 25万8,200円 |
| 横浜市 | 24万4,000円 |
| 青森市 | 3万3,900円 |
| 山口市 | 2万7,400円 |
| 鳥取市 | 2万6,000円 |
参照元:国土交通省「令和6年都道府県地価調査」
最も地価が高い東京都23区と最も地価が安い鳥取市では、実に30倍以上もの差があります。都市部では民泊を始めるのに初期費用が1,000万円超もかかるところを、田舎であれば数百万円程度にまで抑えられるケースも少なくありません。
ランニングコストも抑えられる
民泊経営では、清掃費や水道光熱費などさまざまな費用が毎月発生しますが、都市部と差が出やすいのが「固定資産税」や「都市計画税」です。田舎の不動産は評価額が低くなりやすいため、これらの税負担も少ない傾向にあります。
また、家賃も都市部に比べれば低いことが多いため、賃貸物件を転貸して民泊経営をする場合も、利益を出しやすいでしょう。
空き家の場合は改修費が高額になることも
民泊の営業許可を得るためには、以下の設備を必ず設けなければなりません。
- 台所
- 浴室
- 便所
- 洗面設備
設置するだけでなく、宿泊者が快適に過ごせるように外観や内装を整える必要もあります。
空き家を民泊に活用する場合、建物の状態によっては大規模な改修が必要になるケースも少なくありません。
> 例:「壁・床のリフォームで200万円かかった」「水回りの改修だけで100万円ほどかかった」など
結果的に当初予定よりも費用がかさむこともあるため、民泊物件を購入する際は、どのくらいの改修が必要になるか、コストを事前にシミュレーションしておきましょう。
競合が少ない
都市部では民泊の競争が激しく、価格競争に巻き込まれやすい傾向があります。しかし、田舎では民泊の届出件数が少なく、競合が少ないため、安定した経営を実現しやすい可能性があります。
例えば、東京都23区の民泊届出件数は18,036件にのぼる一方で、秋田県・山形県・石川県・福井県などでは100件未満です。
参照元:国土交通省「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」
宿泊施設自体が少ないエリアでは、民泊が貴重な宿泊手段となるケースもあり、高い稼働率を維持しやすいでしょう。
ただし「競合が少ない=需要が少ない」可能性もあるため、安易に開業すると集客に苦しむことになりかねません。開業前に地域の観光客数や既存の宿泊施設の稼働率などをリサーチし、本当に宿泊需要があるのか確認しましょう。
インバウンド需要を取り込みやすい
近年、外国人観光客の増加に伴い、都市部だけでなく地方の観光地にもインバウンド需要が広がっています。実際に、訪日外国人の約5割が地方部(※)にも訪問しており、田舎での宿泊ニーズも高まりつつあるのが現状です。
※東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県以外の都道府県
参照元:観光庁「令和6年版観光白書について(概要版)」
田舎ならではの自然体験や、伝統文化に興味を持つ外国人観光客は少なくありません。外国人観光客を対象とした調査によると、以下のような体験に高い関心を寄せていることがわかっています。
- 日本食を食べる
- 自然・景勝地観光
- 日本の酒を飲む
- 温泉を利用する
参照元:日本政府観光局「日本の観光統計データ 訪日旅行に関する期待内容」
都市部では体験できない日本らしい文化や風景があることが、田舎の民泊の大きな強みといえるでしょう。
とはいえ「文化も言語も異なる外国人に対応できる自信はない…」という方もいるかもしれません。そのような場合は、以下のような施策を取り入れると、外国人観光客の受け入れがスムーズになります。
- 多言語対応のハウスルールやマニュアルを作成する
- 翻訳アプリを活用しながらゲスト対応をする
- 海外向けOTA(Airbnb、TripAdvisor、Expediaなど)に掲載する
集客力を高められるうえに、トラブルを最小限にした運営が可能になるでしょう。
田舎の民泊経営で失敗するケース4選

田舎の民泊は、都市部とは異なる魅力があることに加え、低コストで始められます。一方で、事前の準備が不足していると失敗しやすいのも事実です。
特に以下のようなケースでは想定よりも収益が上がらず、経営が苦しくなる可能性があります。
- 観光需要がない地域で開業してしまう
- 収益のシミュレーションが甘い
- コンセプトやターゲットが曖昧
- 初期費用をかけすぎてしまう
ひとつずつ見ていきましょう。
観光需要がない地域で開業してしまう
田舎の民泊はビジネス利用が見込めないため、観光客の宿泊需要がなければ経営が成り立ちにくくなります。特に、近くに観光スポットがないなど観光地としての魅力が確立されていない地域では、宿泊需要が生まれにくく、集客に苦戦する可能性は高くなるでしょう。
また、観光客が多く訪れるエリアであっても、日帰りで済ませる方が多い場合は民泊の需要は低くなります。例えば以下のようなエリアでは、宿泊せずに日帰りで済ませる方が多いため、民泊の利用者が限られてしまいます。
- 大都市から電車で1時間圏内にある観光エリア
- 見どころが少なく1日で観光が完結するエリア
さらに、観光地であっても、アクセスが極端に悪い場所は注意が必要です。車がなければ行きづらいエリアでは、宿泊者が敬遠する可能性があります。必要に応じて、送迎サービスなどの対策を検討するとよいでしょう。
また、開業前には、その地域の年間観光客数や宿泊者数を確認し、宿泊ニーズの有無を見極めることが大前提です。そのうえで、観光目的の宿泊だけでなく「思わず泊まりたくなる仕組み」を作ることが、地方の民泊経営においては重要となります。
地域の特色を生かし、宿泊者に独自の体験を提供している民泊の事例をまとめてみました。
| 民泊名 | コンセプト | 主な特徴 |
|---|---|---|
| KEHARAHOUSE (奈良県山添村) | 国指定遺跡にある、旅人と村人が交流できる宿 | 奈良・大和高原の伝統的な藁ぶき屋根の建物で、日本の昔ながらの暮らしを体験できる宿。農作業体験や郷土料理の調理、藁ぞうり作りなど、地元住民と交流できるイベントが充実している |
| 里山ゲストハウス晴耕雨読とみだ (岐阜県白川町) | 地域住民が寄贈した大量の書籍が出迎える、特色ある里山施設 | 地域住民が寄贈した約5,000冊の蔵書が並ぶ「里山図書館」を併設し、宿泊者は無料でコワーキングスペースとして利用できる。バードコール作りやアロマオイルクリーム作りなど、五感を活かした自然体験や、地元ヒノキで作られた樽型のサウナ(バレルサウナ)も楽しめる |
| Sea Side Stay (北海道網走市) | ~ホストとともに海のまち網走ならではの地域文化体験が可能 | ホストとともに網走ならではの海の文化を体験できる民泊。冬は流氷観光、夏はクジラ観光クルーズや秋サケ釣りなど、オホーツク海の自然を活かしたアクティビティが豊富。宿泊施設は丘の上にあり、オホーツク海や知床半島の雄大な景色を一望できる。 |
| 百笑宿場 couch (岐阜県本巣市) | ~百姓の日々の生活体験が可能な日本家屋宿 | 四季を通じて農業体験や、日本の田舎暮らしを体験できる施設。野菜作り、木工や漆喰塗りのDIYリノベーション体験、石窯でのピザ作り、流しそうめんや川魚のつかみ取りなど、田舎ならではの多彩なアクティビティを楽しめる |
参照元:国土交通省「民泊の特性を活用した事例集」
実際の事例を参考にしながら「泊まること自体が目的になる」民泊を目指しましょう。
収益のシミュレーションが甘い
田舎の民泊経営で失敗する大きな要因のひとつが、収益のシミュレーションが不十分であることです。
民泊の運営形態は大きく以下の3種類に分けられ、家主居住型/家主不在型のいずれかとなります。法律や営業日数が異なるため、事前に十分に把握しておきましょう。
| 民泊の種類 | 適用される法律 | 営業日数 | 家主の形態 |
|---|---|---|---|
| 民泊新法 | 住宅宿泊事業法 | 年間180日まで | 家主居住型 or 家主不在型(自治体条例で制限ありの場合も) |
| 特区民泊 | 国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例 | 上限なし(最低宿泊日数あり) | 家主不在型でも要件を満たせば認められる例も多い(大田区など) |
| 簡易宿所 | 旅館業法 | 上限なし | 家主が常駐しない(不在型)ケースが主流 |
新法民泊を選択した場合、最大で年間180日しか営業できません。この点を考慮せずに価格設定を行うと、想定した収益に届かないことがあります。
<シミュレーション例>
- 1泊の宿泊料金:1万円
- 稼働率:50%(半分の日程が埋まる)
- 年間営業日数:180日(民泊新法の上限)
上記の条件で計算した場合、年間の売上は90万円(=1泊1万円×稼働率50%×年間180日)です。この売上の範囲内で、光熱費・清掃費・ローン返済・リフォーム費用などのコストを賄い、利益を確保できるかを事前にシミュレーションしておくことが重要です。
特に、田舎の民泊は都市部と比べて季節による宿泊需要の変動が大きい傾向があります。
リゾート地などでは、週末や祝日に宿泊が集中する一方、平日は閑散とするケースも少なくありません。そのため、稼働率を一定に保つのは容易ではなく、収益が不安定になるリスクもあります。
こうした変動を踏まえ、曜日や季節に応じた価格設定やオフシーズン対策など、柔軟な運営方針を取り入れることが、安定した収益につなげるポイントです。
田舎の民泊は、コンセプトやターゲットが不明確なまま運営を始めると、他の民泊との差別化が難しく、集客に苦戦することがあります。特に、都市部と比べてアクセスが不便な場所も多いため、「わざわざ足を運びたくなる理由」を明確に打ち出すことが重要です。
たとえ人気の観光地にある民泊でも、単に「寝るための場所」として認識されてしまうと、リピーターがつきにくく、経営が不安定になる可能性があります。
まずターゲットを明確に定め、そのターゲットが魅力を感じるコンセプトや体験価値を設計することが重要です。
たとえば、ファミリー層向けであれば自然体験や農業体験、カップル向けであれば非日常を感じられる空間演出など、田舎ならではの強みを活かした“ここでしかできない体験”を提示することで、他施設との差別化が図りやすくなります。
コンセプトを決める際の例
| ターゲット | コンセプト | 特徴 |
|---|---|---|
| 都会のファミリー層 | 農泊(農業体験ができる宿) | 田植えや野菜収穫体験、地元食材を使った料理教室 |
| カップルや夫婦 | プライベート重視の一棟貸し民泊 | 露天風呂付き、星空が見える空間 |
| 外国人旅行者 | 日本文化が体験できる民泊 | 地元の祭りや和室体験、着付け体験など |
| 登山・アウトドア好き | 自然が満喫できる民泊 | 焚き火やキャンプ、トレッキングなど |
初期費用をかけすぎてしまう
田舎の民泊は、一般的に都市部よりも低コストで運営できるといわれているものの、初期費用をかけすぎると黒字化が難しくなり、経営が行き詰まるリスクがあります。
特に、古民家をフルリノベーションして開業しようとすると、物件取得費が数百万円でも、改装費に1,000万~2,000万円以上かかることは珍しくありません。こうした大きな投資を回収する前に、宿泊需要が想定を下回り、資金繰りが悪化する事態に陥る可能性があります。
実際、観光庁の「住宅宿泊事業の実態調査」によると、約7割の事業者が500万円以内の初期費用で開業しているというデータもあり、費用を抑えてスタートする傾向がうかがえます。
無理のない範囲で初期投資を抑え、まずは小規模で始めて収益を安定させたうえで段階的に拡張するなど、柔軟な運営計画が求められます。
| 初期費用 | 物件全体 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|---|
| 500万円未満 | 65.5% | 78.7% | 55.0% |
| 500万円以上5,000万円未満 | 15.8% | 19.4% | 12.7% |
| 5,000万円以上 | 13.4% | 1.5% | 23.1% |
観光庁「住宅宿泊事業の実態調査」
初期費用が1,000万円を超えるような場合は、リスクに見合うだけの集客が見込めるのか慎重に検討しましょう。
初期費用を抑えるポイント
- 宿泊施設として使用されていた物件や、設備が整っている空き家を活用する
- 中古家電やリサイクル家具を取り入れる
- リフォーム工事をする場合は複数の事業者に見積もりを依頼して比較する
田舎で儲かる民泊を経営するためのコツ

田舎の民泊で安定した収益を上げるために、以下の施策を取り入れてみましょう。
- ターゲットに合わせた設備やサービスを導入する
- 田舎ならではの体験ができるオプションを用意する
- 複数の集客手段を活用する
ターゲットに合わせた設備やサービスを導入する
ターゲット層に適した設備やサービスを整えることで、宿泊者の満足度が向上し、リピーターの獲得につながります。
- 外国人観光客狙い:多言語での館内案内、スタッフの英語対応、高速Wi-Fi
- 子連れのファミリー層:キッズルーム、子ども用アメニティやベッド柵の用意
- ワーケーション目的:電源タップやノートPC貸出し、長期滞在の割引制度など
田舎ならではの体験ができるオプションを用意する
田舎の魅力を最大限に活かすには、都会では味わえない特別な体験をサービスに組み込むことが効果的です。
| 体験内容 | 料金の目安 |
|---|---|
| 野菜収穫体験 | 3,000円/回 |
| 漁業体験 | 8,000円/回 |
| 祈祷&座禅体験 | 4,000円/回 |
| 蕎麦打ち体験 | 3,000円/回 |
| 乗馬体験 | 10,000円/回 |
体験型プランを用意することで、宿泊単価を上げられるほか、リピーターの獲得にもつながります。
複数の集客手段を活用する
田舎の民泊では、都市部に比べて宿泊需要が限られているため、複数のチャネルを活用した積極的な集客が必要です。
以下のような「OTA(オンライン旅行代理店)」を活用すると、国内外の宿泊客に向けて宣伝ができます。
| 名称 | 特徴 |
|---|---|
| Booking.com | 43言語に対応している世界最大級のOTAサイト |
| Airbnb | 民泊予約のサイトとして知名度が高い |
| agoda | アジア圏最大級の集客サイト |
| Rakuten Oyado | 楽天グループの民泊サイト |
プラットフォームごとの特徴や手数料が異なるため、それぞれの違いを理解したうえで、目的に応じて使い分けましょう。なお、手数料は予約成立金額の15%前後が一般的です。
また、広告費をかけずに集客したい場合は、SNSを活用も有効な手段です。
ただし、SNSは運用に手間とノウハウがが求められ、成果が出るまで時間がかかることもあります。即効性を期待するのではなく、継続的に情報を発信し、ファンやフォロワーとの関係性を築く姿勢が大切です。
田舎で民泊を始めるときの注意点

田舎で民泊を始めるときは、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 開業前に自治体の条例を確認する
- 近隣住民との関係を大切にする
- 田舎の民泊に対応している代行事業者を選ぶ
把握しておかないと、運営に大きな支障をきたす恐れがあります。ひとつずつ見ていきましょう。
開業前に自治体の条例を確認する
民泊は全国どこでも自由に運営できるわけではなく、自治体が独自に営業できるエリア・日数の制限を設けている場合があります。代表的な事例としては以下のようなケースがあります。
| 自治体 | 主な規制(条例)内容 |
|---|---|
| 東京都大田区 | 家主不在型の民泊は基本的に禁止 |
| 東京都江東区 | 月曜正午〜土曜正午まで民泊は禁止。営業開始前に近隣住民への事前説明が必要 |
| 静岡県 | 学校などの敷地の周囲100m以内の区域では、月曜〜金曜まで民泊は禁止 |
参照元:観光庁「民泊の実施制限に関する地方公共団体の条例のとりまとめについて」
例えば、東京都江東区で民泊を開く場合、営業可能日が原則として土日に限られるため、年間でも最大100日程度にとどまります。これは、民泊新法で定めている上限(180日)を大きく下回るため、想定していた収益を得られない可能性があります。
さらに、自治体によっては開業前に近隣住民への説明会が義務付けられているなど、独自の規制が設けられていることもあります。そのため、開業を検討しているエリアの自治体の公式サイトや窓口で、営業条件や申請手続きの最新情報を事前に確認することが重要です。
近隣住民との関係を大切にする
田舎では、都市部以上に住民同士のつながりが強く、地域の理解を得られないと民泊の運営が難しくなる傾向があります。開業前に近隣住民へ挨拶をし、民泊のルールや騒音対策などを説明することで、トラブルを未然に防ぎましょう。
民泊でよくあるトラブルの例
- 宿泊者が夜遅くまで大声で会話をしている
- ゴミの分別ルールを守らず、回収されないゴミが放置される
トラブル対策の例
- ハウスルールで「夜22時以降は静かに過ごす」と明記し、チェックイン時に宿泊者へ説明する
- 防音カーテンを導入する
- 多言語対応の分別マニュアルを作成して案内する
- 万が一の場合に備えて、周辺住民に連絡先を共有しておく
田舎の民泊に対応している代行事業者を選ぶ
民泊の予約管理やゲスト対応、清掃などを代行事業者に依頼する場合は、対応エリアや提供サービスの範囲を事前にチェックしておきましょう。特に田舎の物件では、対応できる事業者が限られており、一部の業務しか提供できないケースもあります。
また、どこまでの業務を委託するかによって手数料も異なります。
たとえば、集客だけを代行してもらう場合と、清掃・鍵の受け渡し・ゲスト対応を含むすべてを任せる場合では、費用やサービス内容に大きな差が生じます。
開業前に自分が担う業務と委託する業務の範囲を明確にし、それに適した事業者を選ぶことが大切です。
以下は、ある代行事業者のサービス内容と手数料の一例です。
| サービス内容 | 手数料 |
|---|---|
| ・ゲストとのメッセージ対応 ・OTAサイトへの掲載 ・レビュー管理 | 売上の7% |
| ・ゲストとのメッセージ対応 ・OTAサイトへの掲載 ・レビュー管理 ・ゲストへの鍵の受け渡し ・日中駆けつけサポート | 売上の15% |
| ・清掃・ゴミ回収サービス ・民泊新法・特区民泊申請代行サービス | オプション料金 |
複数の代行事業者を比較し、サービス内容と手数料のバランスを考えて選びましょう。
なお、民泊運営を完全に丸投げしてしまうと、コンセプト作りや価格設定などの戦略面でオーナーの意向が反映されにくくなる可能性があります。なるべくオーナー自身が積極的に関与するのがおすすめです。
田舎の民泊におすすめの資金調達方法

田舎で民泊を始める際は、物件購入費やリフォーム費用など、予想以上に初期費用がかかることもあります。資金調達に困ったときは、以下の方法を検討してみましょう。
- 不動産投資ローンを活用する
- 民泊専用ローンを活用する
- 自治体の補助金・助成金を活用する
複数の手段を組み合わせ、無理のない資金計画を立ててください。
不動産投資ローンを活用する
物件購入の費用が不足している場合は、不動産投資ローンを活用しましょう。投資用物件の購入を目的とするローンで、民泊経営を目的とした場合は住宅ローンは利用不可です。
- 不動産投資ローンは住宅ローンより金利が高い傾向にある
借入額が大きいほど月々の返済も重くなるため、計画的に検討する必要がある
たとえばセゾンファンデックスの「不動産投資ローン※取扱いエリア内」なら、自己資金なしのフルローンも可能です。
築年数が古い物件でも融資を受けられる可能性があります。融資年率は3.90~5.30%、最大5億円の融資が可能です。開業資金に不安がある場合は検討してみましょう。
民泊専用ローンを活用する
民泊専用ローンは、一部の金融機関で取り扱っている民泊に特化したローンです。物件の購入費用だけではなく、リフォーム資金の調達にも活用できます。
- 一般的な不動産投資ローンよりも高額の借り入れに対応している場合や、目的が限定されている分、金利が優遇されるケースもある一方、年収・勤続年数・物件所在地などの要件が厳しいことも多い
条件が合えば、資金負担を大きく軽減できる方法として有力です。
自治体の補助金・助成金を活用する
田舎の民泊経営では、自治体が提供する補助金・助成金を活用することで、自己負担を減らしながら民泊を始められます。
下記は一例です(直近の公募要領や締切、要件は必ず最新情報を確認してください)。
| 補助金・助成金制度 | 補助率 | 上限金額 | 対象経費 |
| 事業再構築補助金(成長分野進出枠) | 2分の1〜3分の2 | 100万円〜1.5億円 | 事業に必要な建物の建設・改修に必要な経費、専門家に支払う費用、広告宣伝・販売促進費など |
| 小規模事業者持続化補助金(一般型) | 3分の2 | 50〜200万円 | 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、委託・外注費など |
| 地方創生起業支援事業 | 2分の1 | 200万円 | 人件費、設備費、広報費など |
| 宿泊施設サステナビリティ強化支援事業 | 2分の1 | 1,000万円 | 省エネ型空調、太陽光発電、節水トイレなど |
| 空家活用支援補助金(空家・空地バンク登録物件修繕支援事業) | 2分の1 | 50万円 | 空家バンクで取得した物件の修繕費 |
※表内の数値は直近募集回の公募要領を参照
地域振興や空き家活用を目的としたものなど、多様な補助金・助成金が用意されています。申請の手間はかかりますが、うまく利用すれば開業資金のハードルを下げられるでしょう。
田舎ならではの工夫をして民泊を始めよう

民泊で安定した収益を上げるために大切なのは「どのエリアで」「どんなコンセプトで」「どう資金調達するか」という戦略です。実際に、都心部から離れた場所であっても、民泊事業を成功させている事例は数多く存在します。
特に以下のポイントを意識しておくと、成功しやすくなるでしょう。
- 観光需要が多く、宿泊ニーズがある地域で開業する
- ワーケーション・農泊・外国人向けなど、ターゲットに響くコンセプトを打ち出す
- 営業日数の制限やオフシーズンの影響を考慮し、現実的な売上予測を立てる
- 不動産投資ローンや補助金・助成金を活用し、無理のない資金計画を立てる
田舎ならではの強みを活かしつつ、入念な準備と戦略をもって臨めば、民泊経営で安定した収益を目指すことは十分に可能です。まずは気になるエリアの観光需要や、資金調達方法を調べるところから始めてみましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。