借入金は、企業の成長や経営の安定を支える重要な資金源です。
しかし、無計画な返済スケジュールは資金繰りの悪化を招き、結果として経営の不安定化を引き起こします。特に中小企業では、資金ショートが給与遅配や信用低下に直結するため、現実的かつ柔軟な返済計画の策定が不可欠です。
本稿では、借入金の基礎から、返済方法の違い、キャッシュフローを意識した管理手法、シミュレーションの活用、追加借入への備えに至るまで、実務に役立つ返済戦略を解説します。
借入金の基本情報とその影響

借入金とは、金融機関から資金を調達し、一定の利息を付けて返済する義務を負う契約です。資金の用途に応じて、「運転資金(短期)」、「設備資金(中長期)」、「プロジェクト資金」などに分類され、返済期間・利率・返済方式などが異なります。
返済方式には「元利均等返済」と「元金均等返済」があり、それぞれに特徴があります。
・元金均等返済:毎月の元本返済額が一定で、利息が徐々に減るため総返済額は抑えられる。しかし初期の返済額が大きく、資金繰りに負担がかかることも。
過大な返済計画は仕入や人件費など運転資金に影響し、事業継続を脅かすリスクとなります。一方で、適正な借入運用は、信用力の向上や将来の資金調達機会の拡大にも寄与します。
無理のない返済計画の立て方
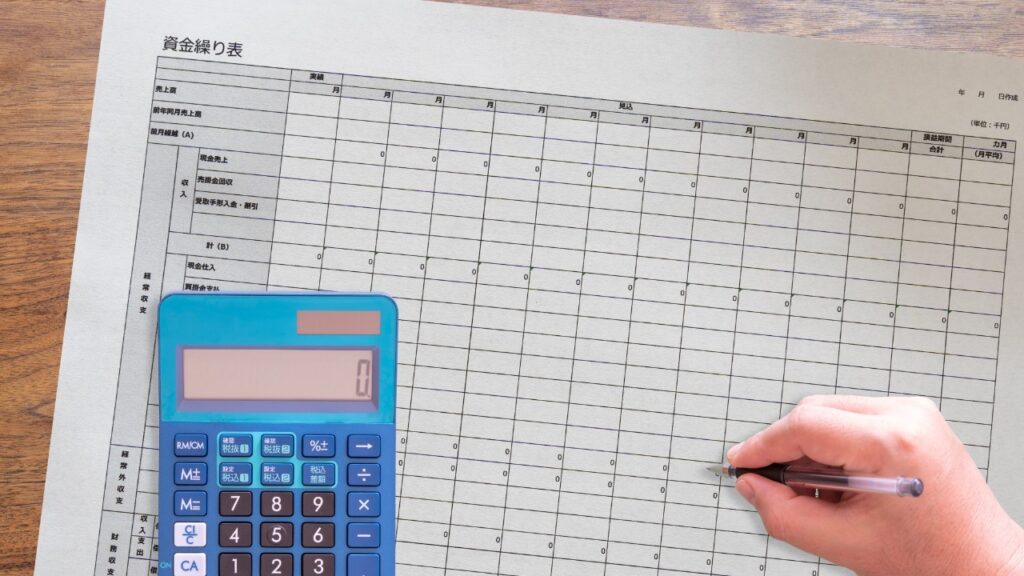
返済計画は「返済可能額」を基準に設計することが鉄則です。金融機関の提示条件をうのみにせず、自社の実際のキャッシュフローに基づき判断しましょう。
業種ごとの特性も、加味が必要です。
・建設業:工期や請負入金のタイミングに応じた返済設定
・製造業:仕入・製造・販売・回収に至るキャッシュサイクルの考慮
帳簿上の利益と現金収支は一致しないため、計画は必ずキャッシュベースで策定することが求められます。
返済シミュレーションのすすめ

借入時点で、売上減少や支払遅延など不測の事態を想定し、返済シミュレーションを行うことが極めて有効です。
たとえば、以下になります。
・想定外の支出(修繕、採用など)
こうした状況を事前に想定し、返済にどの程度影響するかを把握しておくことで、資金ショートへの備えができます。現実的なシナリオを描き、金融機関への説明資料としても活用可能です。
キャッシュフローを意識した資金管理
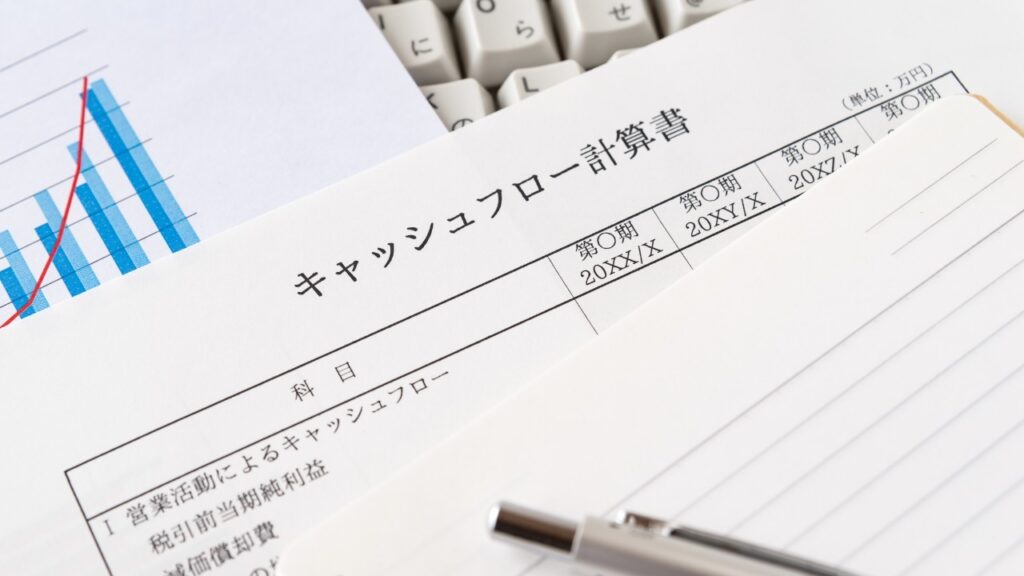
会計上の利益ではなく、「実際に使える資金」を重視した管理が基本です。黒字でも売掛金の回収が遅れれば、資金繰りは悪化します。
・税金・賞与など非定期の大口支出の事前見積もり
・支出項目の削減・平準化
これらを通じて、日々の資金の流れを可視化し、経営判断の精度を高めましょう。資金繰りの安定は、従業員や取引先への信頼にも直結します。
追加借入を考慮した資金計画

将来的な追加借入の可能性を見据えて、現在の返済実績とキャッシュフローの安定性を金融機関に示すことは極めて重要です。
さらに、既存の返済と新規借入の返済が重なることでキャッシュフローが圧迫されるリスクもあるため、借入期間の分散や元金据置期間の活用など、柔軟な設計が求められます。
実際のところ、返済能力に余裕がある企業ほど、有利な条件での借入や資金繰り支援を受けやすくなる傾向があります。
返済計画の見直しと柔軟性

経営環境は日々変化しており、当初の前提が崩れることも少なくありません。そのため、返済計画は固定的なものではなく、必要に応じて見直すべきです。
たとえば、業績悪化時にリスケジュールが必要となった場合でも、日頃から資金繰り表や借入明細を整備しておけば、金融機関との交渉をスムーズに進められます。
また、中小企業庁の経営改善計画策定支援事業(405事業)などを活用することで、再生計画策定費用に対する補助を受けることも可能です。
税理士はこの認定支援機関に登録していることが多いため、早期に相談することが有効です。経営環境の変化や資金繰り不安が出た段階で、できるだけ早く専門家へ相談することで、最悪の事態を避けやすくなります。
事業再生に向けた支援制度を知っておくことは、万一の場合に備えての安心につながります。
事例紹介:現場から学ぶ返済計画の実践

【ケーススタディ:建設業A社の失敗と改善】
売上5億円規模の建設業A社は、元請けからの入金サイトが長く、下請け業者への支払いが早いという資金繰りの構造的課題を抱えていました。
資金ショートを防ぐために1億円の借入を行いましたが、賞与支給時期と返済ピークが重なったことで資金繰りが悪化。
その後、顧問税理士の支援により返済スケジュールを見直し、入金サイトに合わせた返済スパンの延長を金融機関に交渉。
資金繰り表と実績データをもとに誠実に説明した結果、条件変更が認められ、現在は余裕ある返済スケジュールのもとで安定した経営が実現しています。
【ケーススタディ:飲食業B社の成長と資金戦略】
駅前に2店舗を構える飲食業B社は、コロナ禍明けの回復期に3店舗目を出店すべく、2,000万円の設備資金を調達しました。
閑散期に備えて初期半年は元金据置期間を設け、返済シミュレーションを行い、最悪ケースでも人件費・家賃・返済が回る範囲で借入額を設定。
その結果、追加出店後も資金繰りは安定し、半年後には黒字化。追加借入の実績を元に、さらに有利な条件で運転資金の借入にも成功し、信用力が向上しました。
このように、「返せる根拠」を持った計画と情報開示が、成長と信頼を両立させる鍵となります。
【まとめ】

借入金は、経営者にとって「リスク」であると同時に「成長の武器」でもあります。その効果を最大限に活かすためには、返済可能性に基づいた現実的かつ柔軟な返済計画の策定が不可欠です。
キャッシュフローを意識した日常的な資金管理、状況に応じたシミュレーション、追加借入への備えなど、経営者自らが数字と向き合う姿勢が求められます。
特に返済計画や資金繰りは、少しのミスや想定外の支出で致命傷になるため、自己判断に頼らず、数字のプロや専門家と定期的に見直すことを必ず習慣化しましょう。
金融機関との関係において、誠実な情報開示や丁寧なコミュニケーションといった信頼関係の構築が重要です。
しかし、どれだけ信頼を得ていても、返済が滞ればその信頼は損なわれます。信頼関係と同様に、返済できるという事実が何よりの信用につながるのです。
つまり――信頼関係はもちろん重要だが、返済できなければ信頼は崩れる。経営者にとって返済計画は、経営の持続可能性を支える最も重要な判断のひとつです。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、最新情報はホームページ等でご確認ください。


























