自分の死後、「家や土地を誰に引き継がせるか」は、多くの方にとって重要な関心事です。特に不動産は分割が難しく、相続トラブルの原因になりやすい財産です。そこで有効なのが「遺言書」による相続人の指定。
本記事では、特定遺贈・包括遺贈の違いや活用方法、実際の成功例・失敗例、注意すべき法律面のポイントについて、司法書士の近藤崇氏が解説します。
不動産を継ぐ人を指定したい…「遺言書」作成時の2大注意点
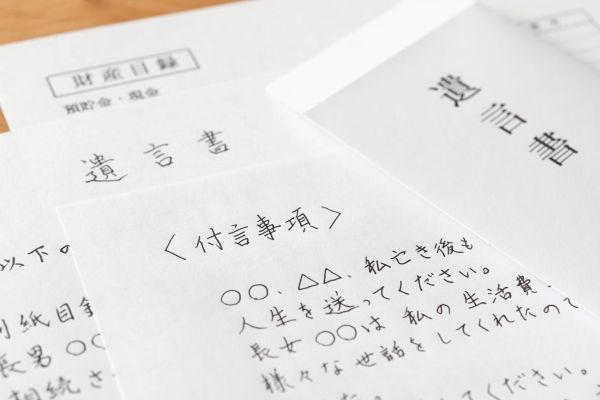
自宅などの不動産を「誰に相続させるか」をはっきり決めておきたい場合、遺言書の作成が必要です。
法的に有効な遺言書としては、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。どちらを選ぶにせよ、特に不動産相続では「登記名義の変更手続き(相続登記)」が必要ですので、物件の特定を正確に行うことが極めて重要です。
注意点①「地番」と「住所(住居表示)」は異なる
まず注意したいのが、登記簿上の「地番」と日常的に使う「住所(住居表示)」は異なるという点です。
遺言書に「○○市○○町1-2-3」などと住所を記載しても、それが登記簿上の「○○市○○町2098番1」などの地番と一致しない場合、登記手続きが進められず、法務局から法務局から補正を求められたり却下されたりするケースがあります。
2024年4月から相続登記が義務化されたこともあり、物件特定の不備によるトラブルが増加しているため、登記簿謄本(登記事項証明書)で正確な地番を必ず確認することが重要です。
不動産は、登記簿に記載された地番・家屋番号などで特定します。そのため、遺言書には必ず登記簿謄本に書かれているとおりの情報を記載してください。
特に都市部では、住居表示がなされていることが一般的ですので、そもそも「地番」と「住所(住居表示)」は異なるものと認識しておいたほうが無難です。
公正証書遺言を作成した場合、公証人や司法書士・弁護士等の専門職が関与していることが多いですので、これらのミスはほぼ心配しなくてよいでしょう。
注意点②都市部で起こり得るリスク
都市部を中心に多いのが「位置指定道路」や「2項道路(建築基準法第42条第2項道路)」に接する敷地です。これらの道路情報は固定資産税が課税されていたため、遺言を書く方の毎年の納税証明書などに反映されていないことが少なくありません。
また、隣地と共有名義のため、わずかな持分のみを有していることも多くあります。しかし、これらの不動産のわずかな名義というのは、相続人が不動産の売却価値や、再建築の可否を判断するうえで極めて重要となります。
遺言書作成時にこのような道路の状況が抜けていると、あとから「接道のない土地しか相続登記ができなかった」「売却ができなかった」といったトラブルに発展するリスクがあります。
このミスについては、不動産登記を専門とする司法書士で相続や遺言の手続きになれている司法書士ならば、見落とすことがないかと思います。
ただ正直なところ、公的証明書に出ないため、権利証等も紛失しているケースでは、司法書士などでも見落とししてしまいがちで、筆者もヒヤリとした経験があります。
またほかの士業や公証人にとっても、納税通知書などだけではわからないため、これらの非課税道路を見落としてしまうことがないとはいえないところです。
こうしたことが発覚するのは実際に遺言を使うとき、つまり遺言者がすでに死亡してしまったあとであることも多いため、下手すると取り返しのつかないミスになり得ます。
もしこれらが遺言書から抜けていた場合――。遺言書があったとしても抜けている部分については別途、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
相続人が複数いて意見がまとまらないと、不動産が「塩漬け状態」となり、売却や利用ができなくなる事態にもなりかねません。
そもそも遺言書が無効になるケースも
物件を正確に特定しても、遺言者自身に「遺言能力」がなければ、遺言書そのものが無効になってしまいます。遺言能力とは、遺言の内容を十分に理解し判断できる能力のことで、加齢や認知症等により判断能力が低下していると、遺言能力が認められないことがあります。
実際に、遺言書作成時の認知機能を巡って遺言の有効性が争われるケースも少なくありません。そのため、「元気なうちに作成する」ことは、こうした法的リスクを回避する上でも非常に重要なのです。
「誰に・なにを」継がせるか?不動産相続における遺言書の書き方と種類

不動産を相続させたい相手が決まっている場合、遺言書によって明確に指定しておくことが大切です。特に不動産は、前述したように正確な物件の記載が求められます。遺言書に記す際は、住所ではなく登記簿に記載された「地番」や「家屋番号」を用いましょう。
たとえば、自筆証書遺言であれば、以下のように記載します。
自筆証書遺言での記載例
私の所有する下記の不動産を、長男 山田太郎(昭和◯年◯月◯日生)に相続させる。
所在:東京都品川区◯丁目◯番
地番:品川区◯番◯
地目:宅地
地積:180.00㎡
また、法定相続人以外の誰か(たとえば甥、姪、内縁の妻など)に対し、不動産を残そうとする場合は、これは遺贈という扱いにするほかありません。遺贈は遺言で行うもので、大きく分けると、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。
包括遺贈と特定遺贈
包括遺贈とは、「財産のすべて」または「〇分の〇」などの割合で遺贈する方法で、遺産全体を包括的に承継します。一方、特定遺贈は、「この不動産を誰に」といったように、特定の財産を特定の人に渡す方法です。
「特定遺贈」と「包括遺贈」、遺言書における記載方法の違い
特定遺贈は「所在・横浜市〇〇区△△@丁目、地番:▼番◯の宅地 及び 所在・横浜市〇〇区△△@丁目 家屋番号 @@番@ の建物を、甥の〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に遺贈する。」などと記載するものです。
一方で包括遺贈というのは、「全財産を従兄弟の@@@(昭和〇年〇月〇日生)に」や「全財産の2分の1ずつを甥の〇〇と姪の〇〇に遺贈する」などと記載します。
財産の記載漏れを防ぐには?
これまでの司法書士としての経験でも多くありましたが、遺贈でも相続でも、上記の特定遺贈のように、特定の相続財産を遺言で記す場合、前述したような「地番」と「住所(住居表示)」のミスや、非課税道路が記載漏れしてしまうというミスを多くみてきました。
そもそも記載されていない不動産については、遺言により登記を行うことはほぼ不可能といってよいでしょう。また「実家は次男に」とのような遺言書の場合、登記できるかどうかも司法書士としても頭を悩ませるところですし、遺言の内容が不明確として相続人間でトラブルになる要因ともなる可能性もあります。
かなり大雑把な話になってしまいますし、遺言を書かれる方の意思と合致していることが前提ではありますが、自筆証書遺言の場合「遺言者の全財産を@@@に相続または遺贈する」という内容は、財産の抜け漏れを一定程度防ぐ効果があります。
ただし、不動産や預貯金の中に特定が困難な財産や記載漏れが生じた場合には、結果的に遺産分割協議が必要となるケースもあるため、完全に抜け漏れがないとは言い切れません。
また、包括遺贈では相続債務も含めて包括的に承継されるため、受遺者にとってはプラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金等)も引き継ぐリスクがあることにも注意が必要です。
なお、司法書士としての実務経験では、包括的な記載以外で遺言者の全財産を完全に網羅できている遺言書に出会うことは稀です。それほど自分自身の財産をすべて正確に把握し記載することは困難なのが現実でしょう。
ほとんどの遺言書で記載が漏れている「予備的事項」の重要性

専門職として遺言書をみていて、前述の物件の特定、書き方の選択と並んで、よくみられる失敗は「予備的事項の記載がない」ことです。
たとえば高齢で子どものいない男性が、年の近い弟に「全財産を相続させる」というような遺言を書いたとします。しかし遺言の作成後、弟が先に亡くなってしまうと、遺言で財産を受領する者がいなくなるため、遺言全体が意味のないものになってしまうのです。
司法書士などの専門職が関与する場合は、相続に詳しい専門職であれば「弟が先に死亡した場合、@@に相続または遺贈する」や、「弟が先に死亡した場合、弟の法定相続人@@に相続させる」などの記載を付けることが一般的です。これを予備的事項と呼びます。
この予備的事項(代替受遺者の指定)は遺言の実効性を高める上で重要な要素ですが、筆者の経験での範囲では、自筆証書の場合に記載されていることは稀といわざるをえません。
記載内容が曖昧な場合には新たな争いの原因となる可能性もあるため、適切な文言選定には司法書士・弁護士等の専門家の助言が欠かせません。そのため、より慎重な作成をお勧めします。
公正証書遺言で作成した場合でも、当然ご本人から上記のような内容を加えたい旨の申し出がない限り、公証人としても勝手に加えるわけにはいきません。そのため公正証書遺言であっても、遺言書として用を為さなくなってしまったケースもありました。
公正証書遺言といえども、あくまで公証人の役割は遺言者の内容を「口授」、つまり話していただいた内容を公正証書遺言として認証することだからです(民法第969条)。
その結果、公正証書遺言ですら、いざというときに効力を失ってしまうケースがあります。公証人は遺言者の希望通りの文言で作成する義務があるため、「内容そのものの法的リスクや家庭状況の変化」まで自動的に担保されるわけではありません。
公正証書遺言を作成した場合も、将来的なリスクや予備的事項を含め、定期的な見直し・専門家への相談が重要です。
~参考~
民法第969条【公正証書遺言】
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人2人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
不動産の相続を確実に行うために

不動産の相続を確実に、かつ円滑に行うには、遺言書に「誰に・なにを・どのように残すか」を明確に記すことがとても重要です。
特に高齢化が進む現代において、認知症等で遺言能力が問われる前に、確実な内容で遺言を作成しておくことが不可欠でしょう。
遺言者と相続人双方の安心や不動産の円滑な承継に繋げるために、司法書士としては、登記に確実に通る遺言書を作成されることを願ってやみません。
なお、2024年4月より相続登記が義務化されており、遺言書による名義変更も期限内の手続きが求められます。未登記や遅延には過料などのリスクもあるため、注意が必要です。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。

























