テレビやネットのニュースで「中東の緊張が高まる」「米中関係が悪化」などの報道を聞くと、「また株価が下がるのかな…」と不安になりませんか?
実際、戦争やテロ、政権交代など世界情勢の変化は、「地政学リスク」として株式市場に大きな影響を与えることがあります。しかし、投資初心者には「地政学リスクなんて難しそう」「遠くの戦争は自分には関係ない」と考えてしまいがち。
本記事では、そもそも地政学リスクとは何か、なぜ株価に影響するのかを、ファイナンシャルプランナー・高山一恵さんがやさしく分かりやすく解説します。世界のニュースに惑わされず、落ち着いて投資と向き合うためのヒントを学びましょう。
「地政学リスク」とは?

「地政学リスク」と聞いて、なんだか難しそう…そう感じる方も多いかもしれません。「地政学リスク」とは、国際情勢や政治的な緊張が、経済や株価に影響を与える可能性のことを指します。そもそも何が“リスク”なのか、まずは基本から見ていきましょう。
地政学リスクの定義
「地政学リスク」とは、国家間の対立や戦争、テロ、政権交代など、地理的・政治的な要因によって経済や市場に不安定さをもたらすリスクのことを指します。文字通り、「地理」と「政治」が関わるリスクです。
また、地政学リスクは“政治や国際関係”だけに限られず、地震や台風などの自然災害も、広義では地政学的なリスクとして扱われることがあります。特に日本のように自然災害が多い国では、そうした要因もマーケットへの影響が大きく、無視できません。
重要なのは、これらのリスクは「いつ、どこで、どのように起きるか予測が難しい」という点です。経済リスクのように周期性や政策対応があるわけではなく、突発的に発生し、市場にショックを与えることが多いのが特徴です。
どんな出来事が該当する?
地政学リスクには、国際的な政治の不安定さや衝突、外交関係の悪化などが含まれます。例えば、戦争や紛争、大統領や首相の交代、国家間の緊張の高まり(米中・ロシア・北朝鮮など)、経済制裁、テロの発生などが代表的です。
最近は特に米中対立が激化し、どちらが世界の“覇権”を握るかという争いが経済にも影響しています。また、トップ(首脳)が誰になるか、その人が“自国第一主義”なのか、“開かれた国際路線”なのかによっても、市場は敏感に反応します。
さらに、実際に事件や戦争が起こっていなくても、“起きそう”という予感だけで投資家心理が揺らぎ、株価が動くこともあります。つまり「報道の内容や社会の空気感」も、リスクとして機能してしまうのが地政学リスクの特徴です。
経済リスクとの違い
「地政学リスク」と似た言葉に「経済リスク」がありますが、両者には大きな違いがあります。
経済リスクは、景気の悪化や金利上昇、物価上昇など、比較的“予測しやすく、政策でコントロールできる要素”が多いのが特徴です。
経済にはある程度“サイクル”があります。不景気になれば、中央銀行(日銀やFRB)が金利を下げてお金を借りやすくしたり、金融緩和をしたりと、手を打つことができます。
景気が過熱した際には逆に引き締めをして抑えることもできるので、どのような方向性になるのか予想しやすいという特徴があります。
一方、地政学リスクは、いつ・どこで・どのように起きるかが非常に読みにくいという点で大きく異なります。
戦争やクーデター、外交関係の急激な悪化など、突発的な出来事が多く、“想定外の衝撃”になりやすく、自然災害(地震や台風)も広義にはこの地政学リスクに含まれます。特に日本のように自然災害が多い国では、その影響を無視できません。
景気後退やインフレなどの「経済リスク」とは異なり、地政学リスクは突発的・予測困難なことが多く、投資家にとって「想定外」の動きをもたらします。経済リスクが“内部要因”なのに対し、地政学リスクは“外部からの衝撃”なのです。
地政学リスクが株価に影響する理由

地政学リスクは、なぜ株価にすぐ反映されるのでしょうか? 実は、株式市場は「今起きたこと」よりも「これから起きそうなこと」に敏感に反応する性質があります。この章では、リスクと株価の関係をやさしく解説します。
投資家の「心理」が先に動く
地政学リスクが市場に与える影響の中でも、最も特徴的なのが“投資家の心理が先に動く”ことです。
戦争が起こりそう、国際関係が悪化しそう……そう感じたとき、まだ何も起きていなくても“危険かもしれない”と感じた投資家たちが先に株を売り始める。そうやって“みんなが怖がる”ことで、株価が一気に下がることがあるのです。
実際に何かが起こってからではなく、「起こりそうな空気」だけで株価が動くというのが、株式市場の大きな特徴です。株価は「景気に先行して動く」と言われますが、それはつまり、投資家たちが未来を予測して先回りするから。
また、特に機関投資家(投資信託や年金などプロの運用者)は、「みんなが売るだろう」と判断すれば、自分たちの判断とは別に、先手を打って売却に動くことがあります。
投資信託などでは“他人のお金”を預かっているため、大きく値下がりする前に守らなければならない。だから“売るしかない”という判断が早く出ることもあるのです。
つまり、知識や経験があっても、運用責任や投資家心理が“早めの売り”を促すことがあり、それが連鎖的に株価下落を引き起こすのです。
企業活動への影響
地政学リスクが表面化すると、企業の経営活動そのものに直接的な影響が及ぶことがあります。例えば、戦争や政治不安で原材料の輸入が難しくなる、物流が止まる、エネルギーコストが上がるなど、さまざまな問題が生じます。
製造業なら、原材料の仕入れ価格が上がったり、そもそも仕入れ自体ができなくなったりすることもあります。すると、製品の価格を上げざるを得ず、それによって売上が落ちて業績が悪化する、という“負のサイクル”に入ってしまうこともあるのです。
つまり、仕入れコストの上昇 → 価格転嫁 → 消費減退 → 業績悪化 → 株価下落という流れが起きやすくなるのです。 さらに、大企業はまだ体力がありますが、中小企業ほどこのようなリスクに耐えきれず、株価への影響も大きくなりがちです。
通貨や資源価格との関係
地政学リスクが高まると、株価だけでなく、通貨や資源の価格にも連動して影響が広がることがあります。
例えば、中東情勢が不安定になれば原油価格が高騰し、それに伴ってエネルギーコストが世界的に上昇します。これは輸送費・製造コストにも波及し、企業の利益を圧迫する原因となります。また、地政学的に不安定な国の通貨は“信用不安”から売られやすくなるという側面も。
テロや軍事的衝突が起こっている国の通貨は、“大丈夫なのか?”という不安感から、どんどん価値が下がる傾向があります。為替の動きが株価にも連動して、さらに不安が広がることもあります。
加えて、「有事の金」と呼ばれるように、不安定な状況下では“安全資産”として金が買われ、価格が上昇するという傾向もあります。これも市場心理の表れの一つです。
株価が大きく動いた主な事例

地政学リスクがどれほど株価に影響するのかは、過去の出来事を見るとよくわかります。ここでは、実際に株価が大きく動いた代表的な事例を紹介し、どんな背景で市場が反応したのかを振り返ります。
2001年:アメリカ同時多発テロ(9.11)
2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロは、世界中に衝撃を与え、株式市場も大きく反応しました。ニューヨーク証券取引所は4日間の休場を余儀なくされ、再開直後にはダウ平均株価が大幅に下落しました。
航空業界や保険業界を中心に深刻な影響が出た一方で、安全資産とされる金や国債に資金が流れる動きも見られました。地政学リスクがどれほど市場心理を揺るがすかを象徴する歴史的な出来事です。
2020年:新型コロナウイルスによるパンデミック
2020年、世界中に広がった新型コロナウイルスの感染拡大は、経済活動の停止とともに株価にも深刻な影響を与えました。
3月には「コロナショック」と呼ばれる暴落が発生し、NYダウは1カ月で約35%の下落を記録。日本市場でも日経平均が2万円を大きく割り込みました。感染そのものは「医療リスク」ですが、世界経済全体への波及効果と不透明感が、地政学リスクと同様の影響を及ぼした例です。
2022年:ロシアのウクライナ侵攻
ロシアのウクライナ侵攻により、世界中の株式市場が大きく下落しました。原油価格の急騰や制裁措置の影響でエネルギーや金融関連株が売られ、地政学リスクが一気に現実化した例として記憶に新しい出来事です。
2023年:中東情勢の悪化
2023年10月、パレスチナの武装組織ハマスとイスラエルとの間で大規模な軍事衝突が発生しました。ガザ地区をめぐる攻防は激しさを増し、アメリカやイランなどの関与も取り沙汰され、「中東全体が戦火に巻き込まれるのでは」と世界中の投資家が警戒しました。
この衝突は軍事的な側面だけでなく、原油価格にも大きな影響を与えました。中東は世界のエネルギー供給の要であるため、緊張が高まると「原油の供給が止まるかもしれない」という不安が広がり、原油先物価格は急騰。これにより、エネルギーコストの上昇 → 企業利益の圧迫 → 株価の下落という連鎖が発生しました。
2025年:トランプショック(関税発言による急落)
2025年4月、トランプ元大統領が復帰後の演説で「特定国への関税を大幅に引き上げる」と発言したことで、世界の株式市場に緊張が走りました。
この発言を受けて、NYダウ先物は急落、日本市場も一時全面安に。 為替も円高方向に振れ、市場全体が「また保護主義が加速するのでは」という不安に包まれました。
ただし、この「トランプショック」は比較的早期に値を戻したことも特徴です。今後もこうした短期的ショックが繰り返される可能性は高く、情報に踊らされずに冷静に動く姿勢が求められます。
初心者が知っておきたい「リスクとの向き合い方」
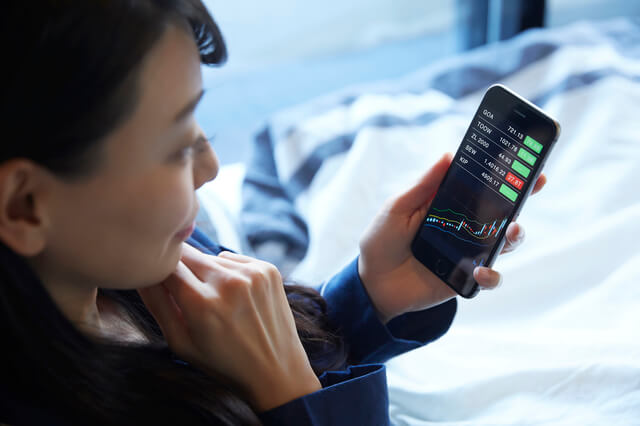
地政学リスクは予測が難しく、株価の上下に大きく影響しますが、「怖いから投資はやめよう」と思う前に、どう向き合えばいいかを知っておくことが大切です。ここでは、初心者が今から意識したいリスクへの向き合い方を紹介します。
情報に振り回されないために
地政学リスクが高まると刺激的な言葉がSNS上にあふれ、不安をあおる情報が次々と流れてきます。
特定のSNSなどでは煽り気味の投稿が多く、読んでいるうちに気分が落ち込んでしまう方もいらっしゃるでしょう。
実際に、そうした極端な言説に影響されて「急いで売らなきゃ」「投資をやめよう」と行動してしまうと、冷静な判断を失い、本来得られるはずだった利益を逃すことにもなりかねません。
大切なのは、情報の“量”ではなく“質”を見ることです。
「本当に信頼できる専門家の発言か?」「感情的な反応ではなく、事実に基づいているか?」を一つずつ見極めていくことで、過剰に振り回されることなく、落ち着いて投資と向き合えるようになります。
長期目線の大切さ
「株価が下がったらすぐ売らなきゃダメ?」と不安になる人も多いですが、投資は短期的な値動きに一喜一憂しない“長期目線”がとても大切です。
チャートを日単位や週単位で見ていると、大きく下がったように感じても、5年・10年という長期で見ると右肩上がりだったりすることもあります。
特につみたてNISAや投資信託などで資産形成を始めた人にとっては、一時的な下落局面でもコツコツ積み立て続ける“継続の力”が将来の差につながるという点を忘れてはいけません。焦って手放すと、その後の回復局面で得られるはずの利益を逃してしまうこともあります。
“今下がっている=失敗”ではなく、“長く育てていく”という視点を持つことが、初心者が不安なく続けるための鍵です。
株だけじゃない!分散投資のすすめ
「投資=株だけ」と思っている人も多いかもしれませんが、一つの資産に集中するのではなく、複数の資産に分けて投資する“分散投資”がリスクへの有効な備えになります。
金(ゴールド)は“有事の資産”と呼ばれ、戦争や混乱があると値上がりしやすくなります。株式が不安定なときでも、資産全体を安定させてくれる可能性があります。
最近では、金の投資信託や積立投資も1,000円程度から始められ、初心者でも少額で分散投資を実践できる時代になっています。また、国内外の株式・債券・不動産などを組み合わせたバランス型の投資信託を利用するのも一つの方法です。
どんな資産にも値動きはありますが、複数に分けておくことで「全部が同時に下がる」というリスクを減らせるのが分散投資の最大のメリットです。
まとめ:地政学リスクを知ることが投資の安心につながる

地政学リスクという言葉は難しく聞こえるかもしれませんが、「世界で起きる出来事が、なぜ株価に影響するのか」を知ることは、投資を安心して続けるための第一歩です。
戦争や外交の緊張、災害、リーダーの交代など、株価に影響する出来事は予測が難しいものばかりです。
しかし、高山一恵さんのお話しのように、「不安になったときこそ、冷静に情報を選ぶこと」「短期ではなく長期の視点でとらえること」「資産を分けて持つことで備えること」など、私たちにもできることはあります。
リスクを“怖がる”のではなく、“理解して備える”姿勢が大切です。
誰にとっても、完璧なタイミングで投資するのは難しいからこそ、焦らず、自分なりのスタンスを持って、コツコツと続けていくことが、未来の安心につながっていきます。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。


























