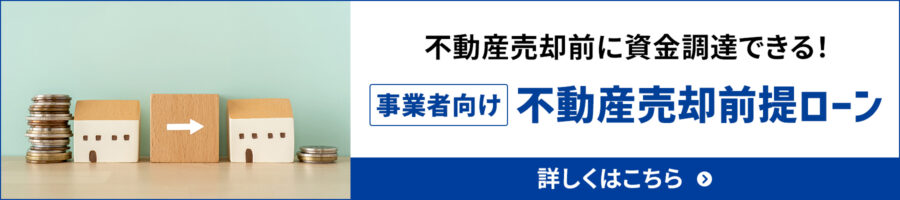事業の継続が困難になった場合、多くの個人事業主の方が廃業を検討することになるでしょう。法人が廃業する場合、一般的には経営者個人が負担するリスクは低いものの、連帯保証人になっている場合など代表者個人が責任を負うケースもあります。一方、個人事業主は個人に借金返済の義務が生じるため、返済計画を見据えて廃業の計画を立てる必要があります。
この記事では、個人事業主の廃業後の借金返済方法を解説します。利用できる公的制度や法的に債務を減額できる手続きについても説明するので、借金返済に悩む事業主は参考にしてください。
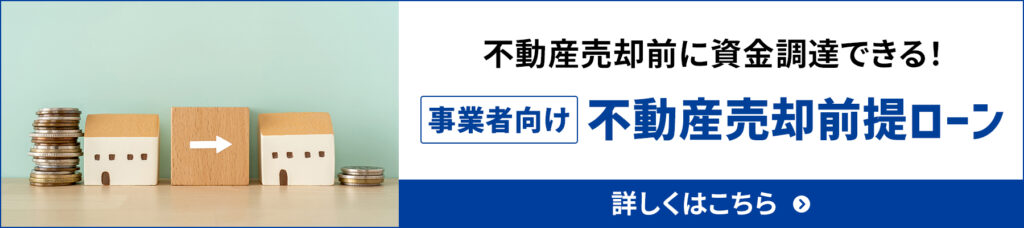
個人事業主が廃業する場合は借金の返済義務が生じる
個人事業主の廃業時に借金が残る場合は、個人の債務になります。法人であれば経営者と個人は別人格ですが、個人事業の場合は同一です。
自己資産を処分しても借金を返済できない場合、債務整理の検討も必要になります。ただし、債務整理を行うと個人の信用情報に記載されることになるため、注意が必要です。
個人事業主が廃業するための手続き・費用
個人事業主が廃業する場合、主に以下の書類提出が必要です。
| 書類名 | 対象者 | 提出期限 | 提出場所 |
|---|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 全員 | 廃業後1ヵ月以内 | 納税地を管轄する税務署長 |
| 所得税の青色申告の取りやめ届出書 | 青色申告の利用者 | 青色申告をやめる年の翌年3月15日まで | 納税地を管轄する税務署長 |
| 事業廃止届 | 課税事業者 | 廃業後すみやかに提出 | 納税地を管轄する税務署長 |
| 給与支払事務所等の廃止届 | 従業員を雇う事業主 | 廃業後1ヵ月以内 | 給与支払事務所などの所在地を管轄する税務署 |
| 健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届 | 全員(厚生年金保険の場合は適用事業所) | 廃業後5日以内 | 事業の所在地を管轄する年金事務所 |
| 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書 | 予定納税をする事業者 | ・第1期・第2期の減額申請:その年の7月1日から7月15日まで ・第2期のみの減額申請:その年の11月1日から11月15日まで | 納税地を管轄する税務署 |
| 事業開始(廃止)等申告書 | 全員 | 廃業後10日以内 | 所管の都道府県税事務所 |
なお、これらの書類提出に関する費用はかかりません。ただし、従業員の給与や退職金の支払い、在庫商品や設備の処分費用などが発生する可能性があります。
廃業時の借金返済で利用できる主な公的制度
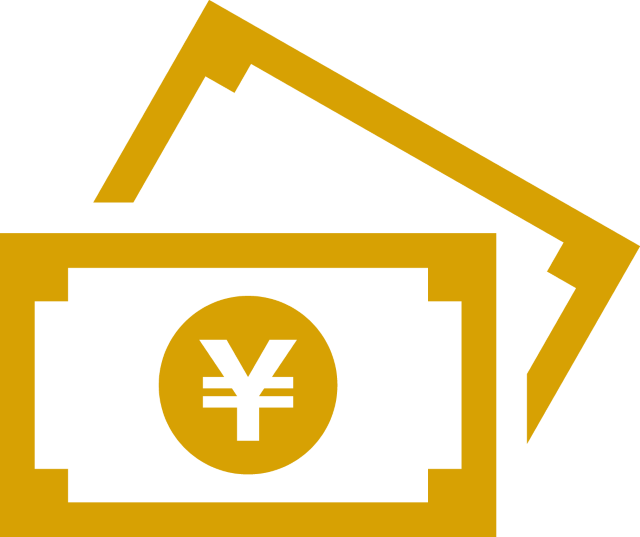
ここでは個人事業主が廃業時に利用できる公的制度を紹介します。
- 小規模企業共済制度
- 事業承継・引継ぎ補助金(廃業・再チャレンジ)
利用にはそれぞれ条件があるため、申請前に確認してみてください。
小規模企業共済制度
小規模企業共済制度の契約者であれば、「廃業準備貸付け」制度が利用できます。
小規模企業共済制度とは、国の機関である中小機構が運営する、個人事業主や小規模企業を対象にした制度です。加入者は退職や廃業時に共済金を受け取れる他、さまざまな貸付を受けられます。
廃業準備貸付の詳細は以下のとおりです。
| 申込受付期間 | 廃業予定日の1年前から |
|---|---|
| 借入窓口 | 商工組合中央金庫の本店または支店(申し込みは中小機構) (※借り入れ申し込みは事前に中小機構へ行う必要あり) |
| 借り入れの限度額 | 掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、50万円以上1,000万円以内(5万円単位) ※算定基準日における掛金残高と納付月数に応じて、年に2回(4月・10月)設定される |
| 借入金の使途 | ・設備の処分費用 ・事業債務の清算等 ・廃業の準備に要する資金 |
| 借入期間 | 12ヵ月 |
| 返済(償還)方法 | 期限一括償還 |
| 利率 | 年0.9% |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 利息支払方法 | 借り入れ時に一括前払い |
| 延滞利子 | 年14.6% |
手続きを希望する方は「共済サポート navi」のお問い合わせフォームから申し込んでください。
参照元:共済サポートnavi「契約者貸付の概要」
事業承継・引継ぎ補助金(廃業・再チャレンジ)
事業承継・引継ぎ補助金の「廃業・再チャレンジ」枠は、M&Aや事業承継により廃業する個人事業主や中小企業が対象で、以下の費用を補助します。
- 廃業支援費
- 在庫廃棄費
- 解体費
- 原状回復費
- リースの解約費
- 移転・移設費用
補助率は対象経費の3分の2以内で、上限額は最大150万円です。申請には電子申請システムの「jGrants」を利用します。jGrantsを利用するには「GビズIDプライムアカウント」の作成が必要です。そのため、GビズIDのホームページで申請書をダウンロードしてください。また、以下も必要になるため、準備しておきましょう(個人事業主の場合)。
- 印鑑登録証明書(発行日より3ヵ月以内)
- PCなどの申請用端末とメールアドレス
- SMSを受信できる電話番号
申請書に記入し実印を押したら、印鑑登録証明書とともに送付します。審査完了後にSMSによる本人確認が行われ、アカウントが作成されます。なお、マイナンバーカードがあればオンライン申請も可能です。
アカウント作成後、以下の書類をjGrantsから送信してください。
- 交付申請書(jGrantsで入力)
- 以下の書類のいずれか
- 事業承継・引継ぎ支援センターから交付された支援依頼書の写し
- M&A支援機関(仲介事業者や金融機関など)との業務委託契約書の写し
- M&Aマッチングサイトへの登録を確認できるもの(WEBサイトやメールの写しなど)
なお、この補助金は募集期間が定められています。年間のスケジュールは発表されずに随時更新されるため、申請前に確認してください。補助金の審査に通る事業者数の割合は募集期間ごとに異なります。事業承継・引継ぎ補助金の「廃業・再チャレンジ」の採択率は以下のとおりです。
- 1次:55.8%
- 2次:42.8%
- 3次:44.8%
- 4次:35.7%
- 5次:45.9%
- 6次:62.1%
- 7次:35.7%
- 8次:54.5%
- 9次:56.0%
補助金申請は事前準備や専門的な知識が必要になる場合もあるため、不安な方は、税理士や司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
参照元:事業承継・引継ぎ補助金「廃業・再チャレンジ」
廃業後の借金返済が困難な場合は債務整理の検討も必要
廃業後に借金が残る場合は、個人で返済する必要があります。その際、自力での返済が困難な状況であれば、債務整理を検討する必要もあります。
任意整理
任意整理とは裁判所を通さずに債権者と話し合い、返済金額を削減する方法です。利息の負担を免除してもらい、元本を3〜5年で分割返済します。交渉は弁護士や司法書士に依頼するケースが一般的で、費用が発生します。金額は債権者の数により異なりますが、1社につき2万円~7万円程度です。他の債務整理手続きと比べて返済負担の軽減効果は小さいですが、手続きが簡易的で費用も安いため、残債が少ない場合によく選択される方法です。
特定調停
特定調停とは裁判所が仲介役となり、債権者と債務者で返済計画を立てる方法です。任意整理と同様に利息の支払いを免除してもらい、元本の返済を行う仕組みになります。個人で行えば1,000円程度の費用で済む一方、手続きが煩雑であるため利用者数は大幅に減少しています。
個人再生
個人再生は裁判所に申し立てをして返済額を大幅に減らす制度です。借金を5分の1〜10分の1程度に減額させ、3〜5年で返済する仕組みです。返済負担を大幅に軽減できる一方で、任意整理よりも手続きにかかる費用が高額であり、具体的には裁判と弁護士費用合わせて50〜90万円程度が必要となります。
自己破産
自己破産も個人再生と同様に裁判所に申し立てる必要があります。財産の大半を手放す必要がありますが、一部を除く全ての借金が返済免除されます。費用は50〜130万円程度必要です。
自己破産と聞くと、すべてを失うかのようなイメージを持つ方が多いでしょう。しかし、実際は99万円以下の現金や生活必需品などは手元に残すことができます。一方、自己破産手続きを行うと、一定期間は特定の職業に従事できないなどの制約が課せられる点には注意が必要です。
不動産がある場合は「不動産売却前提ローン」の利用がおすすめ
不動産を借金の返済に充てる場合は、「不動産売却前提ローン」の活用が効果的です。
不動産売却前提ローンとは、売却予定の不動産を担保に資金を借り入れる制度です。慌てて売却する必要がないため、不本意な値段で手放す必要がありません。ただし、返済期間内に売却できなかった場合は、元金を一括返済する必要がある点には注意が必要です。
廃業費用以外にも生活資金や新たな事業への投資としても利用できます。売却成立までの返済は利息分のみになるため、借金返済後の生活が苦しいときでも安心です。
さらに、不動産売却前提ローンは一般的な無担保ローンに比べて金利が低い点も特徴です。利息分の負担を抑えられるため、総返済額の削減にもつながります。
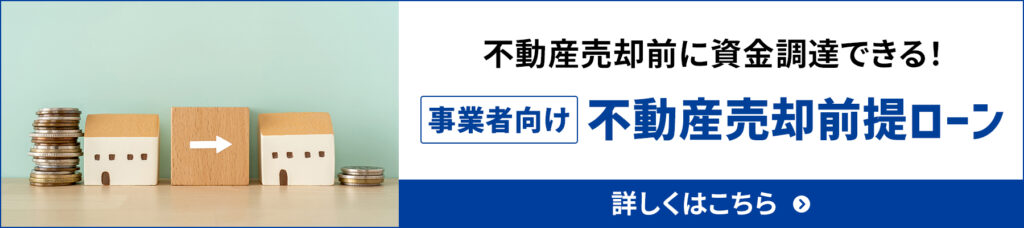
おわりに
個人事業主が廃業する場合は、借金を個人で負担する必要があります。金額が大きく返済が難しい場合は、公的な支援制度の活用も頭に入れておきましょう。
また、債務整理で法的に借金を減額する手段もあります。個人再生と自己破産は裁判所での手続きが必要になるため、不安を伴うかもしれませんが、借金の大幅な減額が可能です。
不動産を所有する方は、「不動産売却前提ローン」の利用も検討してみてください。このローンは不動産の売却を担保に借り入れをするため、返済に困るケースが少ない特徴があります。
慌てて売却する必要もなく、自分が希望する金額で譲れる可能性も高まります。他の金融機関からの借り入れがあっても、担保価値があると判断されれば高額な融資も期待できる点も魅力的です。一方、返済期限までに売却できないと、元金を一括返済する必要があることは覚えておきましょう。
最後に、廃業や借金の問題は決してひとりで抱え込む必要はありません。専門家や相談窓口のサポートを受けながら、冷静に次のステップを考えていきましょう。
不動産を保有している方は、セゾンファンデックスの「不動産売却前提ローン」を検討してみてください。
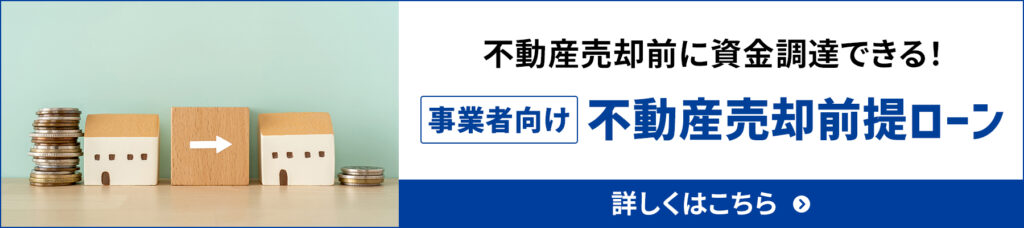
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。