年齢を重ねるにつれ、身体の冷えを感じやすくなった方も多いのではないでしょうか。筋力量の低下や臓器機能の衰えなどにより、年齢とともに冷え性になりやすいといわれています。冷え性にはさまざまな原因がありますが、改善するには身体を温める食べ物を取り入れることことが有効です。
そこで、このコラムでは冷え性を改善する食べ物を詳しく紹介していきます。また、身体を冷やす食べ物、体を温める食べ物の見分け方、冷え性を改善する食事法についても紹介します。「冷えがつらい」「冷え性を改善したい」と悩んでいる方は参考にしてください。
冷え性になる主な原因

冷え性の原因はさまざまですが、以下の4つは特に注意しましょう。
- ホルモンバランスの乱れ
- 生活リズムの乱れによるイライラなどのストレス
- きつい下着や靴など、身体の締め付けによる血の巡りの悪化
- 筋肉量の低下
特に女性は、男性と比較し筋肉量が少ないことから、熱を作り出したり、血液を送り出す力が弱くなります。また、女性はスタイル保持のため、締め付けが強い下着を付ける方も多いので、男性に比べると女性の方が冷え性が多い傾向にあります。
関連記事:【医師監修】冷え性になる5つの原因とは?足が冷えたときのおすすめのアイテムや隠れた病気についても解説 | セゾンのくらし大研究
冷え性を改善する食べ物10選

血行を良くする食べ物を取り入れることで、冷えの予防や冷え性の改善効果が期待できます。冷え性の方におすすめの食べ物を10種類紹介します。
生姜
生姜の辛味成分である「ショウガオール」という成分は血流を良くするとされています。血流が良くなることで身体が温まり、冷えを改善する効果が期待できます。ただし、生のままの生姜は、逆に身体を冷やしてしまいます。加熱したり乾燥させる必要があるので注意しましょう。
薬効成分は皮に近い部分に多いので、皮ごとの調理がおすすめです。
にんにく
にんにくには、血流の流れを良くするとされている成分「アリシン」が含まれています。アリシンには、ビタミンB1の効果を高めて、疲労回復や血行促進、体力増強などに加え、殺菌作用もあるとされています。
にんにくは、風邪の予防にもおすすめです。ただし、食べ過ぎると胃の荒れを引き起こす原因にもなるため、ご注意ください。
玉ねぎ
玉ねぎの外皮に含まれる「ケルセチン」は抗酸化力があり、血管の拡張を促したり、血液をサラサラにしたりするといわれる成分です。ケルセチンは油との相性が良いので、炒めものなどに取り入れることがおすすめです。
また、玉ねぎにも辛味成分の「アリシン」が含まれています。玉ねぎを切ると涙が出るのは「硫化アリル」という成分が原因です。硫化アリルは、体内で「アリシン」に変わります。
赤ピーマン
赤ピーマンは、特にビタミンB6を豊富に多く含んでいます。ビタミンB6は、筋肉のエネルギー源となるたんぱく質の代謝に関わる栄養素です。
また、免疫力の強化やがん予防に役立つβ-カロテンが、緑ピーマンに比べ約2.5倍ほど含まれています。ピーマンのビタミンCは熱に強く壊れにくいので、油による加熱調理がおすすめです。
ナッツ類
ナッツ類は、血管を広げて血流の流れを良くするビタミンEや良質な脂質が含まれています。ビタミンEは血行を促進する作用があり、冷え性や肩こりに有効とされる成分です。
また、ナッツ類に含まれる脂質は、オレイン酸やリノール酸など、血中コレステロール値を抑制し、動脈硬化や高血圧を予防する働きがあるとされています。間食するなら、ナッツ類がおすすめです。
玄米
玄米は、ビタミンB6や糖質を分解するビタミンB1が豊富に含まれています。ビタミンB6は、たんぱく質の代謝に関わる栄養素で、筋力アップに欠かせない成分です。
玄米は、大きく分けて3種類あります。
- 玄米:精白米よりも栄養価に優れ、特にビタミンB群やカルシウム、マグネシウムが豊富です。ただし消化が悪いのでよく噛んで食べましょう。
- 胚芽精米:糠だけを取り除き、胚芽を残して精白しています。ビタミンB1やリノール酸を豊富に含み、玄米よりも食べやすい米です。
- 発芽玄米:玄米の胚芽を発酵させたもので、発芽の過程でGABAが増え血圧を安定させる効果が期待できます。
冷え性改善には、普段の主食を玄米にすることも効果的です。ただし、消化が悪いので、よく噛んで食べましょう。
鶏むね肉・ささみ
冷え性の改善には、筋力アップが大切です。肉類は、優れたたんぱく質源で筋力アップには欠かせません。さらに肉類には、エネルギー代謝を促進するビタミンB群も含まれ、疲労回復にも有効とされています。
中でもおすすめは脂肪の少ない鶏むね肉やささみです。鶏むね肉は柔らかく、クリーム煮や照り焼き、蒸し物に向いています。ささみは淡白なので、筋を取り除いて和え物やサラダに取り入れると良いでしょう。
イワシ
イワシは、エネルギー源となる脂質や、血流の流れを良くするEPAが豊富に含まれています。さらに、鉄やカルシウム、ビタミンB群、ビタミンDなどの栄養素が含まれていて、新陳代謝を活発にしたり骨や歯を強化する効果が期待できます。
イワシは鮮度が落ちやすいので、すぐに内臓を取って冷蔵庫へ入れましょう。買ってきた当日中に食べることをおすすめします。骨ごと食べられるつみれやハンバーグにすれば、筋肉や骨を強化するカルシウムをしっかり摂取できます。
サンマ
サンマもイワシと同様に、エネルギー源となる脂質や、血流の流れを良くするEPAが豊富に含まれています。サンマに含まれる脂肪酸やビタミン類は、骨や歯、筋肉を丈夫にして貧血や冷え性の改善に効果的です。
サンマなどの青魚の脂は身体に良いので、なるべく逃さないようにしましょう。大根おろしと一緒に食べると、魚の焦げに含まれる発がん物質を抑えるのに役立ちます。
ココア
ココアに含まれるカカオには、血管拡張作用のある「ポリフェノール」と「テオブロミン」という成分が含まれています。末梢血管を拡張して、手足の血流を促します。
ココアは「リグニン」という食物繊維も豊富に含まれているので、便秘の改善にも役立つでしょう。便秘に悩んでいる方は、朝食時にココアを飲むことがおすすめです。
冷え性の改善をさまたげる食べ物

冷え性の改善をさまたげる食べ物も確認しておきましょう。身体を冷やすといわれる食べ物は、主に夏野菜やフルーツです。また、一部の飲み物にも注意が必要です。
例えば、以下のような食べ物が挙げられます。
- 夏野菜:きゅうり、トマト、ナス、大根、レタス
- 果物:バナナ、パイナップル、グレープフルーツ、スイカ、メロン
- 飲み物:ビール、コーヒー、牛乳、豆乳、緑茶、白ワイン
しかし、身体を冷やしやすいから食べない方が良いということではありません。例えば夏野菜なら、加熱調理して温かい状態で食べる、フルーツは、食べ過ぎず少量を食べるようにしましょう。
冷え性の改善に役立つ食べ物を見分ける4つの方法
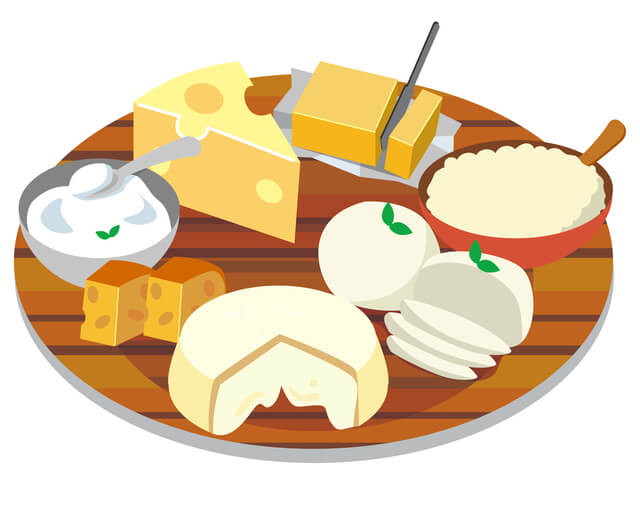
冷え性の改善に役立つ食べ物を全て頭に入れるのは難しいでしょう。しかし、冷え性の改善に役立つ食べ物を見分ける方法があります。ひとつずつ見ていきましょう。
寒い国で育つ作物を選ぶ
身体を温める食べ物を選ぶなら、寒い環境で育つ作物がおすすめです。寒い国では身体に熱を吸収して蓄えなければならないため、身体を温める作物が育ちやすくなります。例えば、大根やねぎ、人参などが挙げられます。
一方、南国ではこもった熱を下げるために、身体を冷やす食べ物が育ちやすい環境です。例えば、きゅうり、なす、トマトなどが挙げられます。身体を温めるなら、冬に旬を迎える作物を選ぶと良いでしょう。
地面の下で育つ食べ物を選ぶ
地中で育つ食べ物は身体を温めます。一方、地上で育つものは身体の熱を下げます。冬に地中で育つ根類に身体を温める作物がが多いのは、動物や人間が身体を温める必要があるためです。
地中で育つものの例は、根類や地下茎類です。代表的な食べ物をご紹介します。
- 根類:人参、大根、カブ、ごぼう、さつまいも
- 地下茎類:じゃがいも、れんこん、生姜、里芋
- 地下鱗茎類:玉ねぎ、にんにく、らっきょう
地下で育つ作物を、積極的に取り入れてください。
発酵食品を選ぶ
発酵食品は、血行促進や代謝をアップさせる効果があるとされています。
- 味噌や醤油
- 納豆
- ぬか漬け
- チーズやヨーグルト
- キムチ
日頃の食事に取り入れやすい食べ物ばかりです。毎日の食卓にプラスしてみてください。
色の濃い食べ物を選ぶ
色の濃い食べ物は、身体を温めるといわれています。濃い橙色や赤色などの暖色系の食べ物は身体を温めるとされています。白色や緑色など色が薄い、寒色系の食べ物は身体を冷やすとされています。
ただし、暖色系でもトマトやスイカは身体を冷やすため、色の濃さが全てではありません。その他、形が丸く水分量が少ない作物(例えば、じゃがいもやカブなど)は身体を温めやすいので、覚えておくと良いでしょう。
冷え性を改善するために取り組みたい食事習慣

冷え性を改善するためには、食事習慣も大切です。こちらでは、冷え性を改善するために取り組みたい食事習慣を5つ紹介します。ぜひ取り入れてみてください。
朝食を抜かない
冷え性を改善するには、朝食をしっかり摂ることが大切です。睡眠中は体温が下がり、代謝活動も低下します。私たちの身体は、朝食を摂ることにより、体温を上げる仕組みになっています。
朝食を抜くと体温が上がらないまま1日が始まり、ずっと体温が下がった状態で過ごすことになってしまいます。朝食をしっかり食べて、体温を上げ、冷え性を予防・改善しましょう。
たんぱく質・ビタミンB6を多く摂る
冷え性を予防するには、筋力の低下を防止することが大切です。筋肉とエネルギーの材料になるたんぱく質と、その代謝に関わるビタミンB6を充分に摂取するようにしましょう。
たんぱく質とビタミンB6が多く含まれる食べ物は、それぞれ以下のとおりです。
- たんぱく質:肉、魚、大豆製品、卵
- ビタミンB6:肉、魚(特にマグロの赤身)、にんにく、ごま、バナナ、ピスタチオ
食事には、肉や魚などのたんぱく質が豊富な食材をメニューに取り入れる工夫をしましょう。
鉄分を多く摂る
血行を促進するには、鉄分も欠かせない栄養素です。鉄分をしっかり摂取して貧血を改善することで血行が良くなり、冷え性の改善が見込めます。
鉄分が豊富に含まれる食品は、以下のとおりです。
- レバー
- ひじき
- あさり
- 菜の花
- 納豆
鉄分の吸収率を高めるには、ビタミンCやたんぱく質と一緒に摂ることがおすすめです。
冷たい飲み物を控える
冷たい飲み物は身体を冷やすので、冷えが気になる方は避けた方が良いでしょう。お腹が冷えると感じる方は、内臓が冷えている可能性があります。冷え性を予防・改善するなら、夏でもなるべく温かい飲み物を選びましょう。
水分の摂りすぎに注意する
水分を過剰に摂取すると、冷え性になる可能性があるので注意が必要です。水分を摂りすぎると、体内に水が溜まります。水は熱を奪う性質があり、身体を冷やすため血流が滞ってしまいます。冷え性の予防・改善には、常温または温かい飲み物をこまめに飲むことがおすすめです。
おわりに
冷え性の改善には、食べ物の選び方が大切です。食材を選ぶときに身体を温める食べ物、冷やしやすい食べ物を意識しましょう。冷え性を改善するなら、食事習慣も大切です。ぜひ毎日の食事に、冷えを改善する食べ物・食べ方を取り入れてみてください。
参考書籍:『栄養学の基本がまるごとわかる事典』
参考書籍:『一生役立つきちんとわかる栄養学』
































