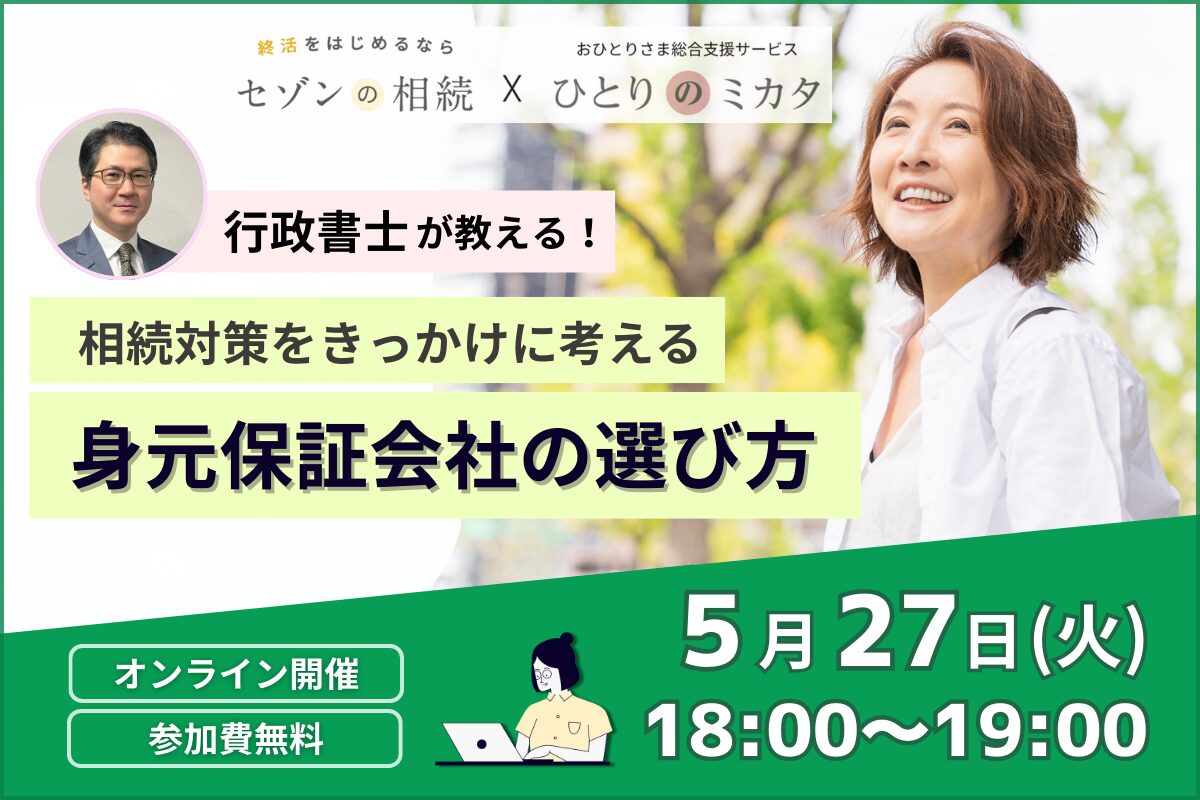「介護に追われて人生が台無しになってしまう……」そんな不安や焦りを感じている方は少なくないでしょう。介護への献身的な思いとは裏腹に、心身の疲労が蓄積し、仕事や家庭生活との両立に行き詰まってしまうケースが増えています。
しかし、介護者が自分の限界を超えて頑張りすぎることは、介護する側もされる側も不幸な結果を招きかねません。大切なのは、一人で抱え込まず、適切なタイミングで介護の限界を見極め、解決策を見出すことです。
本記事では、介護の限界サインの見極め方や、介護保険サービスの活用、施設入所の検討など、具体的な打開策をご紹介します。あなたらしい介護と、自分らしい人生を両立させるためのヒントが見つかるはずです。
- 在宅介護では時間的・身体的・精神的な負担が重なり、介護者の生活を大きく制限。特に要介護3以上では終日の介護が必要に
- 介護うつや腰痛など介護者の心身の不調、住環境の問題、医療ケアの必要性が在宅介護の限界を示す重要なサイン
- 地域包括支援センターへの相談や介護保険サービスの活用、施設入所の検討など、早めの対策で介護負担を軽減可能
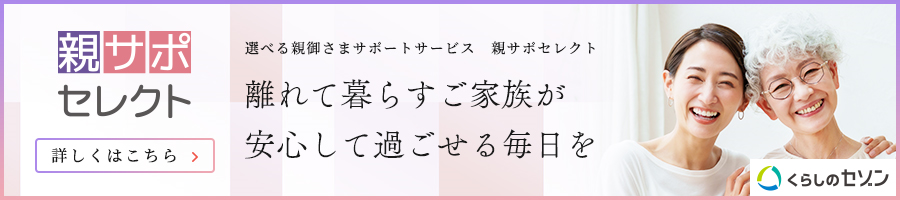

「介護で人生が台無しになる!」在宅介護の現状

令和2年の段階で、要介護(要支援)認定者は計682万人に達しており、その数は年々増加の一途を辿っています。医療の進歩により、入院日数は短縮され、患者は早期に自宅での療養生活へと移行するようになりました。従来の「治す医療」から、病を抱えながら生活する人を支援する「支える医療」へと、医療のあり方自体が大きく変化してきているのです。
一方で、核家族化の進行や女性の就業増加、世帯人数の減少、三世代世帯の減少などにより、家族による介護力は著しく低下しています。介護と仕事の両立支援として、育児・介護休業法により介護休暇制度が整備されていますが、実際の取得割合は低く、働き盛りの世代が介護を理由に離職を余儀なくされるケースも増加しています。
特に深刻なのが、介護者自身の心身の健康状態です。家族介護者へのアンケート調査からは、慢性的な疲労や睡眠不足、うつ症状などを訴える声が数多く寄せられています。介護の長期化により、介護者の生活や人生設計そのものが大きく影響を受けることも珍しくありません。
このような状況を踏まえ、各自治体でも家族介護者支援の取り組みを重要視し始めています。介護者が孤立することなく、適切なサポートを受けられる体制づくりが進められているのです。介護を理由に人生を諦めることがないよう、早い段階から利用可能な支援制度やサービスについて知っておくことが重要です。
参考:厚生労働省 老健局「介護分野の最近の動向について」
厚生労働省「市町村・地域包括支援センターによる家族介護者支援マニュアル」
「介護で人生が台無しになる!」と感じる原因

「介護で人生が台無しになる」と感じる背景には、介護者が抱えるさまざまな負担があります。特に在宅介護では、時間的・身体的・精神的な負担が重なり、介護者の生活を大きく制限してしまいます。
以下では、具体的にどのような負担があるのか解説します。
日中目が離せない
介護の時間的な拘束は、要介護度が上がるにつれて顕著になっていきます。
厚生労働省の調査によると、要介護2までは「必要なときに手を貸す程度」が半数以上を占めていましたが、要介護3になると「ほとんど終日」の介護が必要となるケースが32.5%と最も多くなります。
さらに要介護5では、半数以上が「ほとんど終日」の介護を必要とする状態となり、介護者の自由な時間はほとんど確保できない状況となってしまいます。
体力的な負担が大きい
在宅介護における身体的負担は、日常生活のさまざまな場面で発生します。
起き上がりや着替え、立ち上がり、ベッドから車いすへの移動、歩行の介助、入浴や清拭、寝返り、排せつの介助など、一日を通して体力を使う介助が必要となります。さらに、認知症などで徘徊のリスクがある場合は、夜間も目が離せず、十分な睡眠時間を確保することができません。
このような状況が続くと、介護者は慢性的な疲労状態に陥りやすくなります。特に夜間の体位変換やトイレ介助などで睡眠が中断されると、日中の疲労も十分に回復できないまま、さらなる体力の消耗を強いられることになります。これは腰痛や膝痛など、介護者自身の健康状態の悪化にもつながりかねません。
精神的なストレスも強い
認知症の症状がある場合、コミュニケーションの困難さや予期せぬ行動への対応に追われ、精神的な負担は一層増大します。暴言や暴力が伴う場合もあり、介護者は常に緊張状態にさらされることになります。
また、介護期間は平均して6~7年とされていますが、10年以上続くケースも少なくありません。「いつまで続くのかわからない」という不安は、介護者の心理的負担を大きく増幅させます。さらに、介護の悩みを相談できる相手がいない場合、孤立感や無力感に苛まれることも。
経済面での不安も大きな要因です。介護サービスの利用には一定の費用負担が必要となり、特に長期化する場合は家計への影響も無視できません。介護のために仕事を調整したり離職したりすることで、収入が減少するケースもあり、将来への不安はさらに深刻なものとなります。
介護で人生を台無しにしないために!限界を見極めるポイント

在宅介護の限界は、介護者と要介護者の双方にとってさまざまな形で現れます。早めに限界のサインに気づき、適切な対応を取ることが、介護で人生を台無しにしないための重要なポイントです。
以下では、在宅介護の限界を見極める3つの具体的なケースを解説します。
家族介護者の心身に影響がでた
介護は介護者の心身に大きな負担をかけます。腰痛や関節痛などの身体的な不調や、睡眠不足による慢性的な疲労は、介護の質を低下させるだけでなく、介護者自身の健康を著しく損なう可能性があります。特に要介護度が3以上になると、排泄や入浴などの身体介助が増え、体力的な負担は一層大きくなります。
また、認知症の進行により徘徊が始まると、昼夜を問わず目が離せない状況となり、介護者は十分な休息を取ることができません。このような状況が続くと、不眠やイライラ、抑うつ症状などの精神的不調を引き起こし、介護うつに発展するリスクも高まります。
介護者の心身の健康が損なわれることは、結果として介護の質の低下にもつながり、共倒れの危険性も出てきます。
自宅での生活が難しくなった
高齢になると身体機能が低下し、転倒のリスクが高まります。特に住宅内の段差は大きな障害となり、手すりを設置しても階段の昇降が困難になるケースが増えていきます。アパートやマンションの2階以上に住んでいる場合、この問題は更に深刻です。
大腿骨骨折などで入院した後は、それまでの住環境での生活継続が難しくなることも多くあります。エレベーターがない建物では、デイサービスなどの送迎にも時間や人手がかかり過ぎて、サービスの利用自体を断られる可能性もあります。
住環境の問題は、要介護者の自立した生活を阻害するだけでなく、介護サービスの利用機会も制限してしまう重大な課題となります。
医療ケアが必要になった
医療的なケアが必要になることは、在宅介護の大きな転換点となります。中心静脈栄養や胃ろう、痰吸引などの医療処置が必要になると、専門的な知識と技術が求められ、家族だけでの対応は極めて困難になります。
訪問看護などの在宅医療サービスを利用することで、在宅生活を継続することは可能です。しかし、日常的なケアの家族負担は依然として大きく、働いている介護者は介護離職を検討せざるを得ない状況に追い込まれることも少なくありません。
医療ニーズの増加は、経済的負担も含めて家族全体の生活に大きな影響を及ぼすため、早い段階での施設入所の検討や、介護・医療の複合的なサービス利用を考える必要があります。
在宅介護に限界を感じたらすべきこと

在宅介護に限界を感じたとき、一人で抱え込まず早めに対策を講じることが重要です。以下では、具体的な解決策をご紹介します。
専門家に相談する
介護に関する問題を専門家に相談することで、解決策を見つけるきっかけになります。具体的には、地域包括支援センターやケアマネジャー、主治医といった専門家が重要な役割を果たします。
地域包括支援センター
地域包括支援センターは、高齢者を地域ぐるみで支えるための中核機関です。主任ケアマネジャー、社会福祉士、看護師・保健師といった専門職が連携して、介護から生活全般まで幅広い相談に対応します。介護保険の申請手続きから、介護サービスの紹介、金銭管理の支援まで、ワンストップで支援を受けることができます。
ケアマネジャー
ケアマネジャーは介護支援の専門家として、利用者の状況に合わせた最適なケアプランを作成します。介護保険サービスの調整だけでなく、施設入所に関する相談にも応じてくれます。
定期的な訪問を通じて状況を把握し、必要に応じてプランの見直しも行います。
主治医
特に認知症の場合は、主治医への相談が重要です。認知症の進行状況を定期的にチェックし、症状に応じた治療や投薬を行うことで、介護負担の軽減につながる可能性があります。また、医療面からの客観的な判断は、今後の介護方針を決める上でも重要な指針となります。
周囲の人に相談して協力を仰ぐ
介護は一人で抱え込むものではありません。家族や親族、職場の同僚など、周囲の人々に状況を説明し、協力を得ることが大切です。
特に仕事との両立には、職場の理解が不可欠です。介護休暇や介護休業制度を活用することで、介護離職を防ぎながら必要な介護時間を確保することができます。
介護保険サービスを活用する
要支援・要介護認定を受けることで、さまざまな介護保険サービスを利用することができます。
デイサービスや訪問介護、短期入所生活介護(ショートステイ)など、状況に応じて必要なサービスを組み合わせることで、介護の負担を軽減することができます。費用は原則1~3割の自己負担で利用できます。
施設入所も検討する
施設入所は決してマイナスの選択肢ではありません。24時間体制の専門的なケアや、緊急時の迅速な対応など、在宅では得られない安心感があります。
費用面で不安がある場合は、特別養護老人ホームなどの公的施設や、さまざまな料金体系の民間施設について、ケアマネジャーに相談するとよいでしょう。
民間の介護サービスを活用する
介護保険外のサービスも、生活の質を向上させる重要な選択肢です。家事代行や配食サービス、外出支援など、介護保険では対応できない細かなニーズにも対応できます。
これらのサービスを上手に組み合わせることで、介護者の負担を軽減しながら、要介護者の生活の質も向上させることができます。
介護に悩むご家族に「親サポセレクト」がおすすめ

デイケアや通所リハビリなど、介護保険サービスを利用していても、在宅時の見守りや介護支援に不安を感じる方は少なくありません。そんな時におすすめなのは、セゾンカードでおなじみのクレディセゾンのグループ会社「くらしのセゾン」が提供する「親サポセレクト」(選べる親御さまサポートサービス)です。
センサーによる見守りシステムや緊急時の専任スタッフ駆けつけサービスで、親の日常を見守ってくれます。また、通院や買い物の付き添い代行、掃除・洗濯などの家事代行も利用できるため、一緒にくらしていない親の生活にかかる負担を軽減できます。さらに、入院時の準備や手続きのサポート、施設入居時の荷造り・引っ越しまで、状況に応じて依頼することができます。
介護の状況は一人ひとり異なるため、必要な時に必要なサービスを選べる柔軟な料金体系であることも「親サポセレクト」の特徴の一つです。介護の不安や負担を軽減したい方は、ぜひ問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。
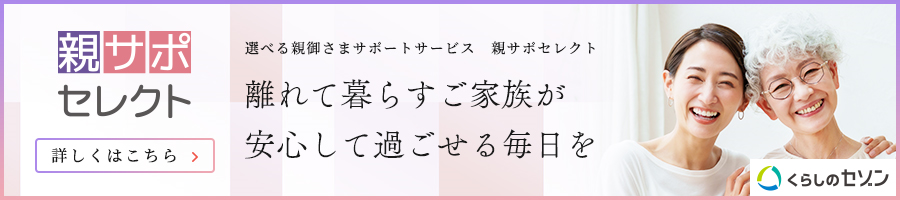

おわりに
介護に伴う「自己犠牲」は、介護者と要介護者の双方を不幸にする結果となりかねません。介護への献身的な思いは大切ですが、一人で抱え込まず、早めに限界を見極め、適切な支援を受けることが重要です。
専門家への相談や介護サービスの活用、施設入所の検討など、状況に応じた対策を講じることで、介護者も要介護者も、より良い生活を送ることができます。介護を理由に人生を諦めることなく、自分らしい生活と両立させながら、持続可能な介護を実現していくことが大切です。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。