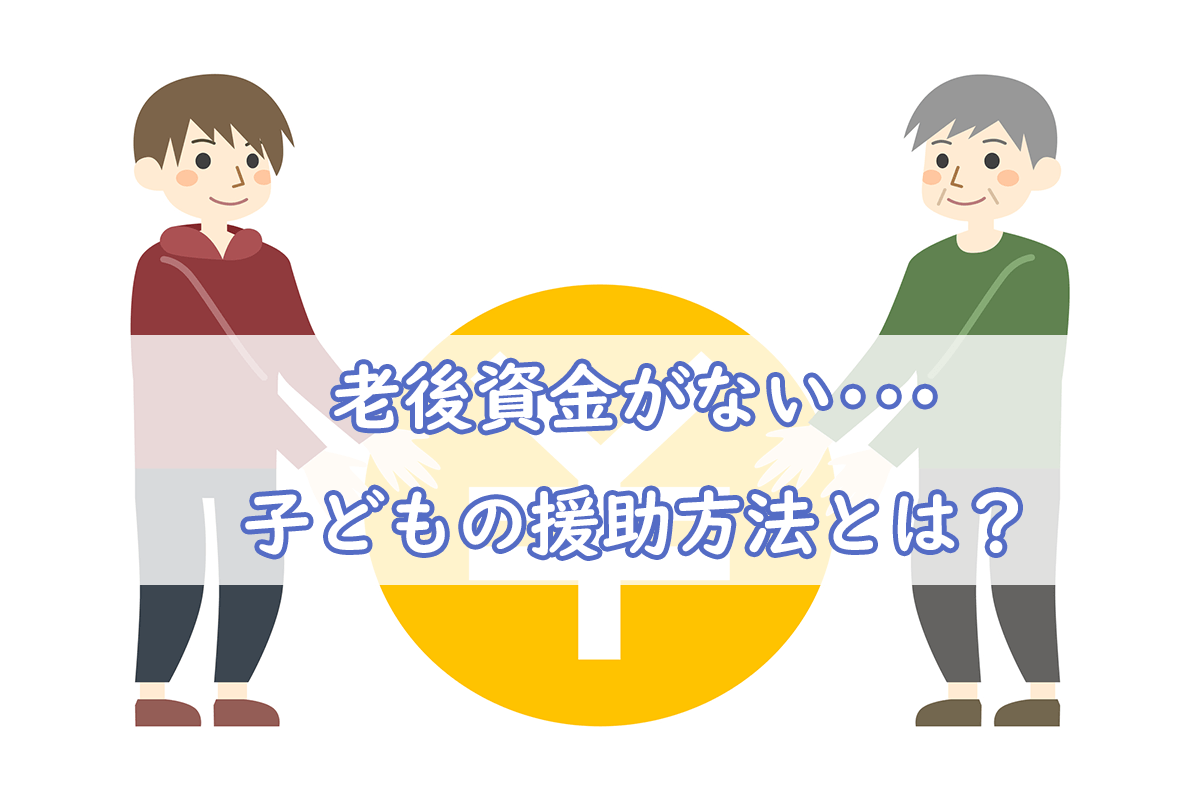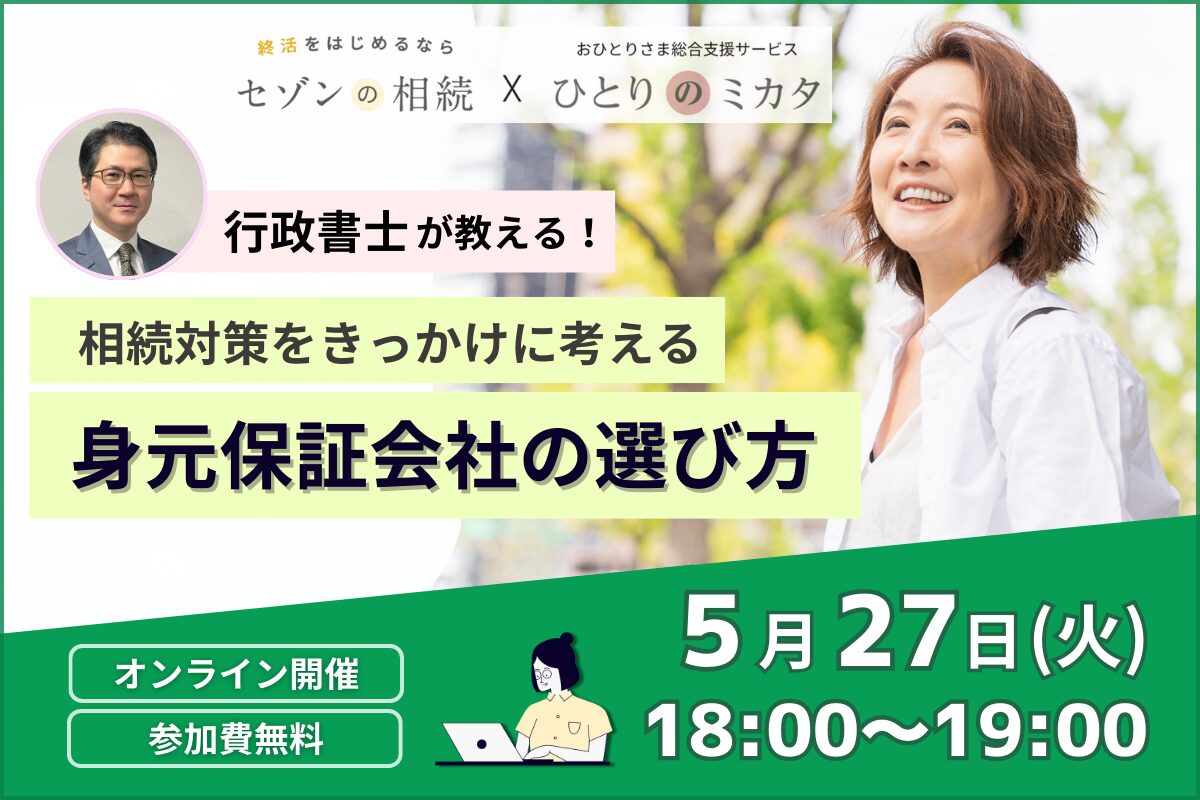親の介護に向き合う中で、「自分の人生が犠牲になっているのでは…」と不安を抱える方も多いのではないでしょうか。家庭や仕事、そして自身の生活を両立させることは決して簡単ではありません。しかし、適切な支援制度を利用し、自分の負担をコントロールすることができれば、無理なく介護と生活のバランスを取ることが可能です。本記事では、親の介護と自身の生活を両立させるための具体的なコツや、活用できる国や職場の介護支援制度、さらに無理をせず介護を続けるための心構えを詳しく解説します。
- 介護と生活を両立するには、自分の限界を認識し適切なサポートを活用することが大切
- 国や職場の介護支援制度を理解し利用することで負担を軽減できる
- 無理をせずに介護するためには、家族や周囲の人との協力体制が重要
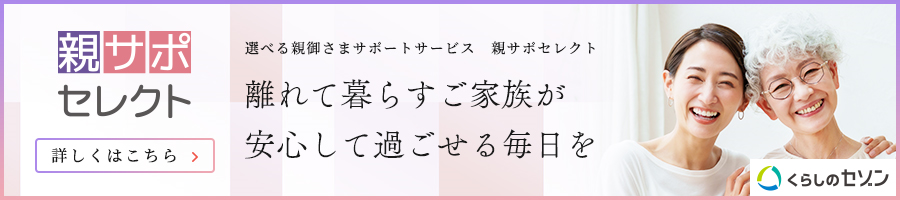

親の面倒・介護と自分の人生を両立するには

介護離職者は年間約10万人いると言われており、多くの人が「親の介護」と「自分の生活」の両立に悩んでいます。親の介護は突然始まることも多く、精神的にも時間的にも余裕がなくなりがちです。
しかし、一人で抱え込まず、適切な支援を受けることで、介護と自分の生活を両立させることは可能です。
国や勤務先の介護支援制度・支援体制を確認する
政府は「介護離職ゼロ」を目指し、仕事と介護の両立支援のためのさまざまな制度を整備しています。例えば、介護休業制度では、対象家族1人につき通算93日まで休業を取得でき、その期間中は休業前賃金の67%が介護休業給付金として支給されます。
また、短時間勤務制度やフレックスタイム制度、時差出勤制度なども利用可能です。これらの制度は、介護が必要な期間中、柔軟な働き方を実現するために活用できます。まずは、自分の勤務先の就業規則を確認し、どのような支援制度があるか把握しておくことが重要です。
家族の状況を職場や近所の人に伝えておく
介護と仕事の両立には、周囲の理解と協力が不可欠です。介護は誰もが直面する可能性がある問題なので、日頃から同僚や上司に自分の家族の状況を伝えておくことで、いざというときに「お互いさま」という気持ちから協力を得やすくなります。
特に、遠距離介護の場合は、親の近所に住む人々との良好な関係づくりが重要です。日頃からの付き合いを通じて、緊急時の連絡や見守りなど、さまざまな形での協力を得られる可能性が広がります。
「自分でできる範囲」「支援を受けること」を考える
介護の専門職の間では「自分の親の介護はするな」という言葉が伝えられています。これは決して親の介護を放棄するという意味ではなく、介護者と要介護者の双方の健康と尊厳を守るための重要な考え方です。
介護はゴールが見えにくく、プライベートの時間をすべて費やしてしまうと、精神的にも肉体的にも疲弊してしまう可能性があります。そうなると介護放棄といったトラブルにも発展しかねません。
むしろ「介護はプロの手で」と考えて、休みの日こそ介護サービスや介護保険外サービスを積極的に活用しましょう。
国や勤務先の介護支援制度・支援体制

介護離職をなくすため、国はさまざまな支援制度を整備しています。介護休業や短時間勤務など、仕事と介護の両立を支援する制度を知り、活用することで、自分らしい介護との向き合い方を見つけることができます。
以下、主な支援制度をご紹介します。
介護休業制度
介護が必要な家族を介護するために取得できる休業制度です。
【主な特徴】
- 対象家族1人につき通算93日まで取得可能
- 3回まで分割して取得できる
- 休業中は賃金の67%が介護休業給付金として支給
- 申請は休業開始2週間前までに
- 介護保険制度の要介護認定を受けていなくても取得可能
介護休暇制度
介護が必要な家族の通院の付き添いや介護サービスの手続きなどに利用できる休暇制度です。
【制度の概要】
- 対象家族1人の場合:年5日まで
- 対象家族2人以上の場合:年10日まで
- 時間単位での取得が可能
- 介護休業や年次有給休暇とは別に取得可能
- 給与支給の有無は会社の規定による
短時間勤務等の制度
事業主は以下のいずれかの制度を設けることが義務付けられています。
【選択可能な制度】
- 短時間勤務制度
- フレックスタイム制度
- 時差出勤の制度
- 介護費用の助成措置
【利用について】
- 対象家族1人につき、3年以上の期間で2回以上利用可能
- 介護休業とは別に利用できる
所定外労働の制限
就業規則などで定められた勤務時間を超える労働(残業)を免除される制度です。
【制度の詳細】
- 介護終了まで利用可能
- 1回の申請で1ヶ月以上1年以内
- 申請回数に制限なし
- 事業の正常な運営を妨げる場合、事業主は請求を拒める
時間外労働の制限
法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働を制限できる制度です。
【制限の内容】
- 1ヶ月24時間まで
- 1年150時間まで
- 1回の申請で1ヶ月以上1年以内
- 申請回数に制限なし
深夜業の制限
午後10時から午前5時までの深夜労働を制限できる制度です。
【制度のポイント】
- 1回の申請で1ヶ月以上6ヶ月以内
- 申請回数に制限なし
- 介護ができる16歳以上の同居家族がいる場合は対象外
- 事業の正常な運営を妨げる場合、事業主は請求を拒める
介護保険制度
介護を社会全体で支える仕組みとして2000年に創設された制度です。
【対象者と利用可能なサービス】
- 65歳以上:原因を問わず利用可能
- 40-64歳:特定疾病が原因の場合に利用可能
- 訪問介護、訪問看護、通所介護(デイサービス)など多様なサービスを提供
- 費用の1-3割の自己負担で利用可能
地域包括ケアシステム
住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるよう、以下のサービスを一体的に提供する仕組みです。
【システムの特徴】
- 医療・介護・予防・住まい・生活支援のサービスを包括的に提供
- 24時間365日の在宅医療・介護サービスの提供
- 地域包括支援センターでの無料相談
- 地域の実情に応じた柔軟なサービス提供
介護に無理は禁物!負担が大きくなりやすいケースは?

介護は身体的にも精神的にも大きな負担を伴う場合があります。特に以下のような介護疲れや介護うつにつながりやすいケースでは、負担が増大しやすく、介護者自身の生活や健康にも影響を及ぼす可能性があります。早めに対策を講じることが、持続可能な介護を実現するポイントとなります。
被介護者の症状が重いケース
要介護度が高い場合や認知症の症状がある場合は、介護の難度が格段に上がります。特に認知症の介護には専門的な知識や対応が必要となり、介護者の精神的・身体的負担は非常に大きくなります。
認知症の方の場合、24時間の見守りが必要になったり、予期せぬ行動への対応が求められたりします。また、コミュニケーションが難しくなり、夜間の介護が必要になることもあります。
このような場合は、デイサービスやショートステイなどの介護の専門家による支援を積極的に活用すると良いでしょう。
老老介護のケース
高齢者が高齢者を介護する「老老介護」のケースでは、介護者自身の体力的な限界から、さらに負担が増大します。同居の主な介護者の約30%が75歳以上となっており、介護者自身の体力的な限界や、外出機会の減少による認知症リスクの上昇が懸念されます。また、家事と介護の両立が困難になったり、緊急時の対応が難しくなったりすることもあります。
介護の悩みを他人に相談できないケース
介護に時間を取られることで、家族や友人、職場の同僚との付き合いが減少し、相談できる相手を失ってしまうことがあります。また、「介護は家族でするもの」という意識から、他人に相談することをためらってしまう方も少なくありません。
実際のデータでは、介護離職経験者のうち、勤務先に介護の相談をした方の割合は約25%に留まっています。周囲に相談できない状況は、介護者の精神的な負担をさらに増大させる要因となります。
介護により自分の健康状態が悪くなったケース
介護による負担が重なると、介護者自身の健康状態が悪化するリスクが高まります。身体面では腰痛や膝の痛み、慢性的な疲労、睡眠不足といった症状が現れやすくなります。また精神面では、強いストレスや不安感の増大、抑うつ状態、意欲の低下といった症状が出ることもあります。
これらの症状を放置すると、最悪の場合「介護うつ」や「介護疲れ」といった深刻な状態に発展する可能性があります。自身の健康状態の変化に気づいたら、早めに医療機関を受診したり、介護サービスの利用を検討したりするなど、適切な対策を講じることが重要です。
介護に負担を感じたらライフステージに合ったサービスを選べる「親サポセレクト」がおすすめ!

介護の負担で自分の時間が持てない方々にとって、セゾンカードでおなじみのクレディセゾンのグループ会社、くらしのセゾンが提供する選べる親御さまサポートサービス「親サポセレクト」は、心強い味方となります。このサービスは、親のライフステージに応じて必要なサポートを柔軟に選択できる会員制プランとして注目を集めています。
「親サポセレクト」の特徴は、親の状況変化に合わせてサービスを組み合わせることができる点にあります。元気な時期からの見守りサービスはもちろん、通院や買い物の付き添い、さらには緊急時のご家族サポートまで、包括的な支援体制が整っています。
また、日常生活のサポートも充実しています。高齢になると感じる生活の負担を和らげるため、外出時の同行から掃除、洗濯、食事の準備まで、多岐にわたる家事代行サービスを提供しています。
安全面での配慮も万全です。見守りサポートでは、自宅に専用の見守り機器を設置することにより、在宅時の親の様子を見守ります。簡単な操作で通報でき、体調不良などの異変時には専任スタッフが迅速に駆けつけ対応します。この仕組みにより、親と離れて暮らす子どもの不安を解消し、自身の生活との両立をスムーズにすることができます。
介護と自分の生活の両立に悩む方々にとって、適切なサポートを受けることは、大きな支えとなるでしょう。介護の負担が重く感じたら、一人で抱え込まず、選べる親御さまサポートサービス「親サポセレクト」の無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。
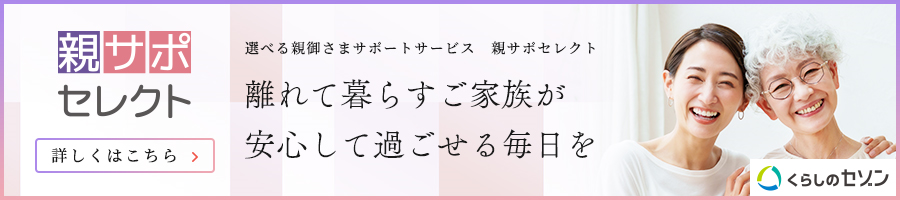

おわりに
介護と自分の生活の両立は、適切な支援制度の活用と周囲との協力関係の構築によって実現できます。介護は誰もが直面する可能性がある課題であり、一人で抱え込まず、必要な支援を受けることが重要です。介護休業制度や地域包括ケアシステムなどの支援制度を活用し、専門家のサポートを受けることで、介護者自身の健康と生活を守りながら、持続可能な介護を実現することができます。介護に直面したら、まずは地域包括支援センターに相談し、自分に合った支援の形を見つけることから始めましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。