親が入院した際、仕事との両立に悩む人は少なくありません。突然の入院に対応するためには、休暇制度や給付金の活用を検討し、適切な手続きを進めることが大切です。また、入院費用や介護負担の軽減策についても事前に把握しておくことで、精神的・経済的な負担を和らげることができます。
本記事では、入院費用の相場や高額療養費制度、親の入院に伴い仕事を休む際のポイントについて詳しく解説します。また、会社で利用できる休暇制度や給付金、介護保険外サービスの活用方法についても紹介します。親の入院に直面したときに冷静に対応できるよう、ぜひ参考にしてください。
- 親の入院費用は平均19.8万円で、平均入院日数は17.7日、高齢になるほど入院期間が長期化する傾向にある
- 親の入院時には高額療養費制度や傷病手当金などの公的支援制度を活用でき、経済的負担を軽減できる
- 仕事を休む際は速やかに上司に報告し、業務の引き継ぎや休暇の期間を具体的に伝える必要がある
- 会社には介護休暇(年5日)や介護休業(最大93日)という制度があり、休業中は給付金も受け取れる
入院費用の相場と日数

親が入院した際の費用は、治療内容や入院期間によって大きく変わってきます。まずは、入院時にかかる費用の種類と相場を把握しておきましょう。
入院にかかる主な費用は以下の通りです。治療費には病気やケガの治療費用のほか、手術費用やリハビリ代も含まれます。また、入院基本料には診察や看護の費用、室料、寝具代なども含まれています。さらに、食事代や差額ベッド代なども必要です。
医療費の自己負担割合は年齢によって異なり、70歳未満の場合は3割、70〜74歳は2割、75歳以上は1割となっています。ただし、70歳以上でも現役並みの所得がある方は3割の負担となります。
生命保険文化センターの調査によると、入院時の自己負担費用の平均は約19.8万円で、平均入院日数は17.7日となっています。自己負担額の内訳をみると、5〜10万円未満が26.5%、10〜20万円未満が33.7%を占めており、20万円以下が全体の7割を占めています。一方で、100万円以上の高額な費用がかかったケースも3%存在します。
病室については、4床以下の病室を利用する場合は差額ベッド代が必要です。個室や2人部屋など、病室の区分により料金は異なります。また、先進医療費は厚生労働省が認めている高度な医療技術による治療や手術に対する費用で、公的医療保険の適用対象外となるため、数百万円かかることもあります。
その他にも、病院への交通費や入院中の差し入れなどの消耗品費も必要となりますので、予め余裕をもった準備が必要です。
親が入院した場合に備えて準備すること
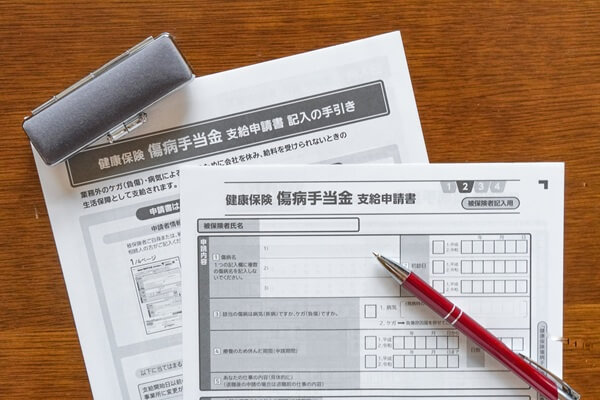
親の入院による医療費の負担や、介護の必要性が生じた場合に備えて、利用できる制度を知っておくことが重要です。
ここでは、高額な医療費への支援制度と、仕事を休んだ際の所得保障について解説します。
高額療養費制度
医療費が高額になった場合でも、経済的な負担を軽減できる制度があります。高額療養費制度は、1ヶ月(1日から月末まで)の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に、その超過分が払い戻される仕組みです。
入院が2月にまたがる場合は、それぞれの月ごとに分けて自己負担額を計算し、申請する必要があります。例えば、1月10日から2月10日まで入院した場合、1月分と2月分を分けて申請することになります。
自己負担限度額は年齢や所得によって異なります。
70歳未満の場合、標準報酬月額83万円以上の方は252,600円+(総医療費-842,000円)×1%、標準報酬月額53万~79万円の方は167,400円+(総医療費-558,000円)×1%となっています。
70歳以上75歳未満の一般所得者の場合は、外来(個人)で18,000円、外来・入院(世帯)で57,600円が自己負担限度額です。
医療費が高額になることが事前に分かっている場合は、「限度額適用認定証」の利用がおすすめです。この認定証を医療機関に提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
傷病手当金
傷病手当金は、健康保険に加入している方が病気やケガで働けなくなったときに保障される制度です。支給を受けるには、次の4つの条件をすべて満たす必要があります。
まず、業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であることが条件です。次に、仕事に就くことができない状態であることが求められます。さらに、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったことが必要です。最後に、休業した期間について給与の支払いがないことが条件となります。
ただし、傷病手当金には支給が停止されるケースもあります。例えば、出産手当金を受け取る場合や、資格喪失後に老齢(退職)年金を受けられる場合、同じ病気やケガで障害厚生年金を受けることになった場合などは、傷病手当金は支給されないか、または調整されることがあります。
親の入院に伴い仕事を休む場合のポイント

親の入院により仕事を休む必要が生じた場合、適切な報告と業務の引き継ぎが重要です。スムーズな休暇取得のために、誰に、どのように連絡するべきか、具体的な方法を解説します。
仕事を休む場合の相談先
直属の上司には、まず最優先で相談する必要があります。従業員の少ない会社やシフト制の職場では、他の従業員に協力を仰ぐことになるため、休暇の頻度や期間を詳しく伝えましょう。
また、業務との兼ね合いや自分が不在時の対応について具体的に相談し、業務に支障が出ないよう配慮することが大切です。テレワークが可能な場合は、その旨を上司に打診するのも一つの選択肢となります。
連絡方法・タイミング
親が緊急搬送されたり、入院中に危篤になったりした際は、速やかに会社へ報告します。基本的には電話での連絡が望ましいものの、深夜や早朝の場合はメールでの一報も認められています。
上司と直接話せない場合は、同僚に伝えてもらい、後日改めて上司に詳しい状況を報告することも可能です。時間の経過とともに状況が整理されたり、事態が落ち着いたりした場合は、追加で報告することを忘れないようにしましょう。
伝える内容と伝えなくていい内容
会社への連絡では、「誰が」入院することになったのか、休暇がどのくらい必要になるのかを明確に伝えることが重要です。業務の引き継ぎに関する具体的な提案や、テレワークが可能な場合は就業可能な時間帯についても伝えましょう。
一方で、病状や治療の詳細など、個人情報に関わる内容は伝える必要はありません。例えば、次のような文面が適切です。
「申し訳ありませんが、母が倒れて緊急入院することになりました。容体は不明ですが、高齢の父に代わり対応できる者が私しかおりません。つきましては、本日と明日はお休みをいただき、状況が分かり次第、ご連絡させていただきます。なお、本日予定していた△△社との打ち合わせは××さんに引き継ぎたいのですが、よろしいでしょうか」
このように、必要最小限の情報を簡潔に伝えることで、上司も状況を理解しやすく、適切な対応が可能となります。
利用できる会社の休暇制度と給付金

親の入院により介護が必要となった場合、会社にはさまざまな休暇制度が用意されています。
ここでは、介護のための休暇制度と、休業中の所得を補償する給付金制度について説明します。
介護休暇
介護休暇は、要介護状態にある家族の介護のために取得できる休暇制度です。対象となる家族は、親、祖父母、配偶者、義父母、兄弟姉妹、子、孫となっています。
この制度では、家族1人に対して年間5日まで休暇を取得することができます。また、時間単位での取得も可能となっているため、通院の付き添いや介護の手続きなど、短時間の用事にも対応できます。手続きは口頭での申し出でも可能で、書類でのやりとりは必須ではないため、急な入院時にも活用しやすい制度といえます。
介護休業
介護休業は、家族が要介護状態となり、継続して2週間以上の期間にわたり介護が必要になった場合に利用できる休業制度です。職場に席を残したまま、介護に専念することができます。
対象家族1人につき3回まで、通算93日まで利用可能です。休業を取得する際は、休業開始予定日の2週間前までに書面等で事業主へ申し出る必要があります。また、休業終了予定日は、あらかじめ決めていた予定日の2週間前までに申し出れば、1回に限り予定日を延期することもできます。
介護給付金
介護給付金は、家族の介護のために仕事を休む場合に、経済的な支援を提供する制度です。休業開始時の賃金の67%が支給され、要介護状態にある家族1人につき、通算で最大93日間まで受給することができます。この期間は3回まで分割して取得することが可能です。
休業期間には、実際の勤務日だけでなく、土日や祝日も含まれます。給付金の申請は会社を通じてハローワークに行う必要があるため、会社の担当部門に相談することが重要です。なお、給付金は休業終了後に職場復帰をする方が対象となり、受給には復職後の申請手続きが必要となります。
介護保険外サービスを利用する方法もある

介護保険サービスには利用条件や提供できるサービスに制限があります。そこで、介護保険では対応できない部分を補完する介護保険外サービスの活用を検討してみましょう。
介護保険外サービスでできること
介護保険サービスでは、生活援助として掃除や洗濯、寝具の整え、衣服の整理と補修、一般的な調理、買い物、薬の受け取りなどが提供可能です。身体介護では、食事介助、排せつ介助、入浴介助、衣服の着脱介助、通院・外出介助、就寝・起床介助などが含まれます。
一方、介護保険外サービスでは、散歩や趣味のための外出介助、金銭管理や契約書の記入の手伝い、同居家族の援助となる家事全般、正月などの特別な調理、大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスかけ、家具の移動や修繕といったサービスが利用できます。さらに、草むしりや花木の水やり、ペットの世話、車の洗車や清掃、来客対応なども提供可能となっています。
介護保険外サービスの種類と費用相場
各地域でさまざまな事業者が介護保険外サービスを提供しています。市区町村が実施する高齢者在宅サービスでは、おむつサービス(月額6,000~10,000円)や訪問理美容サービス(1回500~2,500円)、配食サービス(1食500円前後)などが用意されています。
介護予防・日常生活支援総合事業では、訪問による生活援助サービス(1回60分まで200~250円)や、通所による活動援助サービス(1回300~400円程度)が提供されています。
介護サービス事業者による保険外サービスでは、家事全般や認知症の見守りなどが利用可能で、料金は1時間あたり2,000~4,000円程度となっています。デイサービスでの宿泊(お泊りデイ)は、1泊4,000~8,000円前後です。
社会福祉協議会の支援サービスは、家事支援が1時間800円程度、介護援助が1時間1,000円程度で利用できます。シルバー人材センターの支援サービスは、1時間あたり1,067円からとなっています。
民間企業のサービスは、配食(1食500~700円)や家事代行(1時間3,000円前後)など、豊富なメニューが用意されています。費用は他のサービスと比べて高めですが、緊急時の対応や柔軟なサービス提供が可能という特徴があります。
おわりに
親の入院による仕事への影響は、誰もが直面する可能性のある重要な課題です。入院費用や各種制度の理解、適切な会社への報告、介護保険外サービスの活用など、さまざまな選択肢を知ることで、より良い対応が可能となります。特に会社の休暇制度や給付金制度を活用し、必要に応じて外部サービスを利用することで、仕事と親の看病を無理なく両立することができるでしょう。事前に準備をし、周囲のサポートを得ながら、この困難な状況を乗り越えていくことが大切です。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。






























