入院時に病院に提出する入院申込書には、ほぼ例外なく、入院費用の支払いを担保してくれる連帯保証人を記載する欄があります。また、身元引受人(緊急連絡先)の記載を求められる場合もあります。
しかし、少子高齢化が進み、身寄りのない高齢者が増えている中、入院時の連帯保証人や身元引受人(緊急連絡先)が容易に確保できない方が増えています。
入院時の連帯保証人や身元引受人(緊急連絡先)が確保できない方は、入院することはできないのでしょうか?今回は、この問題について、掘り下げて考えてみたいと思います。
入院時の連帯保証人の条件
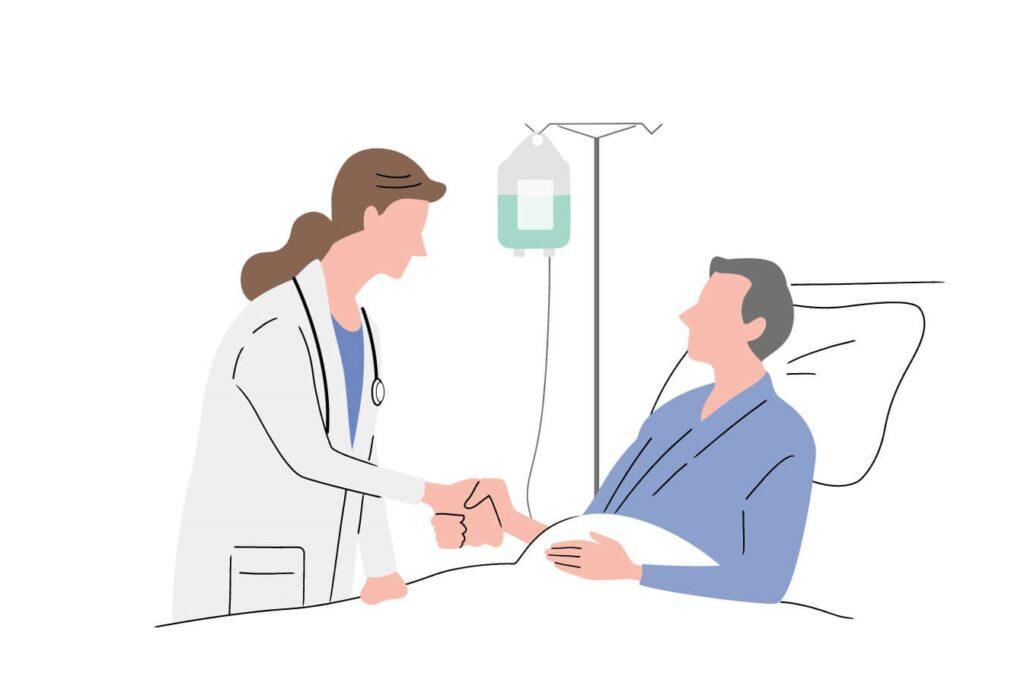
多くの病院では、入院時の連帯保証人として、「(入院患者と)独立した生計を営む成年者」を求めています。この条件に即して考えると、子どものいないご夫婦の場合、夫の入院時に妻を連帯保証人とすることはできません。
夫の兄弟姉妹や甥・姪などの親族の他、場合によっては友人などに頼らざるを得なくなってしまいます。
「私には充分な資力がある」と主張しても取り合ってもらえず、謝礼の金品を持参のうえ、親族や友人にお願いする方も多いようです。
「筆跡を変えて、適当に知人の名前を書いておけば問題ないでしょう?」という方がいらっしゃるかもしれませんが、これは立派な私文書偽造となってしまいます。
実際、このような虚偽の記載が行われた結果、病院が連帯保証人に請求した際に回収できなかったという事例もあるようです。
連帯保証人の依頼方法
連帯保証人を依頼する際は、以下の手順を踏むことをおすすめします。
- 適切な人選:まずは、親族や親しい友人の中から、経済的に安定しており、あなたの状況を理解してくれそうな方を選びます。
- 事前の準備:依頼する前に、入院の詳細(期間、治療内容、予想される費用など)を整理しておきましょう。また、あなたの支払い能力や保険の適用範囲についても明確にしておくことが重要です。
- 丁寧な依頼:直接会って話すのが理想的ですが、難しい場合は電話や手紙で丁寧に依頼します。突然の依頼にならないよう、事前に都合を確認しておくと良いでしょう。
- 役割と責任の説明:連帯保証人の役割と責任について明確に説明します。特に、あくまでも「万が一の際の保証」であることを強調し、通常はあなたが全ての責任を負うことを伝えます。
- 時間的余裕:相手に考える時間を与えましょう。即答を求めるのではなく、「○日までに返事をいただければ助かります」といった形で期限を設定するのが良いでしょう。
- 感謝の気持ちを伝える:承諾してくれた場合は、心からの感謝の気持ちを伝えましょう。また、入院中や退院後も適宜状況報告をすることを約束し、信頼関係を維持することが大切です。
- 断られた場合の対応:もし断られても、相手を責めたりせず、理解を示しましょう。その上で、別の候補者に依頼するか、病院と相談して代替案を探ることを検討します。
連帯保証人の依頼は決して簡単なことではありませんが、誠実な態度で丁寧に説明することが重要です。以下に、実際の依頼文の例を示します。
【連帯保証人依頼の文例】
突然のお願いで大変恐縮ですが、私は来月○日より△△病院に入院することになりました。
つきましては、入院時に必要となる連帯保証人をお引き受けいただけないでしょうか。
■入院予定期間:○月○日~○月○日(約○週間)
■入院の理由:○○の治療のため
■病院名:△△病院
■概算医療費:○○円程度(保険適用後)
連帯保証人の主な役割は以下の通りです:
1. 入院費用の支払い保証
2. 緊急時の連絡先
私としては、できる限り自己責任で対応いたしますが、万が一の際にはご協力をお願いしたく存じます。
ご多忙中、誠に恐縮ではございますが、ご検討いただけますと幸いです。
敬具
(あなたの名前)
医師法第19条第1項と病院側の柔軟な対応事例

医師法第19条第1項には、「診療に従事する医師は、診療治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定められており、連帯保証人等を確保できないことのみを理由に、患者の入院を拒否することはできないとされています。
最近では、「一定額の入院保証金を病院に預託できる場合は、連帯保証人を免除」「入院費用の支払をクレジットカード払いとし、入院時にカード番号を登録することで、連帯保証人を免除」「病院の提携保証会社と契約すれば、連帯保証人を免除」といった柔軟な対応を行っている病院も増えてきています。
また、病院で入院支援を行う医療ソーシャルワーカーの皆さんにお話を伺うと、口をそろえて、「私たちの仕事は、ご入院をお断りすることではない。何とかご入院いただけるよう、折り合いをつけることです」とおっしゃいます。
連帯保証人が確保できず困った場合は、医師法第19条第1項を前提に、医療ソーシャルワーカーさんや医事課長さんなどに「柔軟な対応は難しいのでしょうか?」とご相談されてみるのも方法のひとつです。
病院との交渉方法
連帯保証人が見つからない場合、病院との交渉が必要になります。以下の手順で効果的な交渉を行いましょう。
1. 事前準備
- 自身の経済状況(収入、貯蓄、保険の適用範囲など)を整理します。
- 可能な限りの支払い計画を立てておきます。
- 代替案(入院保証金の預託、クレジットカード払いなど)を考えておきます。
2. 適切な相談窓口の選択
まずは病院の医療ソーシャルワーカーに相談するのが良いでしょう。彼らは患者の社会的問題解決をサポートする専門家です。
3. 状況の丁寧な説明
- 連帯保証人を立てられない理由を具体的に説明します。
- 自身の支払い能力や支払いの意思を明確に伝えます。
- 必要に応じて、医師法第19条第1項(正当な理由なく診療を拒否できない)について言及します。
4. 代替案の提示
- 入院保証金の預託
- クレジットカードでの支払い
- 分割払いの提案
- 緊急連絡先として信頼できる知人を指定するなど
5. 誠実な態度での交渉
強引な要求は避け、病院側の立場も理解しつつ、協力的な態度で交渉することが重要です。
6. 合意内容の確認
交渉がまとまったら、合意内容を書面で確認し、必要な手続きを速やかに行います。
7. フォローアップ
入院中も、支払いや連絡に関して約束を守り、信頼関係を築くよう心がけます。
病院との交渉は難しく感じるかもしれませんが、多くの病院は患者の状況を理解し、柔軟な対応を検討してくれます。以下に、実際の交渉時に使えるポイントとフレーズ例を示します。
【連帯保証人が見つからない場合の病院交渉ポイント】
1. 事前準備
- 自身の経済状況を整理(収入、貯蓄、保険など)
- 医療費の支払い計画を立てる
- 代替案を考える(入院保証金、クレジットカード払いなど)
2. 交渉の進め方
- まずは医療ソーシャルワーカーに相談
- 状況を丁寧に説明(家族関係、経済状況など)
- 医師法第19条第1項について言及(必要な場合)
- 代替案を提示
3. 具体的な交渉フレーズ例
- 「連帯保証人は見つかりませんでしたが、入院費用は確実にお支払いします。」
- 「入院保証金として○○円を預けることは可能です。ご検討いただけませんか?」
- 「クレジットカードでの支払いや、分割払いなどの選択肢はありますか?」
- 「緊急連絡先として、近隣に住む知人を指定することは可能でしょうか?」
4. 交渉後の対応
- 合意内容を書面で確認
- 必要書類の準備と提出
- 支払い計画の遵守
病院側の立場を理解しつつ、自身の状況を明確に説明し、建設的な解決策を一緒に探ることが重要です。
入院時の身元引受人(緊急連絡先)の条件

入院申込書に連帯保証人とは別に、身元引受人(緊急連絡先)の記載が必要な場合もあります。身元引受人(緊急連絡先)については、単に「成年者であること」を条件としているケースが多く、生計を同じくする同居の親族でも問題ありません。もちろん、連帯保証人と同一人物でも構いません。
身元引受人(緊急連絡先)不在のケースで、病院が最も困るのは、病院で亡くなられた場合のご遺体の引き取りです。病院で亡くなられた場合、病院の霊安室には、半日程度しか、ご遺体を安置できません。
また、そもそも霊安室がない病院もあります。「ご臨終後すみやかに、ご遺体を病院の外に搬出する役割を誰が担うのか?」という点が問題になります。
ケーススタディ:おひとりさまの入院準備
佐藤さん(72歳・離婚歴あり・年金生活者)の場合
佐藤さんは突然の腹痛で救急搬送され、緊急手術が必要になりました。子どもはいますが、海外在住で連絡が取りにくい状況でした。
佐藤さんの対応
- 救急搬送時、病院側に身寄りがない状況を説明しました。
- 病院は緊急性を考慮し、連帯保証人なしで手術を行うことを決定しました。
- 退院後の支払いについて、分割払いの相談をしました。
- 退院後、地域包括支援センターに相談し、今後の緊急時対応について助言を受けました。
結果:無事に手術を終え、1週間後に退院。この経験から、事前の備えの重要性を実感し、任意後見制度の利用や、地域のサポートネットワークづくりを始めました。
【おひとりさま入院準備チェックリスト】
連帯保証人・緊急連絡先の確保
□ 依頼状の作成と送付
□ 承諾の確認
□ 必要書類の準備(身分証明書のコピーなど)
病院への事前確認
□ 入院費用の概算
□ 必要な持ち物リスト
□ 面会規則の確認
□ Wi-Fi環境の有無
自宅の準備
□ 郵便物の転送手続き
□ 植物の世話の依頼
□ 冷蔵庫内の整理
□ 家賃・公共料金の支払い手続き
職場への連絡
□ 上司への報告
□ 休暇申請の手続き
□ 業務の引き継ぎ
持ち物の準備
□ 健康保険証
□ お薬手帳
□ 衣類(パジャマ、下着など)
□ 洗面用具
□ モバイルデバイスと充電器
□ 入院中の趣味の道具(本、編み物など)
退院後の準備
□ 食料品の宅配サービスの手配
□ 家事代行サービスの検討
□ リハビリ施設の下見(必要な場合)
この チェックリストを活用して、漏れのない入院準備を心がけましょう。
よくある質問(FAQ)
いいえ、必ずしも親族である必要はありません。多くの病院では、独立した生計を営む成年者であれば、友人や知人でも連帯保証人になることができます。ただし、病院によって基準が異なる場合がありますので、事前に確認することをおすすめします。
連帯保証人が見つからないからといって、病院が入院を拒否することは法律上できません。医師法第19条第1項により、正当な理由がない限り、診療を拒否することはできません。病院の医療ソーシャルワーカーや医事課に相談し、代替案を探ることをお勧めします。
病院によっては、一定額の入院保証金を預託することで連帯保証人を免除する場合があります。ただし、これはすべての病院で適用される方法ではありません。入院を予定している病院に直接確認することが重要です。
多くの場合、身元引受人と緊急連絡先は同じ役割を果たします。ただし、病院によっては別々に記入を求める場合もあります。基本的に、患者の状態変化や緊急時に連絡を受け、必要に応じて病院に来院できる人を指します。
入院申込書に虚偽の情報を記入することは絶対に避けてください。これは私文書偽造罪に該当する可能性があり、法的な問題に発展する恐れがあります。また、病院との信頼関係を損なう結果にもなります。正直に状況を説明し、病院側と解決策を探ることが重要です。
はい、一部の病院では入院費用のクレジットカード払いを条件に、連帯保証人を免除するケースがあります。これは病院の方針によって異なるため、入院予定の病院に直接確認することをお勧めします。
通常、連帯保証人の責任は患者の退院時に終了します。ただし、未払いの医療費がある場合は、その支払いが完了するまで責任が続く可能性があります。詳細は病院との契約内容によって異なりますので、事前に確認することが重要です。

































