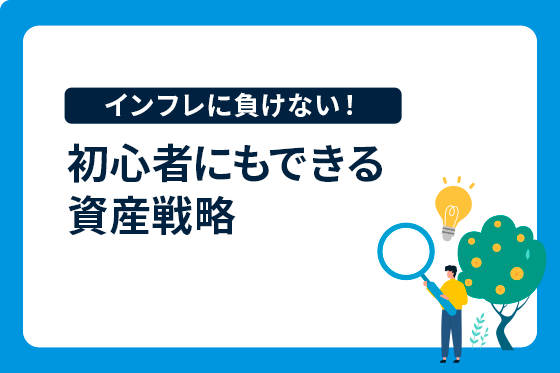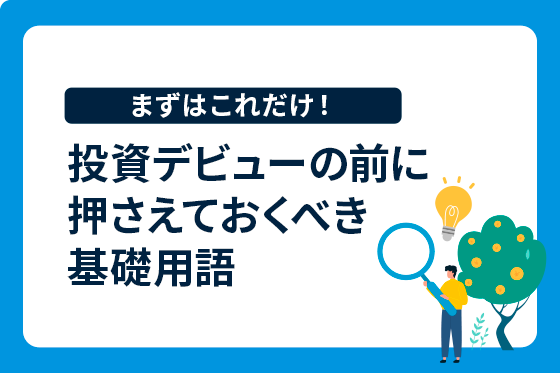個人事業主は経費計上できる支出項目が多いため、会社員に比べ節税方法が豊富です。確定申告する際の「社会保険料控除」もそのひとつです。支払った社会保険料の全額が所得から差し引かれるため、申告忘れのないよう正しい理解が求められます。このコラムでは、個人事業主が社会保険料控除として申告できるものを解説します。余分な税金を納めないためにも、ぜひ参考にしてください。
社会保険料控除とは
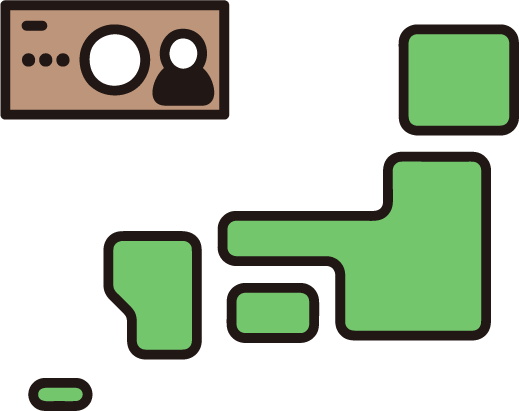
社会保険料控除とは、1月1日~12月31日の1年間で支払った社会保険料を所得から控除できる制度です。控除により課税所得が減額されるため、所得税や住民税が抑えられます。会社員は年末調整で適用されますが、個人事業主は確定申告で申請する必要があります。
控除対象となる保険料は主に以下のとおりです。
- 国民健康保険
- 国民年金
- 厚生年金
- 介護保険
また、社会保険料控除は納税者本人の社会保険料のほか、生計を一にする家族の社会保険料を支払った場合も対象です。生計を一にするとは、同居または仕送りで生活費を共有する状態を指し、主に配偶者や子ども、親などが対象になります。例えば、配偶者の国民健康保険や子どもの国民年金保険料を支払った場合、自分の社会保険料控除に含めて申請できます。
個人事業主の社会保険料控除に該当するもの

個人事業主の社会保険料控除に該当するものを紹介します。
- 国民健康保険料・介護保険料
- 国民年金保険料
- 労働保険料
- 国民年金基金の掛金
- 後期高齢者医療保険料
社会保険料控除は節税につながるため、忘れずに申告しましょう。
なお、社会保険料はクレジットカードで納付可能です。中でも「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード」は、さまざまな経費の支払いに使えるビジネス用のクレジットカードです。事業用の銀行口座と連携すると、プライベートの出費と分けられ経費の管理が容易になります。
また「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード」はご利用いただくと永久不滅ポイントが貯まります。事業用のクレジットカードをお持ちでない個人事業主の方は、この機会に「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード」をご検討ください。
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードの詳細はこちら


国民健康保険料・介護保険料
個人事業主が支払った国民健康保険料は、社会保険料控除の対象です。確定申告時に申請すると、所得から控除され税負担を抑えられます。
国民健康保険には扶養制度がないため、配偶者や子どもの保険料も支払っている方は多いでしょう。その場合は、ご自分の社会保険料控除に含めて申請できます。
また40歳以上65歳未満の方は、国民健康保険料に介護保険料が含まれていますが、併せて控除申請が可能です。
なお、国民健康保険の支払い額は、所得や自治体により異なります。毎年12月から1月頃に各加入者へ通知書が送付されます。
例として令和6年度東京都新宿区で1ヵ月にかかる国民健康保険料は、以下の表のとおりです。
| 総所得金額 | 介護保険料なし | 介護保険料あり |
|---|---|---|
| 300万円 | 30,074円 | 36,075円 |
| 500万円 | 49,224円 | 58,825円 |
| 700万円 | 68,374円 | 81,575円 |
参照元:東京都新宿区「令和6年度 国民健康保険料 概算早見表(給与・年金)」
国民年金保険料
国民年金保険料も社会保険料控除の対象です。納税者本人に加えて、配偶者や子どもなどの生計を一にする家族の保険料を支払った場合も含めて申請できます。
1年間で支払った国民年金保険料の総額は、日本年金機構から送付される「社会保険料控除証明書」で確認可能です。また「ねんきんネット」では年間の支払額の他、将来受け取れる年金の概算額も確かめられます。
なお、国民年金保険料を社会保険料控除で申請する際は、社会保険料控除証明書の添付は不要ですが、申告内容を証明する書類として、忘れずに保管しておきましょう。
国民年金保険料は、一部の国際ブランドに対応したクレジットカードでも納付でき、6ヵ月分や1年分、2年分の前納も可能です。いずれも毎月納付する場合と比べて割引が適用され、もっともお得な2年分の前納では約1ヵ月分(1万4,540円)安くなります。
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードは、国民年金保険料の支払いにも対応したクレジットカードです。前納を選択すれば保険料を抑えられるだけでなく、支払い額に応じたポイントも付与され、さらにお得になります。
またクレジットカードで国民健康保険料も納付可能です。国民年金保険料と同じく、支払い額に応じたポイントが付与される点も、クレジットカード払いのメリットです。クレジットカード払いにすると定期的に引き落としされるため、納付忘れも回避できるでしょう。
ビジネス専用のクレジットカードは、事業の費用と生活費を明確に区別できるのも魅力です。個人事業主におすすめのセゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードをご検討ください。
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードの詳細はこちら
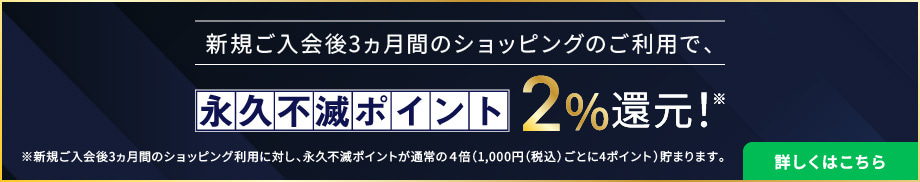
参照元:日本年金機構「国民年金保険料の納付に利用できるクレジットカード」
労働保険料
個人事業主でも従業員を雇っている場合は、労働保険の加入が必須です。その際支払った保険料は、社会保険料控除の対象になります。また建設業のひとり親方や個人タクシーなど、特別加入制度を利用して労働保険に加入している場合も申告できます。
労働保険料は原則年1回の納付です。納付した金額を忘れてしまったときは、管轄の労働局へ「労働保険料等納付証明書」を請求すると確認できます。
なお労働保険とは労災保険と雇用保険の総称であり、従業員を雇う企業は加入が義務付けられています。ただし、個人事業主は労働者にあたらないため、従業員を雇っていない場合は加入義務がありません。
労働保険料は、賃金総額×労働保険料率(労災保険率+雇用保険率)にて算出されます。
例えば、1年間の賃金見込み額が350万円(毎月25万×12ケ月+年間の賞与50万円)の大阪府の小売業の場合、令和2年度における業種・保険率は、労災保険率は3.0/1000 、雇用保険率は9.0/1000です。
労働保険料は3,500,000 × ( 3.0/1000 + 9.0/1000 ) = 42,000円
雇用保険料は従業員と事業主の双方が負担しますが、労災保険料は全額事業主の負担になります。
国民年金基金の掛金
国民年金基金の掛金は、全額が社会保険料控除の対象となります。
国民年金基金とは、自営業者や個人事業主など厚生年金保険に加入していない方(厚生年金被保険者の扶養に入っている専業主婦・主夫は除く)が任意で加入できる制度です。掛金を支払うと、老齢年金を受け取る際に年金額が上乗せされます。
なお国民年金基金への掛金は「社会保険料控除証明書」で確認できます。確定申告の際、証明書を添付して申請してください。掛金の上限額は月額6万8,000円です。
参照元:国税庁「社会保険料控除」
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療制度の保険料も社会保険料控除が適用されるため、対象者は申告を忘れないようにしましょう。
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方(一定の障害がある65歳以上の方も含む)が強制加入する医療制度です。以下の条件に該当する方は保険料が年金から天引きされます(特別徴収)。
- 年金の年間受給額が18万円以上となっている
- 介護保険料を特別徴収で納めている
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金額の2分の1以下である
年金から徴収されている場合は「公的年金等の源泉徴収票」や「後期高齢者医療保険料額のお知らせ」で支払った保険料を確認できます。なお、これらの書類は確定申告の際に添付する必要はありません。
個人事業主が社会保険料控除を申請する方法

個人事業主は確定申告時に、以下の方法で社会保険料控除を申請してください。
- 申請に必要な書類を準備する
- 社会保険料の金額を合算して確定申告書に記入する
- 確定申告書を提出する
税負担を抑えるためにも、正確な控除額を記入しましょう。
申請に必要な書類を準備する
確定申告で社会保険料控除を申請する際は、以下の書類が必要になります。
- 確定申告書
- 社会保険料控除証明書(国民年金・国民年金基金・健康保険など)
主な記入内容は以下のとおりです。
- 氏名・住所・生年月日
- マイナンバー
- 職業
- 世帯主の氏名・続柄
- 収入金額等
- 所得金額等
- 所得控除
- 税金の計算
- その他(配偶者の合計所得・青色申告特別控除額など)
控除項目の記入漏れを防ぐために、前年の確定申告書を参考にするとよいでしょう。なお、以下の控除は証明書の保管が必要になります。
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 住宅ローン控除
- 医療費控除
- 寄附金控除
- 小規模企業共済等掛金控除
証明書が必要ない控除についても、領収書や銀行の振り込み記録などを保管しておくと、申告漏れを防げるでしょう。
社会保険料の金額を合算して確定申告書に記入する
書類の準備ができたら、対象の社会保険料額を記入します。生計を一にする家族の保険料を支払った際は、忘れずに合算しましょう。
社会保険料控除は、確定申告書第一表の「社会保険料控除」の欄に合計金額を、第二表にその内訳を記入してください。
確定申告書を提出する
記入が完了したら、確定申告書を提出しましょう。提出期間は通常2月16日から3月15日で、以下の方法で提出できます。
- 税務署の窓口へ持参
- 郵送
- e-Tax
提出期限を過ぎると延滞税がかかるケースがあるため、注意してください。
個人事業主が社会保険料控除について知っておきたいこと

個人事業主が社会保険料控除を申告する際は、以下2つのポイントを押さえておきましょう。
- 家族が青色事業専従者のときも申告できる
- 従業員の社会保険料は控除には該当しない
それぞれの項目を詳しく解説します。
家族が青色事業専従者のときも申告できる
青色申告をしている場合は生計を一にする家族を青色事業専従者とし、支払った給与を経費に計上できます。青色事業専従者である家族の社会保険料を負担した場合、個人事業主が社会保険料控除として確定申告が可能です。
なお青色事業専従者として認められるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上
- その年を通じて6ヵ月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事している(他の職業の従事していない)
また青色事業専従者の給与を経費にするには、所属する納税地を管轄する税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。経費に算入する年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や、新たに専従者がいることになった場合は、そのときから2ヵ月以内に届出てください。
従業員の社会保険料は控除には該当しない
個人事業主が従業員を雇い、その社会保険料を一部負担する場合は、社会保険料控除に含めて申告できません。
個人事業主が負担した従業員の社会保険料は「法定福利費」として経費に計上できます。なお従業員が負担した社会保険料は、本人の確定申告で社会保険料控除として申告します。
個人事業主が社会保険料控除を申告する際によくある疑問
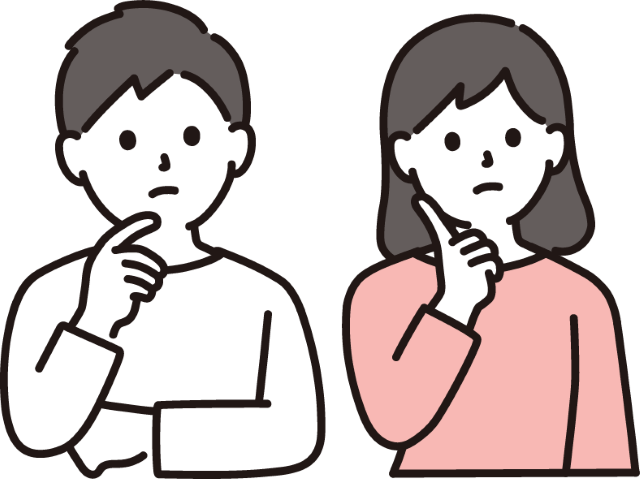
ここでは、個人事業主が社会保険料控除を申告する際の疑問点を紹介します。ご自身のケースに当てはまるか確認してみてください。
同居していない親の社会保険料を支払った場合でも、生計を一にしていると認められれば、自分の社会保険料控除に含めて申告できます。ただし、以下の2点には注意が必要です。
- 仕送りの金額が生活するには十分でない場合は、生計を一にすると認められない可能性がある
- 親の年金から社会保険料が天引きされ、その後に親へ保険料相当額を手渡した場合は、自分の社会保険料控除の対象にはならない
対象になるかどうか判断が難しい場合は、最寄りの税務署に相談してみてください。
国民年金を13ヵ月以上前納した場合、以下のいずれかの方法で社会保険料控除を受けられます。
- 前納した年に全額を控除申請する
- 各年分の保険料を複数年に分けて控除する
なお複数年に分けて控除を選択した場合、途中で一括控除に変更することはできません。また、通常の申告時と同様に、申告する年の社会保険料控除証明書が必要です。
確定申告の期間終了後に控除の申告忘れに気づいた場合は、「更正の請求」により税金の還付を受けられます。
更正の請求を行えるのは、法定申告期限から5年以内です。申請の際は「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」と社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の原本が必要になり、以下の方法で提出できます。
- 税務署の窓口に持参
- 郵送
- e-Tax「確定申告書等作成コーナー」
なお、更正の請求など詳細や不明点は、国税庁のWEBサイトや電話で相談可能です。
相談先:国税庁「税についての相談窓口」TEL:0570-00-5901
社会保険料控除証明書を紛失したときは、以下の方法で再発行できます。
- 「ねんきんネット」から申請(ユーザーIDを取得している場合)
- 「ねんきん加入者ダイヤル」に電話で申請(TEL:0570-003-004・国民年金加入者向け)
- 年金事務所の窓口で申請
なお、ねんきん加入者ダイヤルと年金事務所の窓口で申請する場合は、マイナンバーまたは基礎年金番号が必要となります。
社会保険料控除は、その年に支払った保険料が対象となります。そのため、滞納していた保険料を支払った場合も、支払った年の社会保険料控除として申請できます。ここで押さえるべきポイントは以下のとおりです。
- 複数年分をまとめて納めた場合も同様に、支払った年に控除申請できる
- 滞納分の支払いで、控除証明書に記載された金額より多く支払った場合は、領収書を提出する必要がある
- 領収書を紛失した場合は、ねんきんネットやねんきん加入者ダイヤル、年金事務所で滞納分を含めた控除証明書を再発行できる
注意:延滞金は社会保険料控除の対象外になります。
正しく控除を申告して節税につなげよう
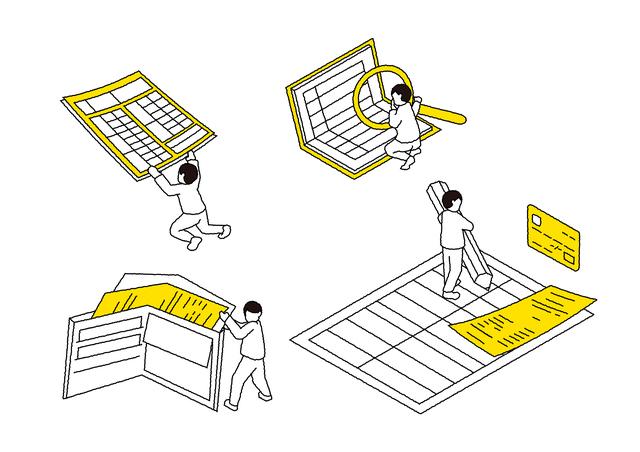
国民年金保険料や国民健康保険料、国民年金基金などの社会保険料を納付したときは、社会保険料控除として確定申告しましょう。いずれも全額が所得控除の対象となるため、課税所得を減らし所得税や住民税を減額可能です。
個人事業主は会社員や公務員と異なり、社会保険料が給料から天引きされません。各自で保険料を納めるため、期限を守って納付することが大切です。クレジットカード払いであれば自動的に引き落とされるため、納付忘れを回避できます。また前納すると保険料が割引されたり、ポイントが貯まったりすることもメリットです。個人事業主の方は納付方法のひとつとして検討してみてください。
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードの詳細はこちら
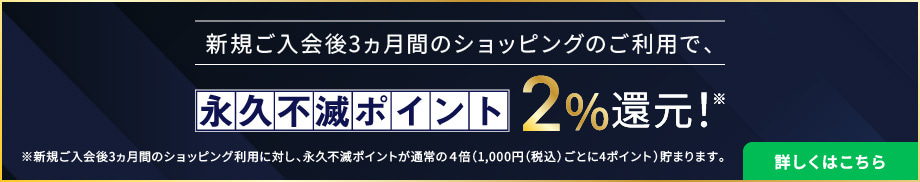
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。