「起業をしたいけど、なかなかアイディアが思い浮かばない」「ビジネスとして成立するか不安」など悩む方も多いでしょう。ではどのように起業のアイディアを見つけ、ビジネスとして形にしていくのでしょうか?
本記事では、起業のアイディアの見つけ方やビジネスとして形にする方法、起業前に準備できることなどを解説します。
- 起業は会社形態や事業規模を問わず新たに事業・サービスを立ち上げることを指す
- 起業のアイディアは日常の悩みや異なるものの掛け合わせなどから生み出せる
- ビジネスを行う上ではアイディアだけでなく資金繰り・資金調達なども重要
起業にはどんな方法がある?
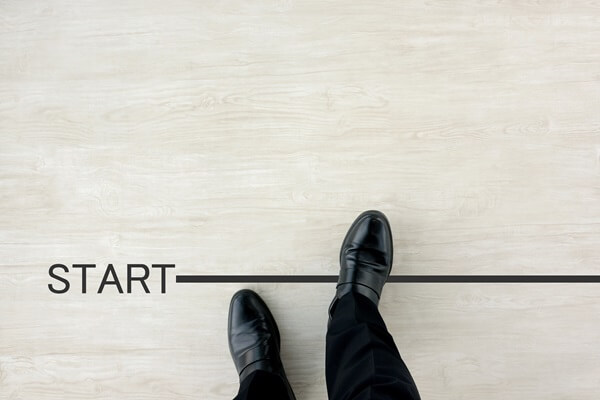
そもそも「起業」とは、新たに事業・サービスを0から立ち上げる行為やプロセスを指し、個人事業主や株式会社、合同会社などの会社形態や事業規模に問わず意味するものです。
とはいえ、起業の方法は2つに大別でき、個人事業主と会社を設立する方法があります。
以下ではそれぞれのメリット・デメリットを踏まえて解説します。
個人事業主になる
個人事業主としての起業は、原則個人の責任の上で事業を運営します。
個人事業主として起業するメリットは、法人設立と比較して初期費用が抑えられることや手続きが簡素であることから、手軽に始められることが挙げられます。
一方、デメリットとしては、事業に関連する借入(債務)は本人に紐づくため、事業が失敗すると自分の財産に影響してしまいます。
個人事業主に多い業種としては、飲食業などの店舗ビジネスや医師や税理士などが独立する際に使われることがあります。
会社を設立する
法人として会社を設立する場合には、現在は以下の会社形態となります。
- 株式会社
- 合同会社
- 合資会社
- 合名会社
法人として事業を行う場合、顧客や金融機関からの信頼を得やすいことや融資・出資を受けやすいこと、法人税の税率は一定であるため、税金の面などでもメリットがあります。
一方で、法人として会社を設立する場合には、煩雑な手続きや一定の費用が伴うことや経営決定に株主・取締役の合意が必要となることなどがデメリットといえるでしょう。
起業アイディアが思いつかない時!やるべき5つの行動

起業するなら、より良いアイデアをもとに事業を行いたいという方も多いでしょう。ここでは、起業のアイディアを見つけるためにやるべき5つの行動をご紹介します。
アイディアを紙に書き出してみる
起業アイデアを見つけるコツとして、アイディアを紙に書き出してみることがおすすめです。
この時のポイントとして、ひとまず質ではなく量を出すことを意識すると良いでしょう。
起業当初はどうしても視野が狭くなってしまい、目先の課題や視野でしか事業を検討できないということに陥りがちですが、発想を柔軟にして多くのアイディアをまず出してみることで、最終的な良質な事業アイディアにつながります。
イベントやセミナーなどに足を運び情報収集する
起業アイディアが思いつかない時には、起業したい方が集まる交流イベントや興味のある分野のセミナーなどに参加するのが良いでしょう。
交流イベントやセミナーでは、自身と異なる価値観・考え方の起業家のアイディアなどを吸収でき、視野が広がるきっかけとなるでしょう。
SNSで情報収集や人脈づくりをする
起業アイディアをビジネスにする過程として、SNSで情報収集や人脈づくりをすることもおすすめです。SNSでは実際に起業した人の生の発信を受け取ることができ、具体的な起業のエピソードなども知ることができます。
さらに、情報を得るだけでなく、SNSでは相互のやりとりもできるため、将来的な顧客となるような人脈作りの一助にもなるでしょう。
起業した方に話を聞きに行く
起業にはどんな方法があるのか具体的に知りたい場合、起業した方に話を聞くのも良いでしょう。
リアルな体験談を聞いて、アイディアの方向性が見えることもあります。
さまざまな悩みを持つ方に困りごとを聞きに行く
さまざまな悩みを持つ方に困りごとや課題感を聞きに行くことも有効です。起業後に苦労することとして、ユーザーニーズを的確に汲み取れないということが挙げられます。
そのため、ユーザーの声、消費者側のニーズを知るためのヒアリングをすることによって、将来実際に製品・サービスを開発・提供する際に役立つでしょう。
起業アイディアを見つけるコツ!目のつけどころ5選

最初につまづいてしまうことも多い、起業アイディアを見つけるコツを5つご紹介します。
流行や世間のニーズを意識する
起業アイディアを考える上で、世間の流行やニーズを意識することはおすすめです。世間で何が求められているのか、業界・社会全体の流れを見ることにより、顧客ニーズから大きく外れたアイディアにはなりづらいです。
今後の流れなどを捉える手前、過去の時代の流れ・ニーズの変遷を辿ると今後の動きも予測がつきやすくなるため、おすすめです。
日常の不満や困っていることを考える
起業アイディアを見つけるコツとして、「こんなサービスがあったら良いのに」「こんな商品あれば良いのに」といった日常の不満や困っていることなどをきっかけにして考えるのも良いでしょう。
起業する際にユーザーインタビューといって他人に悩みごとや課題感をヒアリングする起業家は多いですが、それを自身に置き換えることも可能です。
自分自身を事業・サービスのペルソナとして、日常の不満・困っていることを深掘りすることで、より良いアイディアの一助になるでしょう。
既にある商品・サービス同士をかけ合わせて考える
異なるもの同士をかけ合わせることで新たなアイディアになることも多いです。世界初の特許である「消しゴム」「鉛筆」を掛け合わせた「消しゴム付鉛筆」のようにさまざまな組み合わせを考えると良いでしょう。
「〇〇専用」など特定の商品・サービスを考える
特定(限定)して考えることで、ヒット商品が生まれることもあります。対象の市場が狭くなるという懸念は一定あるものの、特定分野に強みを持った商品として優位性を持たせることができます。
自分の好きなことや経験が活かせる分野から考える
過去の自分のキャリアや好きなことを活かして、起業アイディアのヒントにするのもおすすめです。
個々人によりますが、自分自身の「得意」「好き」を活かした分野で事業を運営することで熱中しやすく、持続性が高くなりやすいでしょう。
起業アイディアをビジネスにするには?4つのポイント

ここまで、起業アイディアを見つける方法・コツを解説しました。以下ではアイディアを実際にビジネスにするまでのポイントをご紹介します。
類似した商品・サービスはないか確認する
アイディアをビジネスにする上で、優位性があるのか、類似品・サービスとの差別化ができているかチェックすることは重要です。
既に市場に同様の商品・サービスがある場合、それなりの優位性が必要であり事業を立ち上げるハードルは高くなります。
一方、狙っている市場に類似商品・サービスがない場合は新たに競合が現れない限り、事業立ち上げのハードルは競合との競走との観点では低くなるため、あらかじめ市場の類似商品・サービスを確認することは大切です。
販売チャネルやターゲットを決定する
販売チャネル(経路)やターゲット層を具体的かつ的確に決定することも大切です。商品・サービスを提供するペルソナが明確に定まっていなければ、ニーズも汲み取れずアイディアありきの起業で終わってしまいます。
また、どんなに素晴らしい商品・サービスが完成したとしても、顧客に届ける販売チャネルがなければビジネスは成立しません。起業アイディアをビジネスにする際には、商品・サービスのアイディアだけでなくターゲットや販売チャネルも合わせて考えておきましょう。
売上の予測や資金計画を行う
売上の予測を立て、現実的な資金計画に落とし込んでいくこともビジネスを行う上では重要です。会社というのは現預金が0になると資金ショートで倒産してしまいます。
これは売上(利益)がない場合にはもちろんですが、黒字倒産といって売上(利益)が十分に出ている場合でも資金繰りが滞ると倒産の可能性があります。
このような事態にならないためにも、ビジネスをする際には売上の予測や資金計画を事前に立てておくと良いでしょう。
少額の資本・副業などから始めて小さくスタートする
起業当初はリスクを低くするためにも、少額の資本、副業から規模を拡大するなど、無理のない範囲でスタートすると良いでしょう。一定程度ビジネスが成功する見込みが高ければ懸念はないのですが、ビジネスは想定以上に上手くいかないことも多々あります。
もし少額資本や副業などから始めた場合には、自身の生活への影響を少なくできるため、初めは小さくスタートするのがおすすめです。
起業後に苦労することは何?準備できることは?

アイディアをかたちにした起業後に苦労することや事前に準備できることをご紹介します。
顧客や販路の開拓
起業後、売上を拡大させるための顧客・販路開拓に苦労する方は多いです。起業当初は会社の知名度や実績、信頼なども乏しく、そもそも営業活動を行なっても話すら聞いてもらえないことも多いです。
また、全く新しいビジネスを立ち上げる場合には、顧客に商品・サービスを理解してもらうのが難しく、商談まで行きついても受注に至らないケースも多々あるでしょう。
起業後にビジネスを成立させるには高い営業力や集客力が重要になります。
資金繰りや資金調達
資金繰りや資金調達も起業後の苦労として挙げられます。ビジネスをする際、売上と支出(販管費など)の入出金のタイミングにラグがあり、この際現預金が0になると資金繰りが間に合わず黒字倒産の可能性もあります。
そのようなことがないよう、資金調達を視野に入れておくことが大切です。資金調達には銀行など第三者を介さず社債や株式などを発行して資金を調達する直接金融と、銀行などから融資を受ける間接金融があります。
多くの会社では銀行から融資を受けることが多いですが、創業当初の会社に銀行がスムーズに融資をするハードルは非常に高いため、直近決算書や事業計画書、各種財務資料などの提出が求められるでしょう。そのため、将来の資金繰りに備えて資金調達を検討している場合は、自社の事業を客観的に説明できるような資料の準備が必要です。
財務経理・法務関係の知識
起業するにあたって必要となる財務経理・法務などの知識がなく、苦労する方も多いです。起業する上で、財務三表や最低限の法務の知識はあるに越したことはないですが、本業に集中するためにも専門家に頼るのもひとつの手です。
起業したらビジネスカードをつくっておこう
前述したとおり、起業後は社会的信用や実績も乏しいことや資金繰りに苦労します。また、事業を運営する上ではさまざまな経費がかかってくるため、日常の事務作業も多くなりがちです。
ビジネスを行うのであればできる限り本業に集中したいという方におすすめなのが「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード」です。このカードは、創業直後の個人事業主や会社経営者でも申し込みしやすいだけでなく、支払いサイクルが最長56日と、資金繰りを円滑にする仕組みづくりの一助にもなります。
さらに、経費削減や業務効率化にも活用でき、個人事業主・創業直後の会社に最適なビジネスカードになっています。年会費が無料で持て、便利で特典も豊富なビジネスカードをこの機会に申し込んでみてはいかがでしょうか。
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードの詳細はこちら


事業が軌道にのったらプレミアム特典が豊富なビジネスカードもおすすめ

事業が軌道にのったらプレミアムサービスが満載の「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード」がおすすめです。通常年会費22,000円のところが初年度年会費無料となっており、お得に利用できます。
また、専任のコンシェルジュサービスや空港ラウンジなど利用可能なプライオリティパスが利用できるなど、プラチナカード会員限定の特別なサービスも付いています。
各種サービスでビジネスを後押ししたい方は、ぜひ申し込みを検討してみてください。
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードの詳細はこちら
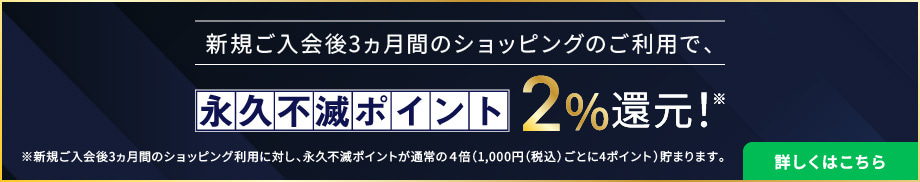
おわりに
本記事では、起業アイディアを見つけるコツや実際にビジネスにする方法、起業後に苦労することなどを解説しました。起業は規模や形態問わず、小さく始めることも可能です。また、日常の疑問や課題感からアイディアを見つけ、肉付けしていくことで商品・サービスにつながることもあります。
本記事を参考にし、起業のアイディアを見つけ、ビジネスを始める一助になれば幸いです。





































