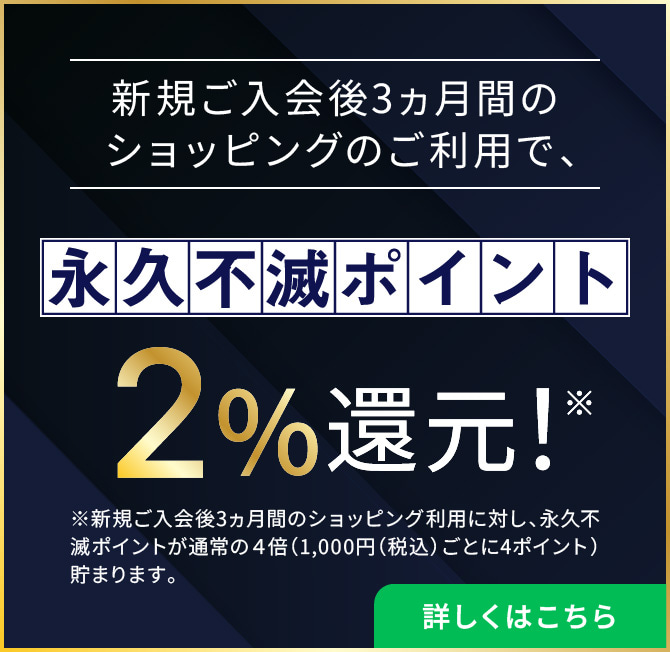個人事業主としてひとりで始めたビジネスも、規模が大きくなるにつれて従業員の雇用が必要になるケースがあります。しかし、従業員を雇うと社会保険の加入が必要なのか、また費用はどの程度かかるのか、正確に理解できている方は少ないでしょう。
個人事業主が従業員を雇用した場合、従業員数や労働時間などの条件に応じて、社会保険や労働保険への加入が義務付けられます。それに伴い事業主側の費用負担も発生するため、従業員を雇い入れる前に保険制度の内容や概算費用を把握し、出費に備えて資金計画を立てることが大切です。
この記事では、個人事業主が労働者を雇う場合の社会保険制度や加入条件、手続き方法などを解説します。従業員の雇用を考える方や将来に向けて知識を深めたい方は、ぜひ参考にしてください。
個人事業主が従業員を雇う際に加入が必要な保険
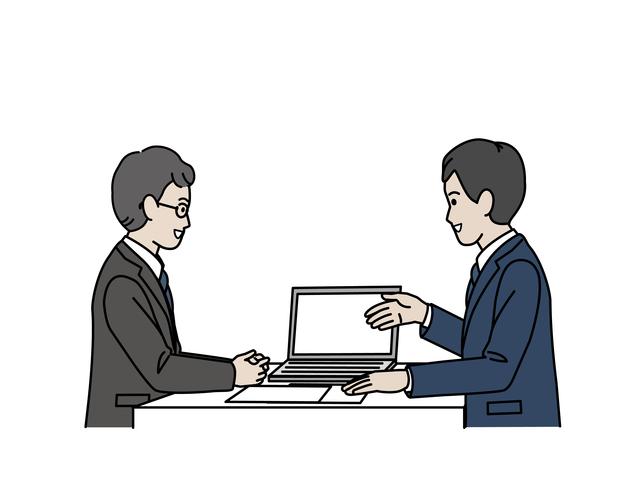
会社勤めをする方であれば、社会保険に加入するケースが一般的です。社会保険とは健康保険や介護保険、厚生年金保険の総称ですが、広義では労働保険(労災保険・雇用保険)を含める場合もあります。
一方、個人事業主が従業員を雇う場合は、条件を満たしたケースに限り加入が必要です。ここではその条件を詳しく解説します。
社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)
個人事業主が常時5人以上の従業員を雇用する場合は、社会保険の適用事業所となるため、以下の条件に該当する方は加入が必要です。
- 75歳未満(健康保険)
- 70歳未満(厚生年金保険)
- 40歳以上65歳未満(介護保険)
- 1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上あるパートやアルバイト
なお、厚生年金保険の被保険者が51人以上いる(1年間で6ヵ月以上の期間)場合は「特定適用事業所」となり、以下の条件をすべて満たす方も加入対象になります(※)。
※一般的には、被保険者であるかを問わず「従業員」が51人以上となる場合に適用されます。
| 条件 | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|
| 1週間の所定労働時間が20時間以上 | 所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書などで定められた勤務すべき時間 | ・所定労働時間が1ヵ月単位で定められている場合の計算方法 「1ヵ月の所定労働時間÷(52週÷12ヵ月)」 ※例外的に労働時間の長短がある月は除く ・1年単位で定められている場合の計算方法「1年間の所定労働時間÷52週」 ・1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合の計算方法「その周期における1週間の所定労働時間の平均値」 |
| 所定内賃金が月額88,000円以上 | 所定内賃金とは、基本給および諸手当を合算した賃金で、以下の賃金を月額換算したもの ・週給 ・日給 ・時給 | 除外対象 ・臨時に支給される賃金 ・1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:賞与) ・時間外労働や休日労働、深夜労働に対する割増賃金(例:残業代) ・最低賃金法で算入しないことを定めている賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当) |
| 学生ではない | 以下の生徒・学生は対象外 ・大学 ・高等学校 ・専修学校 ・各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る) | 以下の者は適用対象 ・卒業見込証明書を有し、卒業前に就職し、卒業後も同じ事業所に勤務予定の方 ・休学中の方 ・大学の夜間学部の学生 ・高等学校で夜間等の定時制課程の学生等 |
参照元:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
また、以下の業種は社会保険の非適用業種にあたるため、個人事業の場合に限り加入義務はありません。
- 農業
- 林業
- 漁業
- 専門・技術サービス(デザイン業・経営コンサルタント業・写真業等)
- 宿泊業・飲食サービス業
- 生活関連サービス業(洗濯・理容・美容・浴場業等)
- 娯楽業(映画館、スポーツ施設提供業等)
- その他サービス業(警備業、ビルメンテナンス業、政治・経済・文化団体、宗教等)
社会保険の適用事業所となる個人事業主は、事実の発生から5日以内に「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を所轄の年金事務所へ以下のいずれかの方法で提出してください。
- 窓口へ持参
- 郵送
- 電子申請
なお、介護保険は健康保険に加入する40歳以上65歳未満の方に無条件で適用されるため、手続きの必要はありません。
参照元:厚生労働省「介護保険制度について」「個人事業所に係る適用範囲の在り方について」、日本年金機構「事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき」「新規適用の手続き」
労働保険(労災保険・雇用保険)
従業員を雇う個人事業主は労働保険の加入義務がありますが、労災保険と雇用保険では加入条件が異なるため、正しい理解が必要です。
【労災保険】
労災保険は雇用形態や労働時間に関係なく、すべての従業員が加入対象です。業務中に発生したケガや病気を保障するだけでなく、通勤中の交通事故にも適用されます。
【雇用保険】
一方、雇用保険は以下の条件を満たした従業員が加入対象です。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上継続して雇用される見込みがあること
上記の条件に該当した場合、パートやアルバイトでも加入義務が生じます。雇用保険は失業時に給付を受けられるほか、育児休業や教育訓練などでも保障を受けられます。
【手続き方法】
労働保険の適用を申請する際は、以下の書類を準備し、管轄の労働基準監督署へ提出しましょう。
- 労働保険保険関係成立届(保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内)
- 労働保険概算保険料申告書(保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内)
また、雇用保険の加入義務がある従業員を雇った場合は、公共職業安定所(ハローワーク)へ以下の書類を提出してください。
- 雇用保険適用事業所設置届(設置日の翌日から起算して10日以内)
- 雇用保険被保険者資格取得届 (資格取得の事実があった日の翌月10日まで)
- 労働保険保険関係成立届の事業主控(労働基準監督署受理済みのもの)
- 事業を確認できる書類(個人事業の場合は以下のいずれか)
- 事業許可証
- 工事契約書
- 不動産契約書
- 源泉徴収簿
- 社会保険の適用関係書類等(保険料納入証明書や健康保険適用事業所関係事項確認(申請)書など)
- 労働者の雇用実態や賃金の支払い状況等を証明できる書類
- 労働者名簿
- 賃金台帳(雇入れから現在まで)
- 出勤簿又はタイムカード(雇入れから現在まで)
- 雇用契約書(パートやアルバイトの場合)
なお、これらの書類の提出後に従業員を追加で雇用する場合は「雇用保険被保険者資格取得届」のみ提出します。
参照元:国土交通省「社会保険の適用関係について」、厚生労働省「労働保険の成立手続」
個人事業主が従業員の保険加入で負担する金額

ここでは個人事業主が従業員を雇用した場合に、負担する社会保険料の金額を解説します。
- 社会保険
- 労働保険
上記の2種類に分けて説明するので、従業員を雇う可能性がある方は参考にしてください。
社会保険
社会保険料は以下の計算式で算出した金額を、個人事業主と従業員で折半します。
- 社会保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率
健康保険の保険料率は、都道府県や保険事業者(全国健康保険協会(協会けんぽ)や各企業が設立した健康保険組合)により異なります。
【保険料率の例(令和6年度):東京都・協会けんぽ】
- 健康保険:9.98%
- 介護保険:1.6%(全国一律)
厚生年金保険料は全国一律で18.3%です。
標準報酬月額とは、社会保険料を算出するための基準となる金額です。基本的には4月から6月の給料の平均額が用いられ、その年の9月から翌年8月までの社会保険料の算出に使用されます。
【計算例】東京都在住・42歳・標準報酬月額30万円・協会けんぽに加入
- 健康保険料:30万円(標準報酬月額) × 9.98%(保険料率) ÷ 2(折半)=14,970円
- 介護保険料:30万円 × 1.6% ÷ 2 = 2,400円
- 厚生年金保険料:30万円 × 18.3% ÷ 2 = 27,450円
- 合計:44,820円
なお、健康保険料率は毎年改定されるため、確認を忘れないようにしましょう。
労働保険
労働保険の金額は、1年間の賃金総額にそれぞれの労災保険料率を乗じて計算します。
【労災保険】
労災保険は全額が事業主の負担となり、保険料率は業種により異なります。主な業種の保険料率は以下のとおりです。
- 林業:5.2%
- 農業:1.3%
- 食料品製造業:0.55%
- 道路新設事業:1.1%
- 交通運輸事業:0.4%
- 小売業:0.3%
- 金融業:0.25%
参照元:厚生労働省|令和6年労災保険料率
【雇用保険】
一方、雇用保険は事業主と従業員の双方が負担します。折半と誤解されがちですが、両者の負担割合は異なり、従業員からは毎月徴収します。
例として、一般事業の保険料率は以下のとおりです。
- 事業主負担:0.95%
- 従業員負担:0.6%
- 合計:1.55%
【計算例(事業主負担分)】:小売業・従業員数2名・1年間の賃金総額800万円の場合
- 労災保険率(小売業): 0.3%
- 雇用保険料率(事業主負担分): 0.95%
計算:
・労災保険料:800万円(賃金総額)×0.3%(労災保険率)=24,000円
・雇用保険料:800万円(賃金総額)× 0.95%(雇用保険料率)=76,000円・年間の事業主負担額:24,000円(労災保険料)+76,000円(雇用保険料)=100,000円
なお、雇用保険が適用されない従業員がいる場合は、除外して計算します。
個人事業主が知っておきたい社会保険のルール
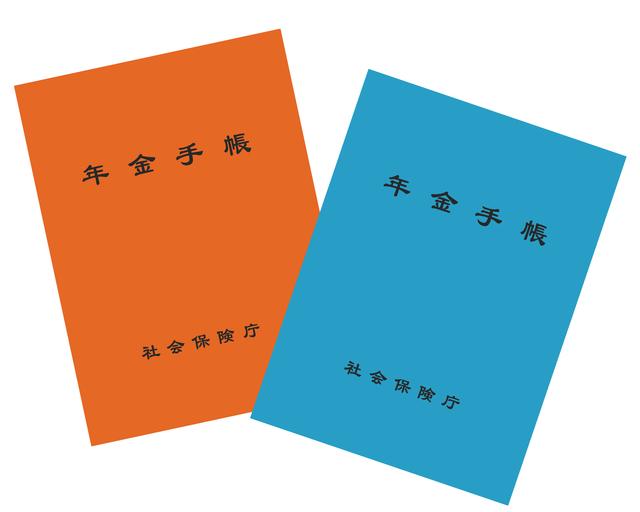
従業員を雇用する際、個人事業主が知るべき規則を4つ紹介します。
- 社会保険適用外の事業所でも条件を満たせば加入できる
- 個人事業主自身は社会保険に加入できない
- 個人事業主は労災保険に加入できるケースがある
- 従業員の保険料は経費にできる
それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
社会保険適用外の事業所でも条件を満たせば加入できる
従業員が5人未満の事業所でも、従業員の半数以上が同意し、厚生労働大臣の認可を受ければ社会保険に加入できます。認可を受けた事業所は従業員全員の加入が必要になりますが、健康保険と厚生年金保険のどちらか一方でも問題ありません。
加入の際は以下の書類を日本年金機構の事務センター、または所轄の年金事務所へ提出してください。
| 書類 | 詳細 |
|---|---|
| 任意適用同意書 | 従業員の半数が同意したことを証明 |
| 事業主世帯全員の住民票原本(個人番号の記載がないもの) | ・90日以内に発行されたもの ・事業所の住所が個人事業主の住民票と異なる場合は、所在地が確認できるものを添付(例:賃貸借契約書のコピー) |
| 公租公課の領収書(原則1年分・コピー可) | 以下のすべてが必要 ・所得税 ・事業税 ・市町村民税 ・国民年金保険料 ・国民健康保険料 |
参照元:日本年金機構「任意適用申請の手続き」
上記の書類は電子申請か郵送、または窓口持参で提出してください。
個人事業主自身は社会保険に加入できない
従業員を雇用して社会保険の加入義務が生じても、個人事業主には適用されないため、国民健康保険と国民年金へ引き続き加入が必要です。
また、家族が従業員として働く場合も社会保険は適用されませんが、以下の条件にすべて該当する場合は加入が認められます。
- 他の従業員と同様に就業規則が適用されている
- 他の従業員と同様に出勤簿やタイムカードなどで就労時間が管理されている
- 他の従業員と同様の給与計算がされている
- 事業主の確定申告で専従者給与として扱われていない
他の従業員と同等の勤務状況の場合は、家族にも社会保険が適用されます。
参照元:日本年金機構「個人事業所の場合、事業主およびその家族は被保険者となるのでしょうか。」
個人事業主は労災保険に加入できるケースがある
個人事業主は原則として労働者にあたらないため、通常は労災保険の加入は認められません。しかし雇用人数が以下の条件に該当する場合は「中小事業主」となり、個人事業主自身も労災保険への特別加入が認められます。
| 業種 | 従業員数 |
|---|---|
| 金融業・保険業・不動産業・小売業 | 50人以下 |
| サービス業・卸売業 | 100人以下 |
| その他の業種 | 300人以下 |
なお、2024年11月に通称「フリーランス新法」が施行され、従業員を雇用しないフリーランスでも条件を満たせば労災保険加入への特別加入が認められました。希望する方は特定フリーランス事業の特定加入団体へ申請してください。
ただし、以下の事業を営む場合は、該当する特別加入団体を通じての加入が求められます。
- 個人タクシー、個人貨物運送業など
- 建設業の一人親方
- 漁船による自営漁業者
- 林業の一人親方
- 医薬品の配置販売事業者
- 再生資源取扱事業者
- 船員法第1条規定の船員
- 柔道整復師
- 創業支援等措置に基づく高年齢者
- あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師
- 歯科技工士
- 特定農作業従事者
- 指定農業機械作業従事者
- 国や地方が実施する訓練従事者
- 家内労働者
- 労働組合等の一人専従役員
- 介護作業従事者
- 家事支援従事者(いわゆる家政婦(夫))
- 芸能関係作業従事者
- アニメーション制作作業従事者
- ITフリーランス
※職種の判断が難しい場合は、特別加入団体へ問い合わせてみてください。
参照元:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「労災保険 特別加入制度のしおり」「フリーランスの皆様へ」
従業員の保険料は経費にできる
従業員の保険料を支払う場合は、法定福利費の勘定科目で経費計上できます。ただし従業員の給与から天引きした社会保険料は、経費に該当しないので注意してください。
なお、自分自身の社会保険料も経費になりませんが、社会保険料控除として確定申告で申請できます。支払った保険料全額が所得控除となるため、節税につながるでしょう。
また国民年金保険料は、まとめて納めると割引が適用されるため、早めの納付がおすすめです。
【例:令和6年度分と7年度分を毎月納付する場合】
- 令和6年度分=16,980円×12ヵ月=203,760円
- 令和7年度分=17,510円×12ヵ月=210,120円
- 合計金額=413,880円
クレジットカードでもっとも割引率が高い2年前納をすると、支払い総額が398,590円となり、毎月納付よりも15,290円お得です。
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードは、国民年金保険料の支払いに対応したクレジットカードです。支払い額に応じて付与されるポイントを備品の購入にも充てられるため、経費削減にもつながります。
さらに国民健康保険料もクレジットカード払いにすると、付与されるポイントが増えるだけでなく、納め忘れも防げます。この機会にセゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードでの社会保険料納付を検討してみてください。
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードの詳細はこちら
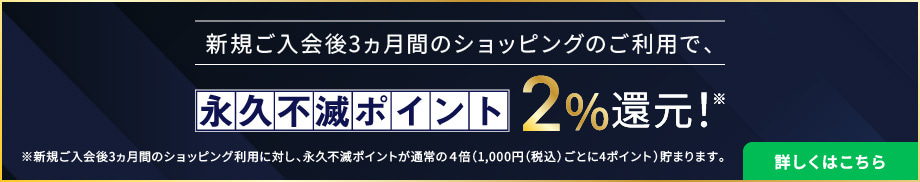
参照元:日本年金機構「国民年金保険料の納付に利用できるクレジットカード」
個人事業主が従業員を雇用すると源泉徴収の義務も発生する
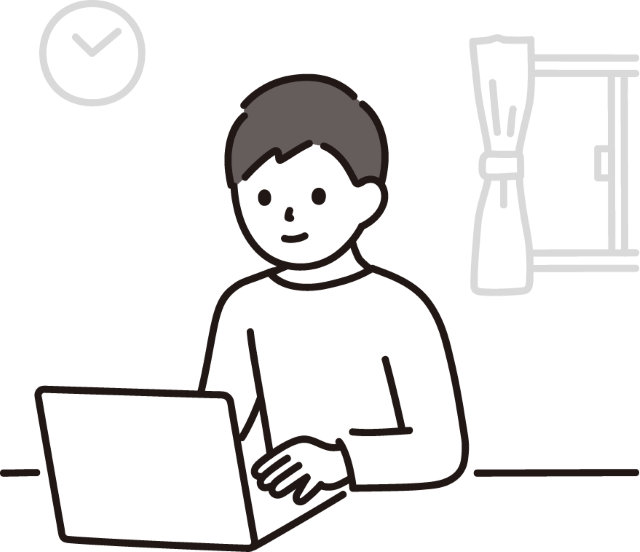
個人事業主が従業員を雇うと、毎月の源泉徴収も必要になります。従業員を雇用した日から1ヵ月以内に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を、給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長へ提出してください。従業員には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいましょう。
源泉徴収の金額は「源泉徴収税額表」を確認して徴収額を算出し、原則として給与支給日の翌月10日までに納付します。例外として従業員が10人未満の場合は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、下記のように半年分まとめての納付ができます。
| 納付対象 | 納付期限 |
|---|---|
| 1〜6月分 | 7月10日 |
| 7〜12月分 | 翌年1月20日 |
参照元:国税庁「第1 源泉徴収制度の概要」
納付方法は以下のとおりです。
- e-tax
- 所轄の税務署
- 金融機関
税務署と金融機関で納付する場合は「所得税徴収高計算書(納付書)」が必要です。なお、家事使用人を常時2人以下雇用する場合は、源泉徴収の必要はありません。
参照元:国税庁「給与所得の源泉徴収税額表(令和6年分)」
個人事業主は社会保険のルールを学び、働きやすい環境を構築しよう

個人事業主が従業員を雇用する際は、社会保険や労働保険の加入が必要になるケースがあります。労働保険のうち、労災保険はひとりでも雇った場合に義務付けられます。雇用保険は条件を満たすと加入が必要です。さらに、5人以上を雇用すると社会保険の加入も義務付けられます。
社会保険料は従業員と折半で支払いますが、労働保険は個人事業主の負担割合が大きい点が特徴です。雇用を決める前に必要になる保険料を把握すると、急な出費に慌てることも減るでしょう。
個人事業主自身は、原則として国民健康保険と国民年金(第1号被保険者)に加入します。これらをクレジットカード払いにすることで、ポイントを貯められるだけではなく、自動引き落としにより納付忘れも防げます。また国民年金保険料を前納すると、保険料の抑制も可能です。イ
個人事業主はルールを守るためにも、社会保険制度や納付方法などに関する最新情報を確認し、必要に応じて専門家に相談しつつ知識を深めていきましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。